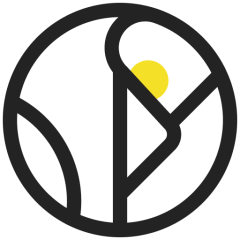教えてくれたのは……経済産業省 水口怜斉さん

経済産業省に入省し、スタートアップ支援や起業家育成、2025年大阪・関西万博関連業務などに従事。現在は健康・医療・介護分野を横断したヘルスケア領域の政策立案を担当。働く家族介護者に対する支援や、介護を個人の課題からみんなの話題へ転換することを目指す「OPEN CARE PROJECT」の立ち上げメンバー。その他、医療の国際展開やヘルスケアスタートアップ支援に関する政策も企画・推進。
親の介護に直面しやすい年齢は「45~60歳」
日常生活全般にサポートが必要な状態である「要介護」の認定率は、75歳以上で約3割、85歳以上で約6割。親の介護に直面しやすい年齢は、45〜60歳が多いとされています。経済産業省で健康・医療・介護などヘルスケア領域の政策立案を担当している水口怜斉さんは、「介護が始まるときがもっとも大変だったと、多くの経験者が話している」と話します。
水口さん 「介護は、転んでケガをしたり、心身の不調があったりなど、突発的に始まることが多いものです。そんなとき、公的な保険制度がどれくらい使えるのか、どんな介護サービスがあるのかを知っている方は少数で、多くの方はまず情報収集から始めています」
水口さん 「介護保険のサービスは、申請して要件に当てはまれば原則として誰でも受けられます。ただ、市町村によっては認定結果が出るまでに1ヵ月以上かかる場合もあります。また、介護保険を申請するには、親御さんの住む家で調査員による訪問調査を受ける必要があります。訪問調査の候補日が仕事の繁忙期に重なって日程調整が思うようにいかなかったり、親と自分の住まいが離れていて移動の負担があったりして、介護が必要になってからサービスを受けられるまでにタイムラグが発生する場合もあります」
親が元気なうちにしておきたい「介護の備え」3つのポイント
いざというとき慌てないために、親が元気なうちからどのような準備をしているといいのでしょうか? 水口さんから教えていただいた「親が元気なうちにしておきたい介護の備え3つのポイント」をご紹介します。
1. 介護の経験がある人に話を聞く
まずしておきたいのが、「親の介護を経験した人の話を聞くこと」です。制度や仕組みを調べるよりも頭に入りやすく、具体的なイメージを膨らませる助けになります。
2. 親が住む地域の介護サービスについて情報収集する
自治体の広報誌には、高齢者向けの介護予防イベントや、利用可能な介護サービスの情報が掲載されています。帰省したときに広報誌をチェックしたり、親が住む市町村のホームページを確認したりしてみましょう。親が住む地域の「地域包括支援センター」を調べておくことも有効です。また、親が住んでいる地域で介護をしたことがある人と話すこともおすすめです。介護サービスの内容や居宅介護支援事業所の情報、ケアマネジャーの雰囲気など、具体的な情報を得ることができます。
3. 親と介護について話す
親と直接話せるようなら、介護や老後資金について、一度話してみましょう。「最近ちょっと調子が悪くて……」など、からだの不調について話題が出たときに切り出すのがおすすめです。親に直接切り出すのが難しい場合は、専門職を頼るのもひとつの方法です。親が住む地域の「地域包括支援センター」に事前相談すると、場合によっては地域包括支援センターに親と訪問するよう勧められ、介護について三者間で話す場が設けられることもあります。第三者の介入により、話がスムーズに進む可能性があります。
親が介護について話すのを嫌がるときは
親が介護サービスの利用を嫌がることもあるかもしれません。そんなときこそ、介護のプロに相談するのが有効だと水口さんは話します。

水口さん 「『デイサービス』と聞くと、『まだまだ私は早いわよ』と拒否反応を示す方は一定いらっしゃいます。そうした声を踏まえて、最近は『シニア専門ジム』と言い換えて健康プログラムを提供している事業者もあります。なかには、施設名が入っていない黒塗りの車で送迎するなど徹底しているところもあるんですよ。また、男性高齢者は退職後に家にこもりがちになるケースもあるのですが、そうしたシニア男性に向けた料理教室を市町村と連携して行っている事業者もあります。プロの知恵を借りながら、手を変え品を変えてアプローチするのも有効です」
いつか介護に直面したときのために、早いうちから経験者やプロの話を聞いて、親とコミュニケーションをとっておくことが大切なのですね。次回は、「仕事と介護を両立するために知っておきたいこと」について水口さんに教えていただきます。