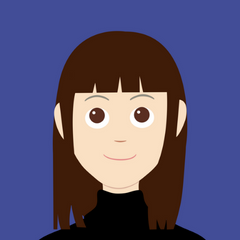子どものコミュニケーショントラブル、どうやって対処してる?
小学校低学年のうちは、シンプルな言い合いやコミュニケーションの齟齬が多く、大人が注意し、お互いに謝って解決というケースがほとんど。
しかし中学年、高学年となると、大人でもありえるような些細な言葉のすれ違いや伝え方のミスなどが増えていきます。
子どもに言葉の選び方やコミュ二ケーションの力を身につけてほしいとき、どのように関わっていくのがよいのでしょうか。
子どものコミュニケーショントラブルあるある
感情的な言葉で傷つけてしまう。
サッカーのクラブチームの試合で熱くなりやすい小5の息子。試合に負けてしまったとき、パスをミスしたりシュートを外した子に「どうしてこうしなかった」「お前のせいで負けた」と責め、チームの雰囲気が悪くなってしまった。
スポーツやゲームで熱くなると、つい必要以上に強い言葉をかけたり、相手を責めるような言い方をしてしまう子は多いです。
しかし、熱くなってるから仕方ないと済ませ、何度も同じことを繰り返してしまうと周囲との関係性が悪くなっていく可能性があります。
イライラしたときはどうすればよいかを話したり、あとから振り返り、言葉の置き換え方を考えられるとよいでしょう。
言葉が足りない。
グループワークの班長となった娘はメンバーに「ここやっておいて」と伝えたよう。しかし一部の子は何をすればよいかわかっておらず、次の日やってこなかった。家に帰ってきた娘は「なんでさぼったんだろう?」と怒っている。
このような言葉の不足やコミュニケーション不和は大人になってもよくあることです。
子どもの話を聞いて信じてあげるのもひとつですが、その場のやり取りを振り返り、伝えた側にもミスはなかったかを確認するのも大切なんですね。
配慮に欠けた発言をする。
娘が学校で、髪を切ってきた友達に「髪切ったんだ。前の方がよかったのに」と言ったら相手の機嫌を損ねてしまったという。娘自身悪気はなく、「思ったことを口にしただけ。」と言っている。
大人同士でも本音をどこまで言うか、迷うときがありますよね。
素直な子どもであれば余計に、配慮の足りない言葉で傷ついたり傷つけたりしやすいもの。
特に「嘘はよくない」という言葉を正面から受け取り、なんでも言ってしまう子もいます。
失敗を振り返ったり、親子でロールプレイをして話しあったりする中で少しずつ配慮を身に着けていけるとよいでしょう。
「自分が言われたら?」はピンとこない。
成長段階にある子どもは「自分がされたらどう思う?」と問われてもピンとこなかったり、「自分は別に傷つかない」と共感から離れてしまうことも多いもの。
また、「普通はこう思うんだよ」「みんなそうやって考えてるの」と言われると考えを押しつけられている気持ちになり反抗しやすくなります。
「ママはそうやって言われたら悲しくなるな」と親自身の気持ちを伝えたり、「パパだったらどう感じるかな?」と尋ねてあとから実際に答え合わせするなどの関わりが役立ちます。
身近な相手が実際にどう感じているかを知り、「自分の気持ちと相手の気持ちは違うんだ」と学んでいけるとよいでしょう。
悪い言葉を指摘するより、よい言葉を褒める
子育てでよくやってしまいがちなのは悪い行動を叱ったり指摘することばかりに目が向いて、よい行動を見落としてしまうこと。
「ほら、そういう言葉遣いがよくないんだよ」などと指摘してしまうと非ばかりを責められている気持ちになり、よいコミュニケーションが身につきにくいんです。
「今の言葉嬉しかったな」「そういう風に伝えてくれるとわかりやすいよ」など、肯定的なフィードバックが何よりの支えとなります。
また、親が「相手を褒めるモデル」を子どもに見せられると、子どもも自然と相手のよい面に目を向けやすくなるんです。
明るい雰囲気の中で、コミュニケーションの力をつけていけるといいですよね。