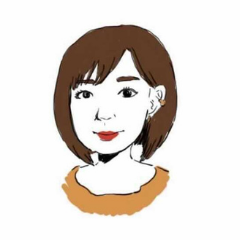教えてくれたのは……清水 聖童先生
精神科専門医・医療法人社団燈心会ライトメンタルクリニック理事長。心理療法、生活習慣、栄養学など幅広い知識を背景とした精神予防医学を専門とし、病前から介入する精神医療を模索したクリニック「ライトメンタルクリニック」を立ち上げる。メンタルヘルスに関する記事監修や講演、取材対応も積極的に行い、専門的な知見を広く発信している。
幸福度が高い人と低い人の決定的な違い「5つの特徴」
幸福度が高い人と低い人には、どのような違いがあるのでしょうか。幸福度の差には、物事の捉え方や日々の行動が影響しているのだと清水先生は言います。
鈴木先生:精神科の診療現場では、「自分は幸せだ」と感じている人と、そうでない人には、日々の考え方や行動に明確な違いがあることがわかってきています。幸福度は、生まれつきの性格や環境だけで決まるものではなく、むしろ、物事の捉え方や人との関わり方を少し意識するだけで、大きく変えることができます。
清水先生によると、幸福度が高い人と低い人には5つの違いが見られるとのこと。それぞれ詳しく教えていただきました。
1.失敗の捉え方
清水先生:幸福度が高い人は、失敗を「自分を成長させるチャンス」と考える傾向があります。失敗しても「次はうまくいくように工夫しよう」と前向きに捉える力があります。一方で、幸福度が低い人は、失敗を「自分には能力がない証拠」と受け取り、自信を失ってしまうことが多くなります。
2.感情との向き合い方
清水先生:感情に振り回されず、冷静に向き合える人ほど幸福度が高い傾向にあります。例えば、悲しみや怒りといったネガティブな感情も「こんなふうに感じているんだな」と受け入れたうえで、自分を落ち着かせることができます。逆に、感情を押し込める、爆発させてしまう人は、気づかないうちにストレスを溜め込みやすくなります。
3.人間関係の質
清水先生:「何でも話せる友人がいる」「自分を受け入れてくれる人がいる」 こうした安心できる人間関係がある人は、心が安定しやすく、幸福度も高くなります。反対に、他人と自分を比べすぎたり、人からどう思われているかばかりを気にしていたりすると、孤独感や不安が強くなり、幸福感は低下しやすくなります。
4.週末や余暇の過ごし方
清水先生:幸福度が高い人は、忙しい中でも自分を癒す時間をしっかり確保しています。散歩や趣味、好きな音楽を聴くなど、リラックスできる時間を大切にしています。一方で、幸福度が低い人は「休むのは悪いこと」と思ってしまい、常に何かに追われているような気持ちになり、心も体も疲れてしまいがちです。
5.自己肯定感の持ち方
清水先生:「自分はこれでいい」と思える力がある人は、他人の評価に左右されず、安定した気持ちで毎日を過ごせます。完璧ではなくても、自分の良いところに目を向けられるのが幸福度の高い人の特徴です。逆に、「もっと⚪︎⚪︎しなければ」と自分に厳しすぎると、常に不満や焦りを抱えやすくなります。
前向きな考え方と習慣が幸福度を高めていく
違いを知ることで、幸福度を高めたいと考える方にとって、前向きな変化のきっかけになりそうですね。
清水先生:幸福度は、「考え方」や「習慣」を少しずつ見直すことで高めていくことが可能です。実際、こうした視点は精神科医療の現場でも、うつや不安の改善に役立つことが多くあります。日々の中で少しずつ意識を変えることが、幸せに近づく第一歩になるかもしれません。