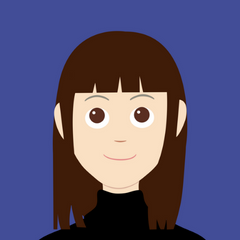「普通でいい」「うちは放任」の背景にある隠れ過干渉とは?
「うちは本当に子どもに期待とかしていなくて。普通でいいんです。」
親御さんはそうおっしゃるものの、子どもはしんどそうにしているケースは多いもの。その背景には、“隠れ過干渉”が潜んでいることも。相談を受ける中で、「うちは放任気味だと思っていた」という親御さんが、実は子どもに強いプレッシャーを与えていた、というのはありがちなんですね。今回は、「一見、過干渉に見えない隠れ過干渉」について、考えてみます。
一見過干渉に見えない“タイプ別隠れ過干渉”
応援型過干渉
塾のテストで思うような点が取れず、元気のないAちゃん。「あなたなら絶対できるよ! ママは信じてるから!」と励まされるが、なんだかモヤモヤする。「もう、頑張っても無理」と呟くも、「そんなことない、大丈夫!」と言われ口を紡ぐ。
「あなたならできる、やればできる子だから」などの声かけは、子どもの自信をつけるために一見有効な声かけに思えますよね。しかしときに、「できる子」というイメージをプレッシャーに感じたり、頑張りきれない自分への自己嫌悪に繋がることも。親は励ましているつもりでも、子どもは「常に頑張り続けること」「できる子でいること」を要求されているように感じる場合があるんですね。
応援や励ましが口癖になっている場合は、
- テストや発表の結果は子どもが言うまで待っておく。
- 子どもの気持ちだけを受け止める。(それはがっかりだったね、つらかったね)
- 応援や励ましを「辛くなったら言ってね」「支えになれることあったら教えてね」に言い換える。
などの対応がおすすめです。
親の肯定的なメッセージを子どもが脳内で消極的に変換してしまうこともある年頃。応援する姿勢から、見守る姿勢に切り替えるのも、子どもの支えとなってきます。
心配先回り型過干渉
放課後、友達とのトラブルがあったBちゃん。帰宅後「何かあった? 無理しないでね。ママ、先生に相談してみようか?」とママ友から聞いた様子で心配顔。「別に話すほどのことじゃない」と言うものの、その後も気を遣って接してくる。親に心配をかけたくない思いから、本当の気持ちはどんどん言えなくなっていく。
心配性な方や気持ちを汲み取ってあげるタイプの親御さんに多いタイプといえます。子どもが自分の気持ちを感じきる前に、親が先回りして不安にや辛さを感じてしまうと、子どもは自分の気持ちを言いにくくなることがあるんです。親が先回りすると、子ども自身が考える余白がなくなり、親の気遣いに気を遣ってしまうんですね。
- 「大丈夫? ~しようか?」ではなく、「話したいときは聞くよ」など、話すかどうかを子どもに任せる。
- 「心配だなあ」「~したら?」と親の感情や提案を控え、「そのときどう思ったの?」と子どもが考える余白を作る。
- 子どもから積極的に話してこないときは沈黙も大切にし、見守ってみる。
子どもに共感的、気遣いが多い親御さんの子どもは、親に似て気遣いが上手なケースが多いもの。そんな子は親に気を遣わず、黙ったり反抗したりするのも成長の証。静かに見守り、子どもが怒ったり泣いたり悩んだりする余白を作るのがカギになります。
~らしくていい型過干渉
学校や塾の成績は比較的よく、周囲からは優秀といわれるポジションのC君。母は「別に東大に行けなんて言ってないよ。C君らしくいてくれればそれでいいの」と言う一方、時折「昔はもっとかわいかったのに」と呟く。何が自分らしいのか分からず、「自分はこのままでいいのか?」とモヤモヤがつのる。
「あなたらしくいていい」という言葉は一見とても優しく聞こえますが、「あなたらしく」も、親が描いている“らしさ”が隠れているときも。「親が言う私らしいって何?」「いつの話をしてるの? 応えないといけないの?」と反発心を抱く子も多いもの。
- 過去のわが子と今のわが子を比べず、目の前にいる本人を認める。
- 「今は~にハマってるんだ。」「最近はこういうのが好きなんだね」と今の本人らしさを知る。
- 子どもは常に変わりうるものとして見つめ、「今のままでもいい、変わってもいい」と伝える。
なんでも口を出す、制限をかけるばかりが過干渉ではなく、子どもにとって、選べない・動けない・気を遣う関わりは隠れ過干渉となっていることも。
これまでの関わりも決して不正解ではありません。
関わり方のバリエーションを増やして、子どもが、より子どもらしく成長していけるよう支えられるといいですよね。