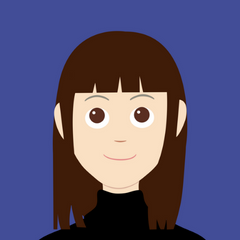夏休み、祖父母から言われた言葉にモヤモヤ。
「男のくせに泣くなんて」
「女の子なんだからお手伝いしなさい」
「普通はこうするもんだよ」
久しぶりに祖父母と会うと、モヤモヤする言葉を言われたことはありませんか? 世代の違いや住んでいる地域の差、親子の距離感によって、考え方の違いが現れやすくなるもの。
自分に言われる言葉だったら聞き流せても、わが子に言われるとピリッとしてしまう方も多いのではないでしょうか。また、子どもが普段とは異なる価値観に触れて違和感をもったとき、どのように声をかけたらよいのでしょうか。
子どもの「違和感」は大事なアンテナ
小学校高学年になると、子どもは自分の考えや価値観を持ち始めます。家で学んだことと、祖父母や親戚の言うことが食い違うと、「あれ、なんか変だな?」と違和感を覚えるようになります。
でも実は、この「モヤモヤ」はとても大切なサイン。それは、自分で考える力が育ちはじめている証拠なんです。
大人の考えがバラバラだと混乱しそうに見えますが、そうした“ズレ”を経験することが、多様な価値観を受け入れる柔軟さや、自分なりのスタンスを育てていきます。
親は“価値観の通訳者”になる
子どもがバラバラの価値観を納得できないまま飲み込んでしまったり、矛盾した考えにモヤモヤしたまま終わってしまうのはもったいないですよね。
そんなとき、親ができることは、「翻訳」です。
たとえば、
- 祖父に「男のくせに泣くな」と言われた→「そう言われたんだね。パパやママは、男の子でも泣いていいと思ってるよ。でも、おじいちゃんが子どもの頃は、そういうふうに教えられてたんだと思うよ。」
- 祖母に「女の子なんだからお手伝いしなさい」と言われた→女の子なんだからって言われたのは、ちょっとモヤモヤしたかもしれないね。でも、きっとおばあちゃんは、“周りを気づかえる人になってほしい”っていう思いがあって言ったんだと思うよ。」
- 親戚に「普通はこうするものだよ」と言われた→「“普通はこうする”って学校ではあまり言われないよね。昔は“みんな同じようにするのが正しい”って教わることが多かったんだよ。でも今は、いろんな考え方があるのが“ふつう”になってきてるよね。」
など、背景を説明しながら、今の価値観もちゃんと伝えていくのが大切です。
“どちらが正しいか”を考えるのではなく、違いがあることをうまく伝えられると、子どもの考え方が広がりやすくなるでしょう。
親も一緒に“アップデート”する
実は親自身も、無意識のうちに昭和・平成的な価値観を引きずっていることがあります。「ちゃんとしなさい」「みんなやってることだよ」などの言葉がつい出ることはありませんか? 子どもが祖父母の言葉にひっかかったときは、親にとっても自分の考え方を見直すチャンスです。
親は「正しさを教える人」である必要はありません。なぜなら、 「一緒に考えてくれる大人」であることのほうが、子どもにとってはずっと心強い存在になるからです。価値観は時代とともに変わるもの。だからこそ、「これからどんな考え方を大事にしたいか」を、親子で一緒に話せる時間を持てるといいですね。