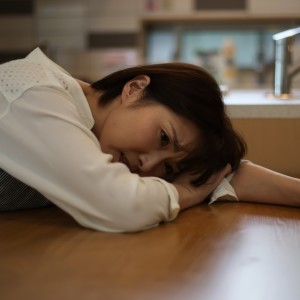お話を聞いたのは……最上悠先生

精神科医、医学博士。思春期や青年期のうつや不安、依存などに多くの治療経験をもつ。英国家族療法の我が国初の公認指導者資格取得など、薬だけではない最先端のエビデンス精神療法家としても活躍。著書は『日記を書くと血圧が下がる 体と心が健康になる「感情日記」のつけ方』(CCCメディアハウス)ほか多数。
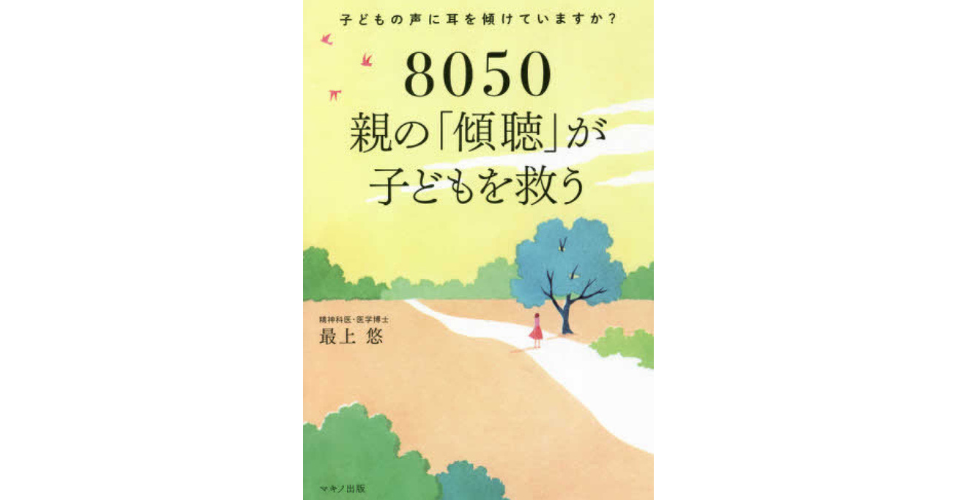
『8050 親の「傾聴」が子どもを救う』
著者:最上悠
定価:1,650円(税込)
正しい傾聴のしかたとは?
――前回、子どもの話を“傾聴する”大切さを伺いました。同時に、傾聴はすごく難しいとも感じるのですが、正しい傾聴のしかたはあるのでしょうか。
まずは、子どもが伝えたいことを黙って聴くことです。さえぎったり、助言したり、評価したりせず、黙って聴く姿勢を見せているうちにお子さんの中に安心感が生まれます。そうなれば、お子さんはさらに胸のうちを話すようになるものです。多少おかしなことを言っていると感じても、まずは黙ってひたすら耳を傾け、子どもが感じていることを理解し共感に努めてみてください。子より人生経験の多い親は、良かれと思い、子どもの話に自分の意見を述べたり、正しい結論に導きたくなりがちですが、繊細な子どもほど、親が何かを伝える前に、十分に気持ちを聴いてもらえないことが続くと心を閉ざしてしまいます。
――心を閉ざしてしまうとどうなるのでしょうか。
よくあるのは、全く手のかからない良い子を演じるパターンです。多少極端な表現ですが、“良い子”なんて幻想で、そこにいるのは、“良い子を演じるのがうまい子”かもしれません。繊細な子は空気が読めてしまうので、きょうだいがわかりやすく駄々をこねていようものなら、自分を押し殺して家族のバランサーになろうとします。親も手のかかる子が一人でもいたら、もう一人が“良い子”でいてくれた方が楽なので、ついつい甘えてしまいがちです。でも、そんな子の中に、あるタイミングでその押し殺した感情を抱えきれずにバランスを崩す子が出てくるのです。実際、今話題のきょうだい児(病児・障がい児の兄弟姉妹)でも、ある年齢からがまんの限界を超えて心身の不調をきたす子は少なくありません。
「子どもの話を聴くことが辛い」親の理由
――そうならないようにするためには、やはり傾聴なんですね。
表面上の言動にはあまり振り回され過ぎずに、子どもの本音や気持ちをちゃんと聴けているかどうかがポイントです。話は聞いていても、子どもが何を考えているかがさっぱりわからないままと言うのであれば、それは声としての「音」は聞けてはいても、やはり「心」は聴けていないということになります。
かといって、「本音があるなら言いなさいよ」と迫ってもそう簡単には話してはくれません。「これまで散々話してきたのに目を向けてもらえず、傷つきこころが折れてしまったから言えない(もしくは自分でもわからなくなってしまった)んだよ」と感じているからです。また、中には「傾聴って、一体何をすればいいのかがピンとこない」とか「子どもの話を聴くこと自体がしんどい」という親御さんもたくさんおられるんです。
――親のほうがしんどいんですか?
例えば、わが子を理解したい、胸の内を聴いてはあげたいとは思いながらも、心のどこかで「私は言いたいことを我慢して乗り越えてきたのに、なんでこの子にはそんなに譲歩をしなきゃいけないの?」という気持ちを持ってしまう方もいます。実際、カウンセリング中にそう言って泣き出す親御さんも少なくないのです。
――親にもトラウマはあり、子育てをしていく中でそのトラウマが刺激されることは多かれ少なかれありますね。
ある20歳の男子学生の話です。6年前に大好きだった祖父が亡くなったとき、部活の大会に出ていて、家族で自分だけ死に目に会えなかったそうです。その時、きょうだいからは「人でなし」と罵られてひどく傷つき、そのつらさを訴えられたお母さまには、「気にしなきゃいいのよ」と助言したことで解決したと思ったのだそうです。確かに、そんなに非のある親子のやり取りには思えないのですが、結果として彼はそのことを思い悩むうちに学校にも行けなくなってしまい、精神科を受診しています。
親子関係で傷ついていない人はいない
――そんなに時間が経過してから症状として出ることがあるんですね。
感情不全が問題化する時期は人それぞれです。この方は、自分でもおかしいと頭ではわかっていても、事あるごとに思い出し、自分を責め続け、こころが疲れ果ててしまったようです。話し合いを重ねる中で、本人は自分の傷ついた感情が処理しきれていないと気づき、「6年前、僕はノーテンキにも部活に打ち込んでいて、おじいちゃんの死に目にも立ち会えなかった人でなしなの。それをきょうだいに罵られてすごく辛かった、苦しかった」と泣きながら、ある診察で付き添ってくださったお母さまに顔を真っ赤にして打ち明けたのでした。心の奥底にがまんしていた一次感情を伝えたのです。ただ、それを聞いたお母さんの第一声は、「知ってたわよ」でした。
――それは、息子さんが求めている言葉ではないですよね?
「他に何か言葉はありませんか?」と尋ねてみたところ、突然にお母さんが、「なんで私がそんな話を聞かされなきゃならないの」と泣き出したのです。「私も親にはそんな話はずっと聴いてもらえずに生きてきた。でも私は我慢したし、病気にもひきこもりにもならずにやってこれたのです。私はしてもらえなかったことを、どうしてこの子にはしてあげなきゃいけないの!」と。
――そう言ってしまうお母さんの気持ちもわかります。それは母親のほうが多いですか?
お父さまでも、「自分は親に弱音を吐くことなど決して許されず、歯を食い縛って頑張ってきたのに、なぜ息子にはそんな甘ったれたことを許さなければならないのか!」とお怒りになる方は少なくはありません。「性格が違うからですよ。心の体質が違うから、お父さまと違ってお子さんは耐えられなかったので心を病んでしまったのではないでしょうか?」とお伝えしたところ、その後のお父さんの関わり方が別人のように変わり、それと共にお子さんが回復しひきこもりから脱していったというケースも実際にありました。
もちろん大なり小なり、親子関係で傷ついたことがない人なんていないのだと思います。確かに、傷ついても自力でがんばれる子もいます。でも、どうしてもがんばれない子もいるのです。親も傾聴・共感が大事だと頭ではわかっていても、お子さんと向き合うことで、苛立ったり、不安に襲われたり、自らの中にある心の痛みに耐えられなくなってしまうことは決して珍しくないのです。
子ども時代に、自身の親との間に起きたことで何かしらの傷を負っているというお話に、ハッとした方もいるのではないでしょうか。子どもの話を聴いてあげたい、理解してあげたいと頭では思っているけど、どうしてもうまくできない理由。それは、あなた自身がこれまで押し殺してきた本音の存在に気づいたからかもしれません。子どもの気持ちを理解するためにも、そのことを自覚することは大きな1歩ではないでしょうか。