お話を聞いたのは……最上悠先生

精神科医、医学博士。思春期や青年期のうつや不安、依存などに多くの治療経験をもつ。英国家族療法の我が国初の公認指導者資格取得など、薬だけではない最先端のエビデンス精神療法家としても活躍。著書は『日記を書くと血圧が下がる 体と心が健康になる「感情日記」のつけ方』(CCCメディアハウス)ほか多数。
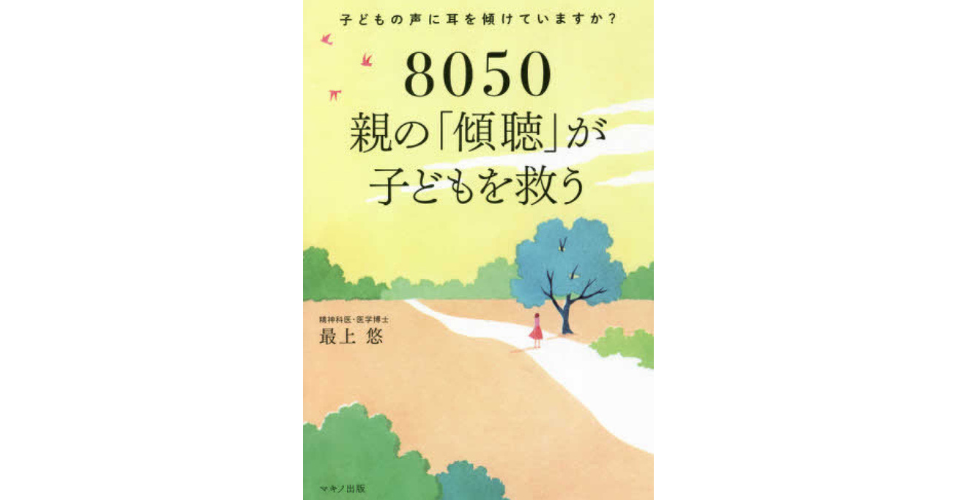
『8050 親の「傾聴」が子どもを救う』
著者:最上悠
定価:1,650円(税込)
「8050問題」とは?
――先生の著書『8050 親の傾聴が子どもを救う』にもある「8050問題」とは、具体的にどのようなものですか?
「8050問題」はその言葉の通り、80代の親が自立できない50代のわが子の生活を支えているという深刻な社会問題を指しています。昨今、親元から自立できない方やひきこもりのまま年齢を重ねていく方が増えています。2018年に内閣府が行った調査では、40歳から64歳の年齢でひきこもり状態にある方は60万人以上と、若年層よりも多いとすら推計されています。
――60万人以上ですか? それは驚くべき数字ですね。
40代より下の年代も含めると、100万人を超えるとも言われています。
必要なのは、繊細さに合わせた「傾聴」と「共感」
――ひきこもりになる人が増えているということですが、新年度が始まって時間が経ったこの時期、子どもの学校への行き渋りや不登校に悩んでいる方も多いです。どのように向き合うべきなのでしょうか。
もちろん、親御さんとしては行ってほしい気持ちになるのは当然かと思うのです。だからまずは「学校に行くように」と正攻法で働きかけるのは当然「あり」なのだとは思います。ただ、それでもどうしても学校に行けないというお子さんに、「学校に行きなさい」と頭ごなしに伝えても解決にはなりません。お子さんが自らを追い詰めるほどに深刻に悩まれているのであれば、「無理に行かせない」という選択肢も必要になるわけです。もちろん許容できない現実の問題があるのなら、まずはその解決が大前提です。しかし、原因がよくわからない場合もあります。その場合に大切なのは、まずは子どもの本音にしっかり耳を傾けることです。
――子どもの話をしっかり聞いてあげているけれど、子どもがひきこもりになってしまったという方も多いと思うのですが。
大半の親御さんは本当に粘り強くお子さんと向き合っておられます。ただ、そんな親の想像を超えた繊細さを持つお子さんにとっては、「それでも足りない」ということが生じるのです。誤解していただきたくないのは、自分より繊細な子を親が先回りして気づくといったことは現実的には非常に困難で、決して「親御さんが悪い」などと安易に責めを負うべきことではないのです。逆に親子によってはそういったズレが生じてしまうのは仕方のないことだとすら私は思っています。ただズレがわかった段階からは、その溝を埋めていく方向に前向きに舵を取りましょうということなのです。
――そのズレが生じた場合、親子共に辛いですよね。
進展が見えてこないと、「この子が何を考えているかわからない」と親の方はついしびれを切らしがちです。一方で、お子さんはお子さんで「何度言っても結局わかってもらえない」とか、「どうせ言ったって無駄だ」という気持ちに陥ってしまう。ただ、親が一生懸命やってくれているのはわかるし、親のことは大好きなわけで、そこで親への気遣いがはじまるわけです。もしくは、「もういいよ、張り切らないでくれよ」と、これ以上がっかりはしたくないと親と距離を置きたがる場合もあります。
子どもの本音を受け止めることが大事
――「何を考えているかわからない」となってしまった場合、その後どのような対応が正解なのでしょうか。
親は十分に子どもの話を聞く時間は割いているし、世間並み以上に一生懸命お子さんを育てられていて何の問題もなさそうなご家庭も少なくありません。実際、同じ育て方でも、きょうだいは何の問題もなく育っていることも多々あります。だから、尚一層問題は深刻とも言えるかもしれません。一人一人タイプがあるので、そのお子さんに合った聴き方ができているかを考えなくてはいけないんです。
ひきこもりや行き渋りになるお子さんの大半はとにかく繊細です。その繊細さに合わせた関わり方をすることが求められるのです。親の悲しそうな態度を感じることは、繊細なお子さんにとってはとても辛いことなので、さらに「いい子を装う」ことで本音が見えづらくなるという悪循環も生じがちです。
――繊細さに合わせた関わり方ってすごく難しいですね。それができないと子どもの中ではどのようなことが起きるのでしょうか。
子どもにとって親の存在は絶対なので、「これ以上傷つきたくない」ために、「自分の本音の気持ち(一次感情)を押し殺す」という方法に出がちです。怖いのは、いつも本音を抑圧していると、徐々にこころの感度が落ち、自分でも何が本音なのかさえわからなくなってしまう、不健康な感情不全の状態が生じてしまいます。するとがんばっても達成感が感じられず、嬉しさや喜びも鈍化し、覇気やチャレンジ精神も失われ、その結果ジャンキーな刺激や行動でしか満たされず不健康な言動が目立ってきます。やりたいことは? と尋ねられてもピンとすらこない……ということも珍しくありません。一見表面上は現実的な原因があるようなことでも、立ち直れないこころの背景にはこういった感情不全が潜在している場合も多いのです。
例えば、お母さんが仕事や介護で忙しいときや、離婚や別居などで大変だとわかっているときでも、「一緒にいたい」「寂しい」と小さな子が感じるのは当然です。でもそんな本音を言ったらお母さんを困らせてしまうと考えた結果、自分の感情をひたすら抑圧してひきこもりとなった40代の方が70代の親に「小学校入学前から、本当はずっと我慢してきた」と泣きながら吐露することも珍しくないのです。もっとも大概の親は、「そんな風には見えなかった」「覚えてすらいない」と答えることも多いのですが。
――子どもは一次感情である本音をごまかさずに育つ環境が好ましいということですね。
親を責める元気があるのはまだ健全な子です。「おもちゃがほしい」と泣き叫べる子は健全なんです。反抗期もそうですが、親の前で自分の感情をうまく表現できない、表現したとしても親にその感情を肯定してもらえない環境で育つと、一次感情の感度低下だけではなく、その反動で二次的なゆがんだ思考や価値観、問題行動や原因のはっきりしない心身の不調が生じることも珍しくはありません。
そしてこういった二次反応も、お子さんが若ければ若いほど、親が傾聴し共感すること、つまり子どもが一次感情をしっかりと表現できる、これは一次感情を感じられているということなわけですが、それができるようになると、たとえば最先端の精神医療では治す方法がない、もしくは生涯お薬を要すると考えられている精神疾患ですら回復に向かうというエビデンスも示されているほどなのです。
「子どもの話をしっかり聞いている」と思っていても、実はその聴き方が十分ではなかったり、親の意見で遮ったりしていることがあるな……ということを、最上先生のお話を聞きながら感じました。「同じ親のもとで育っても育ち方が違う」というお話を聞き、その子に合わせた育て方ということを意識しなくてはいけないんだという発見がありました。次回は、最上先生が大切だという「話の聴き方」についてお話を聞きます。


















