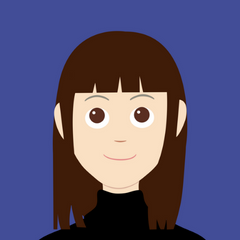年々増えている、”静かな反抗期”。
小学校5年生の息子。「今日どうだった?」と聞けば、「べつに」。楽しそうな話題を振っても、「ふーん」。ちょっと前までは学校のことも友達の話も止まらないほど話してくれたのに、最近は目も合わせない日がある。リビングに来てもイヤホンをしたまま、返事は片手間。でも反抗的な態度ではないし、気分が乗らないだけ? 無気力な時期? どんな風に接すればよいのだろう。
反抗期というと、「くそばばあ」と言われたり、壁に穴をあけたり、激しくぶつかってくるようなイメージをもたれている方も。しかし実際は激しい反抗ではなく、静かに反抗期を始める子が多いもの。
怒ったり殴ったりするのではなく、“何も起きていないように見える沈黙”にメッセージがこめられているケースが増えているんです。親との間に見えない壁を作り出す時期、親がどのような関わりを心がけていけばよいのでしょうか。
「そっけない」「やらない」「話さない」意味とは?
- 親が話しかけていても目を合わさず生返事。
- 「めんどくさい」「どっちでもいい」「別に」が口癖。
- ルールや約束事は守っているが、部屋にこもりがち。
このような様子が増えたとき、「元気ないのかな?」「無気力?」と感じる親御さんは多いもの。
しかし、「どうしたの? なんで返事しないの? 何か困ってるなら話して」と詰めてしまうのは逆効果。
返事がそっけない、親が勧めたことをやらない、自分のことを話さないのは、無気力ではなく自分の中で整理している時期ともいえます。何も言わないのは、「今は言いたくない」「言葉にする準備ができていない」時も多いんですね。
また、反抗期の始まりは「親との距離を模索する時期」ともいえます。距離を模索している時期、子どもは機嫌よく甘えてくるときもあれば、理由もないのに無口になってぶすっとするときもあったりします。これは、「親から離れたい気持ちがある一方で、離れすぎるのも不安」という複雑な気持ちの表れ。
この矛盾した子どもの気持ちに対して「何考えてるの?」と苛立ったり、矛盾を受け止められないとこじれてしまうことも。まずは「難しい時期なんだな」と冷静に見守るのが吉なんですね。
閉ざしている扉をこじあけるのはNG。
話してくれないと、「これからどんどん距離があいてしまうのでは」「ひきこもってしまったらどうしよう」などと不安が募りやすくなるもの。しかしその不安をそのままぶつけると、子どもは親を疎ましく感じたり、余計にガードを強めてしまいます。
また、「なんで返事しないの?」と圧をかけたり、「最近どうなの?」と無理に話させようとするのもNG。まずは”話したくない気持ち”を受け止める姿勢が重要なんです。
無理なく繋がる距離感のコツ
話してほしい、心を開いてほしい、前のように戻ってほしい。親の「~してほしい」気持ちは、子どもの反抗を加速させやすくなります。会話ではなく、日常生活の中で自然な対応を意識するのがポイントです。
- ご飯の準備をする、洗濯物を畳むなど、並行して作業する。
- 宿題をしている隣で仕事をする。
- 「おかえり」「暑かったね」など答えを求めない会話を大切にする。
思春期の子は、“感情を持ちすぎず、言わされる不安のない相手”に安心しやすいもの。「こんな時期もあるか」と腰を据えて、ゆったりと構えるのがおすすめです。
子育ての難しさは、「子どもなしでは生きていけない親自身が、親なしで生きていく方法を子どもに教えなければいけない」ところにあるともいいます。日々変化する子どもの様子を見守りながら、お互いにベストな距離を模索していけるといいですよね。