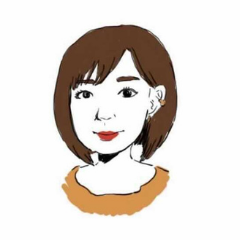教えてくれたのは……島田直英(しまだ・なおひで)先生

精神科医・総合診療医・漢方医。不登校/こどもと大人の漢方・心療内科 出雲いいじまクリニック 副院長。島根大学医学部医学科卒業後、大田市立病院総合診療科、島根大学医学部附属病院総合診療科等を経て、2025年に同クリニックにて副院長に就任。飯島院長に医学生時代より師事し不登校・不定愁訴診療の極意を学ぶ。精神科単科病院にも在籍。
子どもの摂食障害に見られる初期の行動「4つのサイン」
前回の記事では、「子どもの摂食障害が増えている要因や特徴」についてご紹介しました。親が気づきやすい初期のサインや行動の変化には、どのようなものがあるのでしょうか。島田先生によると、食事量や体重の変化だけでなく、精神的・身体的なサインにも目を向けることが大切なのだそうです。
島田先生「食事量や体重の変化以外では、 4つのサインが見られることが多いと考えられます。1つ目は、行動の変化です。一人で食べたがる、食後にトイレに籠る、カロリーを過剰に気にするなどが見られます。2つ目は、心の変化です。イライラしやすい、集中力がない、気分が落ち込むなどが目立つことが多いです。そして3つ目は、寒がる、髪が抜ける、月経が止まるなど、身体の変化が挙げられます。4つ目としては、食への関心が強まることです。料理の画像を頻繁に見るなどの行動も、初期サインのひとつとされています。」
子どもが「食べたくない」と言ったときに「頑張って」はNG
子どもが「食べたくない」や「大丈夫、食べてるから心配しないで」と言うとき、励ましの言葉が逆効果になることもあると、島田先生は言います。子どもが安心して自分の気持ちを話しやすくするために、親が心がけたいポイントを教えていただきました。
島田先生「『食べたくない』という言葉の背景には、体重増加への恐怖や不安があります。無理強いせずに『そうなんだね』と一度受け止め、安心感を与えることが大切です。『大丈夫』という言葉は、心配をかけたくないという気持ちの裏返しであることが多いです。言葉通りに受け取らず、行動や表情の変化に注意を払い、本人が抱える苦しさに寄り添う姿勢を見せてあげるとよいと思います。
『頑張って』『元気出して』といった安易な励ましは、『これ以上どう頑張ればいいのか』と本人を追い詰めてしまうため逆効果です。体型や食事に関する話題は避け、『あなたのことが大切だ』というメッセージを伝え続けましょう。『何かあった?』と聞くよりも、何も言わずにそばにいるほうが、子どもが安心して話し始めるきっかけになることもあります。」
親の価値観が子どもの心に影響することも。親が「大切にしたいこと」とは
島田先生によると、親の無意識な価値観が子どもの心に影響を与えるため、日ごろの言葉が摂食障害の要因になることもあるとのこと。子どもとの関係性づくりに大切なのは、「食べる・食べない」から離れた、安心できる時間の共有だそうです。
島田先生「親が『痩せているほうが良い』『これは太るからダメ』といった価値観を無意識に示していると、子どもは『痩せていないと愛されない』というプレッシャーを感じてしまいます。親自身の体型へのこだわりが、子どもの摂食障害の発症や維持の要因になることもあるため、家庭内の会話や価値観を見直すことも重要です。
食事の話から意識的に離れ、子どもが好きなことや楽しめる時間を共有することが大切です。一緒に散歩をしたり、好きな音楽を聴いたり、映画を観たりするなど、病気とは関係ない会話や活動を増やしましょう。“食べること”を親子の会話の中心にしないことで、子どもの心の負担が軽くなり、家庭が安心できる居場所になります。」
相談先に迷ったときは、まずは身近な医療機関へ
自分の子どもが「もしかしたら摂食障害かもしれない」と思ったときに、まず何をするべきなのか戸惑う親も多いと思います。どこに相談するのがよいのでしょうか。
島田先生「まずはかかりつけの小児科医に相談し、身体的な状態を確認してもらうのがよいでしょう。成長ホルモンの分泌不全など精神の問題ではないこともあるので、安易な自己診断は控えましょう。
小児科で摂食障害と疑われた場合は、精神科や心療内科に紹介してもらうことが重要です。お住まいの地域の精神保健福祉センターや、学校のスクールカウンセラーも初期の相談窓口として有用ですが、必ず医師の診察を受けるフェーズが必要です。何よりも一人で抱え込まず、早めに専門家と繋がることが大切です。」
摂食障害は、親子だけで抱え込まず、周囲と連携していくことが回復への大きな支えになります。次回の記事では、専門家や学校と連携する際に親が意識するとよいことや、親自身の心のケアについてご紹介します。