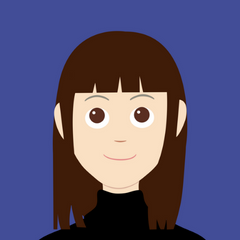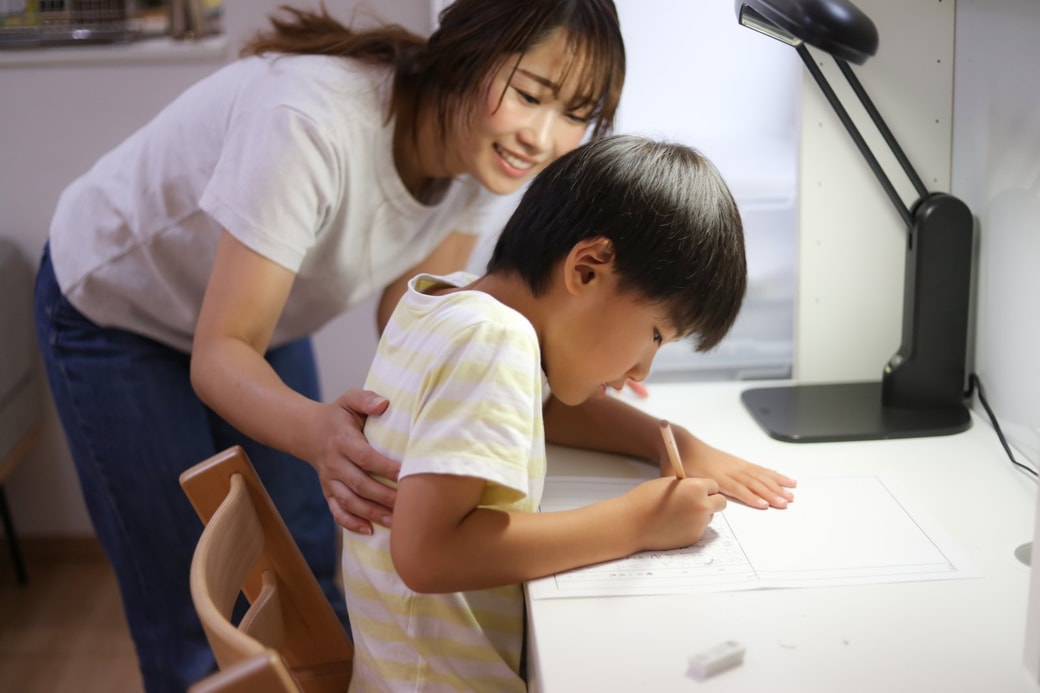何度言っても同じミスばかり。うちの子大丈夫?
朝の準備をしている小6の娘。お母さんが「ランドセルに教科書を入れた?」と声をかけると「うん、入れたよ!」と言ったものの学校から帰宅すると、また教科書を忘れてしまったと話す。「朝も言ったよね?」と再度注意すると、不安そうに「なんでだろう……」と呟く。なんで何度言っても同じミスをするんだろう。
忘れ物が多い、言われたことをすぐに忘れるという現象、実は意欲の問題ではなく、「実行機能」の発達が関係していることが多いのです。
「実行機能」とは、計画や注意のコントロール、目標に向かって物事を進める力のこと。
日常生活で言えば、時間通りに宿題を終わらせたり、約束を守ったりするために必要な力といえます。
小学生では、実行機能がまだ完全には成熟しておらず、使いこなせていない時期です。今回は、実行機能の役割を理解し、その子の状況に応じてサポートする方法を考えていきましょう。
実行機能は、どのように伸ばしていける?
「行動の選択肢」を増やして、自分で決める力を育む
指示を出すだけでは、子どもはその選択肢を自分でコントロールする力がなかなか育ちません。
たとえば「宿題を早く終わらせなさい」と言うのではなく、子どもに「先に算数をやる? それとも国語から始める?」と選ばせてみるのがポイント。
自分で選ぶことで、自分の行動をコントロールしている感覚が生まれ、実行機能の一部である「決定力」を育むことができるんですね。
この方法は、自分の行動に責任を持つ感覚にも繋がり、将来的に計画性や自己管理力の向上にもつながります。
選択肢を与えることで、子ども自身が「どうするか」を考える時間を作るのが実行機能の向上に役立ってくるんですね。
「今」に集中する力を養う
実行機能がうまく働かない原因の一つに、注意が散漫になっていることがあります。
そこで、マインドフルネスや簡単な瞑想を取り入れてみるのも一つの手です。マインドフルネスとは、「今この瞬間」に意識を向け、評価や判断をせずにありのままを受け入れること。
例えば、毎晩寝る前に「今日はどんなことをしたかな?」と自分の一日を振り返る時間を持つことが、注意をコントロールする力を育むきっかけになります。
- 親子で1分程度「呼吸を整える」時間を設ける。
- 夜寝る前、「このときどんな気持ちだった?」と一緒に振り返る。
- フルーツやナッツなど、一つの食べ物をじっくり味わう時間を作ってみる。
「今、何をどんな風に感じているか」「あのとき、どんな風に感じていたか」に目を向けてみるのがおすすめです。
毎日少しずつ行うことで、実行機能につながる「今に集中する力」が身についていくでしょう。
ゲーミフィケーションで楽しく目標達成
実行機能を育むには、楽しい体験がなにより大切。
例えば、宿題や家の仕事をゲーム感覚で進める方法も効果的です。
「算数を終わらせたら、5分間だけ好きなゲームをしてもいいよ」というように、目標達成を楽しさに変換してあげるのもひとつ。
やらなければならないことを「楽しみ」や「報酬」に結びつけるので、意欲も自然と湧いてくるんですね。
「達成感」を感じる瞬間が実行機能を強化する大きな要素となっていきます。
小さな成功を積み重ねることで、自分で計画して行動する力が養われていくでしょう。
「前にも言ったよね」ばかりでも大丈夫
「前にも言ったよね?」が多くても、それは子どもの脳がまだ発達途中であるサイン。
選択肢を与えることで自分で決める力を育んだり、マインドフルネスで集中力を高めたり、楽しいゲーム感覚で目標達成を促すことで、子どもの実行機能を育んでいけると良いでしょう。
「うちの子大丈夫かな?」と心配する時期はあっても、数か月後、数年後は全く別の悩みを抱えているもの。
ゆっくりでも確実に進んでいく子どもの成長を温かく見守っていけるといいですよね。