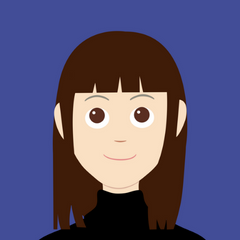朝起きてから、寝る直前まで手元にあるスマホ。
食事中や散歩中、寝る直前ですら手放せないスマホ。
大人も無意識にスマホを手にし、気づいたら時間が過ぎているときは多いのでは。
親自身にとって、SNSがどんな場所になっているかを考えたことはありますか? 学校との連絡手段、家族や友人とのコミュニケーション、仕事や育児の情報収集、趣味で心を癒す時間、、生活に欠かせない存在となっているのではないでしょうか。
では、子どもにとっては?
子どもにとってもSNSはもはや単なるツールではなく、子どもにとっての大切な居場所であり、周囲と調和するために欠かせない軸となっているんですね。それゆえ、時間制限や大まかなルールだけでは通用しなくなってくる家庭も多いよう。特に長期休みに入り普段と異なる生活リズムになるときは要注意。
夏休み、SNSに依存しないための対策を考えていきましょう。
SNS依存にならないための対策とは?
わが子にとってSNSはどんな場所になっているかを知る
一般的なSNSの価値を知るのもひとつですが、わが子にとってのSNSはどのような価値があるのかを知るのが重要です。
例を挙げて考えてみましょう。
中学2年生のAちゃん。姉の影響で始めたInstagramでは自分の描いたイラストを投稿して「いいね」をもらえるのがモチベーションになっている。「いいね」の数が少ないと、投稿を消したり作品を捨てたりするのが親としては気にかかっている。また、家庭内のルールでは夜9時以降はスマホを触らないと決めているのに10時になっても「今LINE抜けると、気まずくなるから」と手放せないときがある。
AちゃんにとってInstagramは、自分が好きなものを表現する場になっていると同時に、作品が認めてもらえないと自信を失う場にもなっているよう。SNSがない時代であれば、Aちゃんの性格を知っている学校の先生や親戚が認めてくれていたかもしれませんが、今は世間が相手となり、「いいね」の数に反映されているんですね。
また、LINEは人間関係を保つツールである一方、リアルタイムでやり取りをしないといけないプレッシャーや仲間外れにされないかと不安に思うストレスも含んでいるといえそうです。
わが子にとって、SNSはそれぞれどんな場所になっているのかを話し合い、そのうえで対策を考えたりルールを決め直したりするのが大事なんですね。
わが子の満たされていない部分を知り、他の方法で補う
わが子にとってSNSがどんな場所になっているのか、SNSで何を満たしているのかを考えることができたら、次のステップへ進みます。
既存のSNSで満たされているものを、他の方法で満たす案を考えていくのが第二ステップ。
例えばAちゃんの場合、
- Instagramでは批判的なコメントや「いいね」の少なさで自信をなくしてしまう。→家族や親戚のみが登録できる非公開アカウントも作成し、「いいね」の数ではなく、身近な相手からのコメントで自信をつけていく。
- LINEでは「今、何を答えるべきか」を考えることが多く、ストレスに。→“今日1日の中で気になったこと・印象に残ったこと”、“実は家族・友達に思っていること”などを交換日記でシェア。振り返る機会・すぐに返事が返ってこない経験を積む。
ポイントは、スマホやSNSを制限する、やめさせるのではなく、今の問題点を洗い出して他の方法に置き換えること。子どもにとって、SNSがどのように機能しているのかを考え、代替案を考えるのがポイントです。
家族みんなでSNSと距離を置く
SNSで満たされる気持ちがある一方、知らず知らずのうちにSNS疲れしているのもまたひとつの事実。
子どもは、自分でセーブするのが難しくのめりこんでいってしまう子も多いので、大人が目をかけてあげるのが大切なんです。
例えば、
- 休日は家族全員スマホを触らない3時間を作る。
- 子どもと同じ時間に、大人もスマホを終える。
- 家族LINEではなく家族連絡帳に置き換えてみる。
“親だってスマホで友達と連絡を取り合っているし、使わないなんて無理”と感じる方もいるかもしれませんが、子ども同様、一刻を争う返信はそんなに多くはないはず。また、家族LINEも便利ですが、あえて紙の連絡帳に置き換えることで一言メモが添えられたり、ほほえましいイラストが追加されるご家庭も。
スマホやSNSは「なくてはならないもの」ではなく、「なくてはならないと思い込んでいるもの」なのかもしれません。この夏はスマホ・SNSなしの充実時間も過ごしてみてください。