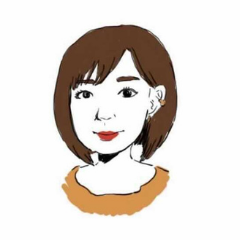教えてくれたのは……松澤 美愛先生
精神保健指定医/日本精神神経学会/日本ポジティブサイコロジー医学会。
東京都出身。慶應義塾大学病院初期研修後、同病院精神・神経科に入局。精神科専門病院での外来・入院や救急、総合病院での外来やリエゾンなどを担当。国立病院、クリニック、障害者施設、企業なども含め形態も地域も様々なところで幅広く研修を積む。2024年東京都港区虎ノ門に「神谷町カリスメンタルクリニック」を開業、院長。
自己肯定感が低い子どもの親の接し方の特徴
自己肯定感が高い子どもと低い子どもには、親の接し方に違いがあると、松澤先生は言います。自己肯定感が低い子どもに共通して見られるのは、親との関係から「人と比較する」思考のクセがついてしまっていることなのだそうです。
松澤先生:自己肯定感が低い子どもの親は、結果を求める傾向があります。たとえ努力をした結果であっても、結果がついてこなければ認めず、努力の過程を褒めることはしません。そのため、子どもは人と比較して優劣を意識してしまい、劣等感を生み出してしまうのです。
否定的な評価やフィードバックを繰り返す状況は、大人になればその関係から逃げることができますが、子どもにとって親は絶対的存在であるため、深く意識に刷り込まれてしまいます。
自己肯定感が高い子どもの親の接し方「3つの特徴」
一方、自己肯定感が高い子どもの親には、以下の3つの特徴が見られるそうです。それぞれのポイントについて、解説していただきました。
1.子どもを「個人」として捉え、個性を尊重している
松澤先生:自己肯定感が高い子どもの親は、子どもに無条件の愛情を示していることが多いです。その背景には、親自身が、自分やパートナーのよいところも悪いところも含めてありのままを素直に受け入れており、大切な存在として認識していることがあります。そのため、親は子どもをさまざまな条件をつけて評価するのではなく、その存在自体を尊いものとして接することができるのです。
また、子どもは自分の所有物ではないことを理解しており、個人としての独自性を尊重して適切にサポートを行います。
2.結果だけを求めず、「ありのまま」を受け入れている
松澤先生:自己肯定感が高い子どもの親は、子どもの行動や成績といった目に見える結果を評価するのではなく、子どもの存在そのものが大切であることを伝えます。たとえ子どもが失敗しても、怒ったり否定したりするのではなく、頑張った過程を評価し、失敗を恐れずにチャレンジを続けることの大切さを教えます。これにより、子どもに成長マインドセットが育まれるのです。
成長マインドセットとは「人間の能力は、学習や経験を通して伸ばすことができる」という考え方のこと。能力は、努力次第で発展するものと考えるものです。成長マインドセットを持つことで、困難に直面した場合にもポジティブに生きることができ、成功を収めやすくなります。子どものありのままを受け入れ、大切にする姿勢を見せることで、子どもに自分を大切することを伝えるとともに、自分同様に相手(他の人)も大切にすることを教えます。
3.自己決定の機会が多い
松澤先生:自己肯定感が高い子どもの親は、子どもが泣いていても笑っていても、自分の感情を適切に表現することを促します。その結果、子どもは感情表現を恐れずにできるようになり、自分の中に感情をため込むことがなく、健やかな心身の成長が育まれます。そうすることで、人との関わりを怖がらずに、積極的に関わっていくことができるのです。
さらに、子どもを一個人として認めて尊重しているため、年齢に応じた自己決定の場を与えていることも特徴のひとつです。自己決定の機会が多いほど、子どもの決断力が養われ、それに伴う責任感も育まれます。ただし、完全に自由奔放に子どもに任せるのではなく、適切なルールや制限などの健全な境界線を設けることも意識できています。子どもが自由に選択できる安心感を与えると同時に、守らなければならない境界線があることも理解し、社会のルールを学んでいけるのです。
自己肯定感の形成には、親の接し方が重要な役割を果たします。子どもの健やかな成長を応援するために、3つの特徴を参考してみてくださいね。