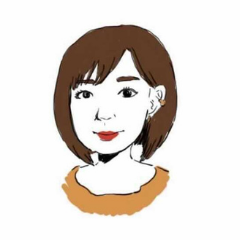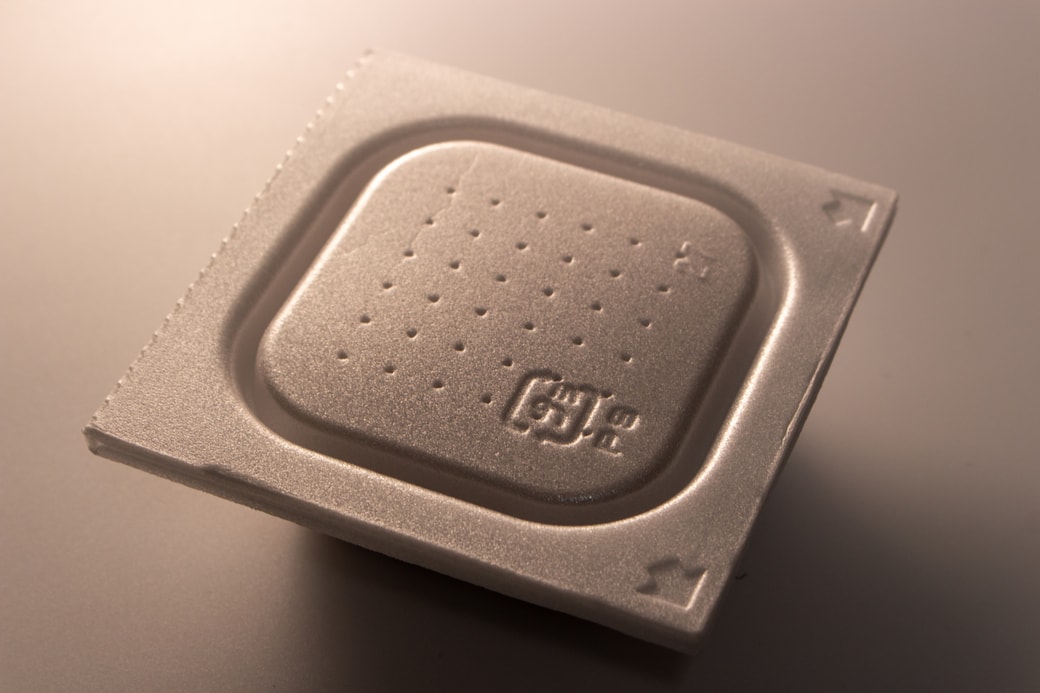教えてくれたのは……管理栄養士 若山あみさん

愛知県にある「あさひの森 内科消化器クリニック」の管理栄養士。クリニックでは保険診療で野菜の栄養と体へのメリットについて栄養指導を行っている。
納豆に含まれる主要な栄養
健康食の代表ともいえる「納豆」ですが、具体的にどのような効果があるのかを知っていますか?
まずは、主要な栄養素7つとその栄養が体にもたらすメリットをご紹介します。
- たんぱく質……筋肉、臓器、皮膚、髪の毛など、体をつくるもとになります。ホルモンや抗体など、体の調子を整える材料にもなり、生命維持に欠かせない栄養素です。
- 食物繊維……便秘の予防、生活習慣病(肥満、糖尿病、高血圧など)を予防します。
- ビタミンK2……血液凝固に関与する栄養素です。骨の形成に関わり、骨粗しょう症の予防に役立ちます。
- ビタミンB2……皮膚や爪、髪の毛などの健康を保つために必要です。
- ビタミンB6……たんぱく質の構成要素である、アミノ酸の代謝を助けます。
- 納豆菌……腸内環境を整え、お腹の不調を改善します。
- ナットウキナーゼ……血栓を溶かし、血液をサラサラにする効果が期待できます。
避けたほうがよい「納豆」の食べ方とは
納豆の栄養素を最大限に活用するためには、“食べ方”も重要なポイントになります。栄養摂取と品質のキープという観点で、避けたほうがよいとされる食べ方は以下のとおりです。
栄養摂取のためには「調理方法」に注目!
納豆に含まれる栄養素のうち、ビタミンK2や納豆菌は熱に強いため、90度前後で数分加熱してもほとんど失われることはありません。ただし「ナットウキナーゼ」は、70度ほどで栄養機能が失われると言われています。
そのため、揚げ物などの高温調理や煮込み料理など、長時間の加熱は避けましょう。そのまま食べるか、低温で短時間の調理がおすすめです。
品質をキープするためには「温度」に注目!
10°Cを超えた状態で保存すると、納豆菌が活発になり再発酵が進むため、粘り気が損なわれて糸引きが不十分になることがあります。アンモニアが発生し、品質に変化が生じる場合があるので注意してください。
納豆を食べる際は、冷蔵庫から出して時間が経ってから食べたり、お弁当などに入れたりして食べることは避けましょう。
「納豆」は毎日がおすすめ!
納豆には、腸内環境を改善してくれるプロバイオティクスの「納豆菌」が豊富に含まれています。納豆菌などの善玉菌は、直接体内に摂り込んでも、全ての菌が腸内に定着するわけではありません。納豆から摂取した菌の多くは、数日で便として排出されてしまいます。
そのため、たまに食べるのではなく、毎日の食事で取り入れることが大切です。
納豆に「ほかの食材」をプラスして効果アップ
最近では、プロバイオティクスとプレバイオティクス(善玉菌のエサとなる成分)を組み合わせて腸内環境を整える「シンバイオティクス」という概念も生まれています。
納豆だけを食べるのではなく、納豆にめかぶや玉ねぎを組み合わせることで、さらに高い腸活効果が期待できますよ!