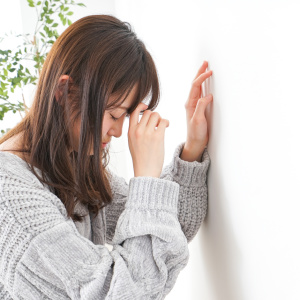教えてくれたのは……徳永 理恵先生

逗子メディスタイルクリニック院長。国立東京医科歯科大学医学部を卒業。同大学病院を経て、横須賀市立市民病院に勤務。2010年、歯科医である夫と共に、逗子メディスタイルクリニックを開院。3人の男の子の母で、乳がん・甲状腺がんの経験者でもある。日本形成外科学会、日本美容皮膚科学会、日本がんサポーティブケア学会に所属。
子どもは「あせも」ができやすい
「大人と子どもは体の大きさが違いますが、汗を作る”汗腺”の数はほぼ同じです。そのため、体が小さい子どもは、皮膚の単位面積当たりの汗腺の数が多く、発汗量も多くなるんです。それに、子どもは新陳代謝が活発で、体温の変化が激しいので、汗をかきやすいんですよ」と話すのは、医師の徳永理恵先生。
さらに、子どもは皮膚のバリアも薄いため、「あせも」以外に「汗かぶれ」も起こしやすいといいます。
汗をかきやすく、あせもができやすい子ども。どんなことに気を付ければ、あせもを防ぐことができるのでしょうか? 徳永先生に、詳しく教わります。
子どもが汗をかきやすいのは、どんなとき?
外で遊んだときはもちろん、寝ているときや起床して体温が上がるタイミングも汗をかきやすいです。また、発熱の後なども、激しく汗をかきます。
最近では、冬でも乳幼児にあせもができることがあります。その原因は、厚着です。「子どもが寒いとかわいそう」「風邪を引いたら大変」と、暖かい部屋で必要以上に厚着させると、あせもにつながってしまいます。
「あせも」にも種類がある?
ひと口に「あせも」といっても、いくつかの種類があり、汗がたまる部分の深さで症状が違います。
水晶様汗疹「白いあせも」
皮膚の浅い部分(角質の下)にできる「白いあせも」は、水晶様汗疹というもの。かゆみのない小さく透明な水疱で、数日で治癒します。このあせもは顔にできることが多く、とくに目の周りなどにできやすいです。
紅色汗疹「赤いあせも」
皮膚の少し深めの部分(表皮)にできる「赤いあせも」は、紅色汗疹。かゆみを伴うことがあり、肘の内側や脇の下、おなかなど熱がこもりやすい部位によくできます。体温が上がると、それを下げるために汗が出ますが、子どもは短時間で汗が出ることも多いため、表皮内の汗管に汗がたまり、表皮の中に汗が漏れ出すことで、この種のあせもができやすくなります。
深在性汗疹
皮膚の深めの部分(真皮)にできるのが、深在性汗疹です。かなり高温多湿の限られた環境で起こるもので、熱中症を伴うこともある汗疹です。汗管の深い部分の病変で、平らな赤味のない発疹です。このあせもは、紅色汗疹を繰り返して起こるので、やはり熱のこもりやすい部位にできやすいです。
あせもの予防法は?
汗をかいたらこまめに拭いたり、シャワーで洗い流したりするほか、吸湿性の高い服を着ることなどで予防できます。
たびたびシャワーで体を洗う場合は、皮膚のバリア機能を損なわないよう、毎回石鹸やボディーソープ、ナイロンタオルやスポンジを使わずに、ぬるめのお湯をかけるだけにする方がいいでしょう。石鹸などを使う場合は、よく泡立てた泡を体につけ、手のひらで優しく転がす程度にし、入浴後はしっかり保湿するようにしましょう。
あせもができてしまった場合は?放っておくと、どうなる?
まずは、先ほどご紹介した予防法を継続することです。
さらに、あせもができて炎症の起こっている皮膚は、とくに敏感になっており、乾燥しやすいので、保湿を心がけてください。ベビーパウダーなどは刺激になるので、使いません。
かゆみがあると搔き壊してしまうことがあります。かゆみを和らげるには、冷やすのも効果的ですが、それでもかゆがるときは、薬を塗りましょう。
掻き壊すのを放っておくと、傷ができ、そこから細菌が感染し、伝染性膿痂疹(とびひ)などの原因になることがあります。たかがあせもと侮らず、広範囲にできているときや、炎症の強いときは、皮膚科にかかるのをおすすめします。
子どもがかゆがると、見ているだけでかわいそうですよね。徳永先生に教わった予防法を実践して、今年の夏はあせもとは無縁で過ごしたいですね。