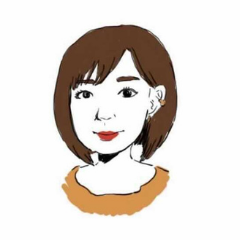教えてくれたのは……清水 聖童先生

精神科専門医・医療法人社団燈心会ライトメンタルクリニック理事長。心理療法、生活習慣、栄養学など幅広い知識を背景とした精神予防医学を専門とし、病前から介入する精神医療を模索したクリニック「ライトメンタルクリニック」を立ち上げる。メンタルヘルスに関する記事監修や講演、取材対応も積極的に行い、専門的な知見を広く発信している。
「幸福度を高める」他人と比べない考え方「5つのコツ」
つい人と比べてしまって落ち込むことはありませんか? 他人との比較が、幸福度を低くしてしまう要因のひとつになると清水先生は言います。
清水先生:現代社会では、SNSなどを通じて他人の生活が簡単に見えるようになった分、自分との違いに敏感になり、無意識に比較してしまう人が増えています。「あの人はすごいのに、自分は」と落ち込んでしまう瞬間、誰しもあるのではないでしょうか。精神科の現場でも、こうした比較思考が自己肯定感を下げ、幸福度を損なう原因になることがよくあります。
清水先生によると、他人と比べずに幸福度を高めるためには考え方のコツは5つあるとのこと。それぞれ詳しく教えていただきました。
1.自分の軸を持つ
清水先生:「他人がどうしているか」ではなく、「自分はどうしたいか」に意識を向けることが大切です。誰かの基準ではなく、自分の価値観や目標に沿って行動することで、他人と比べる必要がなくなります。軸がしっかりしている人は、周囲の意見に振り回されず、心の安定を保ちやすくなります。
2.小さな成功体験に目を向ける
清水先生:他人と比べる代わりに、「昨日より少し早く起きられた」「今日は丁寧に料理できた」といった、自分なりの小さな前進を見つけてみましょう。このような積み重ねが自信となり、自然と自己肯定感が育まれていきます。
3.情報との距離をとる
清水先生:SNSなどの「キラキラした誰かの一面」は、現実のごく一部であることを忘れてはいけません。見れば見るほど「自分は劣っている」と感じてしまうときは、意識的に距離を置くのも効果的です。スマホを置いて、自分の時間を過ごすことが、心のリセットにつながります。
4.「今の自分」に意識を向ける
清水先生:過去や未来、そして他人の人生と比べるのではなく、「今、この瞬間の自分はどう感じているか」に注意を向ける習慣は、マインドフルネスと呼ばれる実践にも通じます。感情や感覚を否定せずに受け止めることで、心の安定感が増し、自分のペースで人生を歩めるようになります。
5.比較より「共感」を意識する
清水先生:「あの人にはあの人の苦労があるかもしれない」と想像することで、単なる競争心ではなく、共感の気持ちが生まれます。他人を応援したり、自分と違う生き方を認められるようになると、気持ちにゆとりが生まれ、自分自身にも優しくなれるはずです。
比べなくても満たされる感覚を育む
意識していても、つい比較してしまう癖が抜けずに悩んでいる方も多いかもしれません。どのように心を整えていくとよいのでしょうか。
清水先生:比べないことは、簡単なようでいて実はとても難しいことです。ただし、自分の軸を見つけ、小さな一歩を積み重ねていくことで、「比べなくても満たされる感覚」は誰にでも育てていけます。焦らず、自分のペースで心のトレーニングをしていきましょう。