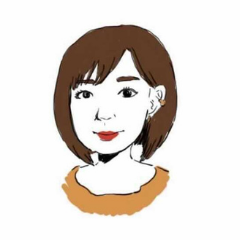教えてくれたのは……吉田 美智子先生

臨床心理士、公認心理師。はこにわサロン東京・代表。
スクールカウンセラー、教育センター相談員などを経て、2016年はこにわサロン東京を開室。主な技法は、ユング心理学に基づいたカウンセリング、箱庭療法、絵画療法、夢分析。子育ての相談、親子関係、トラウマケア、ストレスケア、アンガーマネジメントなどの相談に携わる。
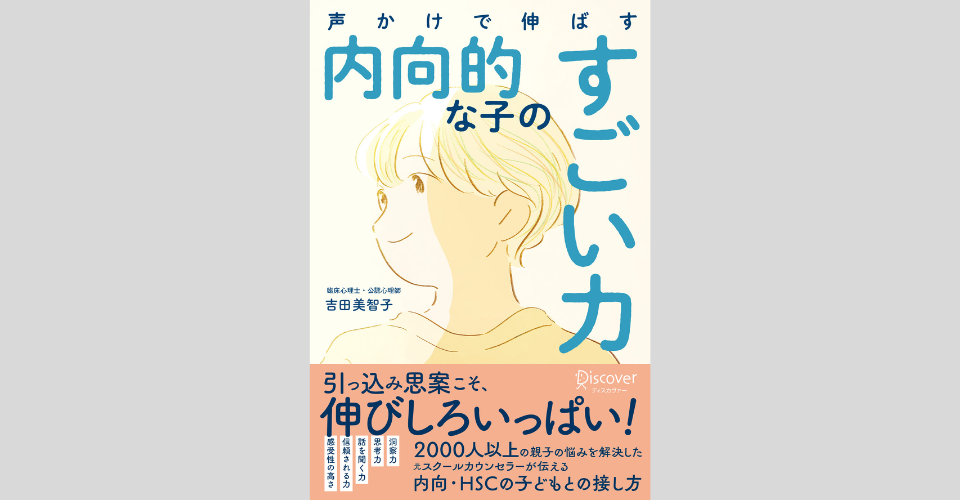
『声かけで伸ばす 内向的な子のすごい力』(株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン)
著者:吉田 美智子
定価:1,760円(税込)
宿題をすぐにやらない子との親子バトルにヘトヘト…
親は「学校から帰ったらすぐに宿題をしてほしい」と思っているのに、子どもがすぐにやろうとしなくて困っているという声をよく耳にします。宿題をやらない子どもに対して、どのように対応するのが適切なのでしょうか。
吉田先生「子どもは、寝るまでの時間の使い方を自分なりに考えていて『宿題は先じゃない』と思っているんですよね。親としては、寝る前になって子どもが慌てることが見えているので、口出しをしたくなるものです。
特に10歳ごろになると思春期の入り口になり、『大人の言うとおりにしたくない』『自分のやり方でやりたい』『言われなくてもわかってる』という年頃。どうしても親の言葉が子どもに届きにくくなってきます。
だからこそ、『親のほうが言っていることが正しい』と親のやり方を押しつけてしまうのはNGです。かと言って、親の考えを伝えること自体が悪いわけではありません。子どもに従わせることを強制しないように、バランスをとることが必要なんですね。
まずは、子どもの言うとおりにやってみることが大事です。子どものペースを認めて大目にみてあげると、うまくいくこともありますよ。」
子どもの中の「こうやりたい」を尊重する
内向的な子どもは特に、子どものペースを見守ってあげてほしいと、吉田先生はおっしゃいます。
吉田先生「外向的な子どもは親との着地点を見つけやすいのですが、内向的な子どもは自分のやり方があるので、外向的な子どもよりも心の中で引っかかりを感じやすい性質をもっています。子どもの中で『こうやりたい』という気持ちがあるのはすごく大事なことで、この気持ちを育ててあげたいですよね。
内向的な子どもほど、本人のやり方をできるだけ尊重してあげてほしいと思います。親は忍耐力が必要になってくるので難しい部分にはなりますが、大事なことだと思ってもらえたらいいですね。」
子どもに伝えるときに意識したい「3つのポイント」
子どもを注意するときに、あれこれ言いたくなってしまい、つい長くなってしまう親の小言。子どもに伝わりやすくするために意識したい「3つのポイント」を吉田先生に教えていただきました。
1.一度にひとつだけ
吉田先生「『〇〇したほうがいいよ』『〇〇してほしいな』など、シンプルに短い言葉で伝えることが大事です。
『昨日も言ったよね』『だから言ったでしょ』『だいたいいつも……』などの言葉はぐっと飲み込んで、心の中に留めておくほうがいいと思います。このような言葉がつくほど子どもに伝わりにくくなり、親子関係が悪くなってしまう可能性もあるからです。長時間叱らないようにしたほうがいいですね。
それでも、どうしても言いたくなるときもあると思います。そんなときは『どうしてこんなに子どもに不満があって、言わないと気が済まないのか』、気持ちの棚卸しをしてみるといいと思いますよ。実は自分に余裕がない場合や他に不安がある場合もあるかもしれません。感情を子どもに向けるのではなく、ご自身や信頼できる人とでもいいので一度振り返ってみることも一つです。」
2.失敗も体験させる
吉田先生「たとえば、宿題をやると言っていたのに、始めようとした時間が明らかに遅い時間になってしまったときに、その場で注意しても子どもの耳には入っていないので伝わりません。
伝えるベストなタイミングは、翌日に学校から帰ってきて『宿題は後でする』と子どもが言ったときです。『昨日それで寝るのが遅くなったよね。順番を変えたらいいと思うんだけど、どう思う?』と子どもに考えてもらう方法をとれるといいですね。
とはいえ、1回で直ることはあまり多くないので、大半の子どもは同じくり返しをすると思います。親が『こうしなさい』と指示してやってもらうよりも、失敗も黙認して体験させながら、子ども自身が『この順番のほうがいいな』と気づけるようにすることが大事ですよ。」
3.ウソを問い詰めすぎない
吉田先生「もし子どもが宿題をやっていないのに『やった』とウソをついた場合、あまり問い詰めすぎないほうがうまくいくことが多いと思います。叱るとますますウソが増えてしまって、逆効果になることも考えられるからです。
ウソの内容にもよるので難しい部分もありますが、『これはウソだな』と親がわかる程度の軽いものであれば、受け止めて流すくらいがいいかもしれません。そのほうが子どもが自分のペースで取り組む力を育むことができて、親子関係も悪くならないと思いますよ。」
「早くやりなさい」ではなく、見守る姿勢がとれるようになると、子どもの自立心を育むための一歩になるようです。吉田先生に教えていただいた対応の仕方をぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。