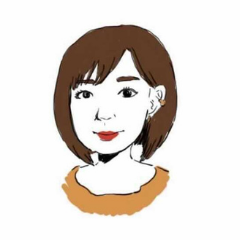教えてくれたのは……浅原 謙さん

法政大学工学部(現デザイン工学部)卒業。学生時代に首都圏学習塾にて講師を務め、5年間の講師生活後、東京都内の飲食コンサルティング会社に入社。3年目に取締役に就任。2016年に合同会社ファーストステップス(2017年に株式会社へ組織変更)を設立、同時にファーストステップス+未来塾の塾長に就任。中学生時代の塾の講師との出会いにより劇的に成績が伸びた経験から、何事もきっかけと自身の目標があれば変わることができると子どもたちに伝えている。
内申点を上げるためには「前向きな姿勢」が大切
前回の記事では、「内申点の基礎知識や地域ごとの取り扱いの違い」などについてお話を伺いました。内申点を上げるためには、日ごろからどのようなことを意識して子どもに学習に取り組んでもらうとよいのでしょうか。
浅原さん「どの教科においても、中間・期末テストの点数だけではなく、学習に取り組む姿勢がとても大切です。たとえ苦手な科目であっても、前向きに努力しているかどうか、チャレンジしようとする意欲があるかどうかが評価されるポイントになります。例えば、英語の授業ではALTの先生(外国の先生)とのコミュニケーションが求められることが多いですが、内気で発言が苦手な子どもであっても、その中でどれだけチャレンジしようとしたかを、先生たちはしっかり見てくれているはずです。
また、小テストや提出物も意外と見逃せない重要なポイントとして考えられています。高校側としては卒業までしっかり3年間通える生徒を求めているので、普段どのように取り組んでいるかという評価をチェックしたいと考えるからです。」
「ノート」を見れば、子どもの状態がわかる
学習の意欲を見るポイントのひとつに「ノート」の取り方も挙げられるのだと、浅原さんは言います。ノートには子どものさまざまな様子が表れるそうです。
浅原さん「先生によってはノートの提出を求めることもありますが、絶対的な評価のポイントになるというよりも、丁寧に書こうとしているか、頑張っていることが伝わるかといった姿勢を確認しているのだと思います。先生たちもプロなので、字を見れば気が抜けているかどうかを一瞬で見抜くことができるんですよね。
また、理解の度合いだけでなく、疲れ気味かどうかなどの心理状態もノートに表れます。ノートの状態が普段と異なる場合、疲れていたり、何か問題があったりするサインかもしれません。例えば、筆圧がいつもより薄い、消しゴムを使って書き直しをしないなどが見られると、『眠かったのかな』『何か嫌なことがあったのかな』など、ノートを見れば子どものさまざまな状態がわかります。」
学習面だけではなく、幅広い活動が内申点アップに影響するという噂を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。その中には「これって本当?」と疑問を感じるものもありますよね。次回の記事で、詳しくご紹介します。