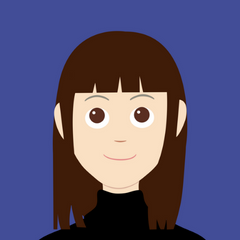「まずはAIに相談」が定番
「昨日学校で嫌なことあって、だから家でもイライラしていたんだよね」と打ち明けてくれた娘。「そうだったんだ。何があったの?」と尋ねると、「AIに聞いてもらって解決したからもう大丈夫」と。自分の気持ちが整理できたようでよかったと感じる一方、「AIに聞くってどうなんだろう」、「親はもう頼りにしていないのかな」とモヤモヤ。
大人も子どもも、AIに悩みを相談する方が増えています。
これまで親や友人、先生に相談していたり、ときには自分自身で抱え込んでいた悩みを、チャットやスマートスピーカーが受け止めてくれる時代になっているんですね。
子どもの相談相手がAIになっている時代、親はどのように子どもを支えていけばよいのでしょうか。
小学生がAIに相談する理由
AIに相談するメリットは「否定されない」「誰にもバレない」「気を使わなくていい」安心感にあるといえます。
24時間いつでも話を聞いてくれて、どんなことを言っても怒らないし、驚きもしない。自分の感情をそのまま出しても、ジャッジされないということが、心の拠り所になっているんですね。
子どもはときに、「親が忙しそう」「言ってもどうせ怒られるかも」という思いが背景にあることもあります。
AIのような中立的で冷静な相手に、まず話をすることで、自分の気持ちを整理する練習をしているとも捉えられるんですね。
「親に話さない=信頼していない」ではない
親としては、「なんで自分には話してくれないの?」と寂しく感じるかもしれません。
しかしそれは、必ずしも信頼がないから、優先順位が低いからではありません。
小学校高学年にあたる10〜12歳ごろから「心の自立」が始まります。AIに相談して気持ちを調整する力がついているのは、むしろ健康なサインともいえるんですね。
AIを“第一の相談相手”にしていても、親が“最後の安心できる場所”であれば、子どもは心のバランスを保つことができます。
必要なのは、“話させる”ことではなく、“話せるときに話せる環境”を整えること。
親の立場はAIにとって代えられるものではないと、自信とゆとりをもって構えているのが大切なんですね。
親にしかできない、二つの役割
AIを「親子で一緒に使う」
子どもにとってAIを“内緒の居場所”にしてしまうと、親子の間に見えない壁ができます。
だからこそ、AIを親子の間に置くという発想がポイント。
たとえば、「今日、AIになんて聞いたの?」と聞いてみたり、「ママも聞いてみようかな」と一緒に使うことで、子どもは「自分の世界を共有してもいいんだ」と感じるようになります。
AIが、“親子で使うツール”になると、親子の絆は保ちやすくなるでしょう。
AIと「違う価値」を見せる
AIはいつでも冷静で論理的に答えてくれます。
一方、“生身の人間らしい温かさ”や“あいまいな感情の揺れ”を持っていません
親ができるのは、「答えを持っている存在」ではなく、「一緒に迷ってくれる存在」になること。
たとえば、子どもが「AIに“自分を信じて”って言われた」と話してきたとき、「ママはね、自分を信じられない日もあっていいと思うよ」と返すなど。
”AIは言わない、ゆらぎのある言葉”に、人間らしい温かみを感じ、心が軽くなるときもあるでしょう。
子どもにとって、一緒に迷って悩んであげる存在が何よりの支えになるときもあります。
AIが正しい道を示してくれるなら、親は寄り道の中にある楽しさや味わいを伝えてみてもよいかもしれません。
日々成長する子どもと進化し続けるAI。どちらの成長も見守りながら、三者で共存していけるといいですよね。