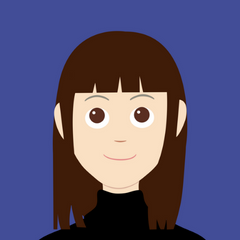「AIが言っていたから大丈夫」は本当に大丈夫?
小6の息子、最近宿題を終えるのがやけに早い。「苦手だった算数の文章題もできたの?」と尋ねると「ChatGPTに聞いたからわかってる」、「どう考えたの?」と聞くと、「AIがこう言ってたから」とだけ返ってきた。確かに便利だけど、考える力は育っているのだろうか。
最近、小学生たちの間で「先生は間違えることがあるけどAIは正しい」「授業よりYouTubeの方がわかりやすい」などの意識が広がりつつあります。
学校の授業よりもAIやインターネットで情報を得る方が効率的だと感じる子どもたちが増えているんですね。
教育への信頼が揺らぐ変化に対して、親としてどう向き合うべきか、どんなサポートが必要なのか考えてみましょう。
AIと人間の「学び」の違い
AIは「知識」を素早く提供してくれるため、学校の授業が「遅い」「無駄」と感じる子はAIを使った学習を好む傾向があります。一方、「人間らしい学び」には対応できないのが現状。
例えば、現実場面での人間関係スキルや感情の理解、協力する力など「社会的な学び」は、AIが教えることができない分野です。
AIが得意とする分野、生身の人間にしかできない分野、どのように分けて理解していくのがよいのでしょうか。
AIが得意な分野
算数の解き方や計算の練習
AIは計算ミスを瞬時に指摘し、なぜ間違えたかを丁寧に説明してくれます。
文章題に関しては質問の仕方を工夫すれば順を追って段階的に教えてくれるので、つまずきやすい子どもにもわかりやすいサポートが可能です。
英語の発音やリスニング練習
AIはネイティブの発音で繰り返し会話の練習ができ、発音のずれも指摘してくれます。
人前では気恥ずかしくて話せない子どもも、AI相手なら学びやすくなることも多いよう。
個別に合わせたドリル学習
継続的にAI学習を行っている場合、子どもの正答率や苦手分野を分析し、レベルに合った問題を自動で選んでくれます。
一人ひとりにぴったりの学習ができるのは、AIならではの強みといえるでしょう。
人にしかできない分野
誰かと話しながら深める国語の読解
登場人物の気持ちや、場面の読み取りは、AIも人間に寄せた回答はできるものの、友達や先生、親子と話し合う中でより深まり味わい深くなるものです。
共感や想像力は、AIの力を遥かに超えるんですね。
自由研究や探究学習の方向づけ
「なぜそれを調べたいの?」「どうしたらもっと面白くなる?」と問いかけ、子どもが自分の関心を深めていくプロセスには、人の関わりが欠かせません。
子どもが自分で考えて、自分で決定する力は人のサポートが必要不可欠といえるでしょう。
交友関係の中で育つ力
協力、対話、思いやりなどの力は、普段の生活や学校の中で他者と関わることで育ちます。AIは理論は教えてくれたとしても、実践、失敗、学びがなければ心の成長に寄与しません。
必要なのは「否定」ではなく「共存」
今の時代、AIを否定するのではなく、これらのツールをどう使うべきか、共存していくのがよいかを一緒に考えていくのが重要です。
しかし、AIに子どもを託すのではなく、子どもとAIが適切に共存できるように周囲の大人がフォローすることが大切。
例えば、宿題をやるとき、なんとなくスマホを触る。少し息詰まるととりあえずググる。
そのような使い方よりは、何のためにAIを活用するのか、目的を定めた方がよいでしょう。
そして、親が時間に余裕があるときは「どうしてその答えにたどりついたのか」「その情報はほんとに正しいのか」を問いかけて会話ができるとなお有意義な学習になります。
親子ともに頭の片隅に置いておいていただきたいのは「AIはたまに嘘をつく」こと。
バージョンが古いままだと最新の情報とは異なっていたり、曖昧なやり取りでAIがうまく処理できなかった場合は適当な情報を混ぜて回答することがあるんですね。
AIを“間違いない、わかりやすい、すごいもの”とシンプルに解釈している子も多いので、親がAIやネットの脆弱性や信ぴょう性を伝えていけるといいでしょう。