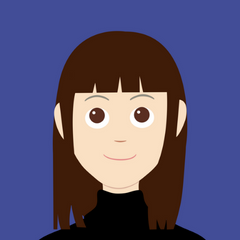スマホの時間を守れない子どもにイライラ
「もうスマホの時間終わりだよ」「いつまでやってるの、いい加減にしなさい!」
小6の息子とスマホの制限時間を決めたものの、なかなか切り替えられず、最近は毎日スマホ問題でイライラ。帰宅してすぐにYouTube、夕飯中もチラチラLINE、寝る前もゲーム。
注意すれば「今やめようと思ってたのに!」と反抗的な態度に。注意してもお互いイライラするし、かといって放っておくわけにもいかないし。どうすればいいのだろう。
このように、スマホ関連の親子喧嘩で悩むご家庭は多く、ご相談も増えています。
スマホに依存していると捉え、いかに引き離すかを考えるべきか。それとも子どもにとってスマホがどのような存在なのかを考えて付き合い方を見直していくべきか。
親子ともにストレスの減る関わり方を考えていきます。
スマホは単なる「逃げ場」ではない
まず親が知っておきたいのは、 スマホ=ただの遊び道具ではないという視点です。
高学年になると、学校や友だちとの関係で気を張ることが増え、家ではほっとしたい気持ちも強くなります。
そのとき、スマホや動画は「現実から逃げたいツール」ではなく、気持ちを落ち着ける“安心スイッチ”として機能していることが多いんです。
たとえば、大人が疲れたときにテレビやSNSを見て“無”になりたくなるように、子どもも「何かしていないと落ち着かない」気分を抱えていることがあるんですね。
スマホを頭ごなしに取り上げてしまうと、心の安全基地を失ったような不安感が生まれてしまうので注意したいところです。
「制限」ではなく「ガイドライン」を一緒に作る
スマホとの付き合い方は、絶対的な正解があるわけではありません。
親の考え方、子どもの年齢や性格によって、その都度柔軟に変更していく必要もあるでしょう。
ルールを決めるときに重要なのは、「どうすればトラブルなく使えるか」「どこで使うと安心か」を、親子で話し合いながらガイドライン化すること。
たとえばこんな話し合いがおすすめです。
- 「平日は何時までにやめられそう? 友達は何時までの約束の子が多い?」
- 「親が使いすぎないように制限をかける方がいい? 自分でセーブする方がいい?」
- 「SNSを見てイヤな気持ちになったときはどうしたらいいと思う?」
「やらされてる」ではなく「自分で決めた」という意識をもってもらうのが大切。
一緒に決めたと感じられると、ルールの定着率がぐんと高まります。
子どもの世界を否定しない
もう一つ大切なのは、「スマホを通して子どもをジャッジしない」こと。
「またそんな動画?」「くだらないゲームばっかりして」などとネガティブなジャッジを口にしてしまうと、子どもは”自分の世界を否定された”と感じるように。
親から見たらくだらないように見えても、子どもにとっては心の拠り所となっているものも多いんです。
子どもを直接否定する言葉がけはもちろん、子どもの世界を否定する言葉がけも避けたいところ。
「その動画、何がおもしろいの?」「好きなゲームのどこが一番好き?」と、興味を寄せてみるだけで、親子の距離はぐっと変化していきます。
”子どもとスマホの付き合い方”を見直すと同時に、”親と子とスマホの付き合い方”もブラッシュアップできるといいですよね。
「行動を変えさせる」のではなく「見方を変える」
スマホをやめさせたい。けれど、強く言えば反発される。
そんなとき、行動を変えようとするよりも、「子どもにとってスマホはどのような存在なのか」という心の背景に目を向けることが大切。
小学校中学年~高学年の時期は、「誰かに見守られながら自分の世界を持つ」ことが健全な成長に繋がります。子どものスマホ使用に悩まされたときは、親子関係を見直すチャンスと捉え、思春期にさしかかっている子どもの心を見つめてみてください。