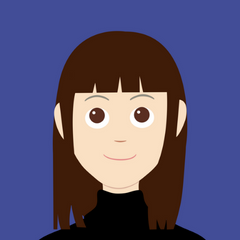“ほどよく”が苦手なわが子が心配
小学5年生の娘は、低学年の頃から板書を丁寧に取る子で先生からもよく褒められていた。しかし最近はきれいに書こうとするあまり、何度も消して書き直し、板書に遅れたり、宿題の最中も文字のゆがみが気になってかなり時間がかかっている。丁寧に書くのはよいことだけど、もっと要領よく、適度に手を抜いたほうがよいのではと見ていて心配になる。わが子のプチ完璧主義、どう付き合っていけばよい?
完璧主義の背景には、さまざまな特徴が隠れていますが、ひとつの要因として「自己観察力の高さ」があげられます。
自分の姿勢、作品の見栄え、周囲の人の反応など、常に自分を客観的に見る力が強いのですね。
その力は長所ともいえる一方、過剰になると「常に監視されているような疲れ」を生んでしまいます。
いわば、“自己観察疲れ”の状態。
そんな子には、親が「あなたを見ているよ」ではなく、「あなたの外の世界を一緒に見よう」と視点を外に向ける関わりが有効です。
たとえば上記の例では、ノートの取り方について言及するのではなく、「今日の授業で面白かった話あった?」と聞いてみるなど。
“どう書けたか”から“何を感じたか”に話題を変えることで、過剰な自己評価のループから抜け出すきっかけになります。
“ほどほど感覚”を体験させる
こだわりの強い子や、完璧主義の子は「8割できていても失敗」と感じているケースが多いです。
そこで大切なのは、“あえて不完全なまま終わらせる体験”を親が仕掛けること。
たとえば、
- 料理の盛りつけを一緒にして、「今日はちょっと傾いたけど、これも可愛いね」と一言添える。
- 「5分だけでここまでできたらOKにしよう」と“時間で区切る完了”を教える。
- 「今日の掃除は手抜いちゃおうかな」「大体でいっか」など、大まかに考える姿を見せる。
こうした体験を通して、「完璧じゃなくても完成していい」「終わらせる勇気も大事」という“ほどほど感覚”を育てます。
”完璧じゃないと気持ち悪い”ではなく、”ほどほどが心地よい”と体感することで少し手を抜く感覚を身につけていけるでしょう。
「評価をリセットする時間」を作る
完璧主義の子は、一日の終わりまで“自分を評価し続ける”傾向があることも。
「今日は~がうまくいかなかった」「もう少しこうすればよかった」など、反省やネガティブなことを思い出し、自分で自分を厳しく評価する癖がついている子も多いんですね。
そんなとき親ができるのは、“反省モード”から“リセットモード”への切り替えです。
おすすめは「3つの気持ちタイム」。
夜寝る前に「今日ちょっと嬉しかったこと」「ちょっと疲れたこと」「明日楽しみにしてること」を1つずつ話すだけ。
良し悪しの評価ではなく、“感じたまま”を言葉にする時間が、心の緊張をゆるめます。
完璧主義の子に必要なのは、「よりよい自分になるためのアドバイス」ではなく、「心のリセットの仕方を教えてくれる大人」なんですね。
「もっと頑張って」ではなく、「もう自分を見つめすぎなくていいよ」と声をかけてあげられると、少しずつ肩の力を抜いていくことができます
”心地よいほどほど”を身につけて、毎日をより楽しく元気に過ごしていけるといいですよね。