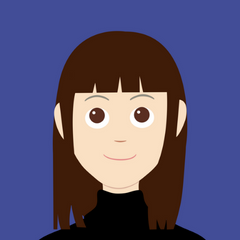「楽しいけど、疲れる」とつぶやく娘。大丈夫かな?
小学5年生の娘は、最近度々「楽しいけど、ちょっと疲れた」とつぶやくように。
クラスでも課外活動でも仲のいい友達はいるけれど、グループの会話では「自分の発言で雰囲気が変わる気がして怖い」と言う。LINEのグループでも、既読をつけたあとすぐに返信しないと「なんで無視したの?」と聞かれることがあり、気が抜けないそう。自分を表現するよりもその場の空気を優先するわが子、大丈夫かな?
「他人からどう見られるか」という意識は中高生あたりから芽生えるイメージがありますが、今は小学生から見られるように。
その背景には、SNSや動画配信文化など、“自分を外から見る機会”の多さがあります。
写真を撮るときのポーズや、投稿に対する「いいね」の数などが日常的な比較対象になり、「他人の目を通した自分」を意識せずにいられない環境。
これは“社会的自意識”が早く芽生えている証拠といえます。
この段階で大切なのは、「敏感であること=悪いことではない」と親が理解すること。
一方で子どもの”どう見られてるかアンテナ”を少し緩めてあげる関わりが支えとなってきます。
「どうすればいい?」より「どう感じた?」を聞く
「人間関係が疲れる」と子どもが言ったとき、親はつい「じゃあ少し距離を置いたら?」「別の友達と遊べば?」と“解決策”を提示しがち。
しかし、子どもは正解を求めているわけではありません。
むしろ、「そのとき自分がどう感じたのか」を整理する手助けを必要としています。
ポイントになるのは”感情のラベリング”。
たとえば
- 「疲れた」って、どんな感じ? 頭がぐるぐるする? 静かにしたい感じ?
- 「ムカついた」の中に、悲しいとか不安な気持ちはあった?
- 「別に」しか言葉にできないくらい、考えたくない日なんだね。
親が“気持ちの翻訳者”になってあげることで、子どもは他人軸ではなく“自分軸の心”を取り戻せます。
”そうそう、そんな感じ”、”ああ、自分ってそう思ってたんだ”と感情を言葉にしていけるようになると、少し気持ちが軽くなってきます。
”家庭=心のオアシス”になるために、親ができること
“話さなくてもつながっている”空間づくり
「沈黙を共有できること」で、”無理しなくていいんだ、そのままでいいんだ”と感じられるようになります。
たとえば、
- 夕食後に一緒にテレビを見る。
- 音楽だけが流れる空間で家族各々好きなことをする。
- いつでもつぶやいたり、話しかけたりしてもいいようなゆったりとした雰囲気。
親は“同じ空間にいる”ことが大事。
このとき、親の機嫌や忙しさを気にかけなくてもよいように、リラックスした状態で同じ空間にいてあげられると子どもの心はしっかりと休まります。
「話さなくても、自分は受け入れられている」と感じ、心が充電できる時間を作れるといいですよね。
“小さな家族ルール”を一緒にアップデートする
「家ではこうあるべき」という固定ルールが多いほど、子どもは外の世界と同じ“評価の緊張”を感じます。
そこでおすすめなのが、家族でルールを緩める会議。
たとえば、
- 「夕食のときは必ず全員そろう」を「疲れた日は、あとから一緒にデザートだけでもOK」にする。
- 風呂掃除や食器洗いなど、決まっている役割について、”有給制度あり”にする。
- 週に1日だけ、ゲームや夜寝る時間を子どもが決めてよいことにする。
家の中に“選べる余白”を作ってあげられると子どもの気持ちが楽になります。
なんとなく決めていた家庭ルールを、年齢に合わせて柔軟に変更していくのも大切なプロセス。
家庭での柔軟な時間が、子どもに「自分の状態を選んでいい」という感覚を育てていくんですね。
人の目から解放されると、少しずつ「無理のない自分」が形作られていきます。
家庭が“誰の目にもさらされない自分”でいられる居場所になるといいですよね。