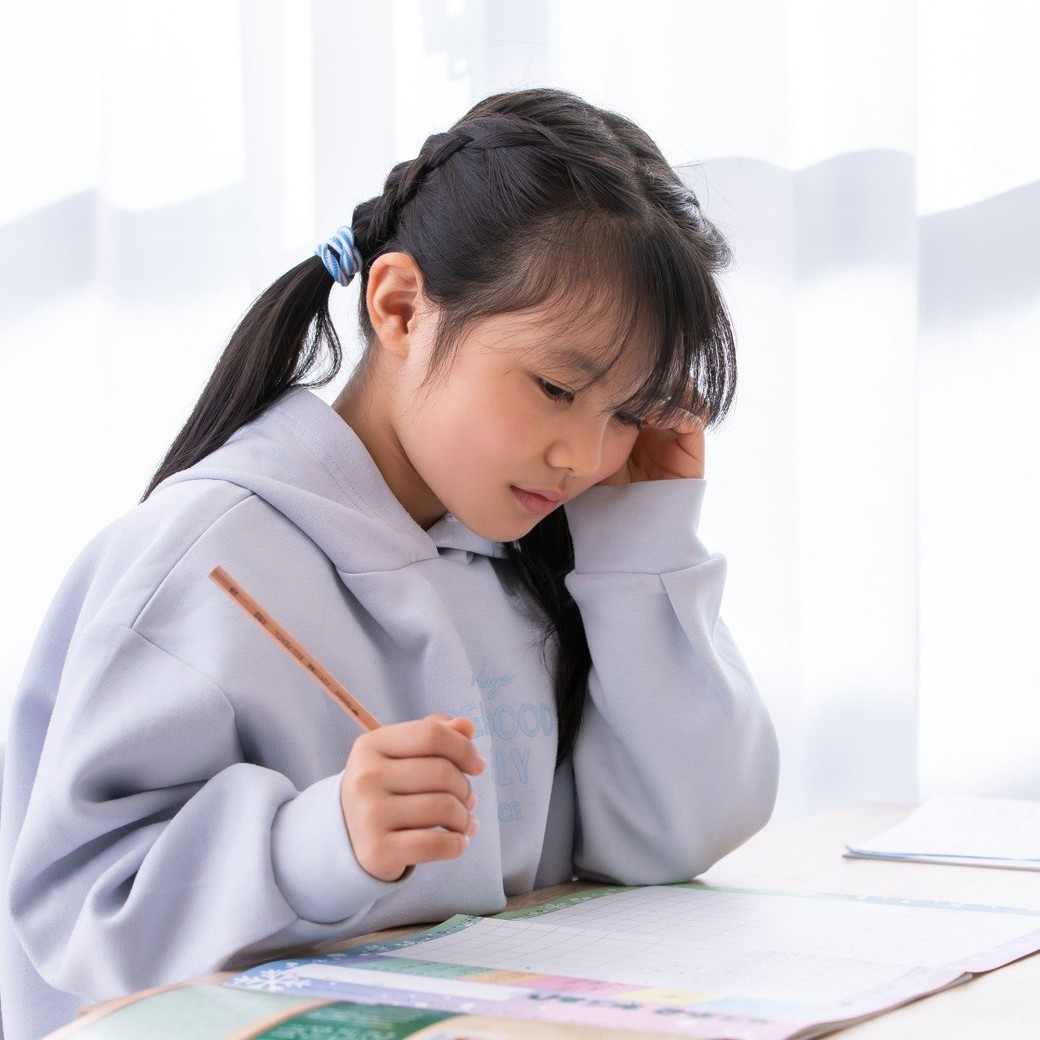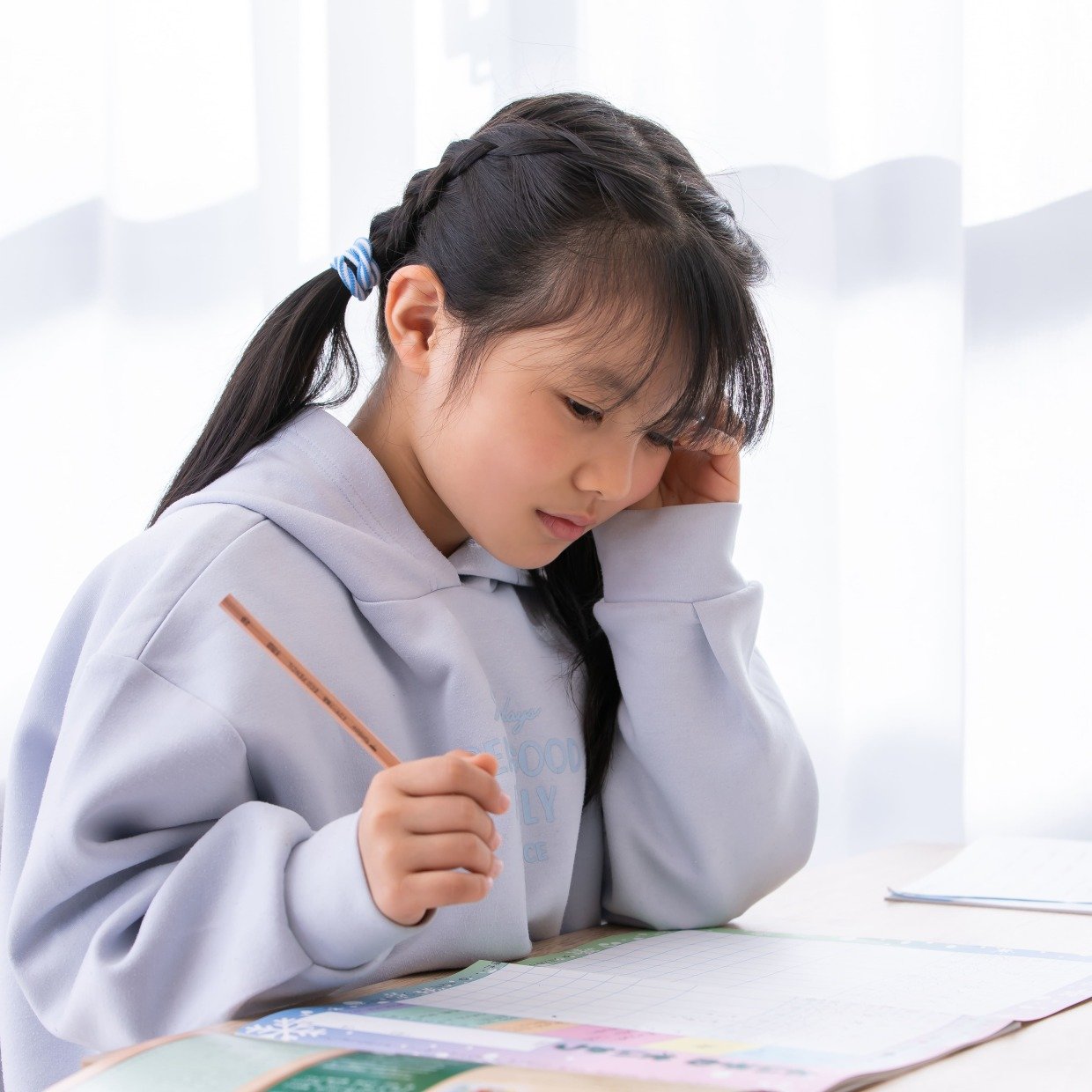「落ち着いて」では落ち着けない
うちのスクールでは、小学1年生から6年生まで、全員が年に5回以上も舞台に立ってプレゼンテーションをします。
もちろん最初は、緊張して頭が真っ白になってしまって、ずーっと黙り込んでしまう子もいる。
そんなときでも、先生や周りの大人はじっと待ち続けます。「早く!」と急かしたりもしないし、過剰に「がんばって!」と発破をかけたりもしません。優しく、温かく、その子が自分を取り戻すまで待つ。大切なのは、その子がまだ立ち直ろうとしているのか、完全に崩れてしまったのかを見極めること。
うつむきながら、それでも何かを言おうとしている、フリーズしてるけど、まだそこにいようとしている。そんなときは、5分でも10分でも待つ。
けど、座り込んでしまったり、泣き出したままどうしようもなくなったり、戦意喪失してしまったときには、次の子にバトンタッチ。それでも、順番を代わって最後にもう一度舞台に立ってやり遂げる子も多いです。
そんな感じで、みんな発表には慣れているけれど、それでも突然緊張や不安で頭が真っ白になってしまうことってある。
娘も不安や緊張があるとテンパってしまうところがありました。発表前に緊張して頭が真っ白になってしまったり。テストでわからない問題が出ると、よく考えれば解ける問題でもケアレスミスをしてしまったり。
子どもなら誰にでもあることですが、娘にとってはそれが自分の課題点だったようです。
ある保護者面談の日、スクールの先生と娘がテンパりグセを課題に感じているということについて話をしました。
「頭が真っ白になってしまったら『深呼吸すること』を伝えるようにしましょうか」
スクールでの生活でも、度々ある頭が真っ白になる瞬間。そのときに「深呼吸」を促してみる、ということになったのです。
「プレゼンのときもただ『落ち着いて!』って声を掛けても、その落ち着き方がわからないんです。だから方法として『深呼吸』をすることを教えてあげるといいと思います」とのことでした。
たしかに。がんばって! 落ち着いて! という声がけは、じつは当事者にとってはただのプレッシャーとなってしまうこともある。「がんばってる」って思うほどに、ますます混乱してしまうこともあるでしょう。
そんなときに、具体的な「深呼吸」は、当人の助けになります。
「深呼吸」という武器を手に入れた
それから、娘は困ったり、不安になったり、緊張したりしたときは「深呼吸」をするようになりました。でも、最初はその深呼吸が浅くて早い。「すっはっ、すっはっ」という感じで、深呼吸になっていないのです。
そこで「ゆっくり『い〜ち、に〜い、さ〜ん』で息を吸うんだよ」など、深呼吸についても具体的に教える。すると段々、深く息を吸うことができるようになっていきました。たったひとつ、「深呼吸」という武器を手に入れたことで、テンパってしまうクセが少しずつ減っていったのです。プレゼン前に深呼吸。何か嫌なことや不安な事があったら深呼吸。この一年間、僕は何度も娘が深呼吸をしている姿を目にしてきました。
「テンパったら深呼吸をすればいい」
この習慣が、娘にとって本当に心強い対策方法となっていたのです。
子どもの成長を信じて、見守れば大丈夫
年度末の保護者面談。「だいぶ頭が真っ白になってしまうことがなくなりましたね」と、先生と一緒に娘の成長を喜ぶことができました。1年間、娘自身も自分の課題として向き合ってきたし、先生も、親も、それをゆっくりと見守ってきました。
この一連のできごとから、あらためて僕は子育てにおいて大切なことを3つ学んだ気がしています。
1.子どもの成長を信じて見守ること
本人だってやりたいと思っていてもできないことは、たくさんあります。大人だって「この子ならもっとできるはず」と期待することもあるでしょう。でも、それだってゆっくり一歩ずつです。焦る本人をけしかけるように、周りの大人や親が焦らせても仕方がないよなと思うのです。
2.具体的な対策を伝えること
「落ち着いて」「がんばって」という気持ちに働きかける声がけも大切ですが、それだけでは本人は何をすればいいかわからないこともある。だから具体的にやるべきことをアドバイスしてあげるのも大切です。
3.できるようにならなくても“気にする必要はない”ということ
ひとつ目にも通じますが、子どもは日々色んなことを吸収し成長しています。課題と思うことも時々によって変わるでしょう。
それらが全部できるようにならなくてもいい。そんなおおらかな気持ちで、接してあげたいなと思うのです。