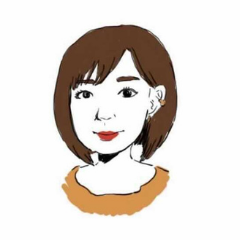教えてくれたのは……島田直英(しまだ・なおひで)先生
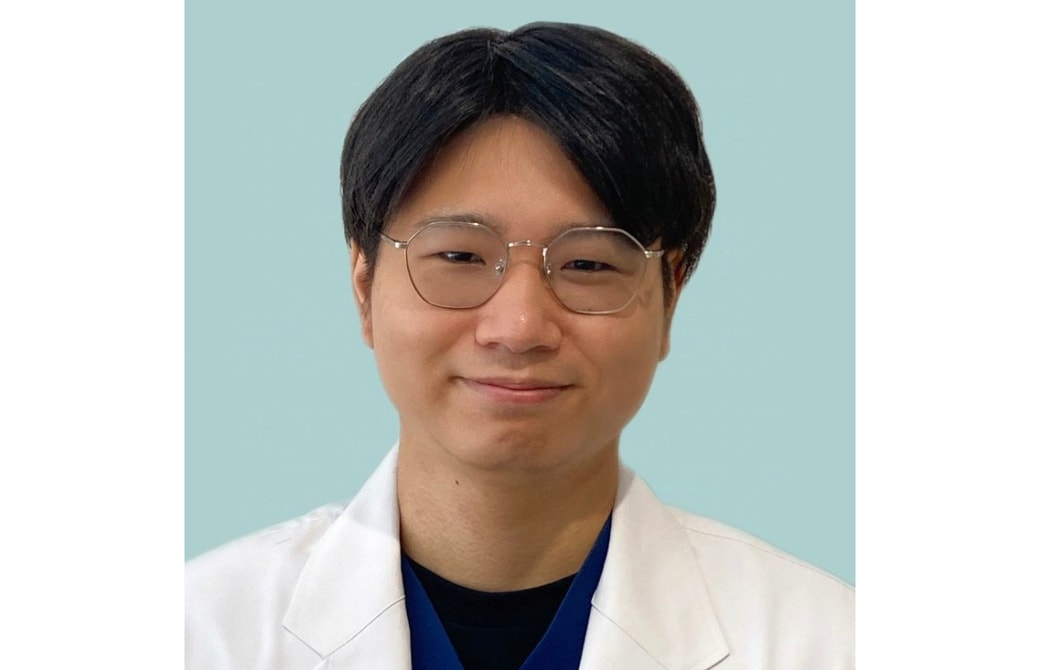
精神科医・総合診療医・漢方医。不登校/こどもと大人の漢方・心療内科 出雲いいじまクリニック 副院長。島根大学医学部医学科卒業後、大田市立病院総合診療科、島根大学医学部附属病院総合診療科等を経て、2025年に同クリニックにて副院長に就任。飯島院長に医学生時代より師事し不登校・不定愁訴診療の極意を学ぶ。精神科単科病院にも在籍。
焦りは禁物。「摂食障害の回復」までのステップ
前回の記事では、「摂食障害の子どもに対して逆効果になる声のかけ方や適切な相談先」についてご紹介しました。子どもの心身を心配するあまり、「早く何とかしなければ」と焦ってしまう親も多いですが、島田先生によると、長い目で見守る姿勢が大切なのだそうです。
島田先生「摂食障害の回復には数年単位の時間がかかることが多く、焦りは禁物です。一般的には、まず低体重など身体的な危機からの回復を目指す「(1)身体的回復期」があり、次に体重や食事が安定した上で、心の葛藤や生きづらさと向き合う「(2)心理的回復期」へと進みます。一進一退を繰り返しながら、徐々に自分らしい生き方を取り戻していく道のりです。」
考え方の癖と「うまく付き合っていくこと」が目標
島田先生「症状が完全に消え、食事や体型に全くこだわらなくなる『完治』を目指すことは不可能ではありませんが、完治に至らず症状を抱えながら生活している方も多くいらっしゃいます。回復の道のりは人それぞれです。まずは症状によって日常生活が脅かされない状態を目指し、考え方の癖と『うまく付き合っていく方法』を身につけることが現実的な目標となります。再発予防に取り組みながら、気長に見守る視点が大切です。」
専門家や学校と連携する際に気をつけるとよいこと
摂食障害は、親子だけで抱え込まず、周囲との連携が回復への大切なサポートになるとのこと。専門家や学校と連携する際に、親が気をつけるとよいポイントについて、島田先生に教えていただきました。
専門家との連携
島田先生「親は、子どもが安心して過ごせる家庭環境を整えることに積極的に関わりましょう。一方、食事の量や体重の管理といった具体的な治療の部分は、専門家(医師や栄養士)に任せ、少し距離を置くのが賢明です。親が『治す』役割を担おうとすると親子関係が悪化しやすいため、役割分担を意識することが大切です。」
学校との連携
島田先生「まずは家庭での様子や医療機関での診断名を具体的に伝え、協力を依頼しましょう。特に給食や体育の授業でどのような配慮が必要か、本人の負担にならない関わり方(体型への言及を避けるなど)を具体的に共有することが重要です。学校と家庭が連携し、本人にとって安全な環境を整えるという共通の目標を持つことが望ましいです。」
「親自身の心のケア」をすることも大切
子どもが摂食障害になったとき、親自身が強い罪悪感を抱き、自分を責めてしまうケースも多いかもしれません。そんなとき、どのように気持ちを整理すればよいでしょうか。最後に、親自身の心のケアについて伺いました。
島田先生「親御さんは『自分の育て方が悪かったのでは』と、罪悪感を抱いてしまうこともあるかもしれません。しかし、摂食障害はさまざまな要因が絡み合う病気であり、決して親だけのせいではありません。まずはその事実を受け入れ、自分を責める必要がないと理解していただくことが大切です。なぜなら親が自分自身を大切にすることが、結果的に子どもが自分を大切にすることを理解するきっかけとなり得るからです。」
親が自分を責めすぎず、子どもに寄り添い続けるためにできるセルフケア
島田先生「一人で抱え込まず、信頼できる人に話を聞いてもらうことが大切です。同じ悩みを持つ親が集まる家族会などで、気持ちを分かち合うことも心のケアに繋がります。また、趣味の時間を作る、意識的に休息をとるなど、子どものことだけを考える時間から離れることも重要です。親自身が心身ともに健康でいることが、長期的なサポートには不可欠です。」
焦らず、子どものペースに寄り添いながら、長期的な視点で支えていくことが回復への近道です。 親自身の心のケアも忘れずに、周囲と連携しながら一歩ずつ前に進んでいけることを願っています。