
第94回 伊澤直美(32)わたしの知らない母と父がいた家で
「お水じゃなくて、レモンの汁で溶くのが好きなの。レモンがごちそうだからね」
ボウルに粉砂糖とレモンの搾り汁を合わせながらレイコさんが言う。オーブンで焼き上げたレモンケーキが冷めるのを待つ間、アイシングを作っている。
「直美ちゃん、取っておいたレモンの皮、ここに入れてもらえる?」
直美が目でスプーンを探すと、「そこ」とレイコさんがテーブルをあごで示す。口の広いガラスの空き瓶に木のスプーンとフォークが差してある。瓶にはトマトとバジルの絵が描かれたシールが貼られている。パスタソースが入っていたらしい。
スプーンでレモンの擦り下ろしをかき集め、アイシングのボウルに空ける。残りはケーキの生地に混ぜて焼いた。キッチンと続きの間のダイニングに香ばしいにおいが立ち込めている。
家に上がってから約2時間。映画一本分の時間。何もしていなかったら、もっと長く感じられただろう。ケーキをオーブンに入れたところで、イザオに抱っこされていた優亜が目を覚まし、泣き出した。イザオがおむつを換えるのを見て、「置いて行ってね」とレイコさんが言い、「すみません」と直美は恐縮した。自分が生まれ育った家なのに、すっかりお客さんになっているのを自覚すると同時に、「おむつ置いて行ってね」がすぐ出るレイコさんは子育てをした人なのだろうと思った。
おむつを替えても優亜がぐずるので、イザオが抱っこし直して外に連れ出した。「ゆっくりしてくるから」と言い残して。「気を遣ってくれたのかな」とレイコさんが察し、レイコさんとふたりきりなんだと直美は急に緊張し、目を泳がせると、サッシ戸の手前にひだまりができていた。母がよくそのひだまりに腰を下ろして編み物をしていた。直美が面倒を見きれなくなった犬のトトに「ぴーちゃん」という名前をつけ直し、腹巻きを編んであげていた。

「どうしたの?」
直美の視線の先に何かあるのかとレイコさんもひだまりに目をやる。
「いえ……この家で3人で暮らしてたのって、いっときだったんだなって」
「いっとき。そうね。家って、いっときの入れものだから」
「入れもの、ですか」
「私はそう思ってるの。だから、人は増えるし、減るし、通り過ぎる。その入れものの外には町があって、国があって、地球があって、この世があって。人生は出たり入ったりの繰り返し」
何かの詩の一節のようなことをレイコさんが言う。不思議な人だなと直美はレイコさんを見る。着ているものは量販店の部屋着のような上下で化粧っ気もないが、近くで見ると、愛嬌のある顔をしている。若い頃は可愛いとよく言われたのではないだろうか。目が吊り上がってきつく見える母とは対照的だ。
「この人何者って思われてる? この家を乗っ取った魔女だったりして」
レイコさんはいたずらっぽく笑った。
「魔女だったら、わざわざケーキを焼くような面倒くさいこと、しないですよね」
「そうね。魔女ではないわね。その前にレイコさんでもない」
「え? レイコさんじゃないんですか?」
「直美ちゃん、なんで私の名前がレイコだって思ったの?」
質問を質問で返された。隠すことでもないし、高校生の頃、寝ぼけた父に「レイコ」と呼ばれたことを話した。
「父が時々外で会っている女性がいるのはなんとなく気づいていて、それで、レイコさんっていう名前なのかなって」
「うさぎなんだって」
「うさぎ?」
「お父さんが小学校のとき、飼育係で育ててたうさぎの名前」
娘をうさぎと見間違えて、「レイコ」と呼んだりするだろうか。
「お父さんね、うさぎのレイコの世話をしてたとき、人生で一番ほめられたんだって。みんなが嫌がる掃除を真面目にきっちりやって、それを担任の先生がえらいねって言ってくれて。あの頃の自分が一番好きなんだって」
そんな話をする仲なのだ。レイコさんではないレイコさんと父は。
「似てるらしいの、私。うさぎのレイコに。それで初対面のときから気を許してもらえたみたい」
レイコさんではないレイコさんと父をつなげたのは、うさぎのレイコだった。
「で、本名はレイコじゃなくて、熊木彩子です。色彩の彩に子どもの子と書いて彩子。サイコとも読めるけどね」
「彩子さんは、父とはどういう……?」
「多分誤解されてると思うんだけど、直美ちゃんが考えているような仲ではないの」
直美もそんな気がしていた。母の元を去った父と一緒になった女性が彩子さんだとしたら、たとえ母の記憶から自分のことが消えていたとしても、合鍵を受け取って家に出入りするようなことはできないだろう。
でも、だとしたら、父とはどういう……?
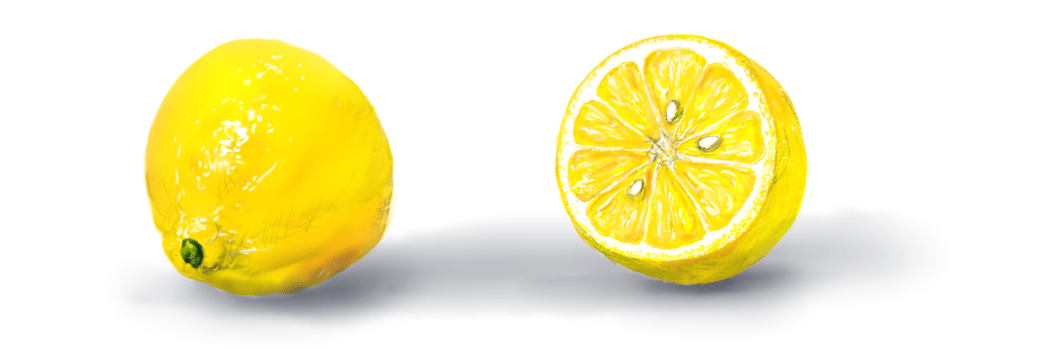
「お父さんの話を聞いていたの。お父さんだけじゃないんだけどね。みんなでケーキを焼きながら、話を聞き合って。そういう会を時々やってたの」
「カウンセラーみたいなことですか?」
「そんなたいそうなものじゃなくてね。聞いて欲しい話がある人はすればいいし、話したくない人は話さなくていい。手を動かしていれば、時間は余らないし、その人の存在も余らない」
彩子さんはそこで言葉を区切ると、テーブルの上のケーキに手のひらを当て、「そろそろいいかな」と言った。ケーキのてっぺんに並べたレモンの輪切りに、ほんのりと焼き色がついている。その上にアイシングを塗っていく。
父が何度か持ち帰ったレモンケーキには、父の手も加わっていた。この家が受け止めきれなかった父を、彩子さんと彩子さんの元に集まった人たちが受け止めてくれていた。その時間が詰まったケーキを何も知らずに食べていたのだ。高校時代のわたしは。
「なんで、そういうことを始めたんですか」
「私自身が、元々、助けてもらった一人だったの」
「今も続けているんですか」
「あちこち場所を変えて、それぞれが行った先でね」
「父は今、どうしてるんですか」
直美が父とも連絡を取り合っていないことに彩子さんは驚かなかった。
「レモン育ててる。今治で」
「愛媛の?」
「そう」
この家を出た父が向かった先は、当時直美がレイコさんだと思っていた女性の元ではなく、瀬戸内のレモン農園だった。
父からは毎年、誕生日にメールが届いた。
《誕生日おめでとう。この一年も元気で》
短い文面だが、そのメールで父の生存確認をしていた。
《ありがとう。元気です》
返信も短かった。今どうしているのか、聞きたいけれど聞けなかった。イザオとの結婚が決まったときは、声で報告をした。母に言ってもらえなかった「おめでとう」を言ってもらえた。「お祝いには行けないけど」と瀬戸内のレモンが送られてきた。差出人はレモン農園の名前になっていた。ダンボール箱にも同じ名前が印刷されていた。

「言ってくれたら良かったのに」
こんなにレモンばっかり送られてもとぼやきながら消費した大量のレモンに再出発した父の時間が詰まっていた。そうと知っていたら、もっとありがたく味わったのに。女の人のところに行ったんじゃなかったら、気を遣わずに会いに行ったのに。
「母は、どこまで知ってるんですか」
そう言って、直美はハッとする。軒先のレモンの木。可愛がっていたぴーちゃんが死んだとき、母が植えたあの苗木は、もしかしたら、父が送ったものだったのだろうか。
わたしの知らない父。
わたしの知らない母。
わたしの知らない夫婦のカタチ。
アイシングを施されたケーキが冷蔵庫に納められる。アイシングが冷えて固まる頃に、母は帰って来るだろうか。何から話せばいいかわからないが、母が気に入っているというレモンケーキを分け合えば時間は埋まる。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第95回 多賀麻希(31)「これ以上わたしから何も盗らないで」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!














