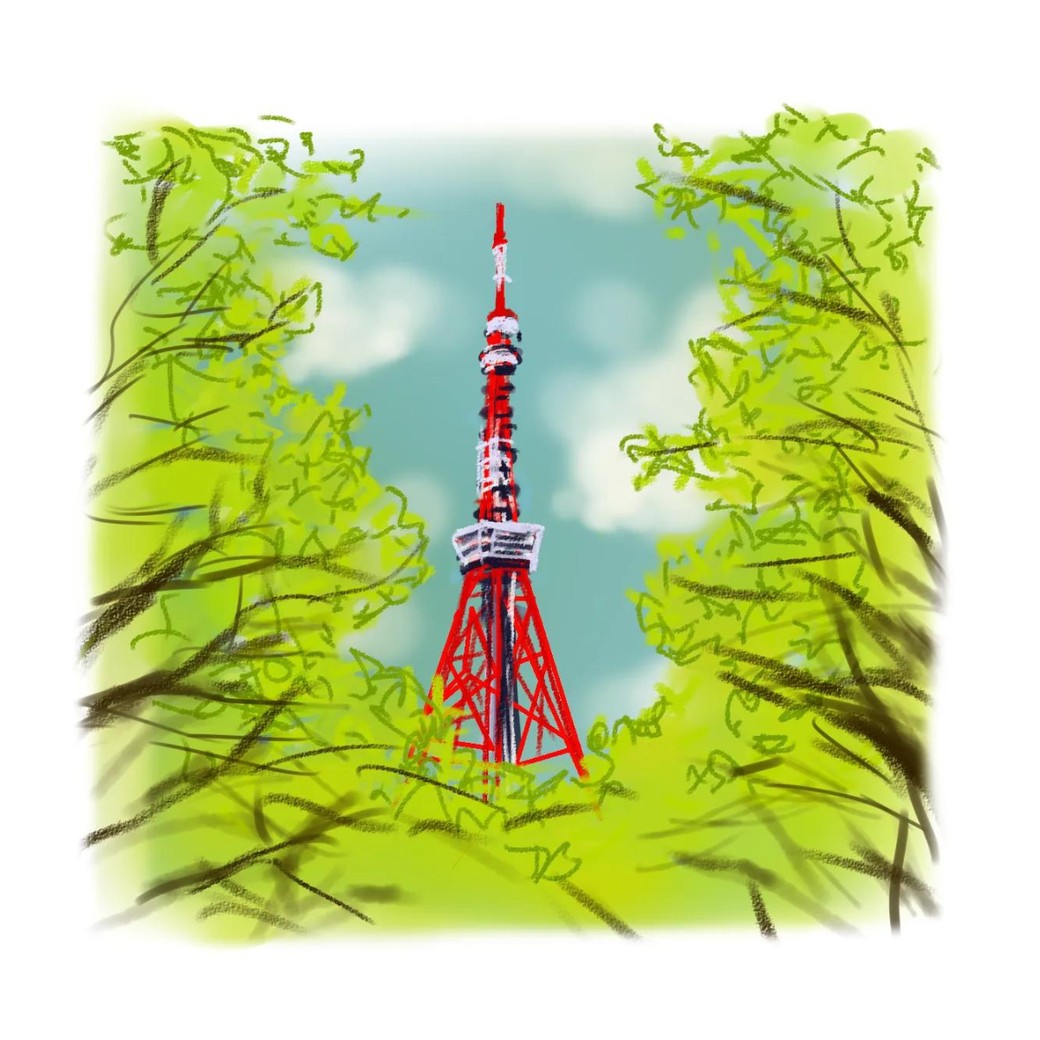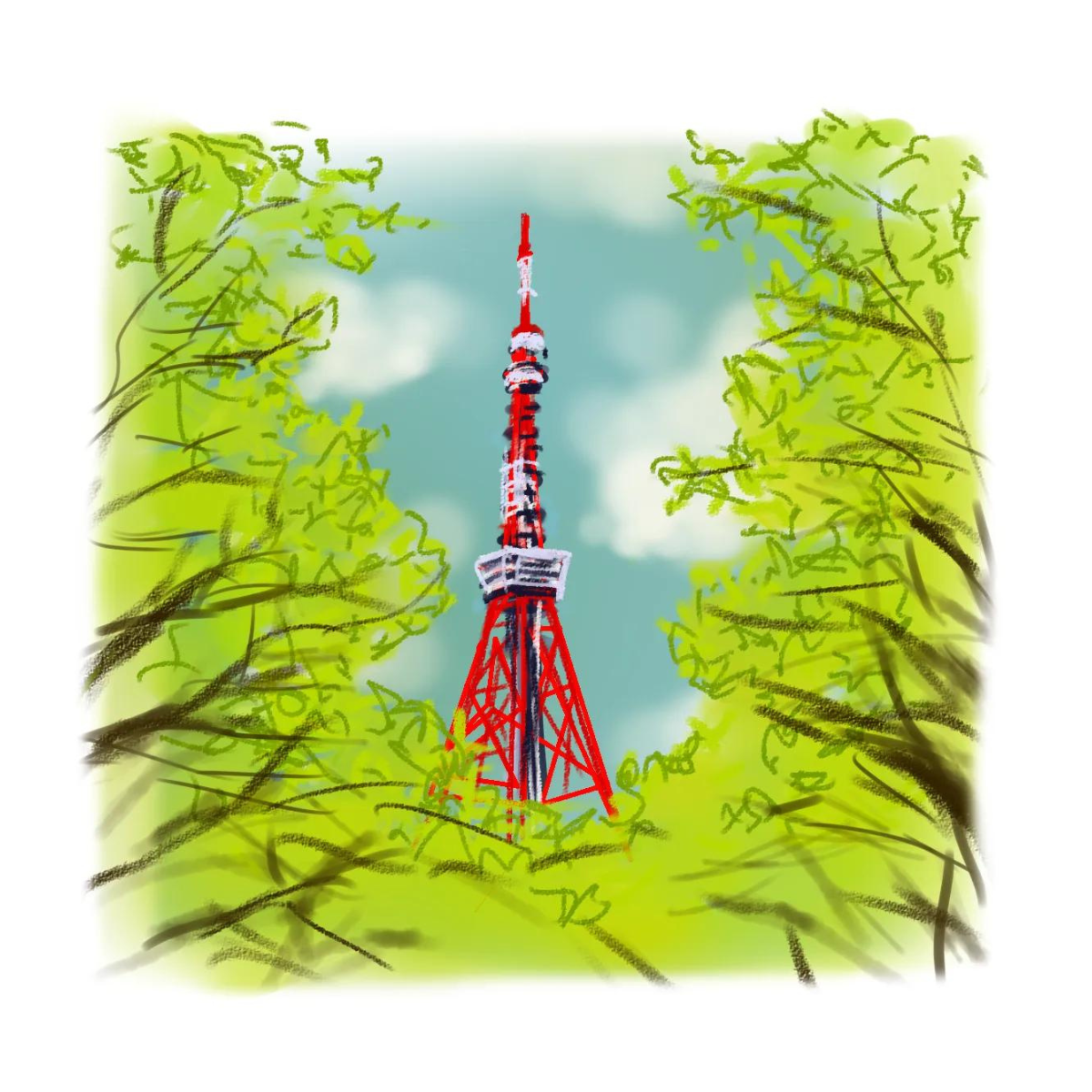第15回 伊澤直美(5) 夫と恋人時代に戻って
「途中で言い合いになって、彼女が先に店出て、彼氏が追いかけるじゃない?」
「ムール貝!」
「そう!中腰でムール貝だけ食べて飛び出すの、良かった」
「俺もその中腰、ツボだった」
春めいた陽気に誘われて、自転車でどっか行こうとイザオが言い、自宅マンションのある目黒から六本木方面に向かい、映画でも観よっかとなった。
たまたま時間が合った、タイトルを知ったばかりで何の情報もない洋画を観たら、主人公のカップルが食べるパエリアがおいしそうで、映画が終わるなり近くで食べられる店を探して、昼からやってるスペインバルを見つけ、ランチのパエリアを分け合っている。注文したのはもちろんムール貝入りだ。
「頭の中パエリアになって、喧嘩どうでも良くなっちゃった」
「もうさ、俺の中では、タイトル『パエリア』になってる」
「そんなタイトルの映画なかったっけ」「もしかして『ピラニア』?」
「それだ!」
どこに行って、何をして、何を食べるか。行き当たりばったり、そのときの気分で選ぶものがうまく重なって、退屈な映画を観ても楽しめるところを見つけて、そのツボが同じだったりして。
恋人時代に戻ったみたいだ。
ふたりで行動しているのにストレスがなくて、ひとりでいるより楽しくて。だから、一緒に暮らすようになって、結婚したんだと直美は思い出す。
「あー。バルなのに泡飲めないの辛い。自転車で来るんじゃなかった」
「飲みたいよなー。でも、自転車じゃなかったら、六本木で映画観て、パエリア食べてないかも」
「確かに」
「ラストムール貝、ハラミ食べて」
ハラミと呼ばれても、今日は気持ちが波立たない。甥っ子の幸太を預かった日に言い合いになって以来、イザオは「子どもどうする?」の話をしなくなった。諦めたわけではないけれど、横に置いている。

「このロゴ、よく見るよね」
スペインバルを出て、腹ごなしに散歩していると、イザオが海外ブランドの自転車ショップ前で足を止めた。色鮮やかなピンクやブルーのフレームに幅の細いタイヤの自転車が並ぶ店内に足を踏み入れる。
「クロスバイク、カッコいいよな」
「こういうのクロスバイクっていうんだ?」
「そう。ロードバイクとマウンテンバイクのいいとこどりしたやつ。スピード出るけど安定感あるから走りやすい」
何気なく金額を見て、結構するんだと直美が驚いていると、直美たちと年が近そうな男性の販売員が「街乗り用の自転車をお探しですか」と声をかけてきた。
「たまたま通りかかったんですけど。こっちとこっちの値段の違いって何ですか」
買う気もないくせに、イザオは気のあるそぶりを見せる。車体の鮮やかな赤に、直美は先日マーケティング調査でオンラインインタビューした主婦の口紅を思い出す。
眉は描いていないのではというくらい薄く、アイシャドウもつけていないその主婦は、マスクの下の唇だけが、なぜか真っ赤に主張していた。小さな子どもがサイズの合わない母親のハイヒールを履いているようなチグハグさがあった。

「ハラミ、試し乗りできるんだって」
イザオに呼ばれて、直美は我に返る。
「まさか、買わないよね?」
「乗ってみるだけ。ハラミも乗らない?」
「わたしはいいよ」
「あの値段の乗り心地、試してみようよ。ここで待ってても退屈だし」
乗ってみるだけならタダだし、イザオの誘いに応じることにした。
試乗用に用意されたクロスバイクも赤だった。販売員さんがサドルの高さを調節してくれるのを待つ間、また真っ赤な唇の主婦のことを思い出していた。
20代の終わりに授かった子が中学生になったと話していた。今の直美の年齢のときには、とっくに子育てを始めていたことになる。
パセリを花束みたいに空き瓶に活けたら3週間持ったとか、その後は生ハーブブーケを3割引で買い、ハーブ料理のレパートリーが広がったとか、真っ赤な唇を開いたり閉じたりして実に楽しそうに話すのを、行ったことのない国の土産話のように直美は聞いていた。
きっとこの人は、子育てが天職だったのだろう。それとも、子どもを産んだら、わたしもこの人のようになるのだろうか。
「ヘルメットかぶったほうがいいって」イザオに差し出されたヘルメットをかぶり、クロスバイクに跨る。ひと漕ぎすると、滑るように、すいっと前に運ばれた。
「うわ、何これ、軽いっ」
「ほら、乗って良かっただろ?」
「うん。気持ちいい」
「気持ちいいよなー」
けやきの木立の向こうに見える東京タワーがぐんぐん大きくなる。軽いのはペダルだけじゃない。恋人時代に戻ったような高揚感があった。
試乗を終えると、イザオはすっかり買う気になっていた。
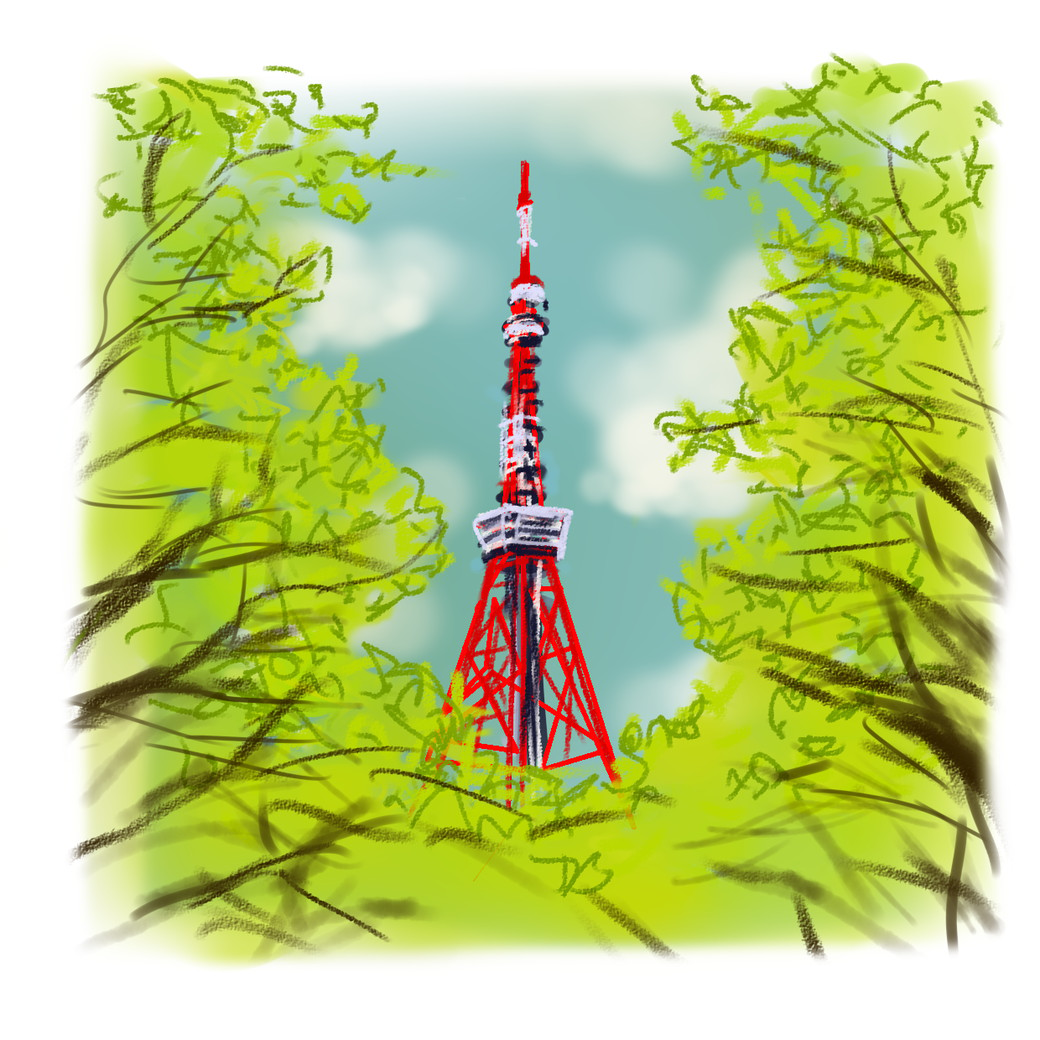
「今乗ってる自転車はどうするの?」
「こっちに乗り換えて、自転車通勤する」
ご自宅からお勤め先までどれくらいですかと販売員さんに聞かれ、イザオが地図アプリで調べると、「自転車で8キロ」と出た。
「でしたら時速20キロで信号待ち入れても30分くらいですね」と販売員さんに言われ、
「電車とそんなに変わんないですね!」とイザオはますます乗り気になった。
「ハラミも自転車通勤にしない?」
「わたしも?」
「俺はブルーのがいいな。ハラミは赤にする?」
「買うって言ってないけど」
「一緒に自転車通勤しようよ。定期代浮くし、運動不足解消になるし、寄り道できるし」
「イザオだけ買えば?」
「あ、わかった。酒だな?」
直美が渋る理由を「飲んで帰れないから」だとイザオは決めつけ、続けた。
「飲み会の日は電車で行けばいいし、急に誘われたら置いて帰ればいいし」
「だったら、さっきだって、泡飲んで、自転車置いてけば良かったよね?」
「だな。次からそうしよ」
クロスバイクを勧めてくるイザオが誰かに似ていると思ったら、少し前の「子どもいいよね」のイザオだった。
自転車に乗ったらお酒が飲めないことが問題なんじゃない。妊娠したらクロスバイクに乗れなくなるし、子どもが産まれたらしばらくはママチャリだってことに、イザオは想像が及んでいない。
「ハラミも気持ちいいって言ってたよね?」
「だから……」
気持ち良かったから、楽しかったから、妊娠したらできなくなることをまたひとつ知ってしまったから、揺れているんだよ。やりたいこと、好きなことの大きさと同じだけ、それができなくなる淋しさは振り子が反対側に振れるんだよ。
「子どもどうする?」と急かしておいて、クロスバイクどうって勧める無神経さに気づいてよ。
黙っておけばいいのに、やり過ごせばいいのに、はっきりさせないと気が済まない性格だから、言ってしまった。
「子どもか自転車、どっちかにしてくれない?」
次の物語、連載小説『漂うわたし』第16回 伊澤直美(6)「HAPPYが壊れた結婚4年目」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!
※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。