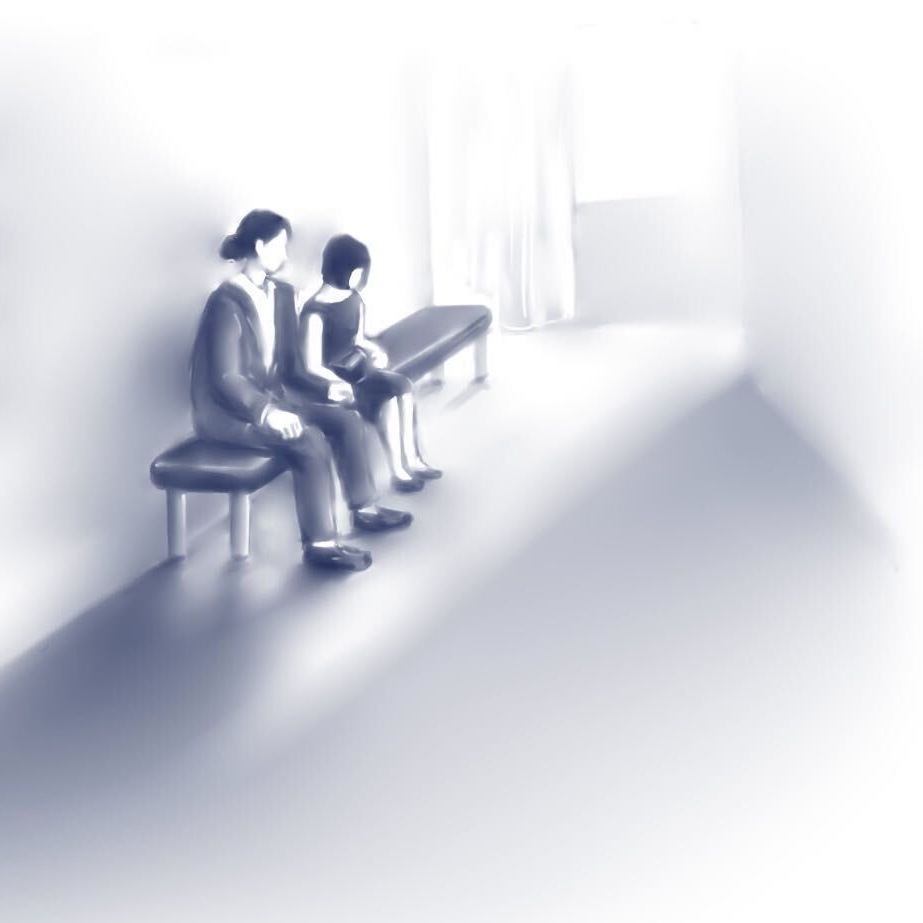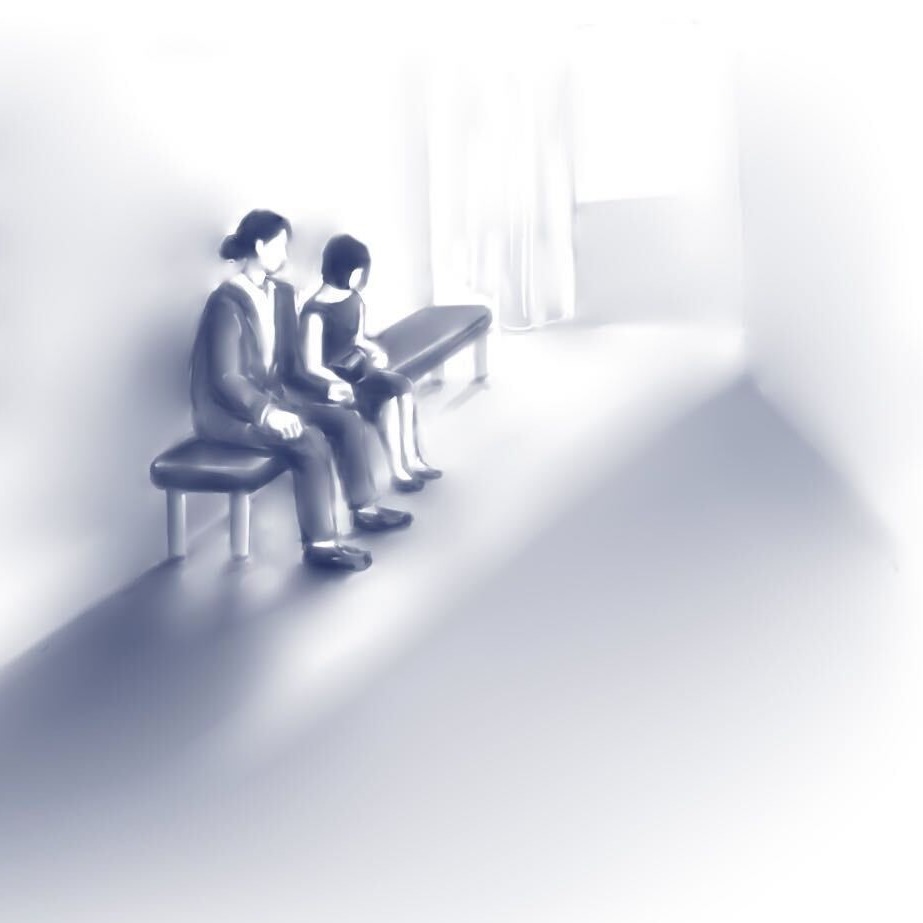第125回 多賀麻希(41)父を待ちながら
「結婚しよっか」
モリゾウが口にしたプロポーズは、麻希が刺繍を施したウェディングドレスを遠目に見て、花嫁の母と言葉を交わした高揚感から出たのではなかった。
ずっと言いたかったけれど、その資格がなかったのだとモリゾウは言った。ふたりで暮らす部屋に戻り、帰り道に買い求めたシュークリームを食べながら。
結婚しようと言える資格ができたと言うのは、いくらかの蓄えができたということだろうか。
「ずっとって、いつから考えてたの?」と麻希が聞くと、
「いつからだろ」とモリゾウは記憶を辿り、
「マキマキのお父さんに会ったときかな」と言った。
麻希が新宿三丁目のカフェへバイトに行っている間に熊本の父が突然訪ねてきて、モリゾウと鉢合わせたのは、2年前の6月だ。
麻希が帰宅すると、父はモリゾウとの同居について問いただした。大学は、勤め先は、蓄えはとモリゾウに遠慮のない質問をぶつけ、今後のことは考えているのかと問い詰めておいて、今さら孫の顔が見られるわけじゃないしと最後は突き放した。「孫の顔見られないって、決まったわけじゃない」と麻希は刃向かったのだが、当時、まだモリゾウとは何も起きていなかった。
売り言葉に買い言葉とはいえ、ただの同居人だったモリゾウを前に妊娠の可能性を主張するとは、大胆というか、挑発的というか。結果的に自分の中にある気持ちに旗を立ててしまった。埋もれていた蝋燭の芯をわざわざ立ち上げ、火をつけたようなものだ。
父に焚きつけられたあの日、モリゾウの気持ちにも変化があったとは。
「まだ何も起きてなかったのに、結婚を意識したの?」と聞くと、
「体だけはつながってなかったけど」とモリゾウは言った。
体だけはつながってなかった。
モリゾウの何気ない言葉がセリフのように聞こえることがある。
「最近また、体だけ、つながってないね」
モリゾウの言葉に乗っかり、あぐらをかいたモリゾウの両脚が作る輪の中に腰を落とした。モリゾウを見上げると、キスが始まり、食べ終えたばかりのシュークリームの名残を交換した。
モリゾウの舌が熱い。このまま続くパターンだ。
結婚しようと思ってくれていたのだ、この人は。これまでだって、そんな気持ちでこんなことをしていたのだ。

「主ゃ今後んこつば、考えとるとか!」
不意に父の姿が脳裏に蘇り、でんと居座って離れなくなった。
「どうした?」
モリゾウの手の動きが止まった。
「お父さんの顔がちらついてる」
かつて父が正座した辺りに手で父を描くと、モリゾウもそこに父の姿を見た。
「お父さん見てるのか」
モリゾウの手は止まったままだ。
「服の中だったら大丈夫かも」
続けて欲しくて、麻希はモリゾウの手を取り、汗ばんだシャツの中に導いたが、やはり落ち着かず、ちゃぶ台のある部屋から奥のベッドのある部屋に移動し、戸を閉じた。
「大丈夫? ついて来てない?」とモリゾウが戸の向こうを気にして、
「お父さん、霊みたいになってる」と麻希は笑った。
モリゾウとの交わりを一時期、「おしゃべり」と呼んでいた。その日はなんとなくその先には進まず、お互いの体に手を這わせ、キスを挟みながらおしゃべりを続けた。
「熊本に行こっか」とモリゾウが言った。
「挨拶ってこと? そこまで考えてくれてるんだ?」
「お前じゃダメだって言われるかもしれないけど」
「言わないよ、今さら」
「何歳になっても、娘は娘でしょ」
そんなものなんだろうか。
逃げるようにして東京に出てきた。振り返ったら負けだ、みたいな気持ちがあった。何も成し遂げないまま独身のまま41歳になった娘に、今さら何も期待していないのではないだろうか。
「今さら孫ん顔ば見らるるわけじゃなかし」
父の言葉がまた蘇った。
「ごめん。お父さん、追いかけてきちゃった」
「挨拶行くのが先だな」
モリゾウが下着に潜り込ませていた手を抜き、おしゃべりは完了した。
それが6月のことだったが、熊本行きが実現しないまま7月が過ぎた。父の体調がすぐれず、夏バテだと思うので、落ち着いた頃にと言われたのだが、8月の頭に急遽熊本へ行くことになった。
父が倒れたと救急車の到着を待つ母から電話があった。

空港から直接病院に向かった。救急車に付き添った母は麻希たちと入れ違いに一旦帰宅した。父の着替えを持って戻って来ることになっている。両親とスープの冷めない距離に住む妹の奈緒は、小学生と幼稚園児の子ども3人が夏休みで家におり、動けない。家族代表で麻希とモリゾウが病院にいる。
父が今、どういう状況なのか、まるでわからない。
てっきり緊急治療室で手術を受けているのだと思ったが、そのフロアに父はいなかった。病院のどこかにはいるのだが、誰に聞いてもわからず、連絡があるまでお待ちくださいと言われた。父が運び込まれてから5時間ほど経っているはずなのだが、まだ連絡は来ない。伝えた番号が合っているのだろうかと不安になる。
がらんとした廊下のベンチで握り締めた携帯電話が震えるのを待ち続けている。他に誰もいない。この病院に自分たちしかいないんじゃないかと思ってしまう。このベンチだけが世界から切り離さされているような心もとなさを覚える。長く続く廊下をどこまでも進んでも、誰もいないのだ。もちろん父もいない。
「わたしたち、何を待ってるんだろね」と麻希が言うと、
「ゴドーを待ちながら、みたいだな」とモリゾウが言った。
ゴドーを待ちながら。
そのタイトルを知っている。おぼろげにチラシの絵柄が記憶の底から浮かび上がる。
20代の頃働いていた映画製作プロダクションの現場で知り合ったエキストラの男の子に「今度、これに出るんですけど」とチラシを渡され、舞台を観に行った。「一人で行かないですよね?」と言われ、一緒に行く相手のアテがないのに2枚買い、1枚を余らせたチケットで。
チラシが縦横2枚ずつの4枚貼られた下北沢の小さな劇場の暗い受付を思い出す。ポスターを作るお金がない舞台は、チラシを並べてポスターの大きさにしていた。
「ゴドーって、どんな話だっけ」
難しかったのか、寝てしまったのか。エキストラの子が何の役をしていたかさえ覚えていない。
「浮浪者の男二人がゴドーを待ちながら話をするんだけど、ゴドーと会う約束をしたのかどうか、そもそもゴドーなんているのかどうかも怪しいっていう話」
そんな話を見たような気もするし、初めて聞いたような気もする。ただ、今のベンチの状況を言い当てていると思う。
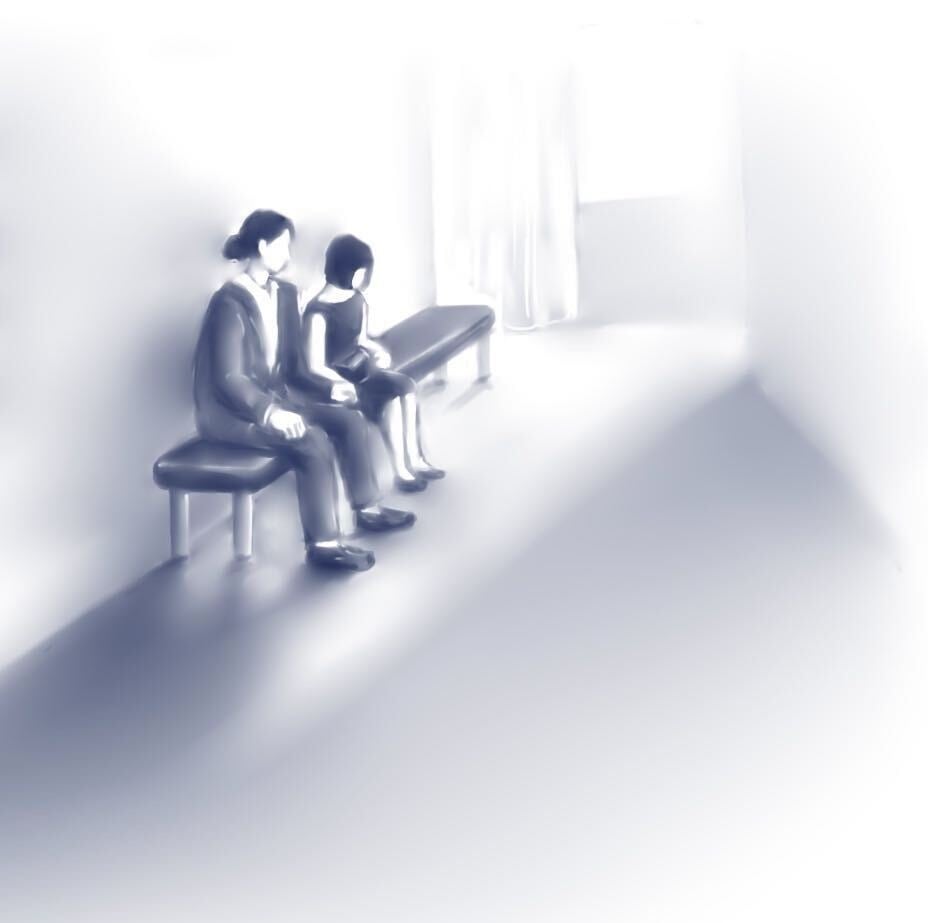
舞台の記憶はまだぼんやりとしているが、打ち上げで酎ハイのジョッキを手に役者の卵たちがゴドー、ゴドーと言い合っていたのを思い出す。その中に、麻希にチケットを売ったエキストラの子もいた。
「演劇の人って、ゴドー好きじゃない?」
「まあね。来るか来ないかわからないものを待っているのが、自分たちに重なるのかな」
「あー。役をつかむのも運が要るしね」
「そうだね。ゴドーはゴッドじゃないかって説もあって」
「神様? 救世主待ちってことか」
「うん。神じゃなくて死だっていう説もある」
「死?」
「ゴドーを待つヒマつぶしに会話をするのは、人生そのもの、みたいな。人生なんて死ぬまでの壮大なヒマつぶしだって……あ、ごめん」
モリゾウが謝り、押し黙った。容態のわからない父を待っているときに死を口にするなんて縁起でもないと思ったのだろう。ふたり揃って黒を着て来てしまったことに気づく。喪服で駆けつけたみたいになっている。
神様も死も自分では呼ぶことも遠ざけることもできない。約束した覚えがなくても不意に現れて、行き先を乱暴に変えてしまう。
「吾郎っていうの」
麻希が沈黙を破ると、「ゴロー?」とモリゾウが聞き返した。
「父。5人目の五じゃなくて、下に口がついてる吾郎」
「ゴローを待ちながら、だ」
「うん。ゴローを待ちながら」
どちらからともなく、ふふっと笑った。力が抜けて、空いた隙間からこぼれたような声だった。隙間ができたところに、涙がせり上がる。
会いたいよ。お父さん。
会わせたいよ。お父さん。
父に生きていて欲しいと強く願った。モリゾウに会わせずに死なれてたまるかという意地なのかもしれないけれど。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第126回 多賀麻希(42)「なんのお祝いだっていい」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!