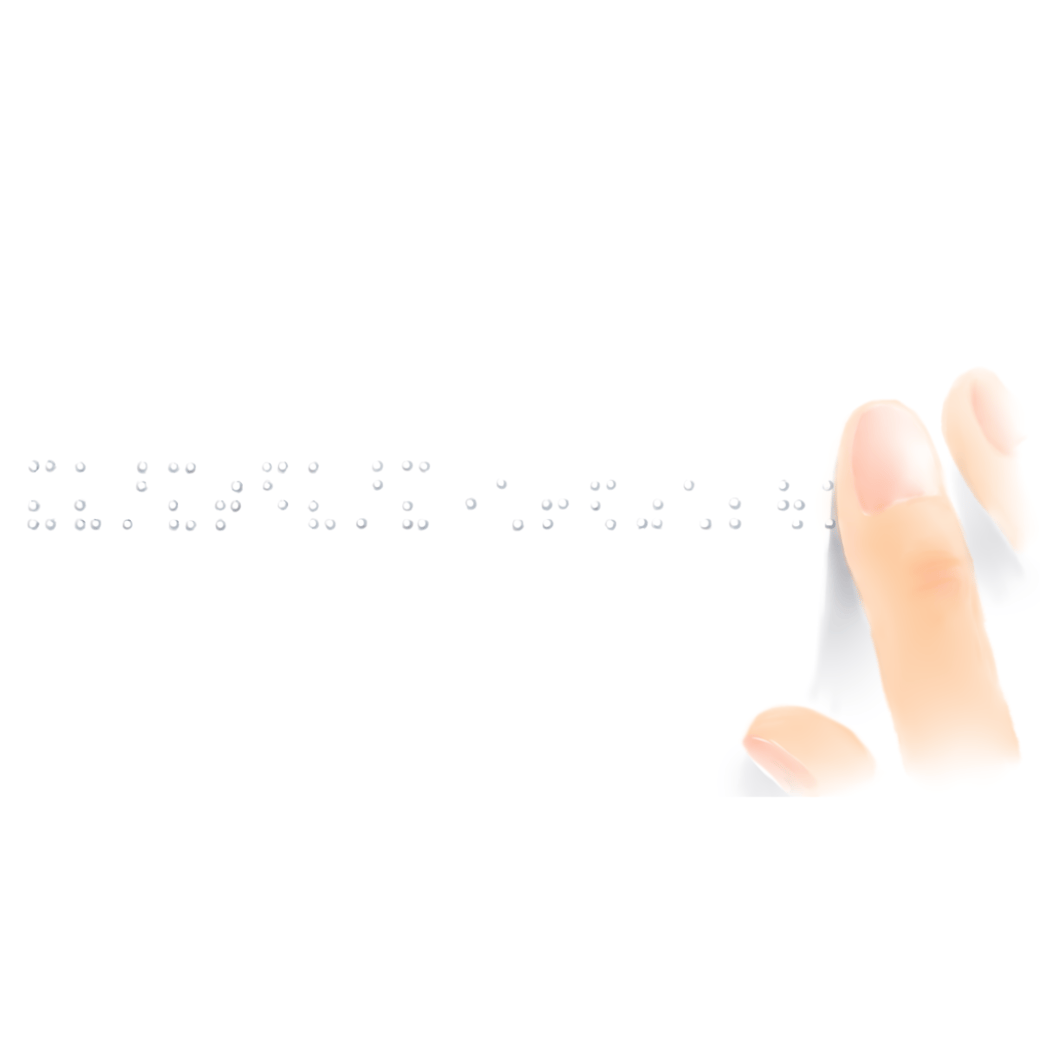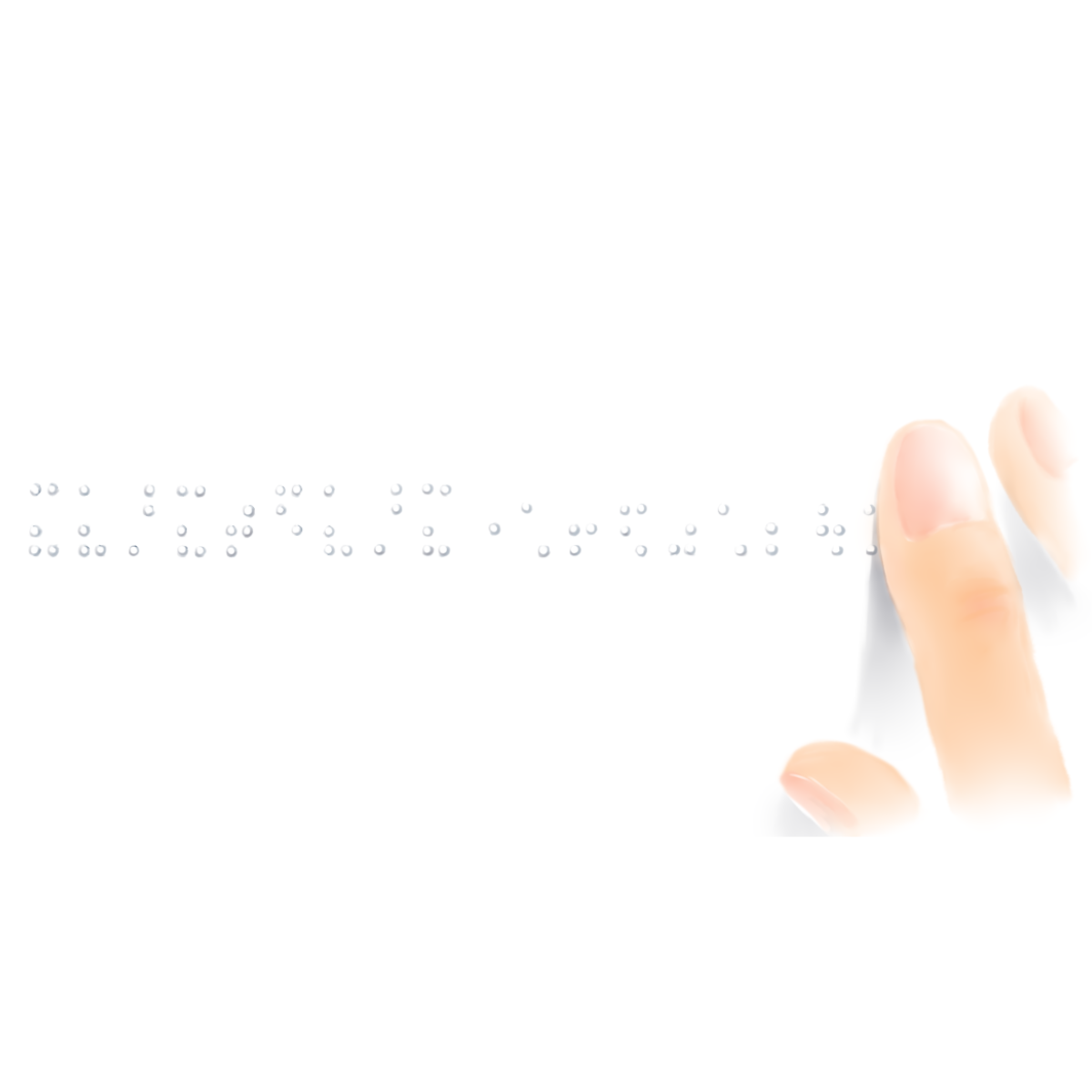第115回 佐藤千佳子(39)ペンネーム十文字パセリ
人に物語を読んでもらうのは、いつぶりだろう。
もしかしたら、自分が子どもだったとき以来かもしれないと千佳子は思う。
心の奥のふたが撫でられて、ふわっと開く。思い出したのは母や同居していた祖母ではなく、幼稚園のノリコ先生の声だ。自分で作ったお話をよく聞かせてくれた。その中には、千佳子のいた「ひまわり組」の子どもたちが登場した。
わんぱくなヒロキ君。
おしゃれが大好きなエリコちゃん。
虫の名前に詳しいアキラ君。
かけっこが早いナオト君。
あやとりが得意なサオリちゃん。
「いつもニコニコしているチカコちゃん」もいた。
そんな風にノリコ先生はわたしのことを見ているんだと、先生が作ったお話に教えられた。
チカコちゃんは、みんなを引っ張っていく子ではなかったが、みんなの足を引っ張ることもなかった。チカコちゃんがニコニコしていると、これでいいんだとみんなは安心できる。良く言えば潤滑油、悪く言えば、いてもいなくても変わらない存在。もしかしたら、他にほめるところがなかったのかもしれない。
どうしたら「みんな」に加われるのだろうと、輪の外から切れ目を探しているような子だった。中から手を引いてもらわないと、入れないのかもしれないと思ったが、入れてと声をかける勇気はなく、誰かが見つけてくれるのを待っていた。だけど、切れ目を探していることに気づかれるのはカッコ悪いから、興味ないふりをしていた。
いつもニコニコ。
輪の外で強がっていたわたしは、ノリコ先生には、楽しそうに見えていたのだろうか。
「月曜日は日曜日の後じゃないか。いやいや。日曜日が月曜日の後なのだ」
白杖のカズサさんの朗読を聞いている。
地域センターの多目的室。長机を並べたパイプ椅子の客席で20人ほどが聴いている。その中に出番を終えたり控えたりしている5人の読み手が交ざっている。

千佳子の目の前には小ぶりの月餅が置かれている。花の模様が太陽のようにも見える。「月」と「日」。お皿代わりのペーパーナフキンで「紙」も揃っている。
朗読サークルの発表会で読みたいとカズサさんに言われたのは春のはじめだった。娘の文香の高校入試を控えた平日の午後、駅前の紅茶専門店でばったり会ったカズサさんと近くのたい焼き屋に立ち寄り、そのまま家に来てもらった。一人一つずつ買ってきたのだが、学校から帰宅する娘さんに一つ残しておきましょうとカズサさんが言ってくれ、上半身と下半身に割って分け合った。
そのとき、「日曜日と月曜日がケンカする話」が完成したことを報告すると、読んで欲しいとカズサさんにリクエストされ、読んでみたところ、「ちょうどいい長さ」の作品を探していたカズサさんが飛びついたのだった。
夫の両親の仲直りのきっかけにと作った話だったから、発表会でお披露目されることになるとは思いもよらなかった。『一週間で一番えらいのは誰?』というタイトルをつけていたが、書き出しの一文、「日曜日と月曜日がケンカした」をタイトルにしたほうが覚えやすくて好きだとカズサさんが言ったので、そうしましょうとなった。
「原稿をメールで送ってもらえたら、点字プリンターで出してもらいます」と言われ、連絡先を交換した。点字を出力できるプリンターがあることを初めて知った。
世の中には知らないことがまだまだある。自分が無知だっただけなのか、自分の世界が広がっているのか、どちらなのだろう。
「このカレンダーは紙でできているから、紙曜日がいちばんえらい!」
カズサさんの勇ましい声に、会場が笑い声で応じる。朗読というより一人芝居を見ているようだ。どこかで本格的に習っていたのだろうか。こんな上手な人にお粗末な朗読を聞かせてしまったと千佳子は恥ずかしくなる。
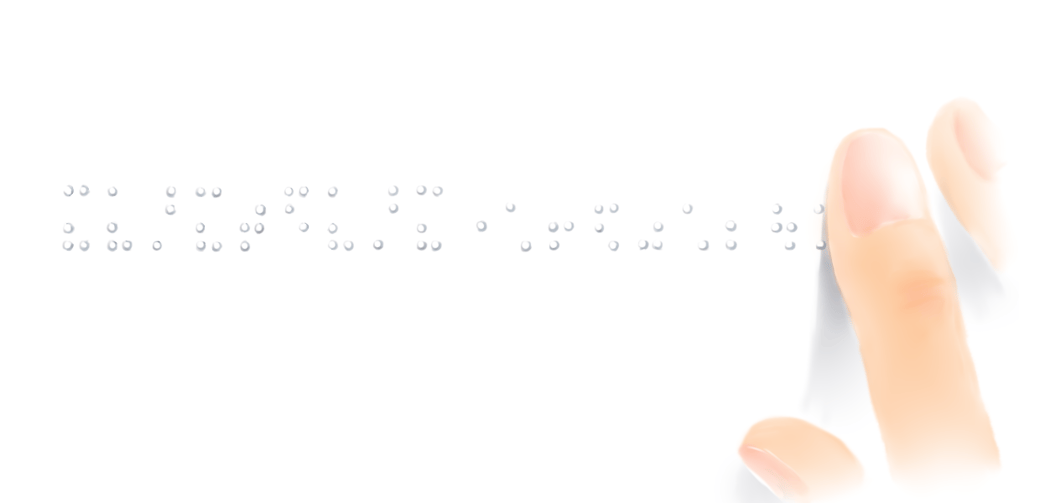
発表会の前、点字で出力された原稿をカズサさんがパート先のスーパーに見せに来てくれた。
「日曜日と月曜日がケンカした」
人差し指を点字に滑らせながらカズサさんが読み上げた。6つの点のどこが出っ張っているのか、指先で読み取り、文字を判別するのだと言う。
「点字を読みながら朗読するって難しくないですか?」と聞くと、
「佐藤さんも、目で文字を追いかけながら声に出して読むでしょう?」と言われた。
「目で読むか指で読むかが違うだけです。耳で読む人もいますし」
「耳で、ですか?」
「あらかじめ録音した音声を聴きながら追いかけるんです。シャドーイングっていうんですけど」
シャドーイング。その言葉は知っていた。娘がやっている英語の勉強法。学習系YouTuberが勧めていたらしい。
「ルートは違うけれど、たどり着くところは同じっていうか。点字が読めるってすごいですねってよく言われるんですけど、これが私の文字、私の読み方なので」
点字を読むのはカズサさんにとっては当たり前のことなのだ、という当たり前のことをカズサさんに教えられた。原稿を読む手段より、朗読の感想を聞きたいのだと言われた気がした。
カズサさんの朗読が終わり、会場が拍手に包まれる。他の人のときより大きく聞こえる。
「ペーパーの『カミ』も神様の『カミ』も点字で表すと同じなんですが、一番恐れ多いのは、噛み噛みの『カミ』様です。今日は降臨して来なくてセーフでした」
笑いをしっかり取って、カズサさんは次の人につなげた。
隣り合った人同士で「良かったね」「面白かったね」などと短い感想を交わすのを見て、誰か誘えば良かったと千佳子は思う。
物語が生まれるきっかけになった夫の両親に声をかけることは遠慮した。スーパーでカズサさんの買い物をよく手伝っている野間さんも旅行の準備で忙しそうだった。高校でもバスケットボール部に入った文香は部活で、夫とふたりで行くのも照れ臭く、一人で行くことを選んだ。
けれど、一人で良かったとも思い直す。
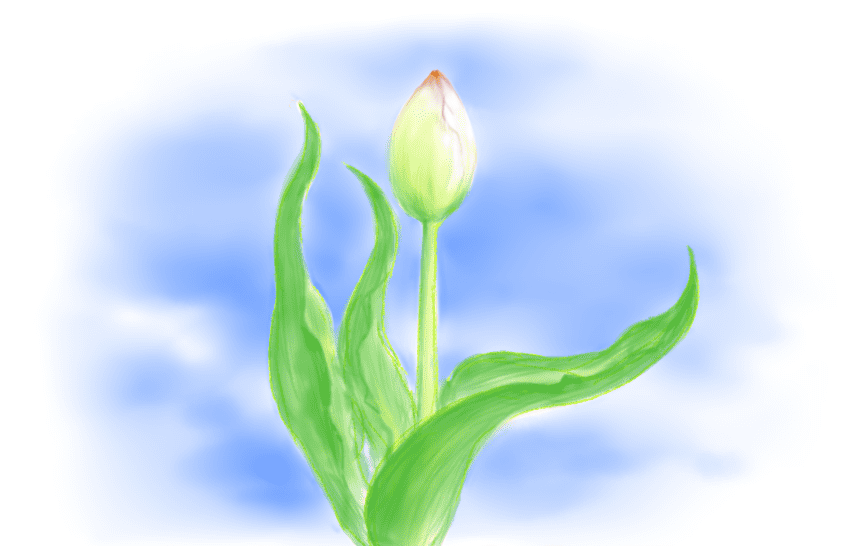
受付で配られたプログラムに、朗読される作品の題名と作者名が並んでいる。「日曜日と月曜日がケンカした」の題名の下に記された作者名は「十文字パセリ」。本名を出すのをためらって、旧姓を組み合わせた名前を作ったら、「ペンネームができましたね」とカズサさんに言われた。
ペンネーム十文字パセリ。
プログラムに載せるために生まれた名前から、佐藤千佳子とは違う、もう一人の自分が生まれたような気がした。
妻でもなく、母でもなく、パート従業員でもない、物語を書く人。
「紙って、閉じることも開くこともできるじゃないですか」
カズサさんの言葉が蘇る。二つ折りのプログラムを手に取り、開いたり閉じたりする。紙曜日のわたしが羽ばたきだす。
十文字パセリ。
この名前と、どこへ飛んで行こう。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第116回 佐藤千佳子(40)「チューリップの赤がしみる」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!