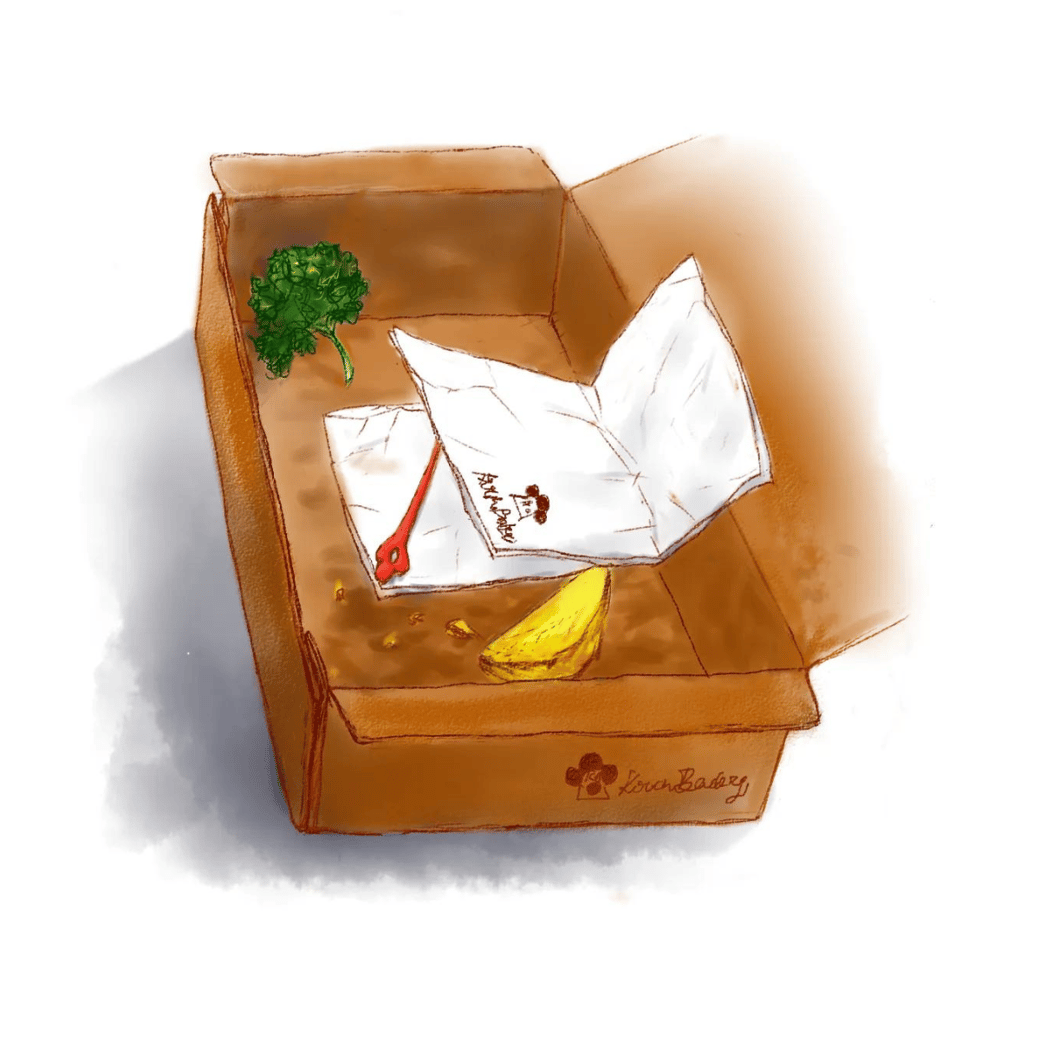第7回 佐藤千佳子(3) ママを引いたら何が残る?
乾杯のグラスを持ち上げたママたちの指先に千佳子の視線が吸い寄せられる。右隣の晴翔くんママの爪はジェルネイル、正面の悠真くんママはフレンチネイル。その隣の銀牙くんママの爪はワインレッド地にラメをあしらっている。一人だけ何もしていない裸の爪が恥ずかしくなり、千佳子はグラスをテーブルに置くと、指を丸めた。
泳がせた視線の先、ベランダに吊るしたプランターでミニバラが咲いている。低層マンションの最上階の広々としたLDK。これだけ広いから温めるのに時間がかかるんだなと思ってしまうが、冷えているのは部屋ではなく、千佳子自身なのかもしれない。
幼稚園時代のママ友の家に来ている。
ママ友と呼んでいいのかどうか。
自宅から一番近いという理由で選んだ幼稚園だった。朝、子どもを送った帰り、家が同じ方向のママ集団の後ろをしっぽのようについて歩き、そこにいない◯◯ちゃんママや◯◯先生の話題を聞くともなく聞いた。家の前まで来て、「じゃあ、お先に」と誰にともなく言うと、おしゃべりが一瞬止み、思い出したように「文香ちゃんママ、じゃあねー」と集団が振り返り、手を振った。
そして、しっぽを切り離した集団は、そこから5分ほど歩いた晴翔くんママの家で迎えの時間までおしゃべりして過ごすのだった。
千佳子は一度も誘われたことがなかった。礼儀として、まずはこちらがお誘いするべきなのかもしれないと思ったが、椅子もティーカップも人数分揃ってないしと気後れしていた。
一度だけ、晴翔くんママとふたりきりで幼稚園から帰ることになった朝、家の前で思い切って声をかけてみた。
「うち、寄っていく?」
「ありがとうー。すごくうれしいんだけど、これから美容院の予約入れててー。また誘ってね」
心から残念そうに言われ、「また誘うね」と千佳子も明るく応じたが、迎えのときに見た晴翔くんママの髪は、朝とどこが変わったのかわからなかった。
「また誘うね」は宙に浮いたまま、晴翔くんママから誘われることもなく、卒園した。小学校の学区が違ったり、私学に進んだりで、晴翔くんママ集団との接点はなくなった。
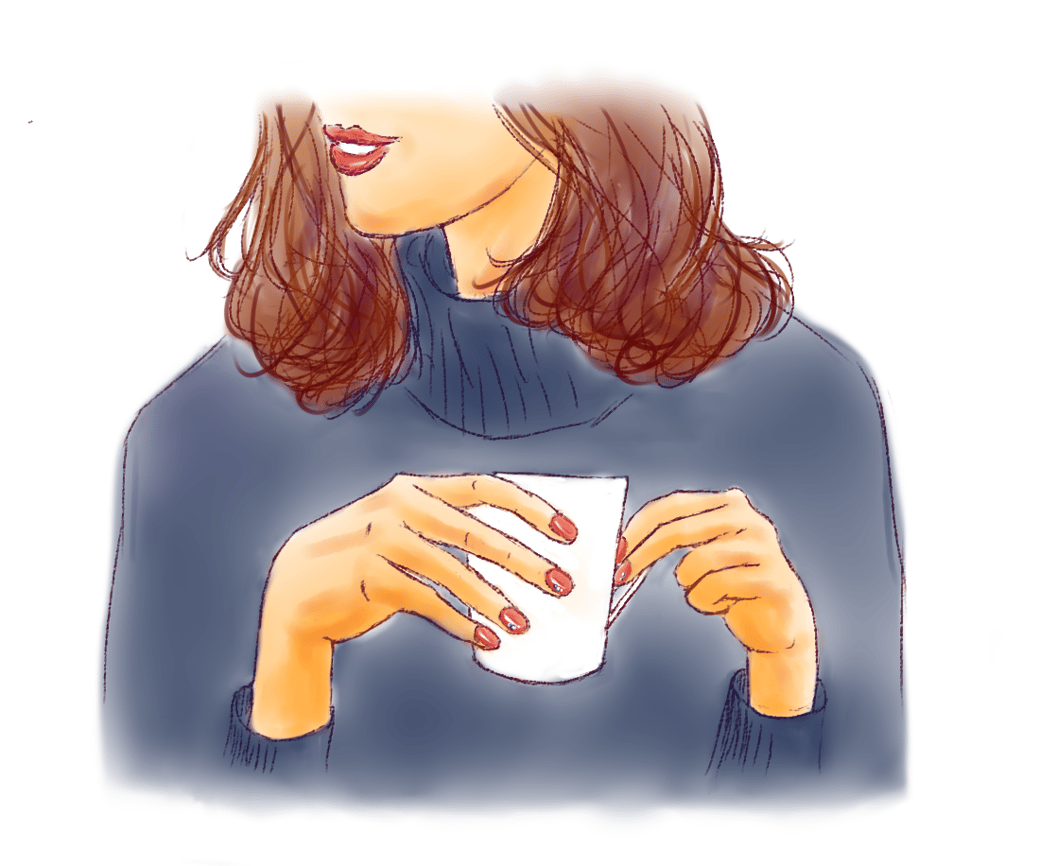
卒園から6年。一度も訪ねることはないと思っていた晴翔くんママの家でランチのテーブルを囲んでいる。
「皆さん、爪、きれいにされているんですね」と千佳子が言うと、ママたちは互いの指を見て、「ほんとだー」と笑い合った。
3人とも千佳子より年下、まだ30代に見える。季節を先取りしたような春色メイクでいっそう若やいで見える。
「これシールなの」と銀牙くんママが言うと、
「ほんと?シールに見えない!」
「サロンかと思ったー!」
悠真くんママと晴翔くんママが銀牙くんママの手元を覗き込み、千佳子は遠慮がちに首を伸ばして目を凝らす。
「私もネイルするの中学校の入学式のとき以来で、ショップカードどっか行っちゃってたー」
「人に会うのも気を遣うよねー。誘っちゃって大丈夫だった?」
「すごくうれしかったー。人の家にお邪魔するの久しぶりで」
「晴翔くんママ、いい機会作ってくれて、ありがとうー」
「こちらこそ、来てくれてありがとうー」
やりとりを聞きながら、千佳子は「そっか」となった。納得したのは、文香の誕生会のことだ。千佳子は例年通りやるつもりだったが、もし開いていたら、呼ばれたお友達やそのママたちを困らせてしまったかもしれない。
よく言えば大らかだが、悪く言えば鈍感。空気が読めない。世間の空気も、テーブルの空気も。今だって、「お誘いありがとう」と言うチャンスを逃してしまっている。
「晴翔くんママに声かけてもらって、ソワソワしちゃった。何着て行こう、何持って行こうって」
「わかるー。遠足の前の子どもみたいになっちゃった」
悠真くんママも銀牙くんママも、だいぶ前にお誘いがあったらしい。千佳子が声をかけられたのは、昨日の夕方だった。パート先のスーパーでレジを打っていたら、「やだー。文香ちゃんママー!」と買い物カゴの向こうから聞き覚えのある華やいだ声がして、晴翔くんママと再会した。
「じゃ、また」と社交辞令で言うと、
「明日のお昼空いてる?」と聞かれた。
多分、誰かが来られなくなって、3人だとバランスが悪いし、誰か適当な人がいたらと思っていたところに千佳子が現れたのだろう。
引き算で考えてしまう癖は子どもの頃からだ。クラスの人気者の誕生会に呼ばれている人数を数え、優先順位の低い自分のところまで回って来るかどうか計算する子だった。
中途半端な期待をして、傷つかないために。
「爪塗るだけで気分上がるよねー。女は先っぽに宿るって言うもんね」
ファッション誌の見出しみたいなこと、さらっと口にするんだと千佳子は感心した。爪にはジェルネイル、ひとつに束ねた髪の毛先をくるんと巻き、エクステのまつ毛をカールさせた晴翔くんママが言うと、説得力がある。
「あれ?恋は先っぽに宿る、じゃなかったっけ」と悠真くんママが言い、
「幸せは先っぽに宿るって聞いた気がする」と銀牙くんママが言い、
「神は細部に宿る、みたいなことかな」と千佳子は思う。
「女も恋も幸せも、全部先っぽに宿るってことで!」
晴翔くんママが景気良くまとめ、笑いが弾けた。
先っぽには神様も宿っているだろうか。
「わたしもネイルやってみようかな」
「やりなよー。文香ちゃんママ、爪の形きれいだし、塗りやすそう」
晴翔くんママの言葉に、悠真くんママと銀牙くんママが千佳子の手元を見て、「ほんとだー」とうなずく。自分が話題の中心になると、なんだかこそばゆい。
「良かったら、私が行ってるネイルサロン紹介するよー」
「ありがとう。でも、洗いものしたら落ちちゃわない?」
「どうかな。うちは食洗機に放り込むだけだから」
「そっかー。うち食洗機ないんだよね。やっぱりオプションでつけてもらえば良かったなー」
そこで会話はしぼんだ。せっかくつかんだとっかかりを自分から手放してしまった。

「ここ、初めてのお店なんだけど、ネットの評判良かったから」
悠真くんママが持ってきたサンドイッチは、一人分ずつクラフト紙のボックスに納められていた。前日までに予約が必要らしい。わたしが来なかったら、サンドイッチが一人分浮くところだったんだと思いながら、千佳子はクラブハウスサンドイッチをかじる。ベーコンの塩っ気がちょっぴり強く感じられる。
人数合わせ要員にされるのには慣れている。呼ばれないはずだった誕生会に当日呼ばれたこともあった。余計な主張をせず、すき間を埋める。あっても邪魔にならず、なくても困らない。彩りのパセリみたいな存在。サンドイッチに添えられたパセリに親近感を覚える。
晴翔くんママの用意したスープのレシピがインスタで人気の料理研究家さんのものだとか、ステイホーム中に見つけた筋トレ動画のこれが良かったとか、千佳子を通り過ぎて行ったり来たりする話題を、大なわとびに加われない子どものように輪の外側から聞いていた。
レシピを知りたい。
メイクを試したい。
新しいお店に行きたい。
情報源のインスタを見たい。
話題のスイーツを食べたい。
あの人と同じ服を着たい。
あれもこれも食べたいし、やせたい。
やりたいことを次々と思いつき、口にするママたちが眩しくて、それに引き換え自分はと物足りないような情けないような気持ちになる。
今のわたしは、彩りにすらなれていない。
「文香ちゃんママ、コーヒーと紅茶、どっちがいい?」
「皆さんに合わせます」
「どっちでも好きなほう言って」
「じゃあコーヒー、やっぱり紅茶で」
悩むようなことじゃないのに、悩んでしまう。食後の飲みものですら選べない。主張できない。
銀牙くんママが持って来たケーキは、文香の誕生日ケーキを買った店のものだった。
「ママは何になりたいの? ママって、やりたいことないの?」
13歳の誕生日を家族で祝ったあの日、文香に言われたことが、答えの出ない宿題となって千佳子の頭の片隅に居座っている。
わたしからママを引いたら、何が残るんだろう。
何かやらなくてはという輪郭のはっきりしない焦りが加算された。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第8回 佐藤千佳子(4)「パセリが主役になる日」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。