
第97回 佐藤千佳子(33)あなたの物語を読みたい
「ママ、描いてみたよ」
娘の文香が通学鞄から取り出したのは、太陽と月のイラストだった。ヨーロッパのアンティークな絵本を彩る銅版画のようなタッチで、線が細かく描き込まれている。
「ふーちゃん、またうまくなったね」
夕飯の準備を進めるキッチンカウンターの中から千佳子は目をやり、言葉をかける。
「毎日描いてるからね」
「授業中に?」
「授業もちゃんと聞いてるよ」
中学1年のとき、声優になりたいと言い出した文香は、3年になった今も憧れを募らせ、「推し」が出ているアニメをせっせと観ている。テレビではなくスマホの小さな画面で。そのアニメに出てくるキャラクターのグッズを買い、絵を描く。最初は横に並べて描き写していたが、今は何も見なくてもさらさらと描く。頭の中にキャラクターの造形が入っているのだ。
文香が描いた太陽と月は、文香の好きなアニメ作品のキャラクターとは佇まいが異なっていた。
「クリスマスのイラスト?」と千佳子が聞くと、
「ママ忘れたの? 日曜日と月曜日だよ」と文香はほっぺたを膨らませた。
日曜日と月曜日。
思い出した。寒空の下、ベンチに並んで焼きいもを半分こながら文香が言ったのだ。「本人」たちがケンカしたら、どうなるのだろうと。「一週間は日曜日から始まるか、月曜日から始まるか」で言い争いになり、今も別居を続けている横浜のじいじばあばは「日曜日と月曜日の代理」でケンカをしているという文香の発想に千佳子は感心したのだが、太陽と月のイラストとつながらなかった。
「そっか。日曜日ってお日様で、月曜日ってお月様だよね」
「そうだよ。ママ今さら何言ってんの?」
今さらなのだが、千佳子は忘れていた。カレンダーの火曜日を見ても火を連想しないし、水曜日を見ても水を連想しない。木も金も連想しない。曜日に色がついていない。月火水木金土日の漢字一文字に集約された記号になっている。
でも、子どもの頃は曜日に色がついていた。それがいつの間にかこぼれ落ちたのだ。イメージに変換する必要がなくなった。いや、ひまがなくなったのかもしれない。
15歳になったばかりの文香は、まだそれぞれの曜日とイメージが結びついているのだろう。
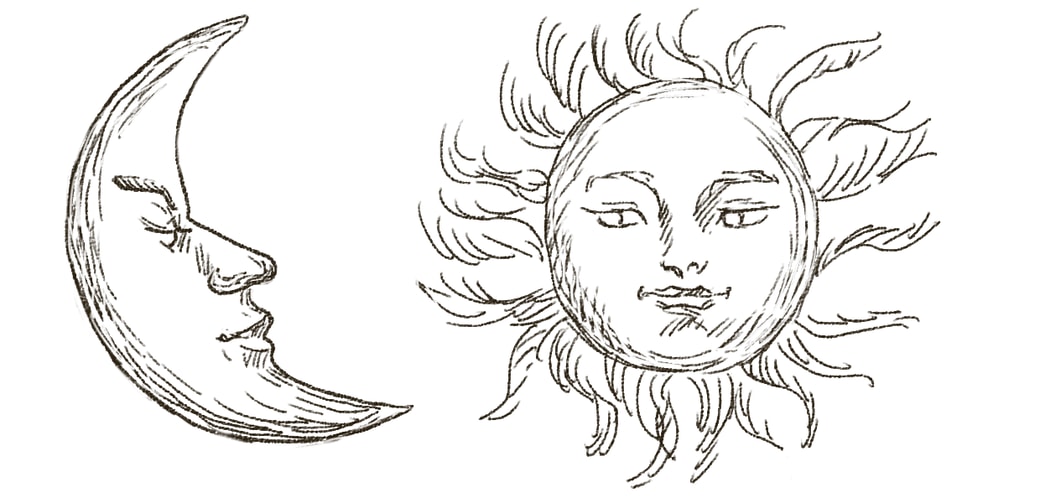
「ママ、この絵、絵本の表紙に使っていいよ」
「なんの絵本?」
「日曜日と月曜日、どっちがえらいかって絵本に決まってるでしょ」
「誰が作るの?」
「ママしかいないでしょ」
「なんで?」と聞くと、「ママお話作るのうまいじゃん」と迷いのない口ぶりで言われ、それだけで千佳子はその気になった。子どもの頃からほめられることが少なかったが、調子のいい娘は出し惜しみせずに持ち上げてくれる。
「ふーちゃんにクリスマスプレゼントもらっちゃったなー」
「毎日プレゼントもらってるでしょ?」
「そうだね。生まれ変わっても、ふーちゃんのママになっていい?」
「ママ、もう生まれ変わる気?」
文香に笑いながら突っ込まれ、生まれ変わるためにはいっぺん死ななくてはならないことに千佳子は気づく。娘を相手にさらりと口にする言葉ではなかった。
「ごめん、ふーちゃん。不吉なこと言っちゃった?」
「不吉じゃなくて大吉っしょ?」
「え?」
「うちのママになれるって、すっごく運いいよ。ママ、前世でどんだけ徳積んだの?」
文香は涼しい顔で生まれ変わり話にかぶせてきた。
「徳積まないと、ふーちゃんのママになれないの?」
「そうだよ。今世で相当頑張らないと、来世の続投はキビシーかも」
この頭の回転の速さと自己肯定感の高さは、どこから来たのだろう。千佳子でも夫でもない。もしかしたら夫の母、佐藤美枝子の隔世遺伝かもしれない。
野間さんの同居人で、今や千佳子のパートの同僚。「佐藤」が二人いるのはややこしいので、「美枝子ちゃん」と呼ぶ野間さんにならって、店長や他のパートさんも「美枝子さん」と呼んでいる。一人だけ「お義母さん」と呼ぶのも変なので、千佳子も「美枝子さん」と呼んでいる。
商品のバーコードをレジに通しながら、千佳子は物語を考える。店内放送がエンドレスでジングルベルを流している。今夜はクリスマスイブ。買い物カゴの中身もクリスマスだ。骨つきチキンだったり、サンタをのせたケーキだったり、もみの木模様のペーパーナプキンだったり。パセリのクリスマスツリーもよく出ている。
去年は本部で余った大量のリボンが「有効活用して」と押しつけられ、店舗によってはありがた迷惑となったが、千佳子たちの店ではいい形で活かされた。今年は本部からのお下がりが回ってこなかったが、「美枝子ちゃん」の友人が社長をやっているラッピング資材会社で在庫がだぶつき、運良くリボンを調達できた。美枝子株は上がる一方だ。
パートを終え、エプロンを脱いで買い物をする間も千佳子の頭の中では月曜日と日曜日がケンカを続けた。火曜日、水曜日、木曜日、金曜日も加わり、われこそがいちばんえらいと言い張り合うところまで話が膨らんだが、ケンカも物語も収拾がつかない。
「金曜日がいちばん偉いんですか?」
近くから声をかけられて千佳子が我に返ると、白杖をついたカズサさんがいた。
「カズサさん、わたしの心、読めるんですか!?」
「そんな特殊能力ないです。佐藤さん、今、金曜日がいちばんえらいってブツブツ言ってましたよ」
「あ……よくやるんです。脳内実況」
「佐藤さんもですか。私もやりますよ」
「仲間ですね」と声が重なり、笑い合った。カズサさんは店員の付き添いを頼まず、一人で買い物している。
「今日はお手伝いしなくて大丈夫だったんですか」
「これで買い物できるか実験中なんです」
そう言うと、カズサさんは商品棚についているプレートを手で触って見つけ、スマホをかざした。「パセリ 198円」と機械音声が読み上げ、「当たり」とカズサさんの声が弾んだ。
「文字を読んでくれるんですね」
「ラベルも読み上げてくれるんです」
だったら一人で買い物できますねと言いかけ、いや違うと千佳子は心の中で打ち消す。お目当ての商品が店内のどの辺りにあるかアタリをつけておかないと、延々と読み上げを繰り返すことになる。
カズサさんは袋入りのパセリを手に取り、根元のリボンを触って確かめると、「クリスマスですね」と言った。

パセリにリボンを巻いても、視覚を使わないカズサさんは目で気づくことができない。去年のクリスマスは「パセリのクリスマスツリー」の存在を知らないまま過ぎてしまった。
季節によってリボンがついていたりついていなかったりするのも、視覚を使わずに買い物する人には混乱を招くのではないか。そう思って、カズサさんに意見を聞いたところ、
「リボンがついてるとクリスマスだなって思うから、期間限定で巻くの、ありです。今年もやるなら教えてください」
と言ってもらえた。今のところ店に来る白杖のお客さんはカズサさんだけなので、今年もパセリのクリスマスツリーを並べることにしたのだった。
「今、日曜日と月曜日がケンカする話を考えているんです」
さっきの独り言の事情を話すと、「その話、読んでみたいです!」とカズサさんが飛びついた。
「読むって?」と千佳子が思わず聞き返すと、
「スマホに読み上げてもらえます」とカズサさんが力強く答えた。
「読みたい」とカズサさんに言われたことへの驚きが咄嗟に口に出たのだが、視覚を使わないカズサさんが「読む」ことへの戸惑いに聞こえてしまったらしい。
「あ、違うんです。物語を読みたいって言われたことにびっくりしちゃって」
「読みたいですよ。佐藤さんが書いたお話。佐藤さんの言葉って、優しくて、温かくて、好きなんです」
「読みたい」と言われたこと以上にびっくりした。夫の母が家を飛び出してからの数か月、それなりに気を揉んだり萎ませたりして迎えたクリスマス。パート先の野菜売り場で思いがけないプレゼントを差し出された。冷えた体に温かいスープがしみるように、このタイミングのカズサさんの言葉がしみる。
ダメ押しのように店内放送の「赤鼻のトナカイ」が流れ、涙を押し上げた。サンタクロースに慰められるトナカイと今の自分が重なった。
あなたはいいものを持っている。あなたが気づいていないだけで。
「佐藤さん大丈夫ですか?」
千佳子の言葉が途切れたことをカズサさんが心配する。
「大丈夫です」
その声に涙が混じっている。
わたし、今、人生でいちばん赤鼻のトナカイの気持ちがわかる。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第98回 佐藤千佳子(34)「ふたりで月日を重ねて」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































