
第151回 佐藤千佳子(51)咲かない花と咲いた花
重みのあるドアを押し開けると、カウンターの中にいるエプロン姿の男性と女性がこちらを見ていて、目が合った。まるで待ち構えていたみたいだ。
「このドアってセンサーか何かついてる?」と野間さんが冗談めかして言うと、「あれ? お客様、以前にも」と男性は声を弾ませ、ひげをたくわえた口元をほころばせた。
「覚えてくれてたの!?」と野間さんも声を弾ませ、「ほら、ここでショップカードもらったの」と千佳子に言い、「一目惚れしちゃいました!」と自分のチューリップバッグを持ち上げ、「それでこれも!」と千佳子のチューリップバッグを指差した。
「な? 言うたやろ? マキマキ」と男性が女性を見た。
「マキマキさん? もしかして」と千佳子が名前に反応すると、
「はい、バッグの作者です」と女性が言い、
「マキマキとモリゾウでmakimakimorizoです」と男性が言った。
マキマキさんとモリゾウさん。
歳は離れているが、お似合いだと千佳子は思う。共通の話題がたくさんあって、黙っていても気まずくなくて、ひだまりでそれぞれ本を読んで、読み終わったらその本を交換しそうだ。
誰でもいい。野間さんとふたりきりの状態から解放されることに千佳子はほっとする。
一時帰国した野間さんが桜を見たいと言い、開園と同時に入った新宿御苑を2時間かけて歩き回る間、ずっと惚気話を聞かされていた。話題を変えようとしても、掃除機のコードをジャッと巻き込むように一瞬で元の位置に戻ってしまう。
近況は手紙に書いていたが、会ったときに話したいことはたくさんあった。野間さんとパートで出会ったスーパーに今も買い物に来てくれる白杖のカズサさんやハーブのマイさんのこと。一時期野間さんの家に居候し、パート仲間にもなった夫の母のこと。娘の文香が3学期から朝起きられなくなり、2限目から、3限目からと少しずつ登校時間が後ろ倒しになっていること……。野間さんのベッドの話を聞くより、ベッドから起き出してこない娘の話を聞いて欲しい。
桜もぐずぐずしていた。今年は開花が遅れていて、ほとんどの木がまだ蕾だった。ソメイヨシノは花が咲いてから葉が追いかける。土気色の蕾をつけただけの姿は枯れ木のようだった。
「蕾がほころんだら別人みたいに見違えるんだよね。おばあちゃんが若返るみたい」
同じことを千佳子も思うのだが、恋人ができて浮かれている野間さんが口にすると、なんだか生々しい。蕾を近くで見ると、ほんのりと花びら色に染まっているものもある。いい歳して色気づいているように見えた。
みんな、ふしだらなんだから。
桜は千佳子をソワソワさせる。スーパーでのパートの帰り道に拾った桜の小枝をドレッシングの空き瓶に生けてキッチンカウンターに飾ったら、「きれいだね」と夫がほめたのは2年前の春だ。その言葉が自分に向けられたのだと一瞬勘違いしてドギマギした。そのとき動画配信講座の中学数学の確率の単元を聞きながら、「恋愛確率」について考えていた。
自分がこの先誰かと恋に落ちる可能性はあるのだろうかと。

行動を起こすほどの衝動はない。風に舞い上がる桜の花びらのように、ふわっと浮き上がり、一瞬の光を浴びて再び散り落ちた感情をあの日の桜は知っている。桜の季節が巡って来ると、秘密を握られているような落ち着きのなさを覚える。
「そう言えば、野間さん、人妻のうちに恋をして、ダンナを嫉妬させたかったって言ってましたよね?」
「言ってたね。でも、やっぱり今がいい。あの頃、他の誰かに出会ってたら、今、彼に会えてなかったかもしれないし。あの頃はまだ生理があったしね」
うわ、生々しい。
千佳子は思うと同時に口にしていた。
「ほんっとラク。妊娠の心配がないって」
野間さんはあっけらかんと言った。つまり、そういう関係を重ねていて、タイミングを気にせず大らかに楽しんでいるのだ。
野間さんって、いくつだっけ。そろそろ60歳だっけ。もう過ぎているかも。でも、日本にいたときより若返っている。
それにひきかえ、わたしときたら。花を開くことのない、桜色に染まる兆しすらない、土気色の蕾のままだ。
ときめきを覚えたことはある。一方的に。文香の高校受験のために契約した動画配信講座で「パセリ先生」とあだ名をつけた英語の男性講師に淡い恋を抱いた。彼の講座を何周も見た。時間にしたら数百時間になる。夫よりも顔を見て、声を聴いている。パセリ先生は夢にまで出てきて、千佳子と恋人になっていた。
唇が触れそうなところで夢を破ったのは、野間さんが間違ってスマホのボタンを押してしまったメッセンジャー通話だった。
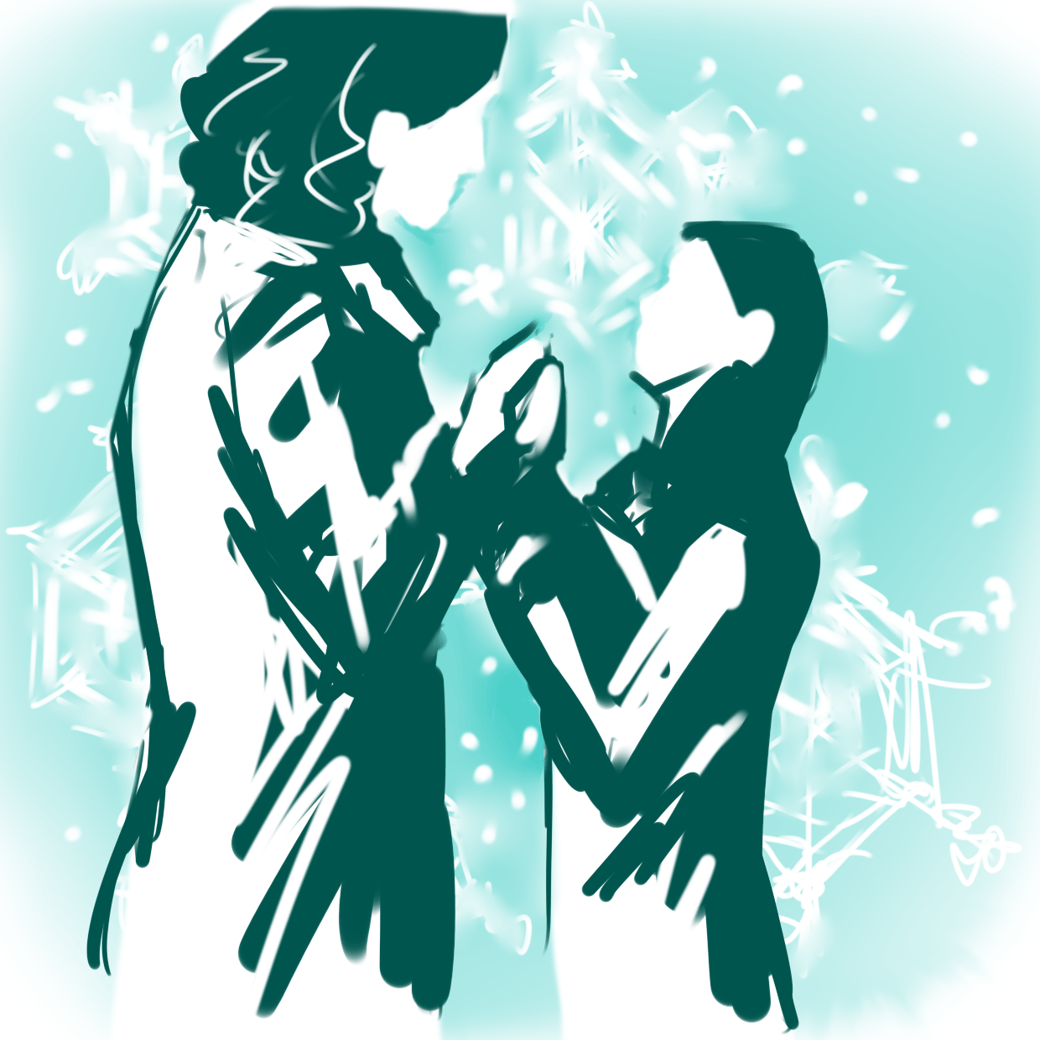
カウンター席に野間さんと並んで腰を下ろした。カウンターの中のふたりが真正面の特等席。
メニューはなく、ドリンクもフードも「言ってもらって、あれば出します」という力の抜け具合がモリゾウさんの飄々とした佇まいとよく合っている。道楽でやっている店という印象だ。野菜を食べたいとリクエストすると、「野菜やったら任せてください」とモリゾウさんは言い、「良かったらドリンクごちそうさせてください」と続けた。
「こっちがごちそうしたい気分。じゃあ一緒に乾杯しちゃいます?」
野間さんのノリの良さに「お仕事中ですよね?」と千佳子は心配するが、「そうしましょ」とモリゾウさんもノリがいい。「シュワシュワ、開けましょ」とモリゾウさんはスパークリングワインのボトルをワインセラーから出した。
他にお客さんはいない。商売っけがないのだ。makimakimorizoが本業で、こっちは趣味なのだろうか。店の前には「焙煎珈琲 然」と書かれた一枚木の看板が壁に立てかけられていたが、メニューも出ておらず、営業中かどうかもわからなかった。野間さんに連れて来られてなかったら、ドアを開ける勇気はなかった。
スパークリングワインのグラスが行き渡り、「何に乾杯?」と野間さんが一同を見回すと、
「テンペイに」とモリゾウさんが言った。
「テンペイに」とマキマキさんが笑う。
「テンペイ?」となりながらも、その響きがなんだか楽しくて、「テンペイに乾杯」と声とグラスを合わせた。

「テンペイってなんですか?」と千佳子が聞くと
「見てる人は、見てるっちゅうことです」とモリゾウさんが言った。
そう言えばと電車での出来事を思い出す。文香のお下がりのワンピースを着せたくなる赤ちゃんを膝に座らせたお母さんと短いやりとりをして、別れ際に声をかけられた。
「うまく聞き取れなくて、オリゾウですかって聞こえたんですけど、そのときもこのチューリップのバッグを持っていて、もしかしてバッグのブランドのことを聞かれたのかなって。それで、バッグをプレゼントされたときに見せてもらったショップカードにmakimakimorizoって書かれてたのを思い出したんです。で、後から思い出したんですけど、そのお母さんに取材されたことがあって。取材っていっても消費者意識調査みたいなやつで、リモートでインタビューされて。後になって、その人が月刊ウーマンって雑誌に見開きで載っていて、わたしのことを話してくれてたんです。わたし、それがうれしくて。自分のこと、添えもののパセリみたいな存在だと思ってたんですけど、パセリが主役になれたって」
「会うべき人には会えるようになってるってこと」
千佳子のたどたどしい説明を野間さんがきれいにまとめてくれた。
「な? マキマキ。やっぱし見てる人は見てるんや。でっかいチューリップ咲いたやん」
「ほんとだ。テンペイだ……」
マキマキさんが目頭を押さえる。千佳子は今日ここでこの話をするために新宿まで出て来たのだという気持ちになる。桜は咲いていなかったけれど、チューリップは咲かせられた。
「実は、アトリエを持てる部屋に引っ越そうと思ってたんですけど、その話がなくなってしまって」
マキマキさんが話し始めた。角地に立つ陽当たりのいいマンションの1階で、通りから見えるリビングをアトリエにしようと考えていた。小さな庭があって、そこに何の花を植えようかと想像を巡らせていたのだが、話が立ち消えになってしまったという。
話を聞いていて、ノマリーアントワネットの庭を思い出していた。野間さんがアムステルダムに行き、今は住む人がいなくなっているが、息子さんたちが週末に来て、庭に水をやり、家に風を通している。
「じゃあ、うちに住んでもらえる?」
一同が野間さんを見た。

次回4月6日に佐藤千佳子(52)を公開予定です。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!


















































































































































































































































































































































































































































