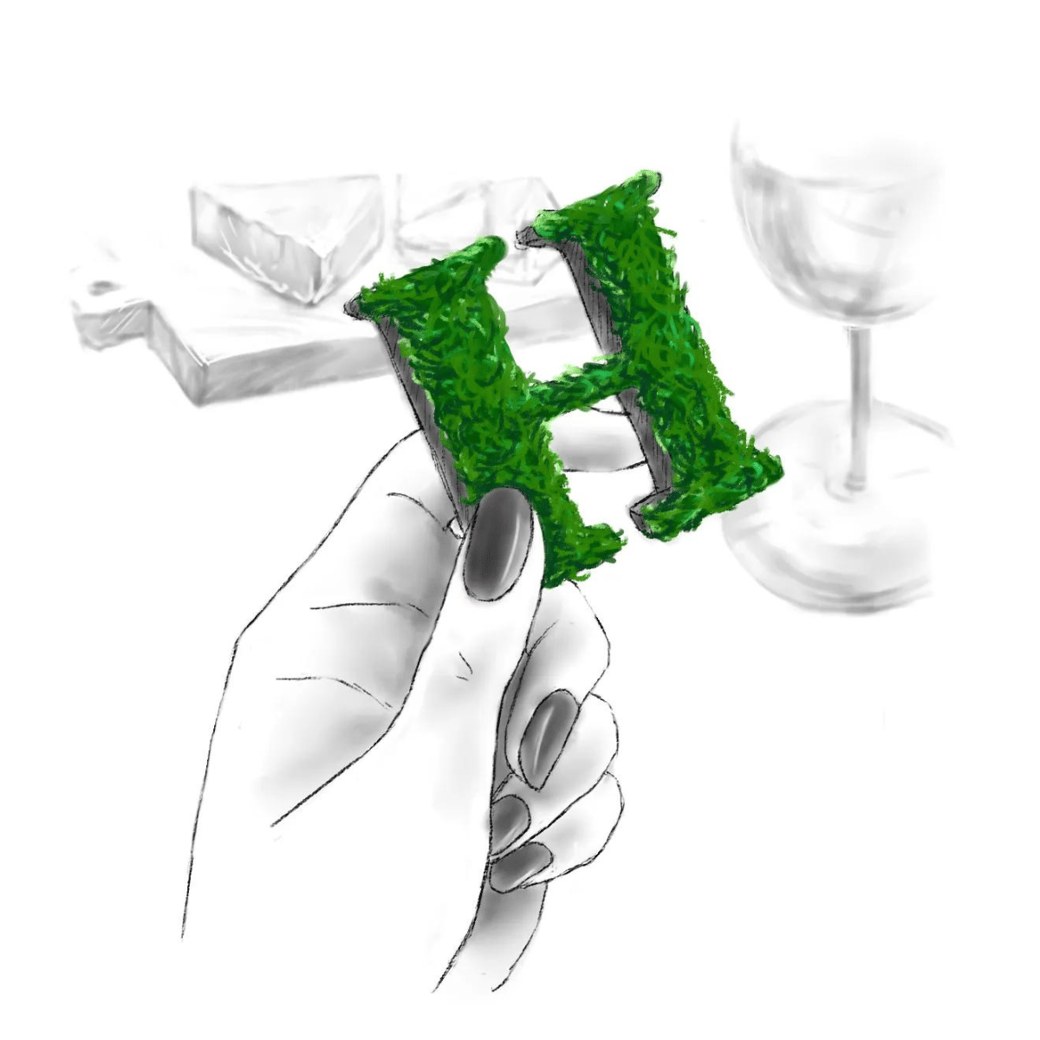第21回 伊澤直美(7) 先延ばしの呪いを解く方法
「Hが取れちゃったかー。ウケる」
「H」と「APPY」に分かれたオブジェは、同期入社のタヌキ(田沼深雪)の手作りだった。祝福の気持ちまで壊してしまったようで、直美は申し訳なく思っていたが、ワインの酔いも手伝って、タヌキは笑い話にしてくれた。
「HAPPY」は結婚式の受付を彩った後、直美とイザオが同棲時代から住んでいた部屋の玄関に飾られた。今のマンションに引っ越してからは、キッチンの飾り棚が定位置になった。イザオが怒りに任せてドアを閉めたときに棚から落ちるまでは。
イザオが出て行った日から1週間経った土曜の夜。イザオは同期のマトメ(的場始)のワンルームに転がり込み、玉突きでマトメの彼女のタヌキが直美の家に来て、ふたりで飲んでいる。
「これボンドでくっつけちゃえば?」
「くっつくかな」
オブジェはボンドでくっつけられたとしても、わたしとイザオは元に戻れるのだろうかと直美は心の中で続ける。
イザオが家を出たことは、何度かある。短いときは数時間。ジムで憂さを晴らして、仲直りのコンビニスイーツを買って帰って来た。長くてひと晩。どこかで夜を明かして、会社に行く時間までには帰っていた。こんなに長いのは初めてだ。
電話でも文字でも言葉を交わしていない。同じ会社に通っているし、マトメの部屋に寝泊まりしているのも知っている。心配することは何もない。不具合があるのは夫婦の関係だけだ。
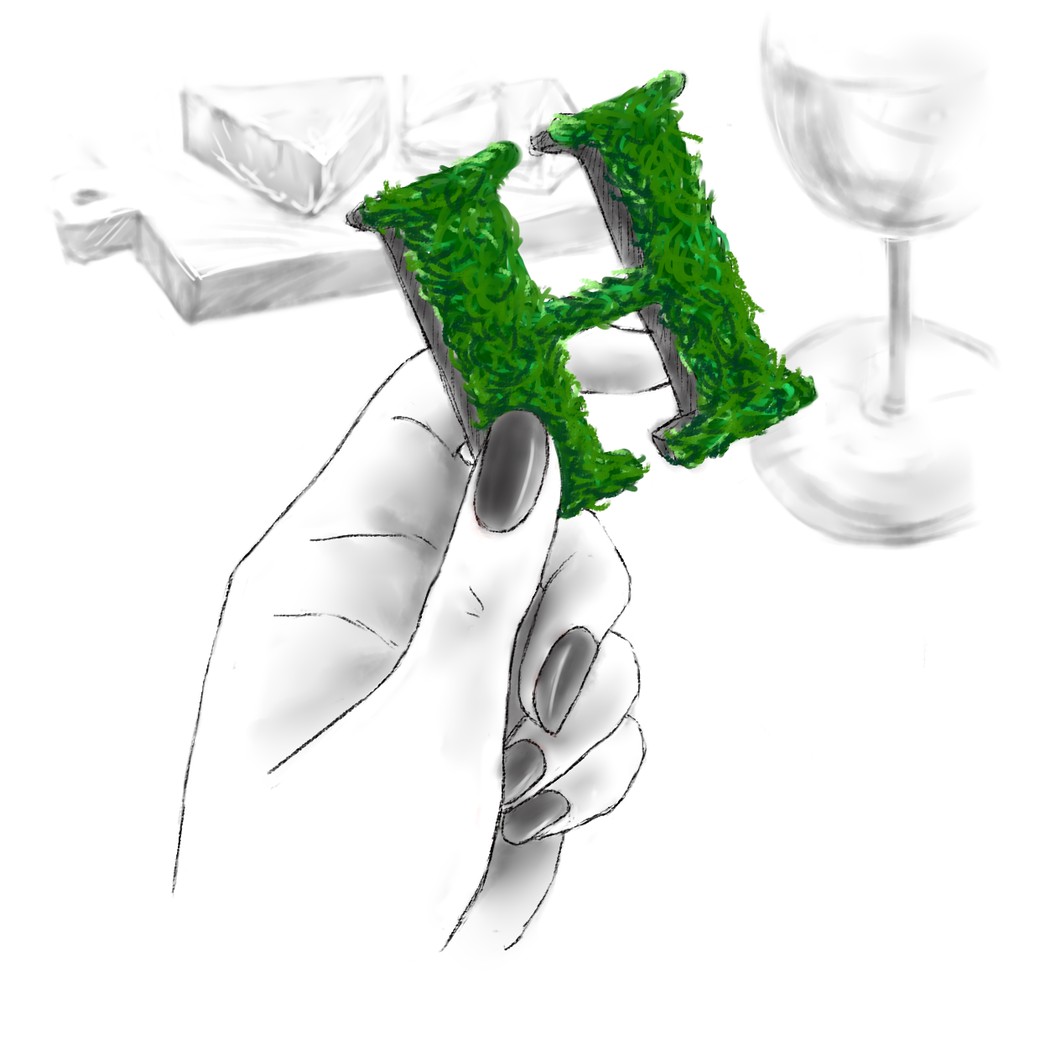
「相変わらず、してないの?」
左手に持った「H」と右手に持った「APPY」をくっつけたり離したりしながら、タヌキが聞いた。返事の代わりに直美はワインを飲む。
「もしかして、これがケンカの原因?」
タヌキが「H」を直美に向けた。
「きっかけは自転車だったんだけど」
輸入ブランドのクロスバイクを買って一緒に自転車通勤しようとイザオが言い出し、「子どもか自転車、どっちかにして」と店の人の前で直美が言い、それをイザオがなじり、反発したら、それ以上の怒りが返ってきた。そのことをタヌキに話すと、
「子どもか自転車かでケンカになる?」
「なるよ。なったよ。子どもができたら、わたしクロスバイク乗れなくなるじゃない? そんなことイザオは気づいてない。なのに、女ばっかり損するって被害者意識持たないほうがいいってイザオに説教されて」
「ハラミはさ、先延ばしの呪いにかかっているんだよ」
「先延ばしの呪い?」
「いつかそのうちって思ってはいるけど、今やってもうまくいかないって決めつけて、『いつか』から逃げてる」
そんなことないと言い返せなかった。今やらなくていい理由を見つけて、先延ばしにしている自覚はある。呪縛にかかっている。いや、甘えている。
「現状維持って、今が満ち足りてる証拠なんだよね。何も欠けさせたくなくて、守りに入っちゃう。でも、それって、思い込みで自分を縛っているだけなのかも」
手酌で注ぎ足したワインを一口飲んで、タヌキは続けた。
「同期で顔合わせした日に、ミスキャンパス獲ってるなら選び放題だったのに、なんでうちの会社にしたのって聞いたよね?」
タヌキも覚えていたのかとワインが苦くなる。美人なのにサバサバしているタヌキに、軽い気持ちで聞いてしまった。タヌキは「一通り内定もらったよ」と答え、直美がエントリーシートで落とされたテレビ局や広告代理店の名を挙げた。ちょっとムッとした口調で。
「あのときはごめん。失礼すぎる質問だった」
「うちの会社だけが、飲みに誘って来なかったって言ったよね?」
「うん」
「ちやほやしてくれた会社は、入ってからの自分の扱いが透けて見えちゃって。得意先との会食にコンパニオン代わりに連れて行かれて、何年かしたら寿退社するんだろうなって。眺めたいんだったら花でも飾っとけっての。派手な顔してるからって派手なとこに就職するわけじゃないよって。自己満足な青年の主張」
差し入れに持って来たチーズを切り分けながら、タヌキは自分語りを続ける。直美は口を挟まず、チーズをつまむ。
「ううん違うな。顔で採用されたんじゃないって言いたかっただけだ。そのくせエントリーシートでは思いっきりミスキャンパスを売りにしてさ。人間なんて矛盾だらけ。だからさ、子ども欲しいって言ってるイザオも、ハラミとクロスバイクで自転車通勤したいイザオも、どっちもほんとなんだよ」
タヌキの話はあちこちに飛ぶ。けれど、惑星の回転周期が合うように、何周か回って話がつながる。
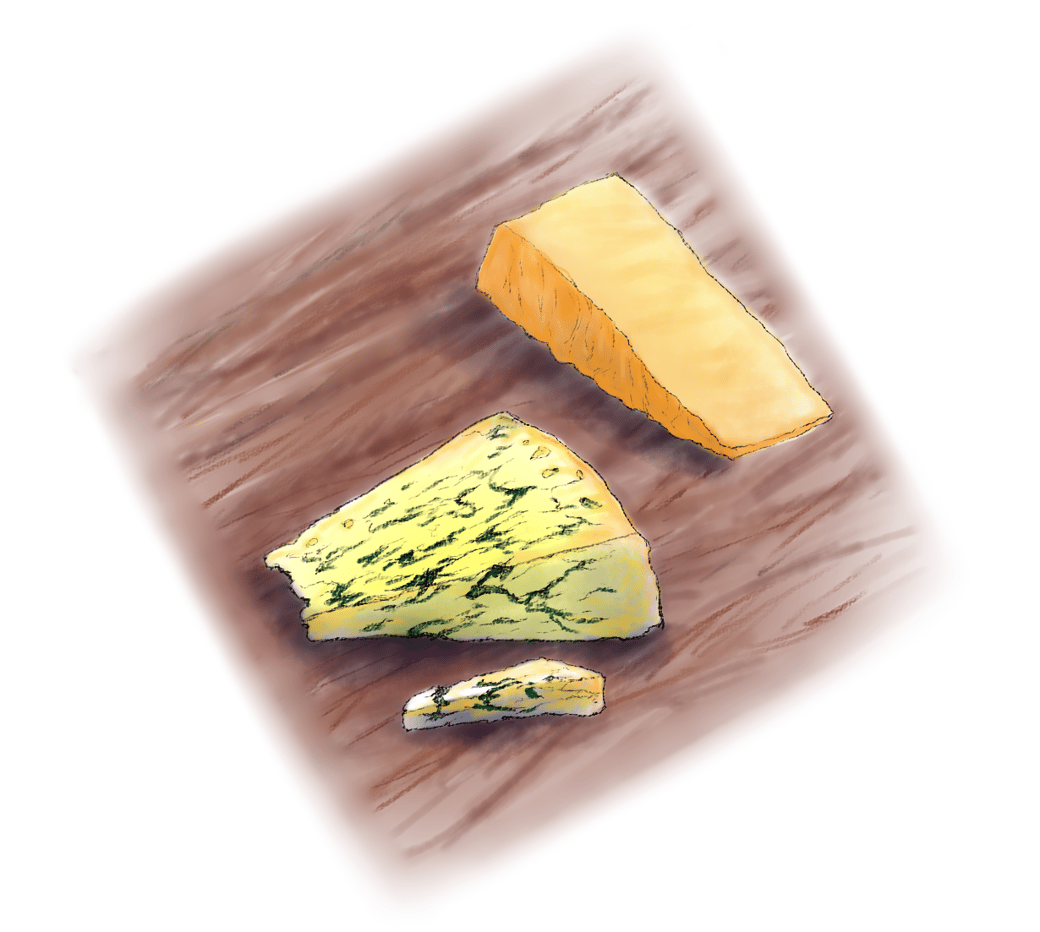
「ハラミ、先延ばしの呪いを解く方法、教えてあげよっか。『いつか』の『か』を後ろにずらす」
「いつかやる」が「いつやるか」になると、先延ばしの言い逃れは、期限を問う疑問文に変わる。
「いつか結婚する」は、「いつ結婚するか」に。「いつか子どもを持つ」は、「いつ子どもを持つか」に。
「で、ハラミとイザオはいつ仲直りするんですか?」
「いつにしよう、か」
「仲直りしてもらわないと困るんだよね。式のことも相談したいし」
「式って? タヌキ結婚するの!?」
「他に誰がいるの?」
「え、だって……いつの間に?」
「オンラインインタビューでパセリの花束のこと話してた人、いたじゃない?」
あの赤い唇の人だ。真っ赤なクロスバイクを見て、その人を連想した。それがあの日のケンカの導火線になった。直美には苦い記憶だ。
「パート先のスーパーで売ってる生ハーブブーケに手が出なくて、代わりにパセリを花束みたいに活けたらキッチンが明るくなって、その後に値引きシールがついたハーブブーケを買って、それも観葉植物みたいに活けてたら根っこが出て、プランターに植えたらどんどんふえて……私びっくりしたんだよね。こんなにしゃべることあるんだって。あれ以来、パセリ見たら、あの人の楽しそうな声が脳内再生されちゃって」
唇に気を取られていた直美は、値引きシールや根っこのくだりを覚えていなかった。同じ話を聞いても響くところがまるで違う。直美には口紅の赤が強烈だったが、タヌキにはパセリの緑が印象に残った。

「私、歳を取るのが怖かった」
ワインがたゆたうグラスに視線を落として、タヌキが言った。
「目減りする一方の私に何が残るんだろって。結婚相手に愛され続ける自信がなくて。だけどさ、パセリの花束とか、値引きシールとか、ささやかなことをあんなに楽しそうに話すあの人を見て、きれいだなって思った」
「きれい?」
「いい顔してた。この人、今の自分が好きなんだなって見とれてた」
直美は逆だった。口紅の色も話の内容も眩しすぎて、その人の顔を真っ直ぐ見られなかった。
「結婚したら、私の知らない私に会えるのかもしれない。食べたことない面白い味のチーズみたいに。その話をマトメにしたら、じゃあ結婚しようってなって。いつにしようかって言われて」
「それで呪いが解けたんだ?」
「解けた」
吹っ切れた顔でタヌキが笑うと、目尻にしわが寄った。出会ったときの気後れしそうな美人から時間が刻まれた今のタヌキもきれいで、見とれた。
「うわー、そんな盛り上がってるときに、うちの夫婦ゲンカに巻き込んじゃって、ほんとごめん」
「謝る前に言うことあるでしょ」
「おめでとう!」
スマホを手に取った。タヌキとマトメがついに結婚する。この喜びを誰よりも分かち合いたい人に電話をかける。今すぐ。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第22回 伊澤直美(8)「子どもよりわたしを欲しがってよ」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!