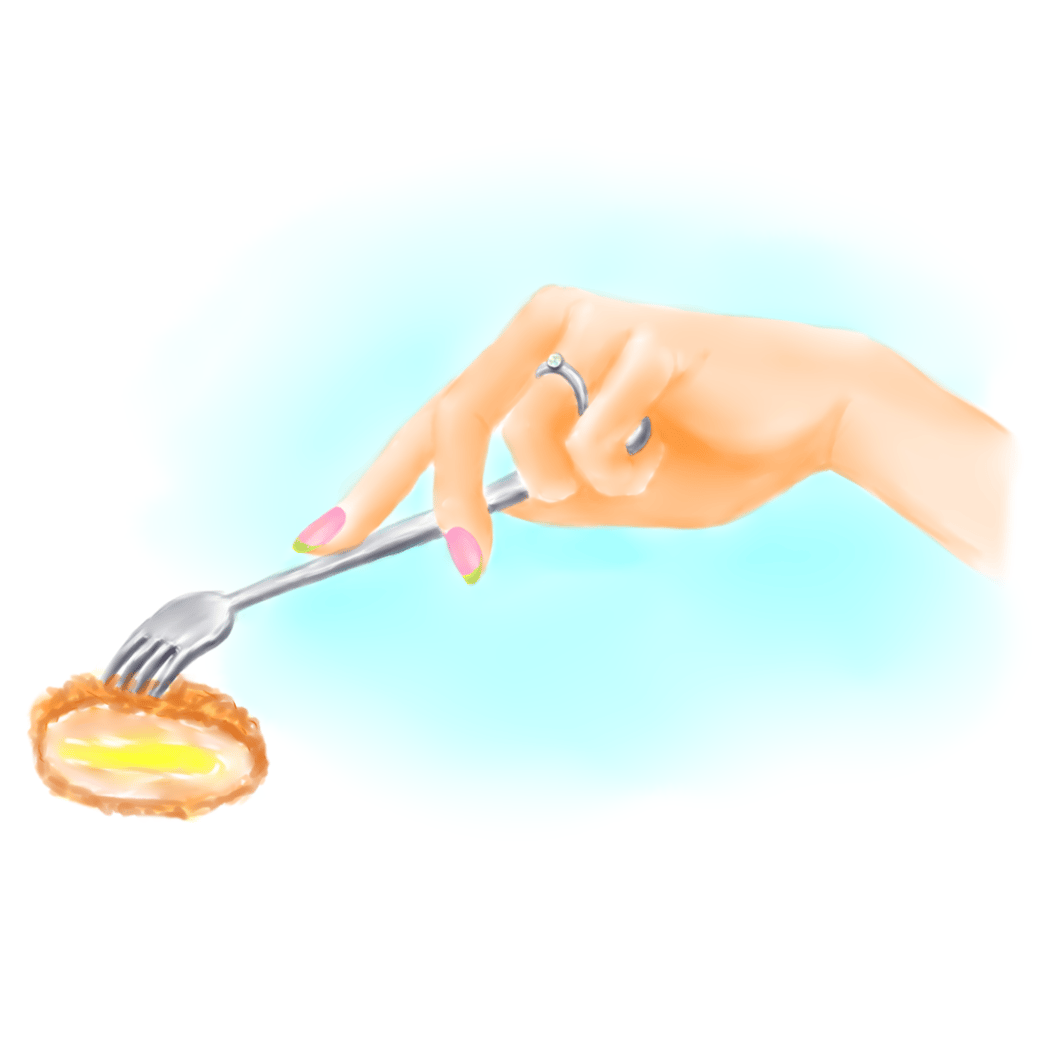第111回 伊澤直美(37)四つ葉のクローバーに胸がざわつく
「ストロベリーピスタチオのつもりなんだけど、マトメは桜餅って言うんだよね」
行きつけの洋食屋。ピンクとライトグリーンのフレンチネイルにしたばかりのタヌキがミラノ風カツレツを突き刺して言う。愚痴が惚気にしか聞こえない。
何度も延期になった挙式を控え、何度目かのウェディングエステに通っているタヌキは、肌も髪もツヤツヤしている。入社式で初めて会ったとき、なんて綺麗な子なんだろと見惚れたが、毎日会ううちに驚かなくなった。美人は3日で飽きるというのは本当だ。でも、このところのタヌキは、30代後半になっても留めているミスキャンパスの名残に磨きをかけ、会うたびに自己記録を更新している。ミセス雑誌の表紙を飾る勢いだ。
爪を伸ばせるのも今のうちだよと直美は思う。優亜を引っ掻いてしまわないように短く切った爪には、何も塗っていない。
「マトメ、和装が良かったらしい」
「袴似合いそうだよね」
「ていうかタキシードが絶望的に似合わない。借り物感すごいんだよね」
「タヌキと並ぶと、添え物感が出ちゃうんじゃないの?」
「それは言える。おつきの者感ね」
タヌキは褒め言葉を遠慮なく受け取る。「謙遜すると、余計イヤミになっちゃうから」というのがその理由で、美人にも美人なりの悩みがあるらしい。お祝いのスピーチで何度美人と言われるのか、直美でさえ今から聞き飽きている。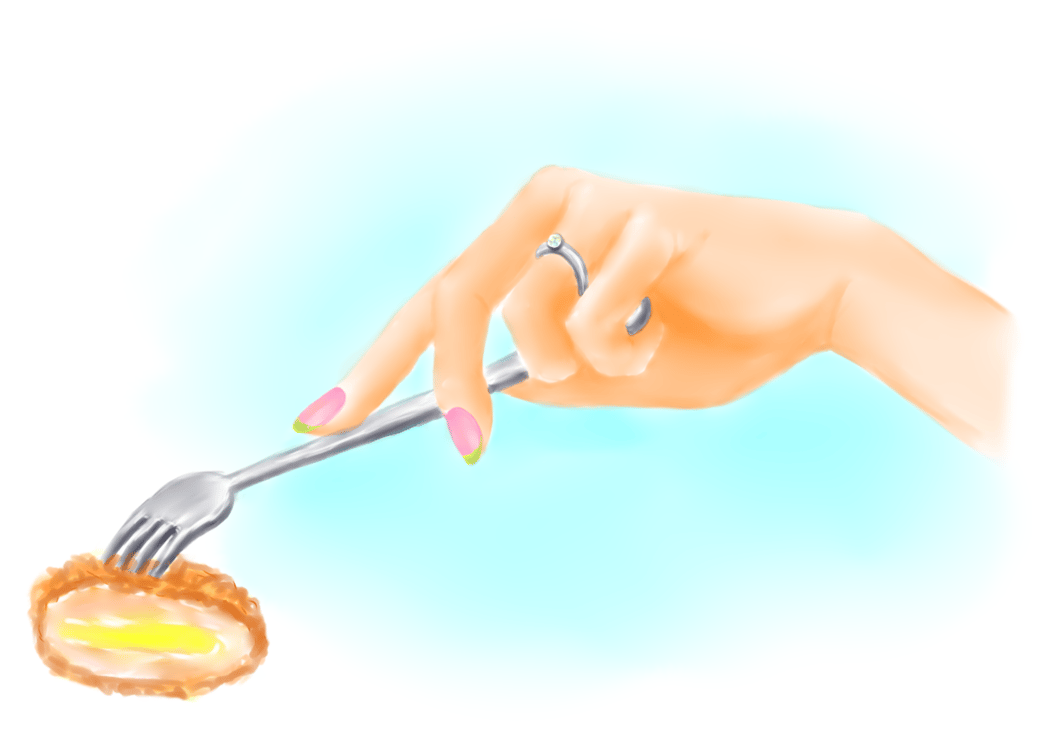
「ドレスどうするの?」
「母親が着てたやつにする」
「タヌキの趣味じゃないって言ってなかったっけ?」
「バーターだから」
式場の空きと希望日が合わず、タヌキの両親、特に母親が希望していた「ザ・披露宴」ができなくなった。そのおかげでタヌキとマトメが希望していたレストランウェディングが復活したのだが、式場で予約していたドレスを着られなくなった。その代わりにタヌキの母親が40年近く前に着たウェディングドレスが浮上したらしい。
レストランは直美とイザオが結婚パーティーを開いた場所だ。その日の3次会で、入社したときから片想いを募らせていたマトメはタヌキに想いを受け止めてもらえた。直美とイザオの結婚記念日はタヌキとマトメにとっても記念日で、パーティーを開いたレストランはタヌキとマトメにとっても思い出の場所だ。自分たちもあのレストランでという願いを一旦は却下されたが、度重なる延期でオセロがひっくり返った。
「ハラミとイザオによろしくって、エザキさん言ってたよ」
毎年、結婚記念日に予約を入れると、にこやかに迎えてくれたダンディな支配人エザキさん。ここ数年は行けていない。お店の営業自粛と重なった年もあった。でも、ちゃんと覚えてくれているらしい。
「女の子が生まれましたって言ったら、2人目ですかって聞かれちゃった」
結婚してから6年経つ。1人目だとしたら遅いのだ。悪気のない言葉だとわかってはいても、エザキさんのことをちょっと嫌いになる。エザキさんの言葉をそのまま伝えたタヌキもデリカシーがないなと思う。
サレ妻だったサエさんが2人目を身ごもったことを報告するインスタ投稿を思い出す。「私以外の人とは、できるんだ」って淋しさを分かち合える人だと思っていたのに。
「ハラミ、なんか暗くない? またレス?」
「またっていうか……」
「レス平常運転かー。うちら、カツレツ食べるときって、なぜかこの話になっちゃうね」
「タヌキがそっち持っていくからでしょ」
「けど、優亜ちゃんのまぐれ当たり、すごくない?」
「まぐれ当たりって言うな!」
タヌキとマトメが間を取り持ってくれてイザオと仲直りをしたあくる朝、優亜がお腹に入った。恩人ふたりの頭文字をつなげて「タマ」という名前を提案されたのは却下したが、あのときのタヌキとマトメがいなかったら優亜に会えなかったことは認める。

ハラヲカシタネとイザオは言った。
ひと月前。酒臭い息とともに。弱いくせに、酔っ払うまで飲んできて、眠っている優亜の顔を覗き込み、「どんどん俺に似てくる」と呂律の回らない口調で言った。それから、「ハラヲカシタネ」と言ったのだ。
最初、誰かの名前かと思った。「腹を貸したね」と漢字に変換されるまでに、十秒ほどかかった。
腹って、子宮のこと?
怒るより、ぽかんとしてしまった。「どういうこと?」と確かめる前に、イザオは床に転がって寝息を立て始めていた。
しばらくは忘れていたが、痛みは後から追いかけてきた。
「お子さん可愛いですね。パパ似かな」
すれ違った見知らぬ人の言葉が「ハラヲカシタネ」に翻訳された。
わたしは優亜が大きくなるための場所を提供しただけ。だから優亜とは似ていない。
人から見ても、そうなんだとダメ押しされた。
それからは、優亜が可愛いと言われるたびに、ハラヲカシタネを思い出し、傷ついた。なんで自分の子を可愛いと言われて傷つかなきゃいけないんだろうと悲しくなって、また傷ついた。引っ掻き傷だと思っていた傷口からバイ菌が入って、ジクジクと膿んでくる。
わかってる。深く考えることじゃない。イザオだって深い意味はなかったはずだ。「こんなこと言われたんだけど」と直美が突きつけたら、「そんなこと言うはずがない」と狼狽えるだろう。決して言ってはいけないことだとわかっているから。だけど、酔って気持ち良くなったときに、ぽろっとこぼれてしまった。それが本音なのだ。
そんなこと言った覚えはなくても、そんなこと思ってるんだ?
場所を貸しただけじゃない。優亜が無事育ち、お腹の外に出て来れるように、体に良いと言われるものをできるだけ取り込み、どれだけ気を遣ってきたことか。レンタルルームみたいに言わないで欲しい。自分は産めないから産んで欲しいと泣いて頼んだくせに。

なんだか割に合わない。自分だけが損をしているような無力感に見舞われる。
再会した母に、イザオは気に入られ、優亜はなついている。わたしと母との距離は縮まらないのに。
ccで入っていた社内プロジェクトの連絡メールが、いつからか届かなくなった。通知が来てうるさいから外してなんて頼んでいないのに。
ひまわりバッグに創作意欲が高まった亜子姉さんは、次々と新作を描いて、画像を送ってくる。わたしが書いた童話は落ちたのに。次の童話なんて簡単に思いつけないのに。
タヌキはウェディングエステでハンドパックされてツヤツヤの指にストロベリーピスタチオだか桜餅だかのネイルをして、浮かれている。わたしは爪を伸ばせないのに。
のに。のに。のに。
人と自分を勝手に引き算して、その差に落ち込む。自分で傷口を広げている。
「クローバーもいいかな」
タヌキは結婚パーティーのテーブルに飾る花を考えている。店に来る途中の花屋の店先に斑入りのクローバーが並んでいたのを見て、思いついたらしい。今のタヌキには全部四つ葉に見えるのだろう。
直美はひまわりバッグを購入したネットショップを思い出す。四つ葉のクローバーの刺繍が施されたポーチが3000円でひまわりバッグが6万円。20倍の差は何なのだろう。もちろん材料費や手間は何倍もかかっているだろうけれど、気が大きくなったのか。欲が出たのか。それで足元をすくわれたのだろうか。
ついスマホを開いて、知らなくてもいいことを調べてしまう。取り上げられた人の物語を消費したいだけなのだろうか。
「そういえば、ひまわりバッグの人に会ったよ」
「どっちの?」
聞き返した声が尖っていた。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第112回 伊澤直美(38)「そこに答えはないってわかってるのに」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!