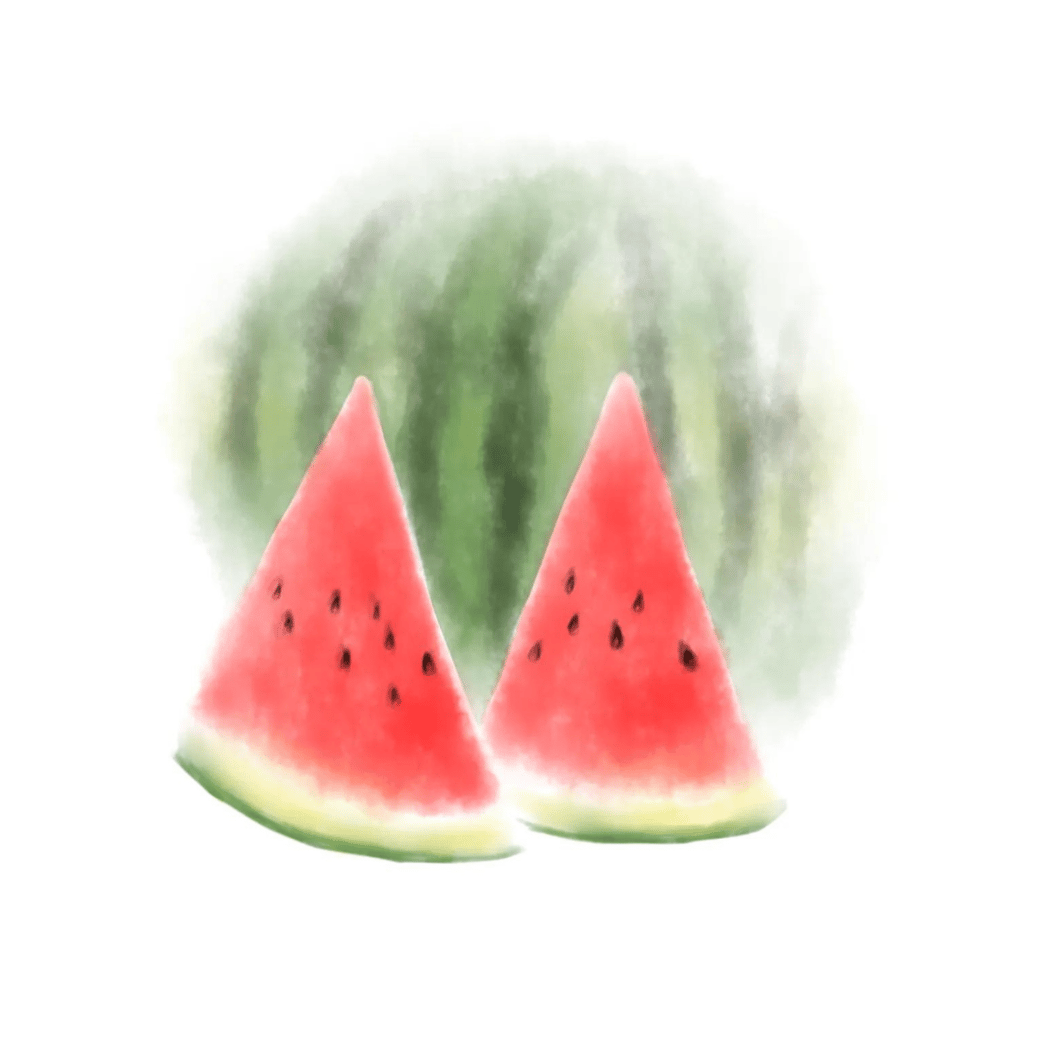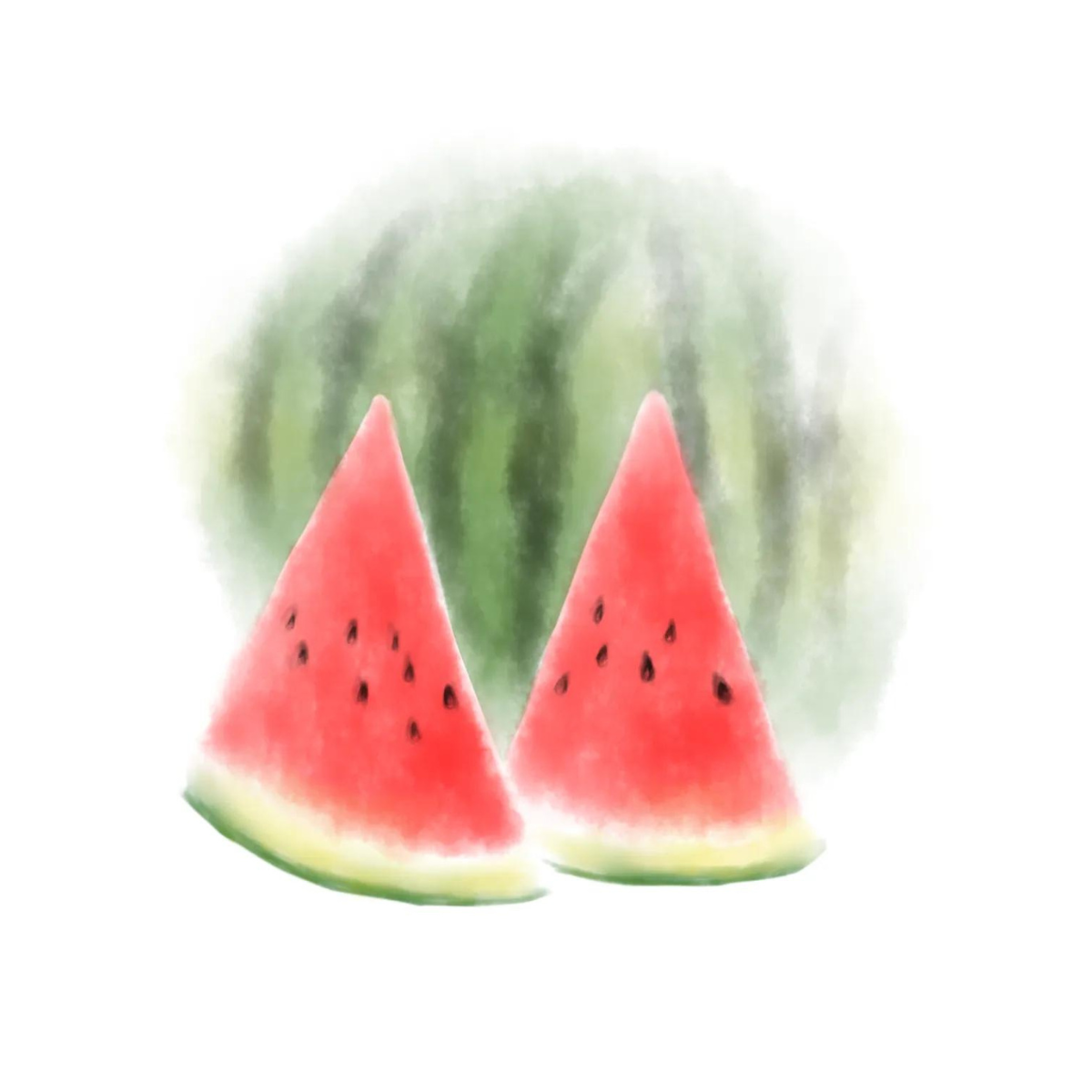第37回 佐藤千佳子(13) 空っぽってわけじゃない夏
足元がぐらついて立っていられなくなり、千佳子がリビングの床にへたり込むと、家がきしみながら揺れていた。
見上げたキッチンカウンターでは、オレンジのガーベラとパセリを活けているドレッシングの空き瓶が左右に首を振り、やじろべえのようにバランスを保っている。ガーベラとパセリが投げ出され、水が飛び散るのを、千佳子は身動きできないまま見ている。
背後でガタガタと大きな音がして、振り返ると、本棚が激しく揺さぶられ、背を壁に打ちつけていた。振動で背表紙が飛び出した一冊が本棚を離れ、放物線を描いて落ちて行く。フローリングの床に角をぶつけて跳ね返され、小さく舞い上がってから、床に着地し、横たわる。揺れる床の上で波打つ絵本は、漂流するボートのようだ。
『ふーちゃんの夏休み』
揺れに合わせて見え隠れする題名を読み上げ、そんな絵本、うちにあったっけと思ったところで目が覚めた。
床は揺れておらず、本棚も真っ直ぐ立っている。寝室ではなくリビングの床で寝てしまっていた。網戸の外から朝の風が流れ込んでくる。
キッチンカウンターの定位置に置いた花瓶代わりのドレッシングの空き瓶も無事だった。パセリの花束を活けて以来、中身を替えて、カウンターを彩っている。桜の小枝を挿したときは、夫が花を見て「きれいだね」と言ったのを、自分への言葉だと早合点した。パート先のスーパーでも生花を扱っていて、季節の花を手頃な値段で買える。今は、パートの先輩、野間さんが「ノマリー・アントワネットの庭」で育てた白いミニバラを活けている。
夢に出てきたガーベラとパセリは、少し前まで飾っていたものだ。夫と娘が贈ってくれた誕生日の花束が、花とパセリの組み合わせだった。

「夢は欲望の充足」だと短大の1年目に取った心理学の講義で教わった。小説の読み残したページのように、塗り残した塗り絵の白い部分のように、起きている間に思考が辿り着けなかったところを夢という形で埋め合わせるのだと。
試験に落ちる夢を、受ける前ではなく合格した後に見るのは、受験前は落ちたらどうしようと起きている間に思い詰めているので、夢に見る分の思い残しがないのだと講師は例を挙げた。その例にはピンと来なかったが、たしかに、十年前の震災のとき、地震は夢まで追って来なかった。怖い夢は昼のうちに十分見ていた。
「ママ、早くない? まだ6時前だよ」
花瓶の水を換えていると、文香が起き出してきて、時計に目をやった。
「地震の夢見ちゃった」
何気なく「地震」と口にしてから、「怖い夢じゃないよ」とつけ足した。
「今年も岩手のじいじばあばのうちに行けなかったからね」
千佳子が見た地震の夢と千佳子の故郷を結びつけた文香は、屈託がなかった。地震といえば十年前の震災を連想するが、それは自分とは遠く離れた土地の出来事だととらえているようだった。
十年前、横浜も激しい揺れに見舞われた。3歳だった文香は、あのときのことを覚えていないのかもしれない。そのほうがいい。千佳子のひざの上で小さな体を強張らせていた文香を、黒いクレヨンが尽きるまで画用紙を塗りつぶした文香を覚えているのは、わたしだけでいい。
現実でも、頭の中でも余震が続いていた。岩手にいる両親にも兄にも親戚にも連絡がつかず、故郷と切り離されたような寄る辺なさを味わった。いつでも帰れると思うから、故郷を離れて暮らしていけるのだと思い知った。あのときのグラグラした気持ちが、2年続けて帰省を見送ったこの夏、呼び覚まされたのだろうか。
千佳子の心の片隅に引っかかっていることが夢の中で揺さぶられて姿を現したのだとしたら、棚から落ちたあの絵本は……。
「『ふーちゃんの夏休み』っていう絵本が夢に出てきた」
「どんな絵本?」
「表紙だけ」
「どんな表紙?」
文香に聞かれて思い出そうとしたが、題名の他は覚えていなかった。どんな色だったか、どんな絵が描かれていたか。
「夏休み、今年もどこにも行けなかったし、ふーちゃんに夏の思い出、作ってあげられなかったよね」
「じゃあ、ママの夢に出てきた絵本は、真っ白ってこと? 自由帳みたいに?」
夢の中でページをめくっていたら、何が描かれていたのだろうと千佳子は想像する。岩手の実家の縁側でじいじばあばとスイカを食べているふーちゃん。あったはずの夏休み。
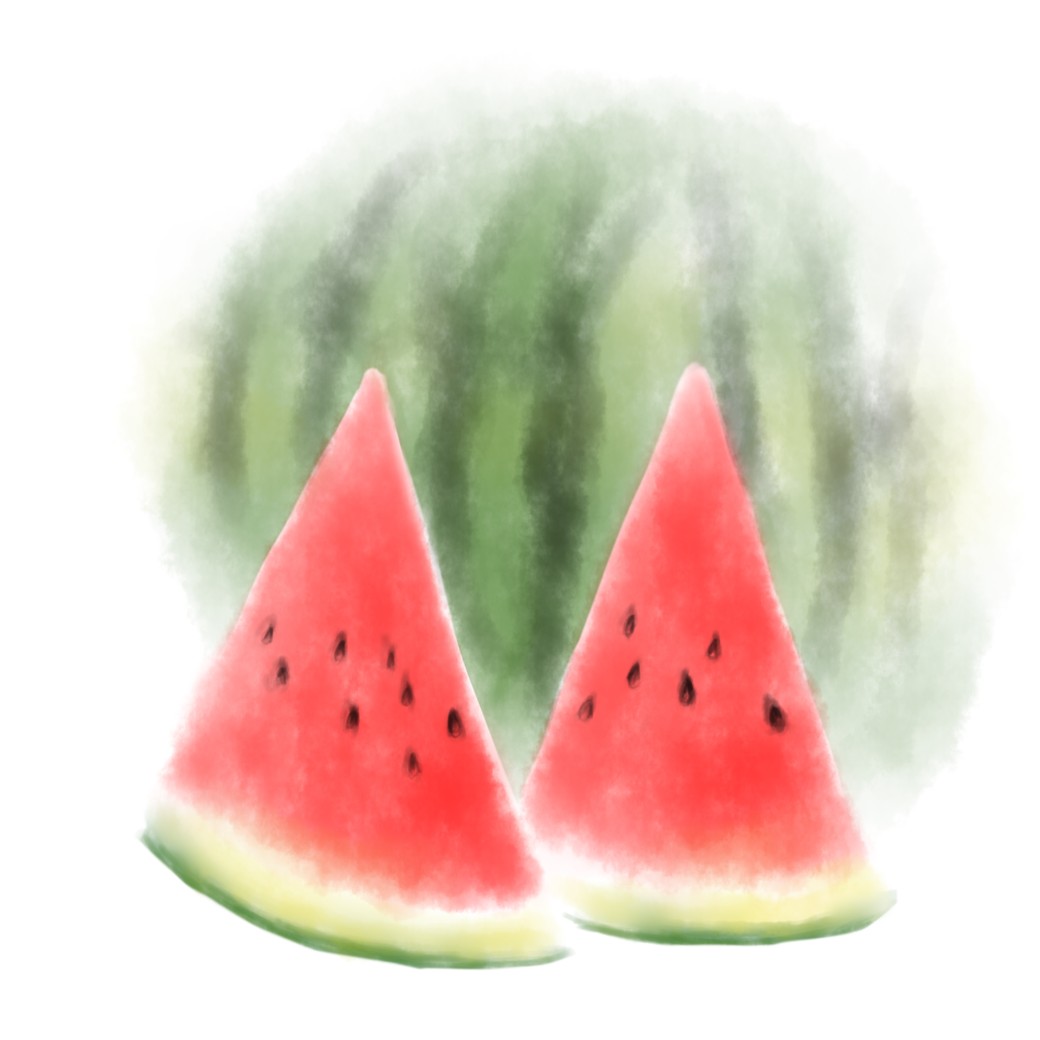
自室に引っ込んで戻って来た文香が、「これ」とプリントを差し出した。
「何?」
「ふーちゃんの夏休み」
「一行日記」と印字された横に「2年2組 佐藤文香」と記名してある。中学校の夏休みの宿題で出されたものだ。一日一行だと、夏休みの記録はA3用紙の片面に収まってしまう。
「読んでいいの?」
「いいよ」
《みんなー!夏休みになったよー!今気づいたけど、去年より行が狭くなってない? 二行書けないじゃん。あ、一行日記だからいいのか。》
《母がパートしているスーパーへ。私に気づいたら、よそ見するなと注意するつもりだったけど、気づかなかった。ヨシヨシ♪》
《油に塩コショウを入れてからフライドポテトを揚げるとおいしいって動画見て、作ってみた。止まらん♪》
《バスケ部の朝練。汗をかいた後の麦茶がおいしい。通販のタイムセールで見つけたタンブラーの保冷力、神♡》
《いいこと発見! ため息ついたら幸せが逃げちゃうっていうけど、マスクしてたら逃げないから、ため息ついてもオッケー♪》
《中学校が別々になったマッキーの誕生日。プレゼント、むっちゃ迷ったー。可愛いペンポ見つけて、私も欲しくなって、おそろにしたよ♪》
一行分の記入欄を目一杯使い、ときには二行になったり枠からはみ出したりして、文香の毎日が綴られている。夏休みらしい特別なことはなく、いつもの延長のような日々なのだが、鉛筆の文字は弾み、「♪」や「♡」が躍っている。なんでもない日の、なんでもない出来事が、文香に書き留められ、リボンをかけられている。
「ペンポって何?」と千佳子聞くと、
「ペンポーチ」と文香は答え、
「毎日それなりに書くことあるから」と日記を取り返した。
そのことを伝えようとして、日記を見せてくれたらしい。

「旅行だけが夏休みの思い出じゃないってことだね」と千佳子が言うと、
「そりゃー岩手のじいじばあばにも会いたかったし、旅行も行きたかったけど、思い出って、親に作ってもらうものでもないしね」
文香はドラマの決め台詞のようなことを言った。
いつの間にこの子は、こんな大人びたことを言うようになったのだろうと千佳子は文香を見る。寝間着にしている量販店の半袖と短パンのルームウェアから飛び出した手足は、夏の間にまた伸びた。背丈は千佳子を追い越し、胸の膨らみは大きくなり、腰まわりは丸くなり、体つきはすっかり大人だ。
地震のときは、わたしにしがみついて離れなかったのに。十年ちょっと前まで、オムツをして、おっぱいを飲んでいたのに。その少し前は、わたしのお腹の中にいたのに。その少し前は、影も形もなかったのに。
「絵本の中身、ママ、一緒に考えようよ」
「絵本の中身? 『ふーちゃんの夏休み』の?」
「うん。地震のとき、お話作ったみたいに」
地震のときみたいに?
「ふーちゃん、覚えてるの?」
次の物語、連載小説『漂うわたし』第38回 佐藤千佳子(14)「かいじゅうが不安を食べた夜」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!