
第60回 多賀麻希(20) どこにも行かないでと彼が言った理由
モリゾウの本名は武田唯人で合っていた。「タケダ・タダト」とモリゾウは自己紹介していた。講師をしているオンライン配信の英語講座で。
「見つかってたんすね」
モリゾウはほっとしたように言った。
「見つかりたくなかった?」
「話すと長くなるから」
「聞くよ」
どこから話そうかなと言ってモリゾウが語り出したのは、長くなると言いつつシンプルな話だった。モリゾウには借金があるのだ。中退してからも受給を止めなかった奨学金の他に、知り合いからまとまった額を借りている。知り合いについては言葉を濁した。古墳王子の顔がよぎったが、聞かないでおいた。誰からいくら借りているのかは麻希には関係のないことだ。
大事なことはすでに聞いていた。昨夜、灯りを消した後、モリゾウの腕に戻ったときに。
「何か言って」と麻希が言うと、
「どこにも行かないで」とモリゾウは言った。
麻希が言いたかったことをモリゾウに言われた。
「行かないよ。わたしのうちなんだから」
「わたしたちの」ではなく、「わたしの」と口にしてから、そう思っているんだなと気づいた。わたしがここからいなくなったらモリゾウはここにはいられなくなる。モリゾウはそのことを恐れているのだろうか。稼ぎはあるけれどモリゾウはどこにも行けない事情があるのかもしれないと想像した。
熊本から東京に出てきたものの年齢と胆石だけを着実に積み上げて40歳になって、ささやかな誇れるものと言えば服飾専門学校で身につけた洋裁技術で、そんな自分を「作家」として売り出そうと言ってくれた居候青年は長身で、魅力的な顔立ちで、抜群に声が良くて、話題も豊富で、彼がどこへも行かず、ここに留まり続ける理由は「お金がないから」ぐらいしか思い当たらなかった。
モリゾウに稼ぎがあると知ったとき裏切られたように感じたのは、お金を入れていないことへの不満というより、いつでも出て行ける自由を手にしていることへの不安が大きかったのだと思う。
お互いをつなぎ止めるようにキスをして、朝を迎えた。そして今、キスに費やしていた口をシュークリームに向けながら、モリゾウの借金の話を聞いている。

「借金を返し終わるまで、好きなだけ、いてくれていいよ」
できるだけ明るく言った。その日がすぐ来ないことを願って。
「借金がなくなったら、ここにいちゃダメなんすか?」
モリゾウが真顔で聞く。
「いたかったら、いてくれていいよ」
「いたいに決まってるじゃないすか」
そうなんだ、と意外そうに言ったが、その言葉を待っていた。
「俺、マキマキさんに一目惚れして、ずっと片想いしてたんすよ」
「それってなんかのセリフ?」
「セリフじゃないっすよ。本気っすよ」
「だって、声が良すぎるから」
「じゃあ黙ります」
モリゾウはすねたように言って、唇を押しつけてきた。麻希が食べているのと同じクリームの味がする。
「待って。シュークリーム食べきっちゃう」
麻希が唇を離してシュークリームをかじると、モリゾウが横入りしてきた。シュークリームとモリゾウを交互に相手にする。夜が明けるまでのキスは、夢中というより必死で、不確かなものを確かめようとしていたけれど、朝の光の中でシュークリームを食べながら交わす今のキスは無邪気だ。ずっと前からこんなことして笑い合っていたような気がする。

モリゾウの大きな手が部屋着の中に滑り込み、麻希の肌に触れる。麻希も手を伸ばす。互いの輪郭を確かめ合うように、肌をなぞり合う。骨がゴツゴツしているところ。ホクロで出っ張っているところ。こんなにじっくりと互いを慈しんだ記憶がなく、これまでは沿道の景色に脇目もふらず山頂を目指していたのだと麻希は気づく。山の稜線をたどるようにモリゾウが麻希の指の一本一本に挨拶する。
「ここ、ペンだこできてる」と低い声が耳元で囁く。
「そう、ペンだこ」
ペンだこって口にすると可愛い響きだ。ペンだこのある中指をモリゾウが口に含む。ペンだこを慈しむ。ペンだこをこしらえた麻希の過去を慈しむ。
服飾専門学校でデザイン画を描いていたときの記憶が蘇る。
同級生で一番目立っていたケイティに見込まれて、自分の課題そっちのけで彼女の課題提出を頑張り、それが認められて彼女は推薦で就職を決め、麻希はあぶれた。思わず振り返ってしまうほど綺麗な子だったけど、今はどうだろう。エステに通って、美貌を保っているだろうか。
エステ。
上京してすぐ、原宿で声をかけられ、芸能事務所のスカウトかと思ってついて行ったらエステの勧誘だった。紫外線にさらされて肌はどんどん老化するけどおしりは老けないと言われ、契約しそうになって逃げ出した。
あれから20年あまり。肌は20年分おしりから遠ざかり、恋愛も遠のいた。
最後の恋から10年あまり。
ツカサ君。
麻希と交わるとき、ツカサ君は「これでいい?」と何度も聞いた。何をするにも自信がなくて、間違っていることを恐れた。これでいいよと認めてもらいたくて脚本コンクールに応募していた。お父さんが倒れて、家業の旅館を継ぐために山形に帰ったのは、脚本家の夢を追いかけるよりも正しいことだったのだろう。
ストロボの連続写真のように過ぎ去った日のことが蘇る。モリゾウの指と舌が麻希の中の鍵のかかった扉を開けていく。モリゾウに触れられながら麻希がツカサ君のことを思い出しているように、モリゾウも誰かのことを思い出しているのかもしれない。
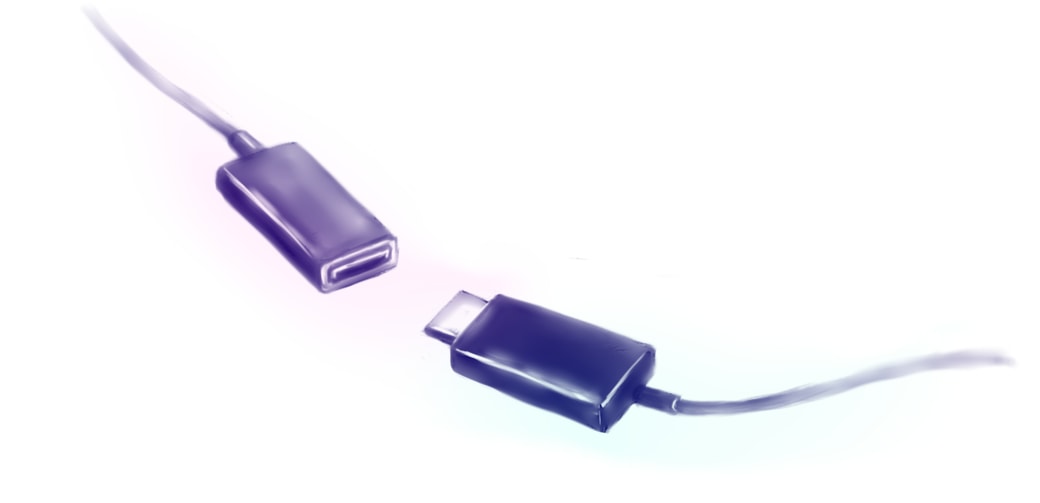
「電気がついたっす」とモリゾウが感想を言った。
「花火に喩えるのは聞いたことがあるけど、ほんと、電気好きだね」と麻希は笑った。
「人間の体ってすごいっすね。体にコンセントついてる」
「それで電気がついたって言ったの?」
コンセントやUSBケーブルにもオスとメスがあり、突っ込むほうがオスなのだとモリゾウの腕の中のピロートークで教わった。
男と女になっても、モリゾウとの暮らしは驚くほど変わらなかった。いつもの営みの延長線上に「電気をつける」が加わった。
バイト先の新宿三丁目のカフェのマスターには「マキマキ、綺麗になったなあ」と言われた。
「マスターに気づかれてました?」
「何が?」
「モリゾウとのこと」
「前からデキてるやん」
麻希とモリゾウが合うと見抜いて引き合わせたのは、マスターだ。体はともかく気持ちはとっくに結ばれていることを本人たちが自覚するより早く気づいていたのだろう。
「どこにも行かんといたりや」
モリゾウに「どこにも行かないで」と言われたばかりなのに、マスターにも同じことを言われた。
「わたし、そんなにどっか行っちゃいそうですか」
「あいつ、ずっと一人やから」
お腹に走った痛みをやり過ごそうとした麻希に病院へ行こうと勧めたとき、人は死にますよとモリゾウが言ったのを思い出した。その言い方が唐突で、突き放すように冷めていて、この人は身近な人を突然亡くしているのかもしれないと思った。
どこにも行かないで。
その言葉でモリゾウがつなぎ止めようとしたものの大きさと重さを思う。誰かを好きになると、その人を失うことを恐れる。だから永遠の約束が欲しくなる。
30代のどこかに置いてきた「結婚」の二文字が頭に浮かんだ。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第61回 佐藤千佳子(21)「こぼれた大豆に哀しみを覚えた頃」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!
























































































































































































































































































































































































































































