
第132回 多賀麻希(44)オリジナルって言い切れる?
ケイティの信者は全国にいる。熊本にだっているだろう。
もしかしたら……。
奈緒の顔が思い浮かんだ。3児の母となった今ではすっかり貫禄のある体型をしているが、昔は華奢で、可憐という言葉がよく似合った。
奈緒の線の細さも色の白さも母譲りだった。麻希は肌の色も骨格も父から受け継いでしまい、男の子とよく間違えられた。前髪を切り揃えたおかっぱ頭は、絵本に描かれた金太郎にそっくりだった。
幼い頃、行く先々で奈緒が「可愛いね」と言われるのを飽きるほど聞いた。奈緒への「可愛いね」は麻希への「似てないね」とセットだった。そんなとき、奈緒は「おねえちゃんはやさしいよ」と姉を気遣った。「可愛いね」と「似てないね」が組み合わさると凶器になること、そこに「やさしいよ」が加わると、傷を癒すどころか傷口を広げてしまうことを幼い麻希は身をもって学んだ。
奈緒の可愛さのピークは幼少期で、成長するにつれ普通になった。子どもの頃はあんなに可愛かったのにと言われてしまう「大成しない子役」顔なのだ。愛嬌の良さと大人受けの良さは衰えず、学校でも人気者だった。遠足や修学旅行の班決めで、どこかに入れてもらえるだろうかとドキドキしながら誰かが声をかけてくれるのを待った経験は、奈緒にはないだろう。
麻希が持っていないものを奈緒は持っている。だが、麻希が東京に出てから奈緒は言うのだ。「お姉ちゃんはいいよね」と。奈緒は奈緒でくすぶっていた。結婚し、子どもが次々に生まれ、3人の子に取り合いされ、再びモテ期が巡ってきて、今は満たされているように見えるのだけれど……。
奈緒の過去と現在に思いを馳せたのは、奈緒とよく似たケイティ信者のことを思い出したからだった。
以前、ひまわりバッグのエゴサが止まらなくなっていたときにインスタで見かけたその人を一瞬、奈緒と見間違えた。よく見ると別人だったのだが、ふっくらした体つきと笑ったときの口の開け方が奈緒にそっくりだった。
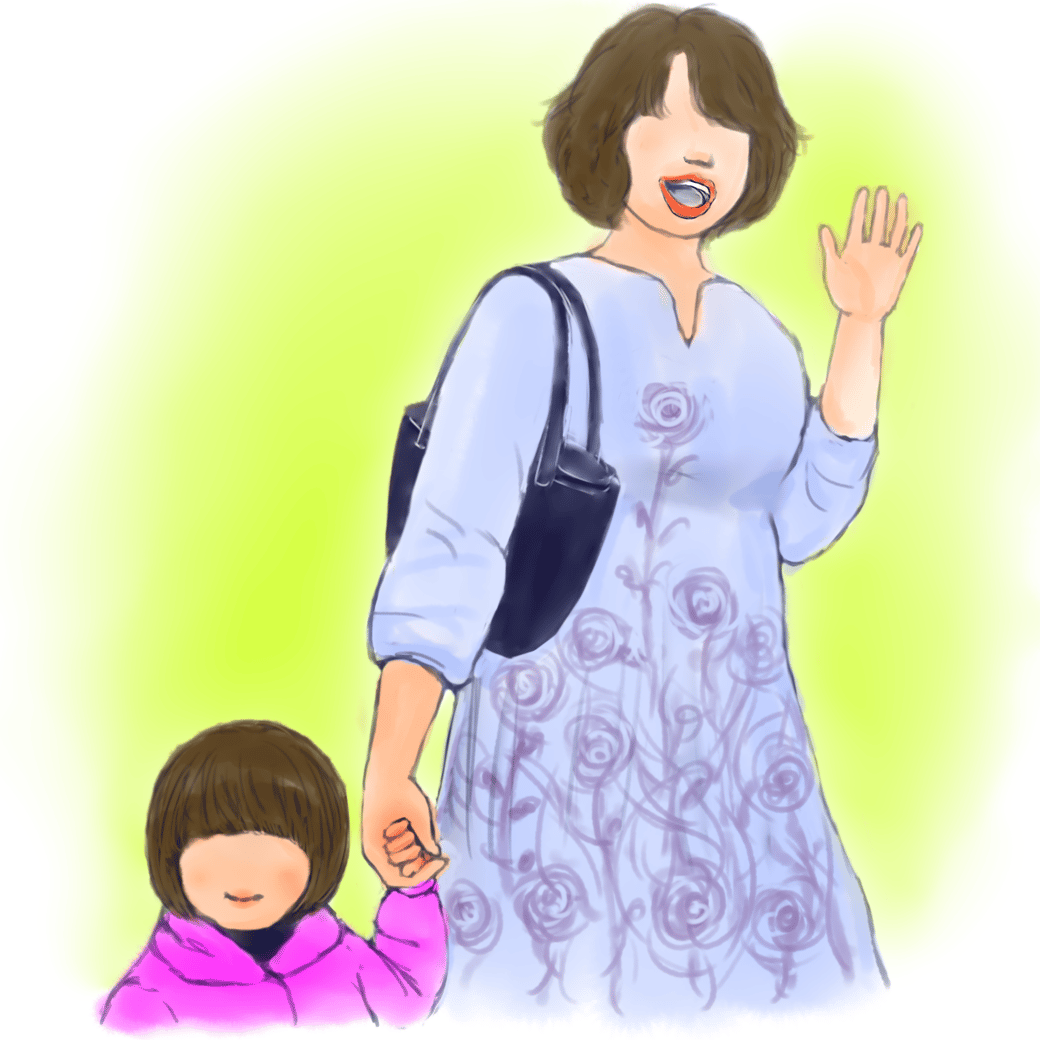
前向きすぎる投稿に前向きすぎるコメントが連なり、煮詰められて煮こじれていた。強気と強がりが混ざり合い、熟成して粘り気を帯び、近づくと絡め取られてしまいそうだった。
私たちはまだまだ行ける。立ち止まってなんか、いられない。
自分たちを「チーム咲きびと」と呼ぶケイティ信者たちは「OKT(オッケイティ)」を合言葉に自分たちを奮い立たせているのだが、センスの悪いTシャツをお揃いで着てはしゃいでいるみたいと冷めた目で見てしまうのは、その輪に入れなかった者のヒガミだろうか。
日の光を人一倍浴びてきた、ひなたの人たち。彼女たちが競って手に入れたお揃いのバッグのペラペラのひまわりは、彼女たちの顔に貼りつけた笑顔みたいだ。
奈緒もひまわりバッグを持って「OKT」を連呼しているのだろうか。
「そんなこと……あるのかな」
動揺が声になってあふれた。
「そんなことって?」とモリゾウが麻希を見る。
「奈緒がケイティのひまわりバッグを買ったのかも。それを見て、悠人がこの絵を描いたのかも」「どうかな」とモリゾウは同意せず、「どっちかっていうと、マキマキのほうに似てない? 色使いとか」と麻希のスマホに届いた絵に目を落とした。
「じゃあ、どっかでわたしのひまわりバッグの写真を見たのかな」
「何も見ないで描いた可能性はないの?」
「そんなこと……」
「ありえない」と言いかけたのを飲み込み、麻希は考える。
悠人がたまたまひまわりバッグを目にして描くのと、たまたま描いた絵が麻希のデザインに似るのと、どちらがありえないのだろう。
「舞台の戯曲をドラマで使われた話、したよね?」
麻希はうなずき、半年前の冬の日を思い出す。カフェのバイトを休み、モリゾウに代わりに行ってもらっている間、スマホでエゴサを続けていた。そんな麻希を部屋から連れ出すために駅まで呼び出したモリゾウから話を聞いた。
『たとえこの雪が溶けてしまうとしても』という舞台の公演から半年ほどして『雪だるまの涙』という連ドラが放送された。医療ミスで記憶の蓄積ができなくなった夫とその妻が結婚前のヒロインとその婚約者に置き換えられていたが、消えゆく記憶を溶けゆく雪に重ねる設定がそっくりだった。ドラマのサイトにあったプロデューサーのコメントは、舞台のチラシにあった言葉がそのまま使われていた。
「覚えてる」
その日、東京に雪は積もっていなかったし、麻希の手はモリゾウのコートのポケットに温められていたのだが、記憶の中では赤い手袋をはめて、ブロック塀に積もった雪を固めている。
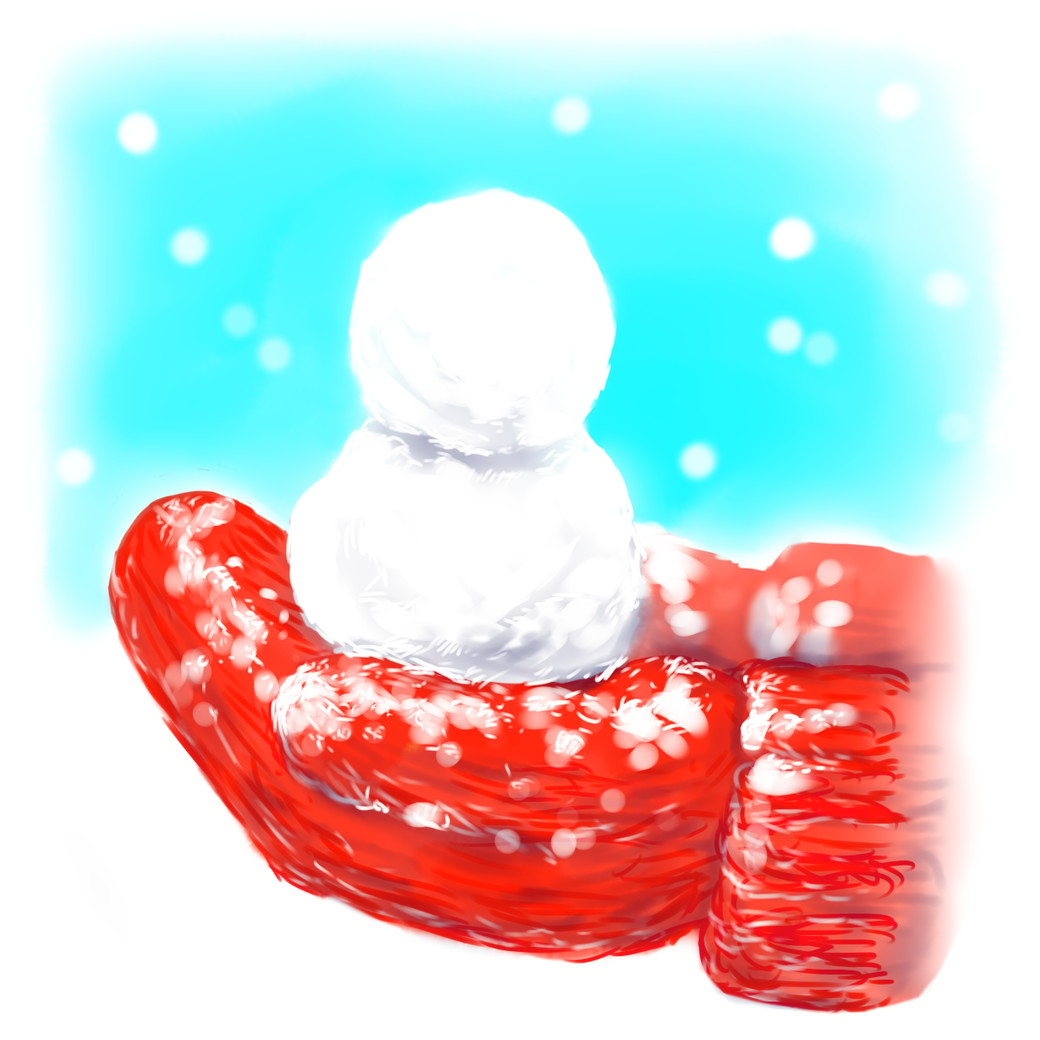
「俺らの舞台にそのプロデューサーを呼んだの、高低差太郎でさ」
「そんな気がしてた」
高低差太郎はモリゾウがつけた役者名だ。モリゾウの演劇仲間だった彼は今「古墳王子」と名乗り、タレント活動で忙しくしている。
「あのドラマ作った後、プロデューサーはバラエティ部に異動になってさ」
「もしかして、古墳王子が出てる番組って……」
「古墳王子を売り出したのが、そのプロデューサーなんだよ」
「やっぱり……そういうこと?」
「どうかな」
今日2回目の「どうかな」が出た。
「あのとき、高低差太郎に言われたんだよ。お前が先に思いついたって、どうして言えるんだって」
「そんなの……」
ケイティに開き直られたときのことを思い出し、麻希は胸の奥がキュッと締めつけられる。
「じゃあチラシの言葉はどうなんだよって食い下がったら、その言葉だけ借りたんじゃないのって」
その論法に麻希はデジャヴを覚える。ケイティも古墳王子もその場その場で自分を正当化し、言語化する反射能力が高いのだ。そういう人がのし上がっていく。
「そんなことあるわけないだろって思った。そのときは。でも、本当にそうなのかな」とモリゾウが言った。
「明らかにあっちが真似してるっていうか、盗んでるでしょ?」と麻希の語気が強くなる。モリゾウの負けは自分の負けだ。
「それはそうだとして。俺より前に同じことを考えた人はいなかったのかな」
モリゾウより前に?
「消えゆく記憶を引き止めるように雪だるまを固める場面って、俺じゃなくても思いつくよね? 同じことを思いつく人は自分の他にもいるかもしれない。いてもおかしくない。じゃあオリジナルって何なんだって話なんだけど」
「何なの?」
何だろねとモリゾウがトルソーに目をやった。クローバーの刺繍を施したウェディングドレスを脱がせてからは、裸のままだ。

「高低差太郎に食い下がったのは、あれ以上の作品を書ける自信がなかったってのもあったと思う。だけど、過去にしがみつくんじゃなくて、次の作品で示すやり方もあったのかなって。オリジナルの主張は難しいけど、オリジナリティは積み重ねで作っていけるから」
ひまわりバッグのオリジナルはひまわりだとケイティは開き直った。言い逃れだと麻希は思ったし、今も思っているが、ひまわりをバッグにするのは突飛なアイデアではないし、それを思いついたら似たようなデザインが生まれる可能性はある。アンティークビーズをふんだんに使ったのは麻希版のこだわりだが、ケイティ版ではスパンコール状のシートになっている。デザインを盗まれたというより、アイデアと形状以外はまったく違う劣化版を作られたと言ったほうがいいかもしれない。
「『これはわたしの』に囚われるより、『これがわたし』を作っていけってこと? わたしも、モリゾウも」
返事の代わりにモリゾウは麻希の頭に手をやり、髪をくしゅくしゅっとする。モリゾウの長い指がかつてエンダツがあった場所に触れる。更地だったその場所に、ほよほよした産毛が生えてエンダツを覆い、今では境目がわからなくなっている。高校生だった麻希が放った火が焼いた裏庭に草が芽吹き、一面の緑を取り戻したように。
そうだ。根っこまで引っこ抜かれたわけじゃない。わたしのひまわりにもケイティのひまわりにも似ていない、別なひまわりを咲かせればいい。他の花だっていい。花でなくたっていい。同じ根っこでつながってる作品は、きっと、わかる人にはわかるから。
何でも受け止めますよと言うように裸のトルソーが凛と立っている。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第134回 佐藤千佳子(46)「たちまち色づいたモノクローム」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!
























































































































































































































































































































































































































































