
第2回 佐藤千佳子(2) このままじゃダメ?
「ママは何になりたいの? ママって、やりたいことないの?」
娘の文香の言葉を思い出し、千佳子は洗濯物を畳む手を止める。タンクトップの胸の部分が二重になっている下着。体育の授業やバスケ部の練習がある日はスポーツブラを着けているが、普段は「こっちのほうがラク」なのだと言う。でも、そろそろカップつきのものを買ったほうがいいかもしれない。「ブラは収納用品」という説を最近ネットで読んだ。胸の脂肪は流動的で、野放しにしておくと型崩れしてしまうらしい。
「歯も生えて いなかったのに もうブラか」
五七五でつぶやいて、また生まれたときと比べちゃってる、と自分に突っ込む。母親は昔と今を比べてしまうけれど、娘は今から続くその先を見ている。振り返ってばかりいると、ますます距離が開いてしまう…。そう思いつつ、娘に投げかけられた質問の答えを探すと、やはり心は過去に飛ぶ。

今の文香ぐらいの年、中学生の頃からの千佳子の願いは、「東京に出たい」だった。生まれ育ったのは、岩手県の釜石市。県内にある短大の家政科へ自宅から通った。父親が口をきいてくれた地元の食品会社で働き始めたが、やっていることはお茶汲みだった。
「東京に出たい」に「結婚したい」が加わった。その二つが、見合い結婚で一度に叶えられた。
相手が東京で勤めている人だと聞いて飛びついた。実際に住むことになったのは神奈川県だったが、千佳子にしてみれば、大した違いはなかった。渋谷にも新宿にも銀座にも一時間あれば行ける。東京と都会は同義語だ。東京ディズニーランドだって千葉にあるのだから。
結婚すると、新たな願いが生まれた。
「子どもを産みたい」
「産めない」が続くと、「産みたい」は「産まねば」という強迫に変わった。そのために結婚したのだから。そのために岩手から出て来たのだから。産まないと、自分がここにいる意味がないように思えた。夫や夫の両親に言われたわけではない。千佳子が勝手にそう思い込み、思い詰めていた。
結婚2年目で不妊治療を始めた。3年近く経っても成果が出ず、病院通いをやめたら、待っていたかのように妊娠した。「そんなもんよ」と夫の母にも自分の母にも、先に産んだ友人にも言われた。拍子抜けしたが、出産するまで気は抜けなかった。無事に産道をくぐり抜けて外に出て来たわが子を抱いたとき、ようやく3つ目の願いは確かなものになった。
「東京に出たい」「結婚したい」「産みたい」
すべての願いが叶った今の幸せが、ずっと続いて欲しい。それだと文香の質問の答えにならないのだろうか。
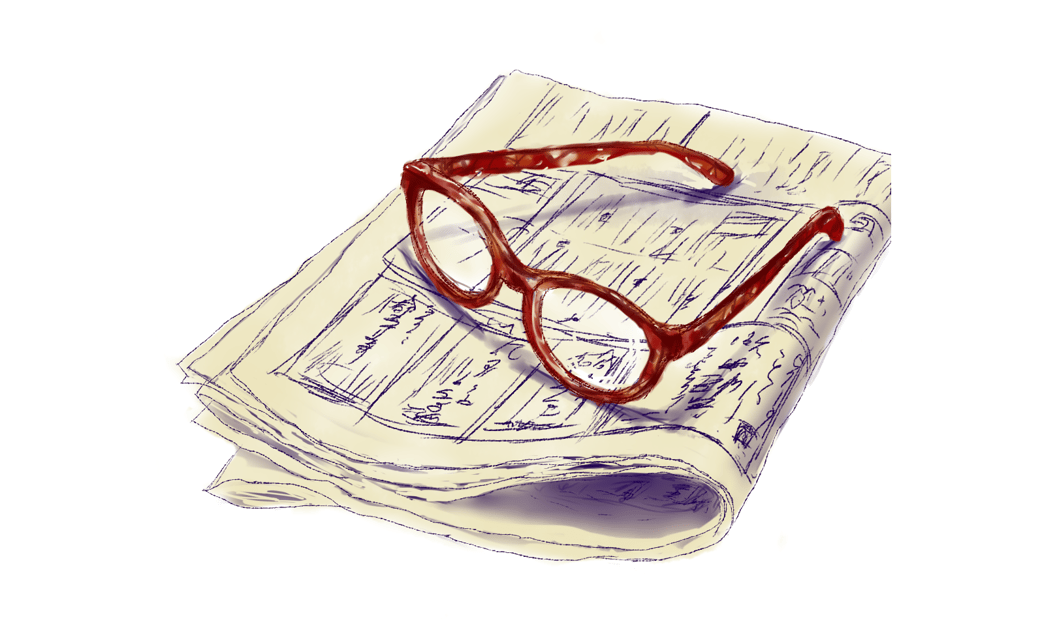
「わたしは今のままで十分だって思っているんだけど、ママは何になりたいの、やりたいことないのなんて、あらたまって聞かれると、このままじゃダメなのかなって」
布団の中で夫に話を聞いてもらいながら「まま」という音が何度も出てくるなと思った。
「で、何が言いたいの?」
突き放すような言い方ではなく、夫は困惑していた。千佳子より6つ年上の48歳。髪が薄くなりかけていて、もう少し上に見える。理系研究員だが薄給で、体つきも細い。家の中での存在感も希薄で、何かと薄い人だ。
「何が言いたいって……」
この話を聞いてもらいたかっただけなんだけど、と千佳子は返事に詰まる。娘に「何になりたいの?」と聞かれた話をしたら、夫に「何が言いたいの?」と言われてしまうとは。
「なんでもない。おやすみ」と会話を打ち切ると、夫は「そう」とだけ言った。
普段から夫婦の会話は育児という業務についての報告、連絡、相談が中心で、共通の話題はとくにない。話が弾むということもない。理系だから論理的に話せない千佳子の言葉がうまく通じないのかと思っていたが、相性の問題なのかもしれない。
見ている風景が違うんだなと感じることがよくある。おなかの子が女の子だとわかり、名前をつけることになったとき、「千佳子さんの旧姓の『十文字』からひと文字いただこう」と夫の父が提案してくれた。日頃から「佐藤なんて、ありふれた名前になってしまって」と気を遣ってくれていた。東北では珍しくない名字なので、恐縮されるとかえって申し訳なかったが、旧姓の名残を孫の名前に留めようという心遣いはうれしかった。
このとき「女の子で十がつく名前って、どんなのがあるかな」と夫が言い、千佳子は夫の父と顔を見合わせた。「十」「文」「字」のどれかだったら、「十」は選ばないのではないか。「字」も難しい。必然的圧倒的に「文」だろう。この調子だと職場でのコミュニケーションにも苦労しているかもしれないと想像したが、会話の噛み合わない感じが研究員っぽいとも思った。
夫には東京へ連れ出してくれる以上のことを期待してなかったから、がっかりさせられることはなかった。
夫は不妊治療にも協力的だった。妊娠が成就するまで、使命感にかられてセックスに励んだ。ときめきも喜びもなく、一言でも口にしたら妊娠運が逃げてしまうとでもいうように、黙々と交わった。
コンビニが全国行事に仕立てた関西発祥の「恵方巻き」なるものに「丸かぶりした太巻き寿司を一本食べ終わるまで口をきいてはいけない」というルールがあると知ったとき、あの頃のセックスを思い出した。出口の見えないトンネルを、手を取り合って抜けようとした3年間。当時は苦痛でしかなかったが、今思えば、夫婦の関係は今よりずっと近くて濃かった。妊娠がわかったとき、手を取り合って、喜び合った。
それからは、刺激を与えてはいけないという自制心が働き、そのままセックスレスに突入した。手を伸ばせばお互いに触れられる距離にいるのに、手がぶつかることはあっても求め合うことはない。淋しい気持ちもあるけれど、なくてもいいかと思う。あるかもしれないと期待するから、ないと淋しいのだ。2人目を産む予定はない。夫婦の間でセックスが役割を終えたと思えばいい。
「千佳子って、欲がないよね」
夫の前に一人だけつき合った相手から別れを切り出されたとき、そう言われた。「欲がないのがいいと思っていたけど、だからダメなんだ」と一方的に持ち上げて落とされた。一緒にいても物足りないし、お互い成長できない、と。
短大の2年の秋から卒業した翌年の夏までの一年足らずの恋だった。同じ高校のひとつ上の先輩。たった一年の差が、あの頃はオトナに思えた。その人が好きだったのか、恋愛にうつつを抜かしていただけなのか、今となってはよくわからない。顔は好きだった。いや、顔が好きだった。笑うと口角がキュッと上がって、笑顔が大きくて、日本人離れしていた。
もう20年も前の話。あの人も禿げてたらいいのにとどうでもいいことを願った。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第3回 伊澤直美(1)「給料日にモヤモヤする理由」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。


















































































































































































































































































































































































































































