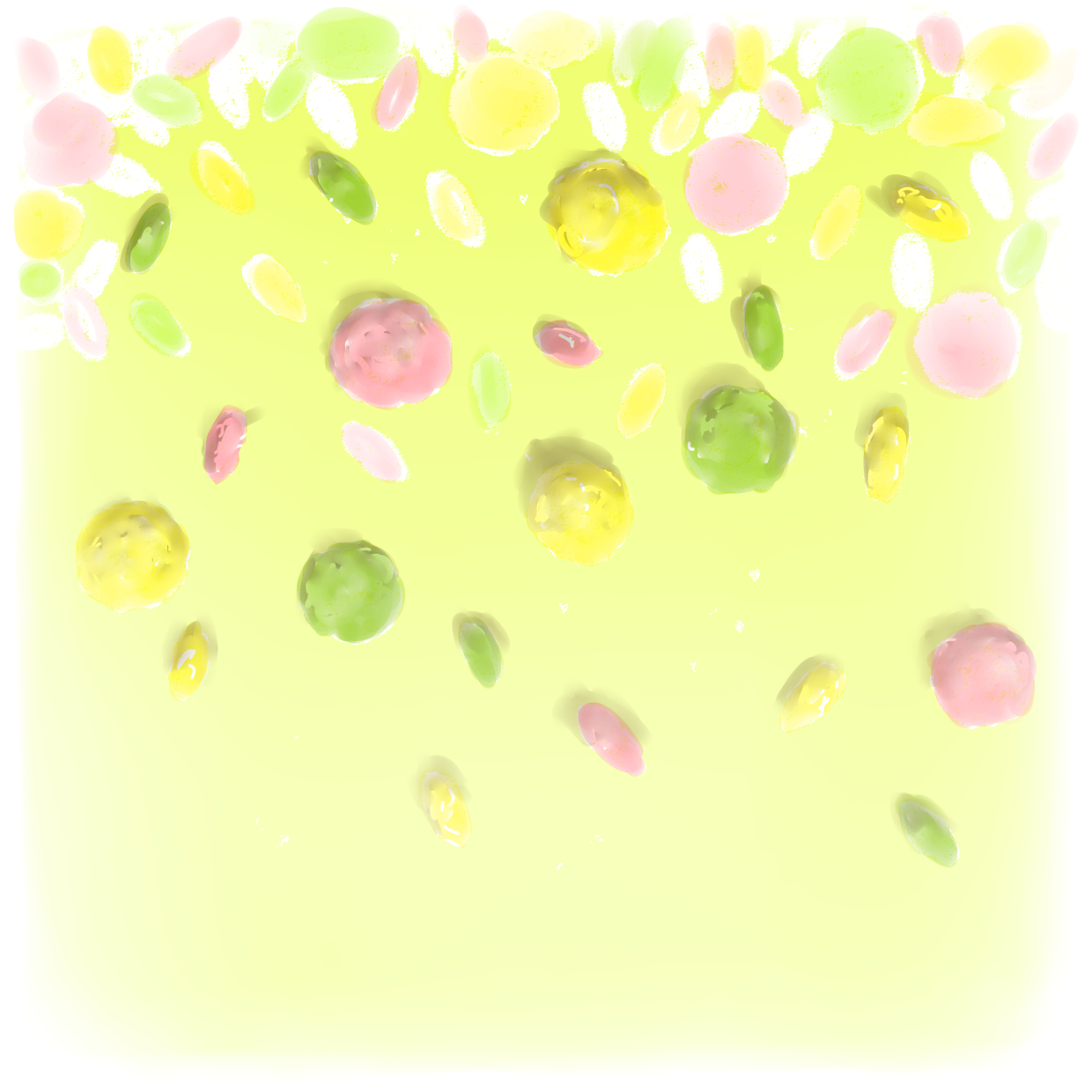第109回 佐藤千佳子(37)埋蔵主婦を卒業します
ノマリー・アントワネットの庭にまた春が巡ってきた。開け放ったサッシ戸の向こうから心地よい風と鳥の声が舞い込み、室内と外をゆるやかにつなげている。
「昼から飲んじゃう?」
千佳子の返事を待たずに野間さんはスパークリングワインのコルクを抜き、ポンという景気の音を聞いて、「うん、いい音」と満足そうに言う。
グラスに細かい泡が弾け、シュワシュワと音を立てる。自称「視覚を使わないプロ」のカズサさんなら、この音でスパークリングワインを見て喉を鳴らすだろうか。
野間さんの庭を見てみたいとカズサさんが言っていたことを千佳子は思い出す。声をかければ良かったかなと思うが、今日は野間さんと積もる話があるから、日をあらためたほうがいい。文香の受験が終わり、ゆっくり会うのは久しぶりだ。
ふたつのグラスをスパークリングワインが満たす短い時間に千佳子の頭の中を原稿用紙10行分くらいの言葉が巡る。
「ふーちゃんも佐藤さんも合格おめでとう。乾杯」
「いただきます」
千佳子は野間さんと合わせたグラスを軽く持ち上げ、「いただきます」と心の中でもつぶやき、野間さんのダンナさんに挨拶する。
蔓を伸ばし、葉を繁らせる葡萄が描かれたグラスは、野間さんのダンナさんが退職祝いにいただいたものだ。このグラスで野間さんと乾杯するはずだったダンナさんが突然亡くなり、野間さんはスーパーマルフルでパート勤めを始めた。ダンナさんが抜けて空いた穴をシフトで埋めた。
千佳子が野間さんと出会ったときには、ダンナさんはノマリー・アントワネットの庭のゴールドクレストになっていた。
かつてダンナさんの部下だった人からお悔やみに贈られたその木は、千佳子が訪ねるたびに背を伸ばしている。ダンナさんの時間は止まっているのにダンナさんの名残の木は光と水と時間を成長に変えている。冬には野間さんのお孫さんに小さなリボンをいくつも結ばれてクリスマスツリーになる。お孫さんは女の子だ。クリスマスのたびに背丈も手も大きくなり、リボンを結ぶのも上手になっているのだろう。
野間さんのお孫さんが娘の幼い頃に重なり、緑の眩しさがしみる。しみじみしてしまうのは、娘が無事中学校を卒業し、義務教育に区切りをつけた春だから、だろうか。
「ふーちゃんも佐藤さんもがんばったよね」
「わたしはお茶淹れてただけですけどね」
文香は第一希望の県立高校に合格した。受験の当日が一番落ち着いて、自己ベストを出せたという。
試験の本番にベストを出せたという記憶が千佳子にはない。浮き上がることも沈み込むこともなく、真ん中辺りを漂っていた覚えがある。成績も、学校での存在感も。
だから、文香を見ていると、不思議な気持ちになる。わたしから生まれた子に、わたしにないものが備わっている。

「今年も咲きましたね」
ゴールドクレストのまわりを春色に彩る色とりどりのチューリップに千佳子は目を移す。イベントが中止になって行き場をなくし、富山県の砺波(となみ)市からノマリー・アントワネットの庭に迎えられたチューリップたちが毎年咲いては球根を残し、翌年も花を咲かせ、4年目の春を迎えている。
「新しい球根も混ざってるから、どれがスタメンかわかんないけど」と野間さんはいたずらっぽく笑い、
「チューリップ見ると、思い出さない? 埋蔵主婦」と続けた。
「しましたね、その話」
「佐藤さんがふーちゃんに聞かれたんだよね。男女っていつから逆転するのって」
「野間さんよく覚えてますね」
「そりゃ覚えてるよ。頭のいい質問だなって感心したもん」
文香が通っていた公立中学校では成績の上位を女子が占めていた。中学受験で私学に進学した男子が抜けたからという理由もあるが、圧倒的に女子が優秀な学年だった。でも、世の中を動かしているのは圧倒的に男性で、「優秀な女子はどこに消えるんだろう」と文香は疑問を抱いたのだった。
「ふーちゃんなりに納得する答えが見つかったのかな。こんなことやって何になるんだろって思ったら、受験勉強なんてできないもんね」
目標に向かって猛勉強した経験のある人の言葉だなと千佳子は思う。
東京に行くことが千佳子の夢だったが、その切符を学力で手に入れようという発想はなかった。勉強なんかして何になるんだろと千佳子自身が疑問を持つ前に、あんたはそんなことしなくていいんだよと両親や祖父母から刷り込まれていた。
《いつもは「ママ」って呼んでいるから照れ臭いけど、あらたまって、「お母さん」と呼ばせてください》
文香の卒業式の日、手紙を渡された。「パパには別に書いたから」と言われ、あて名は「お母さんへ」となっていた。
《私が中学校に入って、お母さんがマルフルで働き始めたときは、時間に余裕ができたんだな、ぐらいの感想でした。でも、お母さんの口数がどんどん増えて、今日こんなことがあってねと私やお父さんに話してくれるのが楽しそうで、青春してるじゃんってあきれながら、うらやましくも思ってました。正直、中学校が楽し過ぎて、このままでいたいって思っていたけど、お母さんを見ていると、大人になるのも悪くないかもって思えてきて、高校生になる文香もその先の文香も楽しみです。将来の夢はまだ探し中だけど、どんな道を進んでも、お母さんを見習って、出会えたものを花束にできる人になりたいと思います》
手紙の最後、便せんの余白に色鉛筆で手描きした桜が舞っていた。

「佐藤さん、よそっていい?」
洋皿に盛りつけたちらし寿司に野間さんがサーブ用のスプーンを滑り込ませる。サーモンとアボカドとハーブに彩られたちらし寿司も春色だ。
「これ、マイさんの本に載ってましたよね?」
「そう。チャービルは庭から産地直送」
マルフルのお客さんでもあるハーブのマイさんが3月にレシピ本を出した。
「ハーブはとっつきにくくて売れない」と取引先に言われたマイさんは、だったらハーブの敷居を思いきり下げてやる!と奮い立った。無理難題を燃料に変えられる人なのだ。
「値引きシールを貼られる前に売り切れちゃう人気者にしちゃえっていう発想が頼もしいよね」
野間さんはそう言って、サーモンとチャービルを口に放り込む。
マイさんと初めて言葉を交わしたきっかけが値引きシールだったことを千佳子は思い出す。マイさんもまたハーブとの出会いは値引きシールだった。今、マイさんは値段でハードルを下げるのではなく、使い勝手の良さでハーブの値打ちを上げようとしている。
レシピ本のタイトルは「がんばらないハーブごはん」だけど、マイさんはがんばった。
野菜売り場のハーブコーナーに本を置いて欲しいと売り込みをかけ、「スペースを確保するのが難しい」と店長が渋ったところ、「POPのスペースがあれば本を置けます!」と切り返した。
「売り物の本がPOPにもなるんです! こちら、見本誌置いていきますので、POP代わりにお使いください!」
断る理由がなくなってしまい、押し切られた店長が見本誌をハーブコーナーに置いてみると、わずかだがハーブの売り上げが伸びた。本を購入したいという問い合わせもちらほら舞い込み、本とハーブを並べて売ることになった。マイさんの粘り勝ちだ。

マルフルの隣にあった本屋が3月いっぱいで店を閉じ、本を手に取って買える場所がなくなってしまったことも追い風になった。
「この方法で、他のレシピ本も売り場に置いてみようと思うんです。ワインコーナーにおつまみのレシピとか」
「佐藤さんもすっかり埋蔵主婦から掘り起こされたね」
「野間さんのおかげですよ。これからもよろしくお願いします」
「その話なんだけど」
野間さんが両手を膝に置いて背筋を伸ばし、千佳子を見た。
「私、マルフルを卒業する」
次の物語、連載小説『漂うわたし』第110回 佐藤千佳子(38)「埋蔵主婦の値段」 へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!