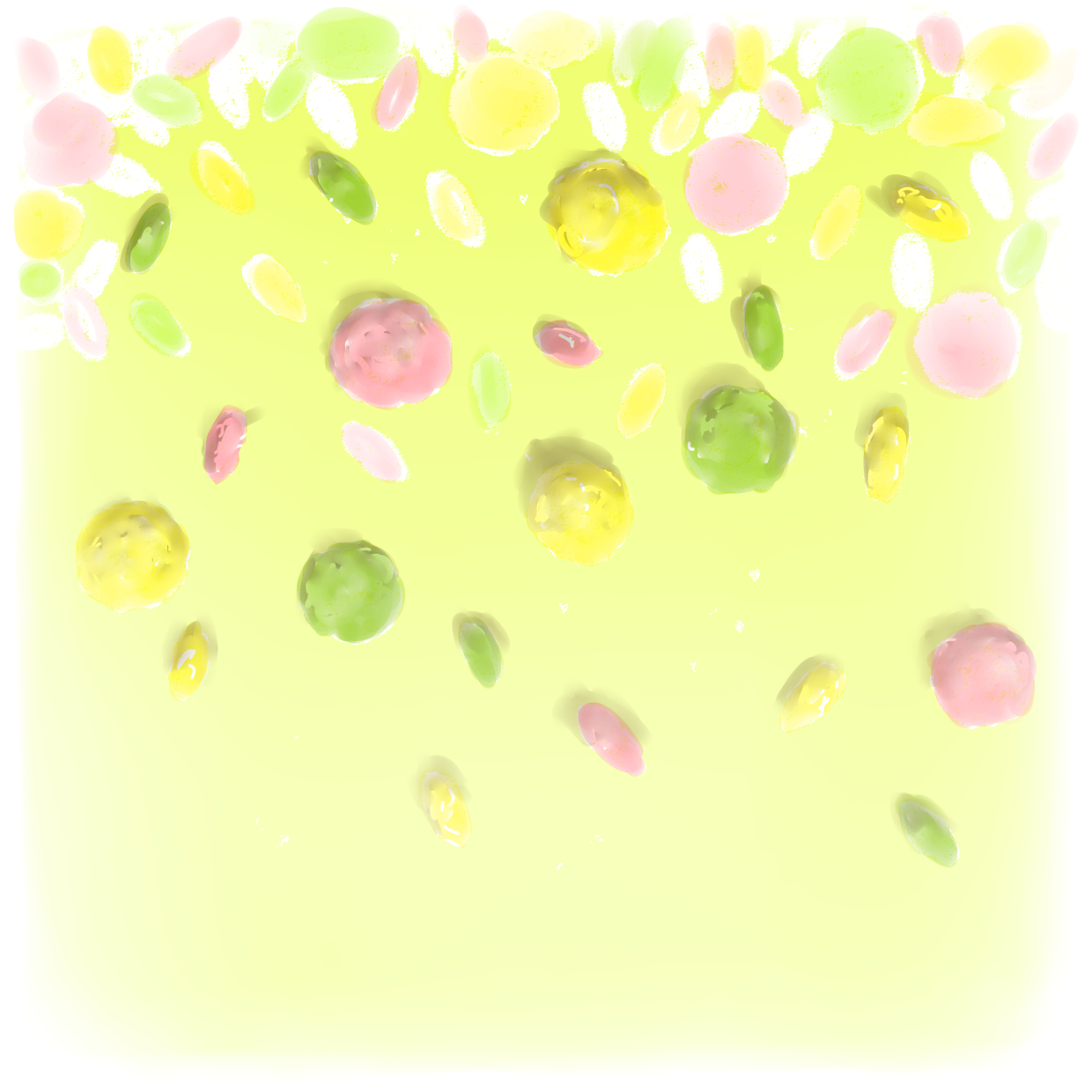第186回 多賀麻希(62)浮かれたっていいじゃない
どこでもうかがいますと田沼深雪から返信があり、家に来てもらうことにした。
約束の10時を少し過ぎて、チャイムが鳴った。
ネットニュースの写真でパーティードレス姿を見た後だったので、普段着にナチュラルメイクの彼女を見て、普通の人だなという感想を持った。2年前に会ったときよりも美しさが落ち着いている。
麻希の目が慣れたのか、本人の力が抜けたのか。人によっては老化だの劣化だの言うかもしれないが、麻希には安心感がある。相手に気後れさせないという意味で。
リビングに通されると、切れ長の目が片隅に立つ裸のトルソーをとらえた。麻希にとっては見慣れた姿だが、彼女の目には、何も着せてもらえず、手持ち無沙汰で立たされているように見えているのだろうか。
トルソーに背を向ける位置の椅子を勧め、麻希は向かいに腰を下ろした。
「すみません。私、何も持って来てなくて」
田沼深雪がテーブルの上に置かれたパック入りの団子に目を留めた。
「あ、これは……」
麻希は口ごもる。
野間さんの友人の美枝子さんが届けたものだった。何駅か離れたところに住んでいるが、思いついたように切り花やら佃煮やら漬物やらを届けてくれる。アムステルダムにいる家主の野間さんには「受け取ってあげるのがプレゼントだから」と言われているが、大抵「なんで今?」というタイミングでチャイムが鳴る。
今日もそうだった。田沼深雪がもう来たのかと慌ててドアを開けたら美枝子さんで、すれ違うようなタイミングで現れた。
その結果、テーブルの上に団子を出したままになっている。一緒に食べましょうと待ち受けていたかのように。
「もしかして、これ、作られたんですか?」
「まさか。たまたま、いただきもので」
2本並んだ串刺し団子の上に練り切りの桜が咲いている。
桜の花びら舞う団子なんて、浮かれているみたいだ。どんな話になるのかもわからないのに、
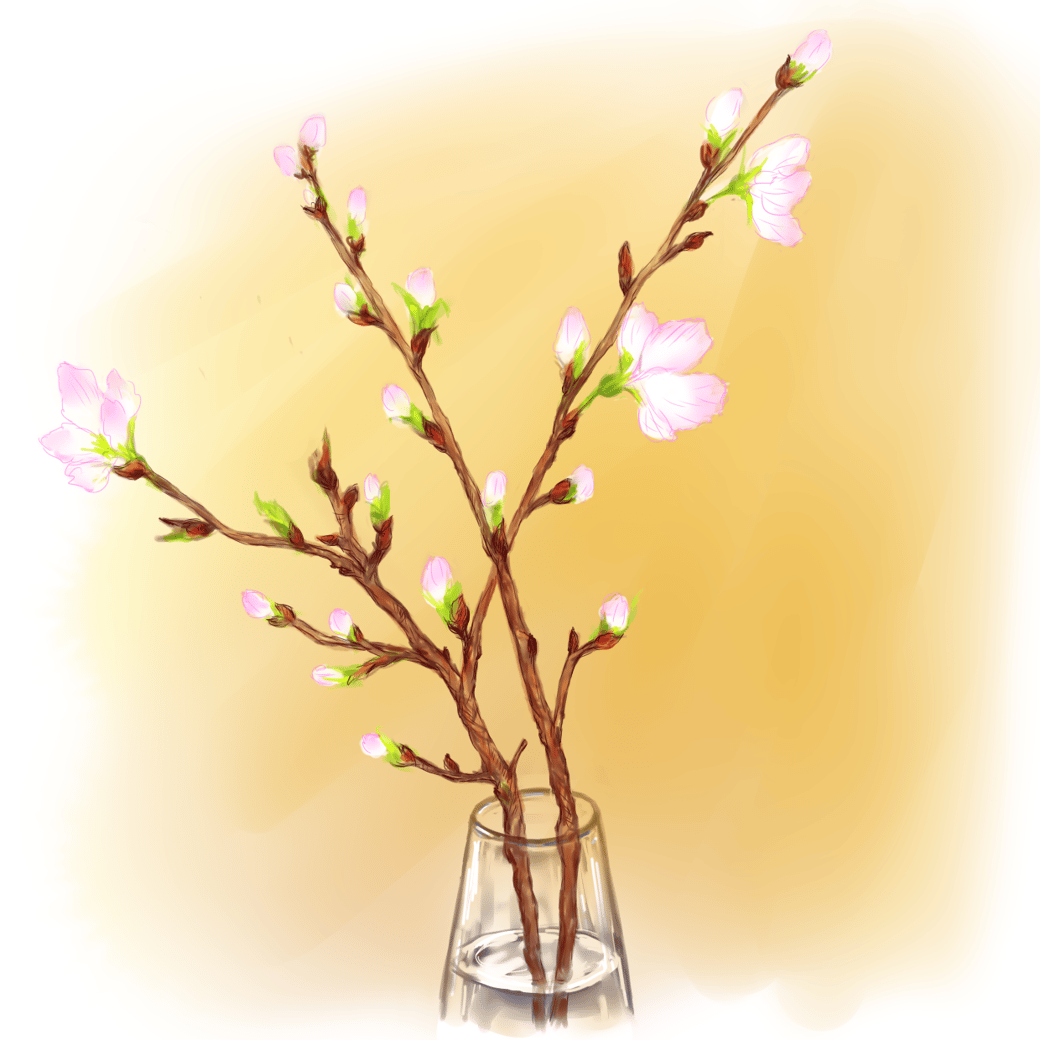
「桜、飾ってましたよね」
田沼深雪が団子を見て思い出したあの日の桜を、麻希も思い出していた。
2年前、彼女から突然連絡をもらい、初めて会ったとき、麻希は新宿三丁目のカフェを指定した。ひまわりバッグのことで因縁をつけられるかもしれないと警戒して。バイトをずっと休んでいるくせにマスターを頼る麻希の身勝手さをなじることなく、マスターは蕾の開きかけた桜をカウンターに飾り、温かく迎えてくれた。
マスターの助けが必要になったら表紙を開くと合図を決めていたスケッチブックにその桜を描きながら、見知らぬ相手を待った。
今回は、ふたりきりだ。モリゾウは朝から出かけている。「いなくて大丈夫?」と聞かれ、「いないほうがありがたい」と答えた。
だけど、いざ田沼深雪を前にすると、何を話していいのか、わからない。彼女を呼びつけて、何を引き出すつもりだったのか。
話を切り出したのは、田沼深雪だった。
「ご迷惑をおかけして、すみません」
まず謝られた。
購入者の伊澤直美は会社の同期だが、夫の姉の代理で購入しており、ひまわりバッグの出番はほとんどなく、もったいないと思っていた。友人の披露宴に借りたバッグが話題になり、ケイティがプロデュースした量産品との決着をつけるチャンスだと思った。わざと煽るような書き込みをしたところ、炎上してしまい、心苦しくなっていたところに連絡をもらえたという。
麻希が何か聞く前に、麻希が疑問に思っていたことに答えてくれた。
「ほんと、すみません。でも、makimakiさんは埋もれてちゃいけない人です」
「ありがとうございます。迷惑です」
田沼深雪はダメ押しのように「すみません」と小さく言った。

「盗まれたって騒ぐほどのデザインじゃないですから」
努めて明るい声で麻希は言った。ケイティにひまわりバッグのデザインを盗まれたことなんて、もう何とも思ってないんですという余裕を滲ませて。だが、
「そう言っていいのは、本人だけです」
田沼深雪は咎めるような口調で言った。
「でも、私にとってmakimakiさんのひまわりバッグは特別なんです。あのバッグを見て、私、一番好きな映画を思い出したので」
映画『幸せのしっぽ』のことだ。ヒロインが着た衣装のデザインは、通っていた服飾専門学校の課題だった。麻希が描き、ケイティのデザインとして提出されたものが採用された。麻希に影を落としたその映画は、高校生だった田沼深雪に光を射した作品でもあった。
「『幸せのしっぽ』に出会ったとき、私、体重が80キロあったって、前に話しましたよね? ケーキはホールで食べてたし、アイスはリットル入りのを抱えてスプーン突っ込んでたし、お団子はパック単位でした。きっかけは母の一言だったんです。私があることで傷ついたとき、私が悪いみたいに言われてしまって。なんで、2度も傷つけられなきゃいけないんだろうって」
その母親を麻希は知っている。ウェディングドレスを着た田沼深雪をモリゾウと遠くから見届けた日、近くで同じドレスに目を向けていた女性。
「あの緑、クローバーなんですよ。雑草ですよね。私に踏みつけられたって当てつけですかね。色々あったんですよ。人様には言えないようなことも」
麻希がクローバーを足した本人だとは知らず、母親は言った。
「今日は一番着たいドレスを着る日だと思います」
正体を明かさず、通りすがりの人を装って、麻希はそう答えた。
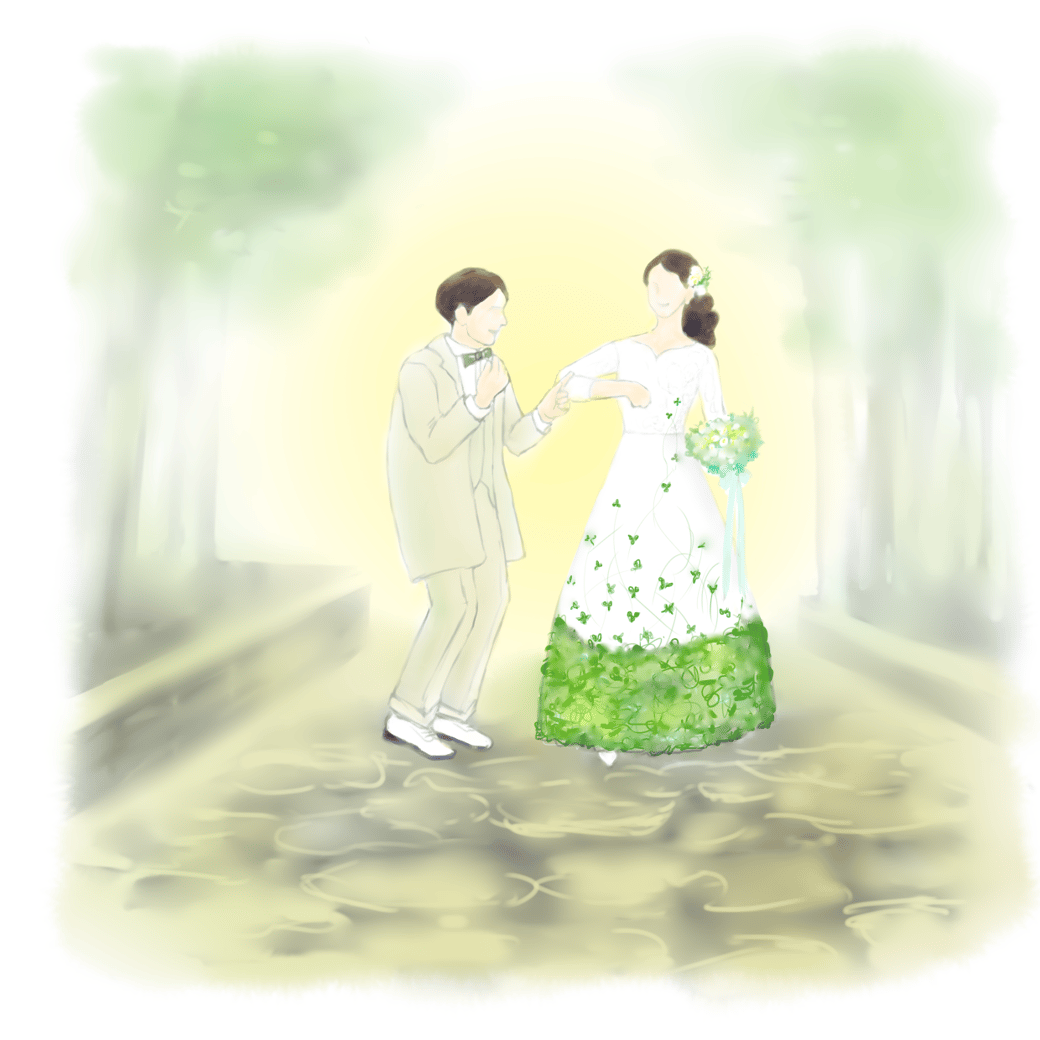
「こちら、受け取っていただけませんか?」
田沼深雪が隣の椅子に置いた大ぶりの黒い肩掛けバッグを示した。
彼女は、手ぶらではなかった。見覚えのあるバッグ。初めて会った日、彼女が持っていたものだ。中身も同じものだろう。麻希が施した刺繍の分、バッグは膨らみを増している。
「受け取るって?」
「ご結婚されるときに、着ていただく約束でしたよね?」
そう言われて、麻希は思い出す。預かったドレスにクローバーをこれでもかと刺繍して返したとき、田沼深雪に代金を聞かれた。お礼は前金で十分受け取ったと答えたが、そういうわけにはいかないと言われ、
「わたしが結婚するとき、このドレスを着させてください」
半分本気、半分冗談でそんなことを言ったのだった。確かに手放すときは名残惜しかったが、その後、取り戻したいと思ったことはない。
「もう、結婚してしまったので」
彼女のウェディングドレス姿を見届けた帰り道、「結婚しよっか」とモリゾウに言われ、熊本の父が倒れて駆けつけた折に紹介し、運ばれるように入籍を済ませた。
「ドレスを着る機会はなかったですし、これからもないと思います」
「だったら」
田沼深雪が振り返り、トルソーに目をやった。麻希が着ないのなら、裸のトルソーにドレスを着せて欲しいということだろうか。

「それは……お礼が重すぎます」
田沼深雪に救われたのは自分のほうだ。何も手につかなかったとき、ドレスに刺繍針を運ぶことで止まっていた時間が動き出した。ドレスをまとった彼女を見届けて、これからはドレスを作りたいという目標ができた。
まだ、動き出せていないだけ。
「お礼っていうか、makimakiさんに持っていて欲しいんです」
「やっぱり迷惑です」
「迷惑ですか……」
「こんなことされたら、うぬぼれちゃうじゃないですか」
田沼深雪が「え?」と麻希を見た。
わたしのデザインをフリー素材みたいに軽く扱う同級生がいるかと思えば、何かを感じて、何度も見つけて、追いかけ続けてくれる人がいる。
喜んでいいのではないか。浮かれていいのではないか。
テーブルの上、田沼深雪と自分の間に横たわる透明のパックに目をやる。
今日は、桜の花びら舞う団子を食べるのにふさわしい日なのではないか。

次回4月26日に佐藤千佳子(63)を公開予定です。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!