
第23回 多賀麻希(7) 最後の恋人によく似た彼
モリゾウの演劇仲間で墳友(ふんとも)の高低差太郎は、名前から想像した三枚目とは違い、綺麗な顔立ちをしていた。長いまつげに縁取られた切れ長の目は、星が入っているみたいにキラキラしている。手足が長くて首も長い。顔の小ささが首長に見せているのかもしれない。
モリゾウの年齢をいまだに知らないが、モリゾウよりもさらに年下、30歳そこそこにしか見えない。
「コウテイサさん?」
高低差・太郎なのか高低・差太郎なのか切れ目がわからず、麻希が語尾を上げて呼びかけると、
「古墳王子って呼んでくださいっ」
見た目通りの爽やかな声で言われた。確かに少女漫画に出てくる王子感はあるが、この屈託のなさは何なのだろう。
「最初は古墳男子って名乗ってたんですけど、いつの間にか王子って呼ばれるようになったんですっ」
「王子」と名乗っても許されるという圧倒的な自信に、麻希は面食らいつつ眩しさを覚える。子どもの頃から人間関係のど真ん中を歩いてきた、ひなたのにおいがする。
近くに古墳があるという代官山のカフェのテラス席をモリゾウと高低差太郎と3人で囲んでいる。気のせいか、まわりのテーブルからの視線を感じる。モリゾウも長身で個性派俳優っぽい雰囲気があるし、アイドル顔の高低差太郎と並ぶと、芸能関係の打ち合わせに見えなくもない。麻希はマネージャーといったところか。
「古墳男子って、ふんどしみたいだな」とモリゾウがからかうと、「それ、毎回言ってるよねーっ」と古墳王子が笑って、左の頬にえくぼができた。
ツカサ君と同じ場所だ。
そう気づいた途端、古墳王子の顔をまっすぐ見られなくなって、ドギマギする。別れてから10年経って淡くなった記憶が上書きされて、ツカサ君ってこんな顔だったんじゃないかと思えてくる。

今朝、ツカサ君の夢を見た。夢の中でツカサ君に赤い靴を贈られた。現実にあった出来事。だけど、何かが違った。
「あれ? カードは?」
夢の中でツカサ君に聞いた。「シンデレラへ」と手書きのカードが添えられているはずなのに、それがなかった。
「カードって、なんのこと?」
「シンデレラのカード」
「シンデレラって何?」
麻希が何か言う前に、夢は終わった。「シンデレラってわたしのことだよ」と夢の中でも口にするのがはばかられて、「自分のことをシンデレラって言うの、よく考えたら寒い」と夢の中なのに冷静なことを考えていた。
明け方の夢のことをモリゾウには話さなかった。恋愛感情がないのにツカサ君の話をするのをためらってしまうのは、なぜなんだろう。ツカサ君との思い出を誰にも触らせたくなくて、立ち入り禁止の黄色いテープを張り巡らせているのだろうか。
ツカサ君と「シンデレラ」が引っかかったまま出かけたら、ツカサ君と同じところにエクボができて自分のことを「王子」と言ってのける高低差太郎が現れた。夢と現実が縫い合わされたようで、なんだか不思議。これが今流行りの引き寄せというやつなのか。
「モリゾウから聞いてたんですけど、ほんと古墳に似てますね! コーフンですっ」
麻希のバッグに王子が目を留めた。小さい「っ」がつくような弾んだ話し方は、ツカサ君と全然違う。ツカサ君の語尾は溶けて消えるようだった。
「写真、インスタに上げてもいいですかっ」
どうぞと麻希が言うと、古墳王子がスマホをつかんだ。バッグだけを何枚か撮った後、バッグに顔を寄せて自撮りする。きっと「古墳バッグ」として紹介されるのだろう。「古墳男子」や「古墳グッズ」のハッシュタグをつけて。インスタには3万人のフォロワーがついているらしい。
「ほんと凝ってますよねっ。これ古着のリメイクですかっ」
「はい。履き古したジーンズと着なくなったシャツと」

ライムグリーンのシャツは、ツカサ君が部屋に置いて行ったものだった。買ったときから古着だった。はじめてふたりで出かけた下北沢のレコード屋の片隅に古着コーナーがあって、そこで見つけた。
派手なボタンは、麻希が後からつけた。元々ついていたボタンがひとつ取れて、どこかに行ってしまい、麻希が代わりのボタンをつけたらチグハグになって、「いっそ全部違うボタンにしたら?」とツカサ君が言った。色とりどりのボタンと、それに合った色とりどりの糸を持っていることに驚かれた。ツカサ君は宝箱をのぞき込む子どもみたいな目をして裁縫箱を見ていた。
ツカサ君。ツカサ君。ツカサ君。
シャツがタイムカプセルになっていて、捨てられなかった。だから鞄にした。
リメイクのバッグを見ても、いちいち思い出してしんみりすることはなくなっていたけれど、今日は結びつけてしまう。夢に出てきたツカサ君は派手なボタンがいっぱいついたライムグリーンのシャツを着ていた。
思い出の中のツカサ君は、いつもそのシャツを着ている。最後に言葉を交わしたときのツカサ君も。実際は違う服を着ていたはずなのに。
「脚本家になる夢はどうするの?」と麻希は聞いた。「十分、いい夢見たから」とツカサ君は小さく笑って言った。左の頬にえくぼを浮かべて。ツカサ君が書く脚本に出てきそうなセリフだった。
ツカサ君が待っていたセリフを、麻希は返せなかった。ツカサ君の故郷は山形で、最寄りの新幹線の駅から車で1時間かかる山奥にあった。熊本からせっかく出てきたのに、そんなところに引っ込みたくなかった。東京を失うことより恋人を失うことを選んだ。
ツカサ君のことをそんなに好きじゃなかったのかと思ったが、喪失の悲しみは時間差で襲ってきた。あれが最後の恋で、もう二度と恋などできないのではないかと思った。実際、その通りになった。恋とも呼べないような、すり減るばかりの逢瀬を重ねた。
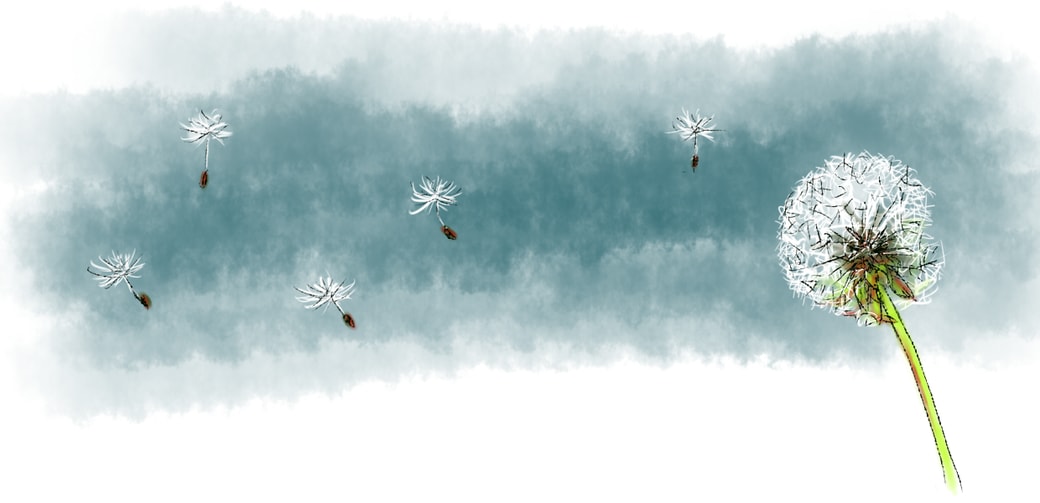
「マキマキさん?」
古墳王子に呼ばれて、我に返る。
「次の公演の衣装、マキマキさんにお願いしたいなってモリゾウと話してて……あの、大丈夫ですか?」
どうしたんだろう。古墳王子の語尾の小さい「っ」が消えている。
「あ、えっと……スケジュールとか、予算とか、ですか?」
「じゃなくて、顔色が……」
古墳王子がそう言うと、モリゾウが「ほんとだ」と気づいて、麻希を見る。ふたりがかりで心配されると、そんなに具合が悪そうに見えるのならどこか悪いのかもしれないと暗示にかかったようになり、血の気が引き、手足の先が冷えていく。
「あれ? 今、ピキッて来た」
咄嗟にお腹に手をやり、背中をかがめる。食あたりでお腹が痛くなるのとは違う、尖った痛みが体を貫くように走った。
「また来た」
さっきより痛みが鋭くなった。切り裂かれるような感覚。とっくの昔に別れた恋人のことを思い出して、思い詰めて、身を切られるように苦しくて、体は正直で……。
「大丈夫ですか?」
古墳王子が麻希の顔をのぞき込む。
「ツカサ君……」
声に出して言ったのか、それとも心の中で呼んだのか。体の奥から痛みの矢を放っているのは、10年経っても癒えていない古傷なのかもしれなかった。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第24回 多賀麻希(8)「いなくなっても同じなんて言わないで!」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































