
第129回 伊澤直美(43)今がいちばん可愛い
この一年あまり、「可愛いですね」と何度言われたかわからない。
自分のことではなく、娘の優亜のことだ。
優亜を連れて出かけると、いろんな人に声をかけられる。同じ道を歩いていても、同じ路線の電車に乗っていても、一人のときは誰にも話しかけられないのに。いつも無言ですれ違っている人たちは、こんな言葉を、こんな表情を隠し持っていたのか。仏頂面の下に。
「ありがとうございます」と応じると、
「おいくつですか?」と相手はさらに踏み込んでくる。
「1歳です」と答えると、
「何か月?」と聞かれ、
「7か月です」と答えると、
「じゃあ1月生まれ?」と逆算され、
「山羊座かな」と星座を想像される。
誕生日も本名も教えないほうがいい。「名前は?」と聞かれたら、「ゆーちゃんって呼んでます」と答える。「言えません」や「秘密です」だと「あなたを信用していません」と取られて気を悪くされてしまうから、答えをふんわりさせる。
「ママとどこにお出かけするの?」
話しかけている相手は優亜でも、間接的に直美に聞いている。「母のところへ」と答えると、「あら、おばあちゃんうれしいわね。親孝行ね」などと言われる。
この人にも子がいて、孫がいて、時々顔を見せに来るのかもしれない。あるいは、そういうことがないのかもしれない。「親孝行ね」は親近感で言っているのか、自分にはないものへの憧れなのか。どちらの可能性もあるので、当たり障りのない笑顔を返す。

「お一人目ですか?」もよく聞かれる。
妊娠の前には性交がある。丁寧な言葉遣いで初対面の相手の性生活に切り込んでいるという自覚は相手にはない。
オヒトリメデスカ オヒトリメデスカ
何かの呪文みたいだ。メデスカ、メデスカ。
だいたい、道ですれ違ったり、電車で近くに乗り合わせたりした相手にいきなり「可愛いね」と声をかけたらナンパだし、挨拶もそこそこに歳や名前や行き先を聞くのは失礼だ。普通はそんなことしないし、したら怪しまれる。
それが赤ちゃんや幼な子相手だと許される。こちらは許した覚えはないが、世の中の空気が許してしまっている。優亜を連れて出かけるということは、「今話しかけてもいいですよ」と旗を立てているようなものなのだ。わが子を褒められて怒る親はいないし、小さな子どもと一緒の親は不機嫌な対応をしないと思われている。
以前にもこんなことがあった。
「トト」と飼い犬の名を思い出した。
子どもの頃、両親にねだって飼わせてもらった子犬。『オズの魔法使い』に出てくる犬の名前をつけたのに、母はなぜか「ぴーちゃん」と呼んでいた。
トトの散歩をしていると、いろんな人に話しかけられた。「可愛いね」だったり、「いくつ?」だったり、「名前は?」だったり。犬の種類もよく聞かれた。「シバ犬?」と聞かれて、「わかりません」と答えた。シバが入った雑種だったと思うが、「雑種」と言うと、トトを雑に扱ってしまう感じがした。
「お手伝い、えらいね」と直美をほめてくれる人もいた。「小学校どこ?」と聞かれ、当時は個人情報保護なんてことは考えず、正直に答えると、「うちの子も通ってた」と言われ、俳句に力を入れていた何代か前の校長先生が亡くなったという話を聞いたりした。
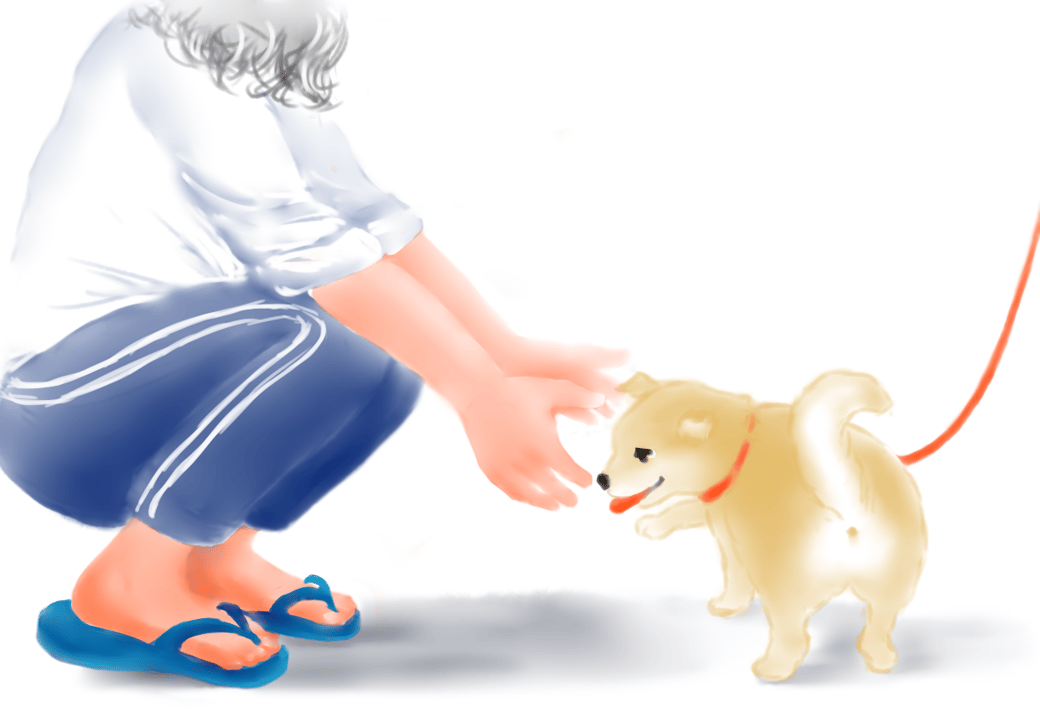
子犬の散歩も子連れの外出も、足取りがゆっくりになる。だから、つかまえやすいというのもあるのだろう。
かといって、相手は名前や歳や行き先を知りたいのではなく、ただ誰かと話をしたいだけなのだ。片言の英語で聞けることが「ワット イズ ユアネーム?」や「ハウ オールド アーユー?」や「ウェア アーユー フロム?」ぐらいしかなくて、初めて会った海外からの観光客にプライベートな質問をしてしまうように。
そんなことを、優亜を膝に乗せ、目黒から多摩川方面へ向かう東急線に揺られながら考えていると、
「可愛いね」
「うん。可愛い」
向かい側の座席の会話が聞こえてきた。中学生か高校生ぐらいの女の子と母親らしき女性が並んで腰を下ろしている。
「ふーちゃんも、あんな可愛い頃があったんだよ」と母親が言う。
ふーちゃん。
「ふー」で始まる名前なのだろうか。フウコとか、フウカとか。
母娘が噂しているのは優亜のことらしい。直美と向き合う形で座っているが、間に大学名の入ったジャージ集団が立っている。その隙間から優亜を見ている様子だ。
「今は可愛くないの?」と女の子がすねる。
「今も可愛いよ。いつも可愛い」と母親が笑いながら言うと、「はいはい」と女の子が言う。
何度も繰り返されているやりとりのようだ。聞いていて直美は頬が緩む。あと十数年経ったら、優亜とあんな会話をするようになるのだろうか。
トトの散歩コースによく現れたおばあさんのことを直美は思い出す。季節を問わず、体育着みたいな上下にサンダル履き。髪はグレーでボサボサ。直美は「魔女」とあだ名をつけていた。
「可愛いのは今のうちだよ。あっという間に大きくなっちゃうからね」
魔女は、しわがれた声で、そんなことを言った。直美には呪いの言葉に思えた。トトが可愛くなくなることなんて、ありえない。腹が立って、散歩コースを変えた。
けれど、やがて魔女の予言が当たっていたことを思い知った。トトが大きくなるにつれ、犬を飼いたいとねだった頃の熱は冷め、学校や部活が忙しくなり、トトに触れる時間が減っていった。トトの散歩は母が引き受けた。

「いくつぐらいかな」と隣の母親に女の子が聞く。
「80ぐらい?」と母親が言い、
「え?」と女の子が驚く。
直美も「え?」となる。
「もうちょっと大きいかな」と母親が言い、「なんでサイズ?」と女の子がツッコミを入れ、直美は「そっか、サイズか」となる。子どもの大きさを年齢ではなく服のサイズで考える人もいるのだ。そういう関係の仕事をしている人なのだろうか。
直美と母娘の間に立っていたジャージ集団がドアのほうへ移動し、見晴らしが良くなった。目が合い、どちらからともなく会釈する。
「今の、聞こえてたかな?」と女の子が母親の顔を見る。
「すみません。つい懐かしくて」と母親が直美に言う。
「親子仲良しでいいですね。姉妹みたいで」と直美はにこやかに返す。
「ほんとですか?」と母親が声を弾ませ、「姉妹だって」と女の子をつつく。
「ええっ、歳の差ありすぎ〜」と女の子が笑う。
直美の膝の上で機嫌良くしている優亜がタイミング良く手を叩き、「ウケてる〜」と女の子が笑い、母親ふたりもつられて笑う。
「今がいちばん可愛いときですね」と母親が優亜に目を細める。
「ママ、さっきと言ってることが違う」と女の子が頬を膨らませる。
「ずっと、今がいちばん可愛いってことですよね?」と直美が言うと、
「そういうことです」と母親がうなずいた。
電車が駅に到着し、ドアが開く。ホームを振り返って駅名を確認した女の子が「あ、日吉だ」と気づいて、立ち上がる。「え、もう?」と母親が立ち上がる。そのとき、膝の上に寝かせていた赤いバッグが持ち上げられ、直美は「あっ」となった。
底だけが見えていたときはわからなかったが、チューリップがバッグの形になっている。黄緑色の持ち手は茎だ。材質の違う布の組み合わせもひまわりバッグを想像させた。
「もしかして、makimakimorizoですか?」
思わず聞いた声がうわずった。
次の物語、連載小説『漂うわたし』 第130回 伊澤直美(44)「母娘の残像」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































