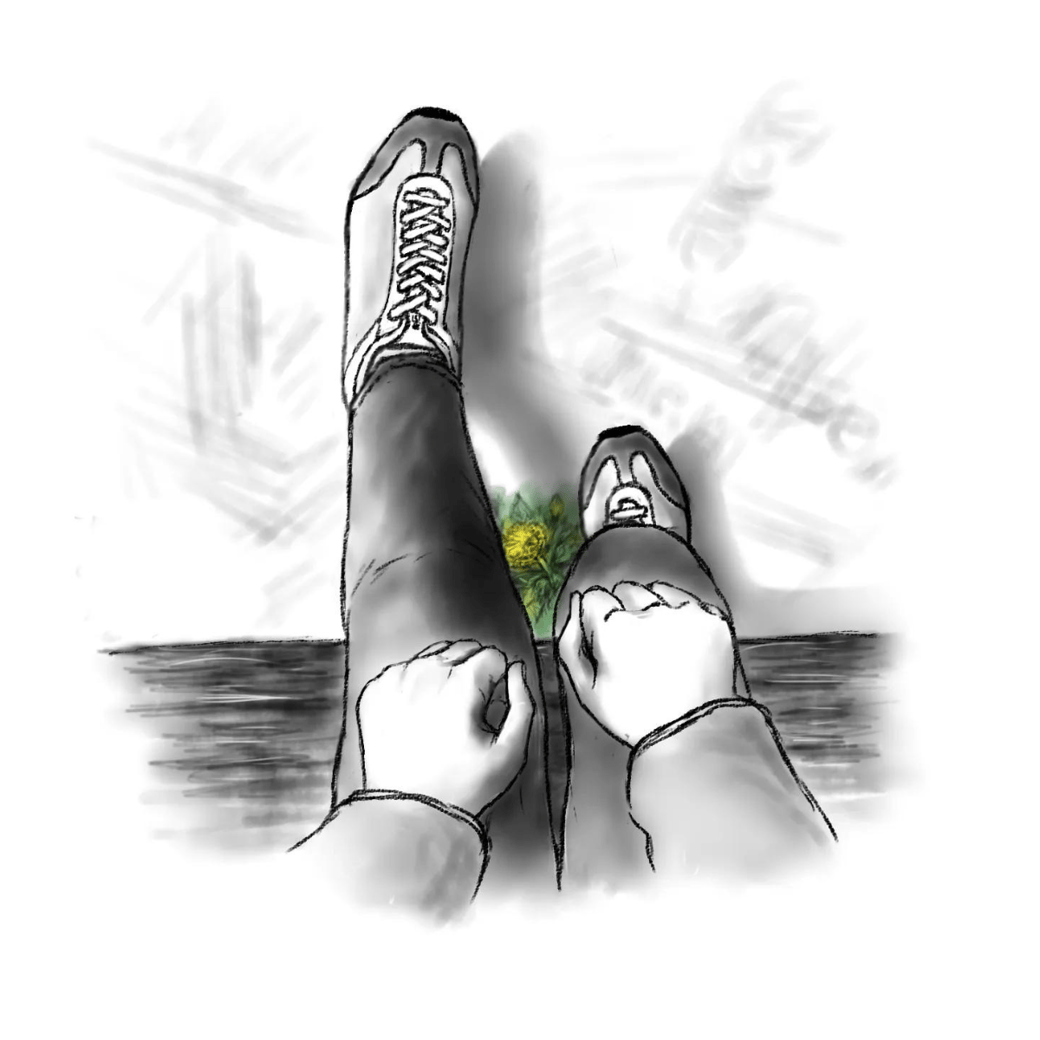第16回 伊澤直美(6) HAPPYが壊れた結婚4年目
「お店の人、ひいてたよ」
「ていうか、イザオもひいてたよね?」
「そりゃひくよ」
結局クロスバイクを買わずに、直美とイザオは自転車ショップを後にした。
「俺思うんだけど、子どもか自転車かって、比べるものじゃないよね?」
「そうだよ。比べるものじゃないし、並べるものじゃない。だけど、イザオは同じノリで欲しがってる」
「同じじゃないって」
「同じだった。子ども欲しいってなってるときのイザオと」
「どこが?」
「いいことしか見えてないところ。自分にとっていいものは、わたしにとってもいいはずだって思い込んでるところ」
「逆に聞くけど、なんでハラミは悪いことばっかり目につくわけ?」
ハラミと呼ばれて、直美はまた胸がざわつく。悪意のないたった3文字のあだ名だって棘になるってこと、イザオに説明しても理解できないだろう。
直美が黙るとイザオも黙り、スペインバルの近くに停めた自転車の前まで戻って来た。映画を観て無性に食べたくなったムール貝入りパエリアを分け合い、店を出たときはあんなにいい気分だったのに。恋人時代に戻ったようなデートの余韻は食べ残しのパエリアみたいに冷めて固まっている。ふたりの気持ちは遠ざかり、自転車だけが仲良さそうに寄り添っていた。

信号に引っかかったイザオを待たず、なんとなく振り切る形になった。まっすぐ家に帰ってイザオと顔を合わせるのも気が進まなくて、家の近くの公園で自転車を停め、ベンチで時間をつぶした。足元にタンポポが咲いていた。なんとなくスマホを見ると、先に帰り着いたイザオから「鍵持ってないんだけど」とメッセージが入っていた。
マンションのエントランスで膨れっ面のイザオと落ち合い、オートロックのドアを開け、エレベーターで5階まで上がり、玄関のドアを開けると、イザオはリビングへ、直美は仕事部屋へ向かった。その間、一言も交わさなかった。
日が落ちて灯りをつけたら、ちょうどイザオから「夕飯作るよ」とメッセージが入った。「助かる」と返事を送った。
「昼ガッツリ食べたから、サラダとスープでどう?」
「いいね。野菜歓迎」
「目標7時」
「りょうかい」
大丈夫。このやりとりの感じなら、普通にしゃべれそうだ。これまでもイザオとすれ違うたび、食事で修復して来た。お酒のチカラも借りて。

アボカドとプチトマトとひよこ豆とキドニー豆のサラダと、根菜ときのこたっぷりのミネストローネスープを分け合いながら、スパークリングワインを1本空けた。
ひよこ豆とキドニー豆は直美とイザオが勤めている会社の「まぜ豆のススメ」シリーズの商品で、直美はレシピ開発にも関わっている。サラダに散らしたハーブを箸でつまんで、「これってフェンネルだっけ」と名前を聞くと「ディル」と答えがあった。
「フェンネルとディルって似てない?」
「うん。俺も見分けつかないけど、パッケージにそう書いてあった」
ハーブの話になって、真っ赤な唇の主婦のことをまた思い出した。
「知ってる? 生ハーブブーケっていうのがあるんだって」
「ああ、売ってるの見たことあるけど。生ハーブブーケがどうかした?」
「こないだオンラインインタビューした40代の主婦の人が言ってた」
「ふうん」
「その人がさ、結婚して、子ども産んで、どんどん世界が広がったんだって。今が一番楽しいって言ってた」
あれ? なんでわたし、自分からこんな話、しちゃってるんだろ。
「俺はそう思ってるよ。ハラミだって、子ども持ったら、もっと世界が広がるって」
「そういう部分もあるとは思ってるけど」
「あんまり被害者意識を持たないほうがいいよ」
「被害者意識?」と思わず聞き返した。
「なんか、女ばっかり損してるって考えにとらわれてない?」
「でも、実際そうだよね」
「ハラミ、なんか失ってる?」
「名前とか」
それでまた思い出したくないことを思い出してしまった。イザオに言っても仕方のないことだし、言わないつもりだったけれど、言わなきゃわかんないかという気持ちになった。
「銀行で住所変更しようとしたらさ、伊澤直美に名義変更しないとできないって言われたんだよね」
「うん」
「仕事でこの名前使っているんですって原口直美の名刺出したんだけど、本名でないと住所変更は受けつけられませんって言われて」
「うん」
「結婚したとき、何の疑問もなくイザオの名字になったけど、カードの数だけ名義変更必要で、いちいち面倒なんだよね」
「うん」
イザオは「うん」しか言わない。反論も言い訳もしない。吐き出してしまえば、ただ話を聞いて欲しかっただけのような気もして、直美は黙ってサラダを口に運ぶ。
「法人化したら? 『株式会社原口直美』って。そしたら原口直美の通帳作れるよ」
イザオはイザオなりに考えてくれている。だけど、ありがたいという気持ちより、そうじゃないという違和感が膨らむ。
「原口直美の通帳を作りたいんじゃなくて、今持ってる原口直美の通帳をこのまま使いたいだけなんだけど」
「でも、それができないんだったらさ」
「だから、面倒くさい手続きをふやしたくないし、やっぱりこっちばっかりシワ寄せ食らってるよね。子ども産んだら、もっと食らうんだろな」
「制度の不自由はあると思うけど、俺ら二人で戦ったって限界があるよ」
「俺らって仲間みたいに言うけど、イザオは恵まれてる組だから。何も削られてないし、これからも削られないし。わかってないくせに理解あるみたいな顔しないで欲しい」
「メンドクセ」とイザオが小さく毒づくのが聞こえた。
「わたしが? 世の中が? いや、わたしなんだろけど、わたしを面倒くさくしてるのは世の中だから」
「わかったわかった。俺が全部悪い。銀行が原口直美を認めないのは俺のせい。世の中が面倒くさいのも俺のせい。日本のジェンダー・ギャップ指数が先進国最下位の121位なのも俺のせい」
「話大きくしないでよ」
「どっちが大きくしてんだよ!」
イザオは椅子を蹴る勢いで立ち上がると、乱暴にドアを開けて、バンッとわざと音を立てて閉めた。その振動で、キッチンの棚に飾ってあった何かが落ちて、コツンと床を打った。
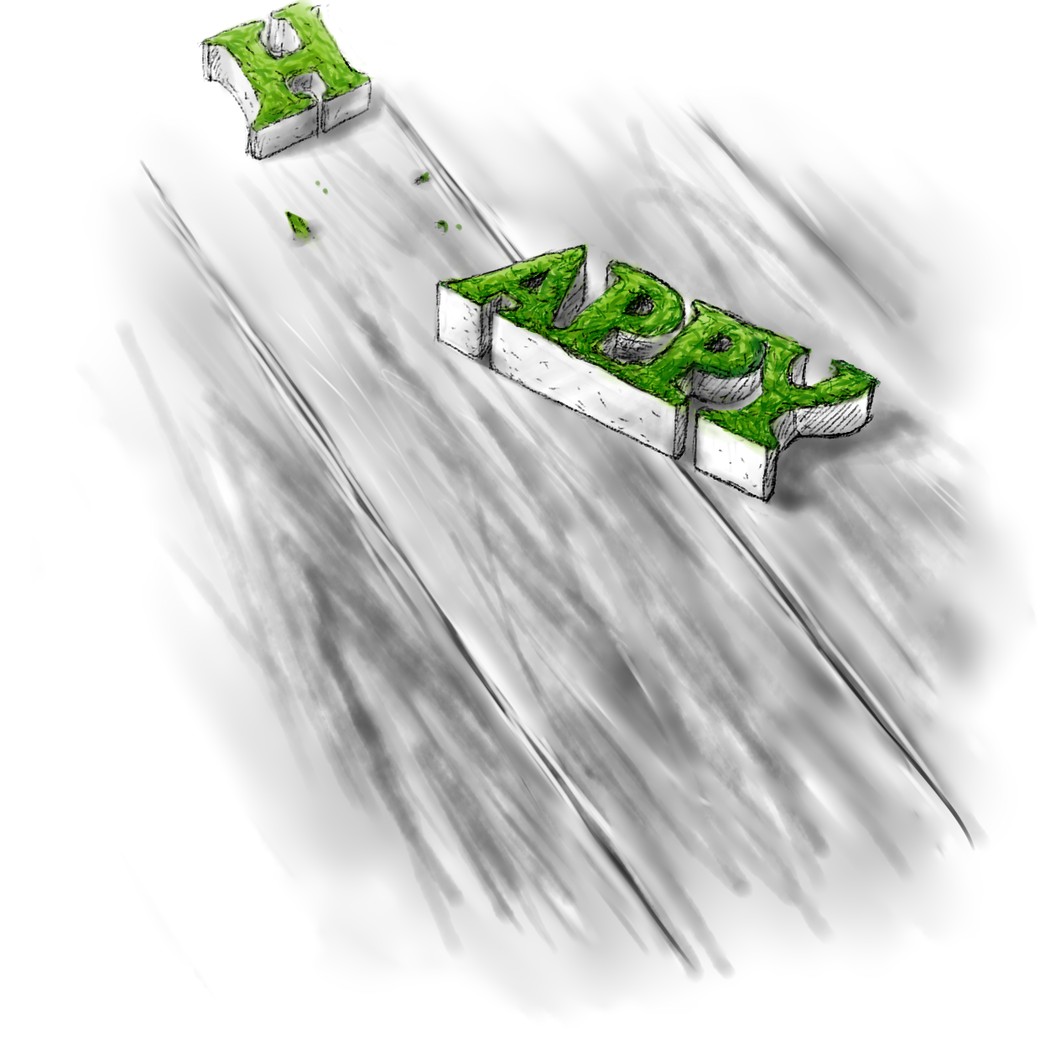
見ると、「HAPPY」の5文字をつなげたオブジェが二つに分かれていた。結婚式の2次会で幹事をやってくれた同期のタヌキ(田沼深雪)が市販のメッセージオブジェにフェイクの苔を貼りつけて受付に飾ってくれた手作りだ。
これまでにも何度か床に落としたことがあったけど、壊れなかった。「案外丈夫だね」「俺たちみたいだな」と笑い合ったこともあった。すでに亀裂が入っていたのかもしれないけれど、今日壊れたことが夫婦の決裂を言い当てているように思えた。
まわりからはお似合いの夫婦だと言われ、自分たちでもそう思っていたのに。わたしたち、すごくうまく行ってたはずなのに。
どこで間違えたんだろう。どこから噛み合わなくなったんだろう。
カラオケで音程が合わないまま歌っていて、サビのところで致命的にずれてしまうように、小さなすれ違いをやり過ごしていたのが、「子どもどうする?」の話題で決定的になったのかもしれない。
玄関のドアが冷たく閉まる音がした。この時間、もうジムは閉まっている。イザオはどこへ行ったのだろう。一緒にいたくない気持ちはすごくわかる。イザオが出て行かなかったら、わたしが家を出ただろう。
結婚4年目。HAPPYが壊れた。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第17回 多賀麻希(5)「彼の寝息を聞きながら」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!
※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。