
第209回 多賀麻希(69) ママという生き物がわからない
「マキマキ、まだ迷ってるの?」
コーヒーカップをテーブルに置き、モリゾウが麻希を見た。
庭側を向いた席が麻希の定位置で、向かい合ったモリゾウの後ろ、カーテンを開けたサッシ戸が結露で曇っている。暖房で温められている室内と外気の温度差が大きいということだ。「寒そうだな」とつぶやいた麻希の声が「行きたくないな」と聞こえたのだろう。
12月の最初の金曜日。隣の学区の小学校の読み聞かせに行くことになっている当日の朝。約束したわけではない。断りきれず、成り行きで、そうなってしまった。
「知らない人ばっかりだし」
知らないママばっかりだし、とは言わなかった。
「ママ」という短い言葉に心が波立つ。
わたしがなれなかったもの。
今後も、なる予定のないもの。
前は何ともなかったのに、今は過敏になっている。漆にかぶれるようなものだ。肌が負けて、かゆみをもたらし、しつこくつきまとう。
「俺は、自分の遺伝子は残せないからさ」
モリゾウがどんなつもりであの言葉を口にしたのか、いまだに確かめられていない。
本読み隊に行くことになったのは、モリゾウも関係がある。
10月の終わりのことだった。毎週日曜日の朝の2時間、夏休みの復習と称して、フミカが通ってきていた。その日曜日も。
フミカが長い英文を読み上げ、ブツブツと解説するのを最初はじっと聴いていたが、どうせ意味がわからないのならと、刺繍の針を運びながら聴くようになった。明るく澄んだフミカの声は、変な引っかかりがなく、日本語でも英語でも聴き流しやすかった。
フミカもフミカで麻希に聴かせたいという気持ちはなく、そこに言葉を向ける先があれば、相手は何でも良く、ウェディングドレスを着たトルソーでも良さそうだった。

極端な話、モリゾウに教わった時間を麻希に返しに来るというのは復習につき合わせるための口実で、声を出せる環境が欲しかっただけかもしれない。
家の中にモリゾウ以外の人がいるのは新鮮で、フミカが来ることで空気が攪拌され、入れ替わるような気がした。
定時に仕事に出かける生活をしていない麻希にとって、週に一度フミカが来るのは良いリズムになっていたが、「今日で最後にします。春に良いご報告をして、今度こそお返しをさせてください」と去り際に唐突に区切りをつけられ、その日が最終日になった。
そっか、もう来ないんだ。来週から淋しくなるなとフミカが座っていた椅子に目をやったら、テーブルの上に辞書が開かれたまま置いてあった。日本語が入っていない英語から英語の辞書。
《辞書忘れてます》とメッセージを送ったが、既読はつかない。家に帰るまで、気づかないかもしれない。
届けに行こうか。
家の場所は聞いていた。モリゾウと散歩で時々通る道にある。
ところが、佐藤家のチャイムを押すと、応答がなかった。帰宅してすぐに出かけてしまったのだろうか。門の脇にあるポストに辞書を入れようとしたが、厚みがあって入らない。紙袋から出してもダメだ。
引き返そうかと思ったとき、「あれ?」とフミカの声がして、見ると、フミカが近づいてきた。両手で包むようにして焼きいもを持っていた。隣で佐藤千佳子が自転車を押していた。カゴには膨らんだエコバッグが入っていて、ねぎの青い部分が頭を出していた。マルフルで待ち合わせて、買い物して来たらしい。
佐藤千佳子は、麻希とモリゾウの家主である野間さんがマルフルで働いていた頃の同僚で、今もそこで働いている。野間さんの留守宅に住んでくれる人を探しているという話をバイト先の新宿三丁目のカフェで聞いたときも、佐藤千佳子は野間さんと一緒にいた。

「マキマキさん!」
待ってましたいうように佐藤千佳子が声を弾ませ、やはり辞書がないことに気づいて困っていたのだと思った。
「ちょうど今、本読み隊の話をしてたんです!」
「え? 本読み隊って?」
辞書を読むことを本読み隊というのだろうか。
「ママ、混ざってるよ。本読み隊はサツキさんでしょ」
フミカに突っ込まれると、佐藤千佳子は口を「あ」の形に大きく開けて息を呑み、
「ほんとだ。マキマキさんってわかってるのに、サツキさんになってた」と慌て、
「ごめんなさい。わたしマルチタスクが苦手で」と麻希に頭を下げた。
マルチタスクって、そういうことだっけと戸惑いつつ、麻希もつられて頭を下げた。
「あの、これ」
と辞書の入った紙袋を差し出すと、
「そんな。お礼をするのはこちらのほうなのに」と佐藤千佳子は恐縮する。紙袋を見て、中身を菓子折りだと勘違いしたようだ。
「違います! 辞書です!」
傍観していたフミカがようやく忘れものに気づき、「あ」となった。驚いたときの口と目の開き方が母親とそっくりだった。
「じゃ、これで」と引き返そうとしたら、佐藤千佳子に引き止められた。
「せっかくなので、本読み隊やりませんか?」
せっかくってなんだ?
本読み隊はフミカが卒業した小学校の読み聞かせ活動で、月初めの金曜日の朝、子どもたちに本の読み聞かせをしてから、図書室の飾りつけをすると言う。
「え? でも、わたし……」
断る理由はいくらでもあったが、咄嗟にまとまらず口ごもっていたら、「大丈夫です」と言い切られた。
何が大丈夫なのか。まだ何も言っていないのに。
「地域の人、どなたでも歓迎なんです」
子どものために良いことをやっていて、誰でも参加したいと信じきっている強さがあった。
「11月の第一金曜日、一緒に行きませんか?」
「ごめんなさい。その日は予定が入ってて」
実際は空いているけれど、塞がっていることにした。
「12月はどうですか?」
そこも塞がっているとは言えず、「じゃあ12月に」となった。
どうして断らなかったのかとその日から後悔しているのだが、数日前に受信した写真が麻希の気をさらに重くしている。

画用紙で作った天使の羽を背中につけた女の子ふたりの後ろ姿。ふわふわのスカートをはいて、手をつないでいる。
写真の差し出し人は原口直美となっていた。義理の姉、伊澤亜子の代理でmakimakimorizのひまわりバッグを購入した伊澤直美のことだ。原口は旧姓だろうか。
亜子が会いたがっていると夏に連絡があり、亜子と共にそれぞれの娘を連れて、この家にやって来た。姉妹のような幼いふたりは、不思議な歌を歌いながら庭でクローバーを摘んでいた。
知らない子たちではないけれど、突然写真を送られて、面食らった。何より麻希を戸惑わせたのは、添えられていた一言だった。
《うちの天使たちです》
ママになると、自分の子を「天使」と呼んで広めてしまうのか。そこに遠慮や謙遜はないのか。恋人や夫を「王子様」などと呼ぶのとは違うのだろう。
ママたちは子どもを中心に世界が回っている。愛してやまないわが子は誰からも愛される存在だと信じている。それが妬ましい、疎ましいというのではなく、自分にはないその感情が眩しくて、遠くて、どうしていいかわからない。
何か返事を書くべきだろうか。
《可愛いですね。幸せな気持ちになっちゃいました》
模範回答はこんな感じだろうか。こんな返事を送ったら、おかわりの天使を送りつけられそうだ。決して迷惑ではないが、持て余してしまう。口に合わないギフト菓子のように。
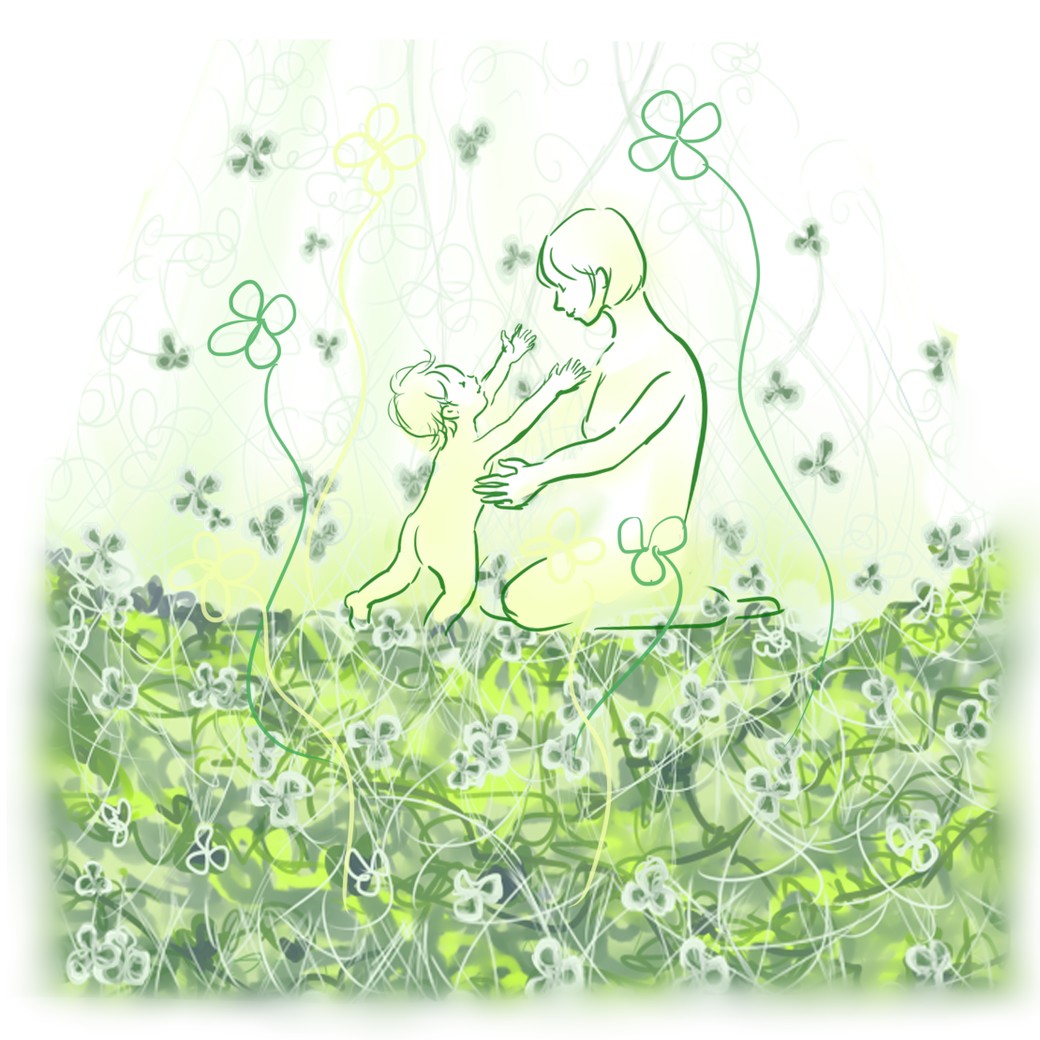
ママという生き物がわからない。距離感がつかめない。同じ言語を使うけれど通じ合えない。違う文化圏に住む人たちみたいだ。
身近なママと言えば、熊本に住む奈緒くらいだが、奈緒はママである前に妹だ。
本読み隊に行ったら、ママだらけだ。天使の親だらけだ。うちの天使自慢に返せる言葉の持ち合わせがない。わたしには天使はいない。わたしは誰のママでもない。
お子さんはおいくつ? 何人? 今どこの学校?
いないんですと答えて、微妙な空気になって、共通の話題がなくなって、ママたちを困らせてしまうのか。
「本読み隊、俺が行こっか?」
モリゾウの声で我に返った。

次回12月20日に多賀麻希(70)を公開予定です。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!


















































































































































































































































































































































































































































