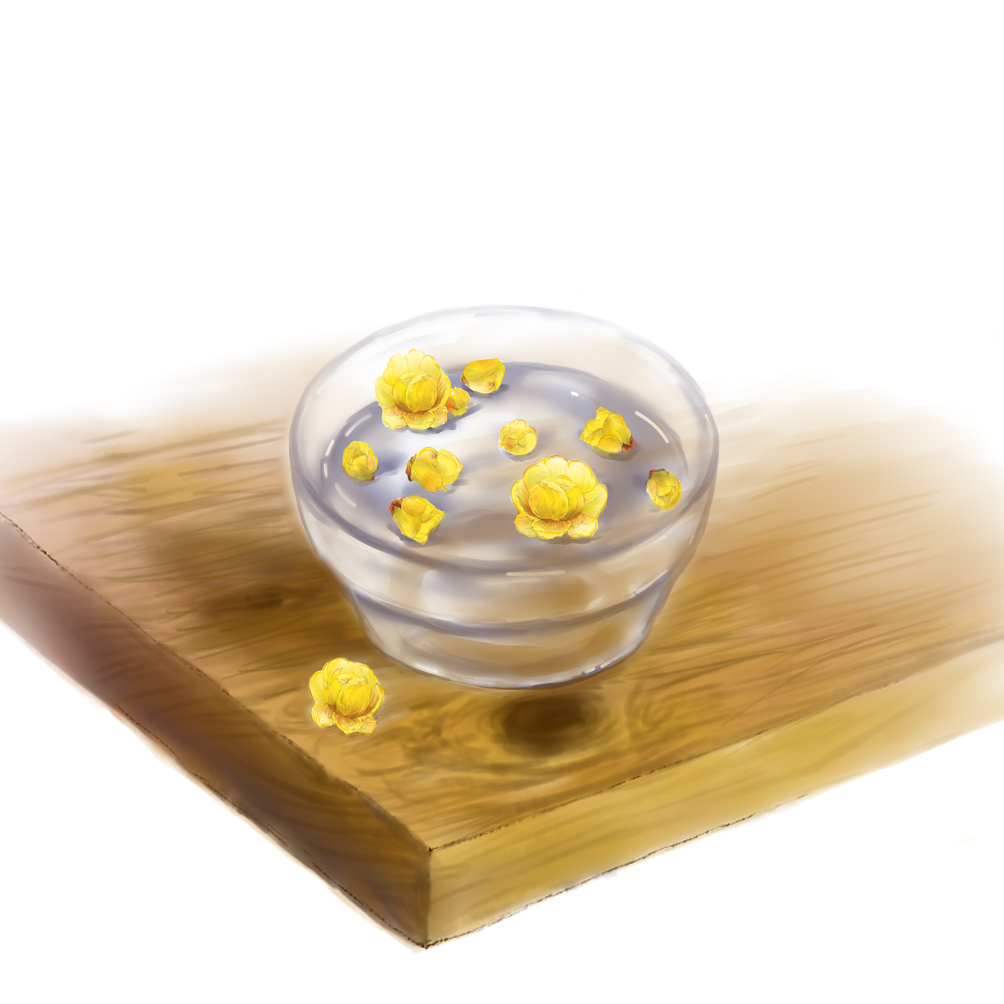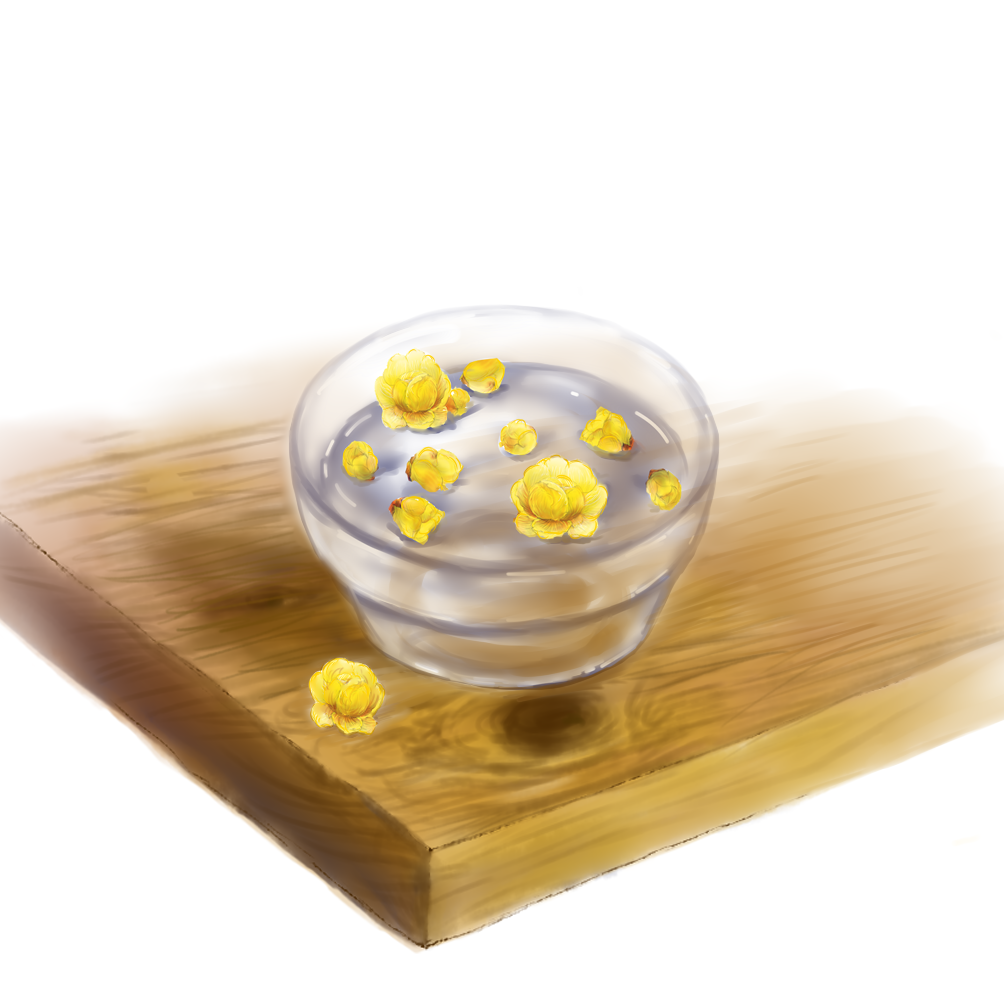第212回 佐藤千佳子(72) ロウバイの季節ふたたび
インターホンを押すと、応対したのは義父の声だった。
ドアを開けたのも義父で、千佳子を見て驚いた顔になった。
「お義母さんは?」と聞くと、
「出かけたよ」と言う。
「今日来るって約束してたの?」
「いえ、時間までは……」
義母から電話があったのは今朝のことだ。
共通テスト当日を迎えた文香が家を出てすぐ、キッチンカウンターに置いたスマホが震えた。文香が忘れ物でもしたのかとヒヤッとしたが、待ち受け画面を見ると、「美枝子さん」からだった。「お義母さん」「横浜ばあば」を経て、現在は「美枝子さん」で登録している。
「蝋梅が咲いているから、千佳子さん、いらっしゃらない?」
それが電話の用件だった。
うかがいますと言ったものの、ぐずぐずしているうちに午後になってしまった。
蝋梅が咲いたから、何なんですかという気持ちがあった。
夏の焼きいもとアイスクリームのあわせ売りをマルフル本部に売り込んだときも、文香の家庭教師をパセリ先生に頼んだときも、わたしを飛ばして勝手に話を進めたのに。
蝋梅だけいただいて帰るのも厚かましいし、お義母さんがいないならと引き返すのは、お義父さんには用はありませんと言うようで申し訳ない。

どうしたものか。
自転車のハンドルに手をかけたり離したりしていると、
「それで来たの?」と義父が聞いた。
地下鉄でひと駅、バスで停留所4つの距離だが、両家とも駅からも停留所からも離れている。家族と来るときは電車かバスを使うが、自転車なら直線距離で行ける。
「今日は一人なので」
そう言ってから、義父と顔を合わせるのは今年になって初めてだと気づいた。
「あ、明けましておめでとうございます」
年末に義父と義母が相次いで風邪を引いたこともあり、受験前の大切なときだからと年始の挨拶を遠慮されたのだった。
「そうだったね。上がって」
「え、でも……」
玄関を入ってすぐの和室を示され、はあと気の抜けた返事をして上がらせてもらった。
義母が留守で義父だけが家にいる事態を想定していなかった。奥の台所から食器を出すような音がする。電子レンジで何かを温めている音もする。手伝いましょうかと言うべきだろうか。来ないでくれと言われてしまうだろうか。
床の間には、あの日のように蝋梅が活けられている。
4年前のちょうど今頃だった。前の年の12月、14歳の誕生日を控えた文香が「誕生日ケーキいらない」と言い出した。友人を招いての誕生会は中学一年の13歳の誕生日に卒業したが、義父母を招いて一緒にケーキを食べて祝った。14歳の誕生日も同じように祝うつもりでいたのだが、「ママがやりたいならやれば?」と投げやりに言われてしまい、どうしていいかわからなくなった。

「誕生日ケーキの顔をしていないケーキにすれば?」
当時パートの同僚だった野間さんのアドバイスで、シフトの帰りに2割引のついたロールケーキを買って帰った。文香はペロリと平らげたが、「ケーキいらない」の真意はわからないまま年を越した。そんな頃に「お餅がたくさんあるから」と義母から電話があった。その頃は、「横浜ばあば」で登録していた。
「ロウバイの季節よね」
この部屋で向き合うなりそう告げられた。文香のことで狼狽しているのを見透かされたのかと焦り、千佳子にしては珍しく、勢い込んで打ち明けた。
すると、文香が一人でケーキを持って訪ねて来たと義母は言った。じいじばあばと一緒に誕生日を祝えなかったからと。千佳子が買ってきたのと同じ、誕生日ケーキの顔をしていないケーキ。値引きシールはさすがについていなかったはずだ。
「ロウバイ」というのはあの花の名前だと義母は床の間の黄色い花を示した。庭で育てていて、毎年この時期に花をつけるのだという。

餅と一緒に持たせてもらった蝋梅を家のキッチンカウンターに活けた。中学校から帰宅した文香が部屋に入るなり、「なんの香り?」と気づいた。
横浜ばあばの家でいただいてきたと話し、ロールケーキを持ってじいじばあばの家に行ったんだってと続け、「ケーキいらない」の心を聞けた。
14歳の誕生日ケーキはこれがいいと文香が指名したものがあったのに、千佳子が忘れていて、「ケーキどうするの?」と聞いた。だから、すねたのだと。
マルフルで働くようになって2年目の冬だった。当時、千佳子は「パセリの花束」にかまけていた。パセリに赤と緑のリボンを巻いて小さなクリスマスツリーに見立てるという思いつきが数字に結びつく手応えに夢中になっていた。
「パートの時間減らしたりしなくていいからね。ママが楽しそうにやってるのは歓迎なんだから。1年前はママってやりたいことないのかなって心配してたけど、ママ、変わったよねー。この1年で娘より成長してない?」
黄色い花を最後はガラスの器に浮かべて楽しみ、ロウバイの季節は終わった。
文香はあれから4度誕生日を迎え、18歳になった。

義父が盆を運んできた音に顔を上げた。ローテーブルに置かれた盆には、お茶の入った湯呑みと半分に割って皿に載せた焼きいもがあった。
「お義母さんの焼きいもですか」と聞くと、
「いやいや、お宅の焼きいもだよ」と言う。
「お宅の」というのは、千佳子が働いているマルフルで買ってきたという意味だろう。その焼きいもをヒット商品に押し上げた立役者が自分の妻だと義父は知らないのだろうか。
「さっき温めていたの、これだったんですか」
「冷めると甘みが弱くなるんだよ。アイスクリームと一緒にどうぞなんて夏にやってたけど、もったいない」
千佳子は思わず吹き出してしまう。義父の知らない義母がいる。
義父はナイフで少しずつ輪切りにして口に運ぶ。おいしそうに目を細める。何か話題を提供しようと思ったが、黙っていても気まずさはない。ねっとりした焼きいもが間を持たせてくれる。
「おかしなことを言うよ」
なんでしょうと千佳子は背筋を伸ばす。何を言われるのだろうか。夫のことか、文香のことか。
「あの日見たのは千佳子さんだったのかな」
「あの日?」
「美枝子がしばらく留守にしていたとき。外で音がしたような気がしてね。窓から見たら、走り去って行く自転車が見えた。さっき千佳子さんが乗ってきた自転車を見てね、あんな色だったなって」
お義父さん、それ、わたしです。あれは留守ではなく、家出ですけど。
「気になって様子を見に来たんですが、にぎやかな声がしていたので、お邪魔かなと思って」
「やっぱり」
せっかくマルフルの焼きいもを買って行ったのに、心配して損したような気持ちになった。引き返した途中でばったり文香に会った。文香とベンチで焼きいもを分け合ってから、文香も同じことを考えていて、焼きいもを義父に届けようとしていたのだと知った。

あの日、分け合えなかった焼きいもを今、義父と食べている。
「インターホン鳴らさなかったのに、よく気づきましたね」
「美枝子が帰ってくるかもしれないって気にしていたのかな」
「お義父さん、待っていたんですね」
「騒いでいるところを見つかったら、何言われるかと思ったんだよ」
お餅がたくさんあるからと呼び出されたときは、自分の知らない文香のことを聞かせてもらった。蝋梅が咲いたからと呼び出しておいて出かけたのは、義父を知る時間を作るためだっただろうか。思いつきで行動する美枝子さんは、きっと、そこまでは考えていない。
ほんのりと蝋梅の甘い香りがする。花言葉は「慈愛」。

次回1月31日に伊澤直美(71)を公開予定です。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!