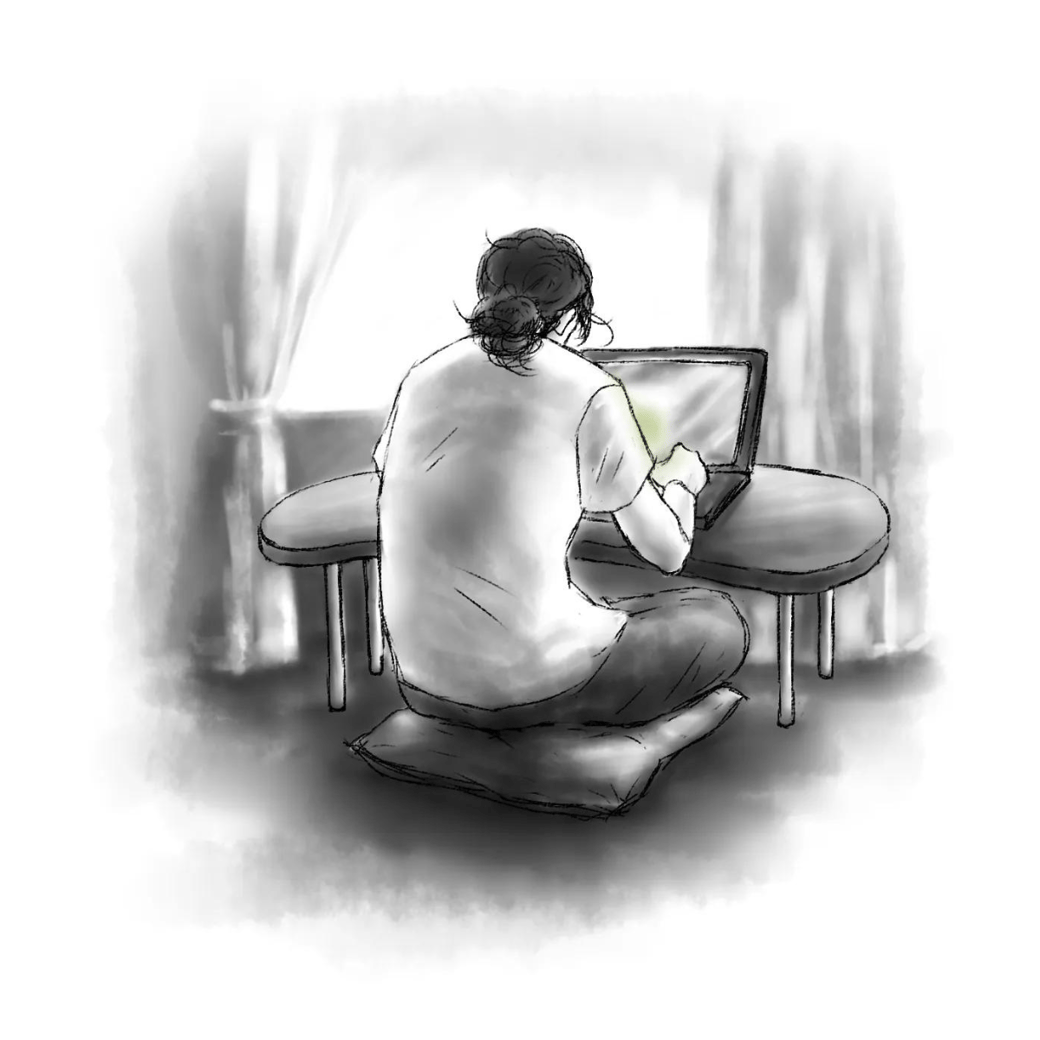第42回 多賀麻希(14) 作家と呼んでくれた彼のシナリオ
「マキマキさんが作ってくれたら、おれが売りますよ」
モリゾウがそう言ったので、麻希は商品になる布雑貨を作ることにした。
今の部屋に引っ越したときに、家具も衣類も食器もほとんど手放したが、ミシンは持って来た。裁縫道具と布やボタンや糸のストックも。布やボタンは出会い物なので、同じものを後から探しても、なかなか見つけられない。
がま口の留め金が3つあったので、古墳王子のバッグを作った布の端切れで、がま口ポーチを3つ作った。余った布は好きにしてくれていいと言われていた。四つ葉のクローバーを刺繍であしらった。
モリゾウはがま口ポーチに「5千円」と値段をつけた。
「高すぎない?」
「クッソつまんない舞台でも5千円するじゃないっすか」
モリゾウの言葉を聞いて、映画製作プロダクションで働いていた20代の頃のことを思い出した。撮影現場で仲良くなった役者の卵たちの舞台のチケットをよく売りつけられた。
2千円から3千円の舞台が多かったが、2千円でも映画を観るより高い。チケットの値段以上の作品にはなかなか巡り会えず、ハズレくじを引き続けた。
麻希にチケットを売った男の子の出番は一瞬で、顔も名前も知らない上半身裸にサスペンダーつきの半ズボンをはいた小太り男が出ずっぱりのワンマンショーのような舞台が、5千円だった。サスペンダーをバチンと弾いて肌に当て、痛そうな音を立てるのをひたすら聞かされ、くだらないのに寝ることもできなかった。座席はパイプ椅子で、音楽はありもので、舞台美術もお金をかけていないのに、なぜか強気な価格設定だった。
一緒に行く相手がいないのに「一人じゃ行かないですよね?」と言われ、チケットは2枚買っていた。一人で観終えた後、このお金でおいしいものを食べられたのにとモヤモヤした。その感想を言い合うために誰かと観たかった。
痛い出費だったが、作り手の立場からすれば、何週間も稽古して作り上げた作品なのだから、それなりの値段はつけたいところだろう。モリゾウにその話をすると、
「頑張りを値段に乗っけるのはプロじゃないっす」とバッサリ斬った。
モリゾウはプロの役者なのだろうか。役者だけで食べていけているとは思えないが、役者以外のことはしてなさそうだ。モリゾウが忙しくなって新宿三丁目のカフェのバイトをやめることになり、入れ替わる形で麻希が後釜に入ったが、モリゾウは次回公演の準備をしている様子もない。

明け方、キーボードを打つ音に目を覚ますと、モリゾウが寝室にしているダイニングの灯りがついていた。引き戸をそっと滑らせると、モリゾウはちゃぶ台に向かってパソコンを打っていた。
「起こしちゃいました?」
モリゾウが振り向いた。寝起きの声ではない。早起きしたのではなく、徹夜したらしい。
「また舞台やるの?」
「なんでですか?」
「シナリオ書いてるのかなと思って」
「パソコン打ってたら、シナリオって思うんですか?」
モリゾウが不思議そうに言う。
「ああ、たしかに」
寝ぼけた頭がゆっくり回転を始める。
パソコンを打っているときは、シナリオを打っているとき。
ツカサ君がそうだったのだ。コンクールを見つけては、書いていた。「書く宝くじ」と言いながら。
「シナリオっちゃあ、シナリオっすね」
麻希がパソコン画面を見られるよう、モリゾウが画面の前から体をずらした。
オンラインショップの麻希のページができていた。モリゾウがアカウントを取得したときは殺風景だった初期画面がカスタマイズされていた。
「こういうの、得意なんだ?」
「舞台の公演ページ作ったりしてるんで」
「あ、そっか」
背景は水色で文字はこげ茶色。モリゾウはなぜわたし好みの配色がわかったのだろう。
「どうっすか?」
「すごくいい。好き」
「好き」なんて口にしたの、いつぶりだろう。

商品ラインナップには、グリーンのがま口ポーチが3つ並んでいた。
「作品の紹介、見てもらっていいっすか」
モリゾウは、麻希が作る布雑貨のことを「作品」と呼んだ。
《ミント色の風が頬に触れて、自分が泣いていることに気づいた。五月の昼下がり。》
ポーチの写真に添えられた文章は、商品説明というより詩のようだった。グリーンの布から、ミント色の風を想像したのだろうか。
形もサイズも同じ2つ目のがま口ポーチの写真には、別な文章が添えられている。
《鏡に映る自分の姿を気にするようになったのは、いつからだろう。そのとき、見ているのは、鏡の中の自分ではなく、誰かの視線。》
これは、ポーチに手鏡を入れてみてはという提案なのだろうか。
3つ目のがま口ポーチの写真には、
《急がないでいいよという言葉にも焦ってしまう私をあなたは誰よりも知っている。》
とあった。「あなた」はポーチのことなのだろうか。
「わかりにくいっすか?」
麻希の反応がないので、理解に困っているのだとモリゾウは察したらしい。
「いや、なんていうか、こう来たかって思った。朗読劇のモノローグみたいっていうか、たしかにシナリオっぽいね」
「そういう意味でシナリオって言ったんじゃないっすよ」
「え? じゃあ、どういう意味?」
「マキマキさんを作家として売り出すシナリオっす」
布雑貨を「作品」と呼ぶモリゾウは、その作り手の麻希のことを「作家」と呼んだ。
服飾専門学校に入った頃、いつか自分のブランドを持ちたいと夢を描いていた。業界の厳しさを知って、いきなり独立するのではなく、どこかに就職して、力をつけてからという現実的な筋書きを考えるようになった。だが、服飾デザイン関係の就職先は決まらず、専門学校で学んだ技術は使われることなく、封印された。

映画製作プロダクションに入り、低予算の撮影現場につくと、その日必要なお弁当の数を数えて注文して配りながら、衣装さんの仕事を眩しそうに見ていた。一度、衣装さんに叱られた衣装助手が撮影に来なくなり、急遽手伝ったことがあった。ありもののワンピースの裾にフェルト地のチューリップをつけるという作業を頼まれた。チューリップをかがった糸でちょうちょの刺繍をあしらってみた。喜ばれると思ったら、「余計なことしなくていいから早く!」と叱られ、取り上げられた。
麻希は、作る技術だけでなく、作りたいという衝動や作る喜びも封印することになった。誰かに喜ばれるために作ろうなんて思っちゃいけないと自分を戒めた。
ツカサ君が残して行った服をリメイクしてバッグを作ったとき、久しぶりにミシンを触った。針と糸を手に取った。誰かのためではない。自分への慰めだった。恋人の服を捨てるのはしのびないけれど、そのまま残しておくのも心苦しい。だから、形を変えて手元に置こうとした。
そのバッグを、出会った日のモリゾウは「古墳みたいっすね」と面白がった。
モリゾウから紹介された古墳王子に古墳バッグを作ることになり、その代金は受け取れなかったけれど、余り布でがま口ポーチを作り、モリゾウがネットで売ろうとしている。
「3パターンの紹介文のどれかに絞るってこと?」
「いや、それぞれ顔見て、つけてるんすよ」
「顔見て?」
「一つ一つ、顔が違うから」
確かに、まったく同じではない。グリーンの布には透かしのように白糸が織り込まれていて、その出方が微妙に違う。3つ並べてみると、表情のバリエーションがあるのがわかる。それをモリゾウは顔の違いと呼んだ。
同じ説明文で在庫3として扱うのと、一つ一つを独立した作品として扱うのとでは、まるで意味合いが違う。
まるで自分が特別に扱われたような気がして、鼻の奥がツンとなる。こみ上げた涙でパソコン画面がぼやけた。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第43回 佐藤千佳子(15)「自分の人生に振り落とされないようにしなくちゃ」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!