
第90回 多賀麻希(30)まわりまわってひまわりバッグ
服飾専門学校を出て20年。モリゾウに会うまでの麻希は削られることのほうが多かったが、ケイティはその逆で、ボリュームと貫禄が増した。意地悪な言い方をすれば、ミニスカートが似合わない体型になった。
今でも綺麗なことには変わりはないが、雰囲気がまるで違う。キラキラがギラギラに変わった。
「知ってる人?」とモリゾウが聞く。
「ケイティ」と答えると、
「専門学校の?」と返ってきた。
「あれ? モリゾウに話したことあったっけ?」
「あったよ。『KT』って日本映画あったよねって話になったとき」
そうだった。「イニシャルがKTの同級生に課題をやらされてた」と軽く話していた。
「ショップのこと、知らせてたの?」
「まさか。卒業してから連絡取ってないし」
「じゃあ、今どうなってるか知らなかった?」
「全然」
連絡を取り合っている同級生はいないし、ネットニュースもあまり見ないから、ケイティがちょっとした有名人になっていたことを知らなかった。
大手のアパレルメーカーに就職した後、30歳のときに独立して自分のブランドを立ち上げ、10年かけて大きくした。その間にファッション誌に連載コラムを持ったり、コメンテーターとしてテレビ出演したり、自分の顔と名前も売ってきた。
ケイティが有名になったからブランドのネームバリューが上がったのだろう。観光地にあるタレント経営のレストランに行列ができるみたいに。
「やだな、性格悪い」
「ケイティが?」
「わたしが。ケイティもたいがいだったけどね」
「ウランデルタール人だねえ」とモリゾウが冗談っぽく言い、
「ウランデルタール人ですよー」と麻希も茶化して言う。
世界史で習ったネアンデルタール人の駄洒落で「ネタンデルタール人」と言い出したのはモリゾウだ。恨んでいるときは「ウランデルタール人」、悩んでいるときは「ナヤンデルタール人」、病んでいるときは「ヤンデルタール人」と活用する。言葉遊びを加えた分だけクローズアップがロングショットになり、悲劇が喜劇になる。
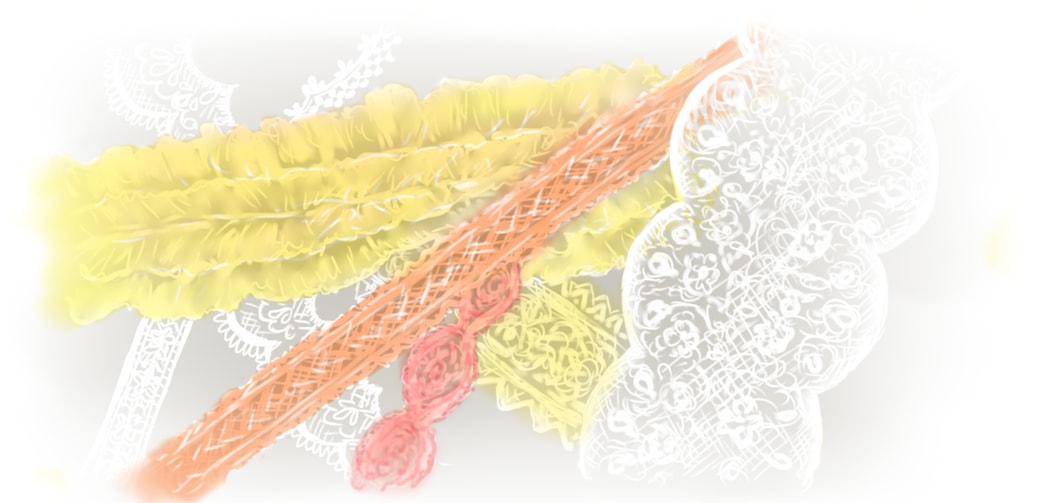
「やりがい搾取されてましたからねー。あの頃はそんな名前ついてなかったけど」
今思えば、ケイティ構文にまんまと乗せられていた。「ここにレースを入れたいんだけど」と言われたら、時間を理由に断れたのに、「ここにレースを入れたら素敵だと思うんだけど、できる?」と言われたら、「できない」とは言えなかった。
「映画で使う衣装のデザインが課題に出たことがあってさ。10案ぐらい描かされて」
女子高生にある日突然しっぽが生えてきたという映画の劇中でヒロインが着る衣装で、ヒロインの姉が駆け出しのデザイナーという設定だった。
「すごい。どんどん良くなる。どうしよう。もう一案見せてもらっていい?」
締め切りまでその調子で、気づいたら10案になっていた。そのうちの3案が採用された。提出点数も採用点数もケイティが一番多かった。
エンドロールに「衣装デザイン協力 ケイティ」とクレジットが入った。ケイティは田川圭子という地味な本名ではなく、通り名での表記を希望した。提出されたデザイン画には、ケイティではなく本名を記した。麻希ではなく自分の筆跡で。
ケイティは推薦枠で大手アパレルメーカーにデザイナーとして採用され、麻希はどこにも決まらず、映画製作プロダクションに事務職で拾われた。
ある日、資料の地層を掘って探しものをしていたら、見覚えのあるデザイン画が現れた。フリルの衣装から飛び出したしっぽ。あの映画を作った会社だったんだと因果に驚いた。
「懐かしいなー。まだ取ってあったんか?」と社長は言い、「それもうほかしといて」と続けた。
「じゃあわたし、もらっていいですか?」
「そんなん欲しいん?」
「わたしが行ってた専門学校の課題だったんです」
麻希のデザイン画は採用されなかった。ケイティの分を描くのに時間を使い切ってしまい、提出が間に合わなかった。

「職場でデザイン画を見つけた話もケイティにしてないんだ?」とモリゾウが聞いた。
「してないよ。ケイティは蒸し返されたくないだろし」
「そっか。自分が描いたことになってるんだもんね」
ゴーストが蘇るようなもんだねとモリゾウは言い、小説を代わりに書くのはゴーストライターだけど、デザイン画を代わりに描くのは何だろうという話になった。「ゴーストデザイナー」が思い浮かんだが、「語呂が悪いね」となり、「だから普及してないのかも」とうなずきあった。
ケイティにとっての麻希は、ゴーストというより透明人間だったと思う。都合のいいときだけ姿が見え、デザイン画を描いてくれる透明人間。卒業してから一度も連絡を取らなかったのは、もし連絡を取っても、「誰だっけ」ととぼけられそうな気がしたからだ。用が済んだ透明人間は、消えてくれているほうが都合がいい。
だから、ひまわりのバッグをケイティが見つけて買い求めたのは意外だった。
たまたま目に留まったのだろうか。ケイティなら、一目見て、麻希の作品だとわかったのではないだろうか。植物をモチーフにしたデザインは、専門学校時代から手がけていた。映画の衣装デザイン画にも黄色い花を大胆にあしらった。
見過ごすこともできたのに、それを買うということは、せっかく消した透明人間にわざわざ色をつけるということだ。
「20年経った今だから、マキマキに連絡取りたくなったんじゃない?」
「だったら、ケイティだよってコメントで知らせてくれれば良かったのに」
相手は麻希に気づいていたのに、こちらだけ知らなかったのが、なんだか居心地悪い。
ひまわりバッグの購入者からの最初のコメントは、「一目惚れして購入させていただきました」だった。発送完了の連絡をすると、「楽しみにお待ちしています」と返信があった。
オンラインショップでたまたま見つけてくれ、作品を通してつながりのできた見知らぬ人だとばかり思っていたら、まさか、ケイティだったとは。
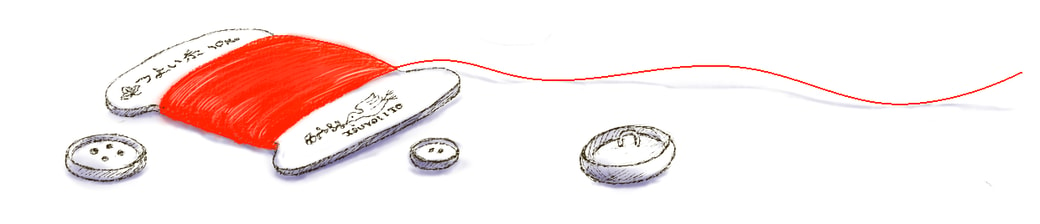
「マキマキとダブルヒロインの脚本書けそうだね」
それは悲劇なのだろうか。喜劇なのだろうか。
「ふたりの20年前と今をカットバックで描いたら面白いかも」
モリゾウは頭の中でプロットを組み始めている。
ツカサ君といい、モリゾウといい、麻希の恋人は笑えない過去を物語にして価値を生み出そうとする。
改良再利用。今流行りのアップサイクル。
「ケイティに連絡取ってみようかな。取材兼ねて」
屈託なさそうに明るく言って、麻希は「あれ?」となる。
「名前、違った気がする」
オンラインショップの取引履歴を開き、ひまわりバッグの購入者情報を見ると、名字も下の名前も「田川圭子」とはまったく違った。どちらかが同じでも購入時にケイティを連想したはずだ。それほど爪痕を残している名前だ。麻希にとっては。
「代理の人が買ったのかな? 秘書とか」
ケイティ以外の人が購入してケイティの手に渡った可能性を考えようとするが、胸騒ぎがする。購入者の住所は都内だが、オフィスではなく個人宅のようだ。
ひとつしか作っていないバッグを、おそらく購入者ではないケイティが持っている。それが何を意味するのか、答えは浮かんでいるが、認めるのが怖い。
彼女にとって、今でもわたしは透明人間なんだ……。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第91回 佐藤千佳子(31)「モブキャラに秋がしみる」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































