
第104回 佐藤千佳子(36)せっかく生まれてきたんですから
たい焼きを半分に割ると、薄い皮にぎっしり詰まったあんこが顔をのぞかせ、ほんのりと湯気が立ち上った。
たい焼き屋を後にし、バス停に着くと、すぐにバスが来た。千佳子の家に着くまで、15分も経っていない。
店の前のベンチで食べるつもりだったのだが、うちに来ませんかとカズサさんを誘った。パートを休んで家にいても、やることはなく、余計なことを考えてしまう。文香が中学校から帰宅するまでの午後を一人で過ごしたくなかった。
「半分こしませんか」と提案したのはカズサさんだ。ひとつは文香にと気を遣ってくれた。
「食べちゃえばわかりませんよ」と千佳子は言ったが、
「子どものおやつセンサー、なめないほうがいいです。うちの子、3時間前のたい焼き、つかまえますから」
実感の込もったカズサさんの言葉に説得された。
カズサさんには、文香より3つ下、小学6年生の娘さんがいる。「視覚を使わないプロ」のカズサさんとダンナさん、視覚「も」使う娘さんの3人家族だ。
「カズサさん、頭としっぽ、どっちがいいですか」
「しっぽがいいです」
「頭のほうが、あんこ多いですけど」
「しっぽが好きなんです。ギザギザの焦げたとこがパリパリしてて、触っても楽しいんですよ」
なるほどと千佳子は相槌を打ち、手に取った頭のほうのたい焼きに指を這わせてみる。
顔の輪郭。口。目。えら。背びれ。うろこ。
「たい焼きの皮って、結構、情報量多いですね」
「そうなんですよ。お店によってちょっとずつ違いますし」
「カズサさん、触っただけでわかるんですか?」
「そこまで気合入れて比べたことないですけど、皮を触ってどこのお店か当てる選手権あったら、本気出します」
そんなことを話しながら食べていたら、丸ごと食べるときよりも時間がかかり、半身のたい焼きを堪能した。
「あれ? この香り」
たい焼きを食べ終えたカズサさんが、キッチンカウンターへ目を向けた。
ドレッシングの空き瓶に金柑の枝を挿している。色づいた小さな実がふたつ。その香りに気づいたらしい。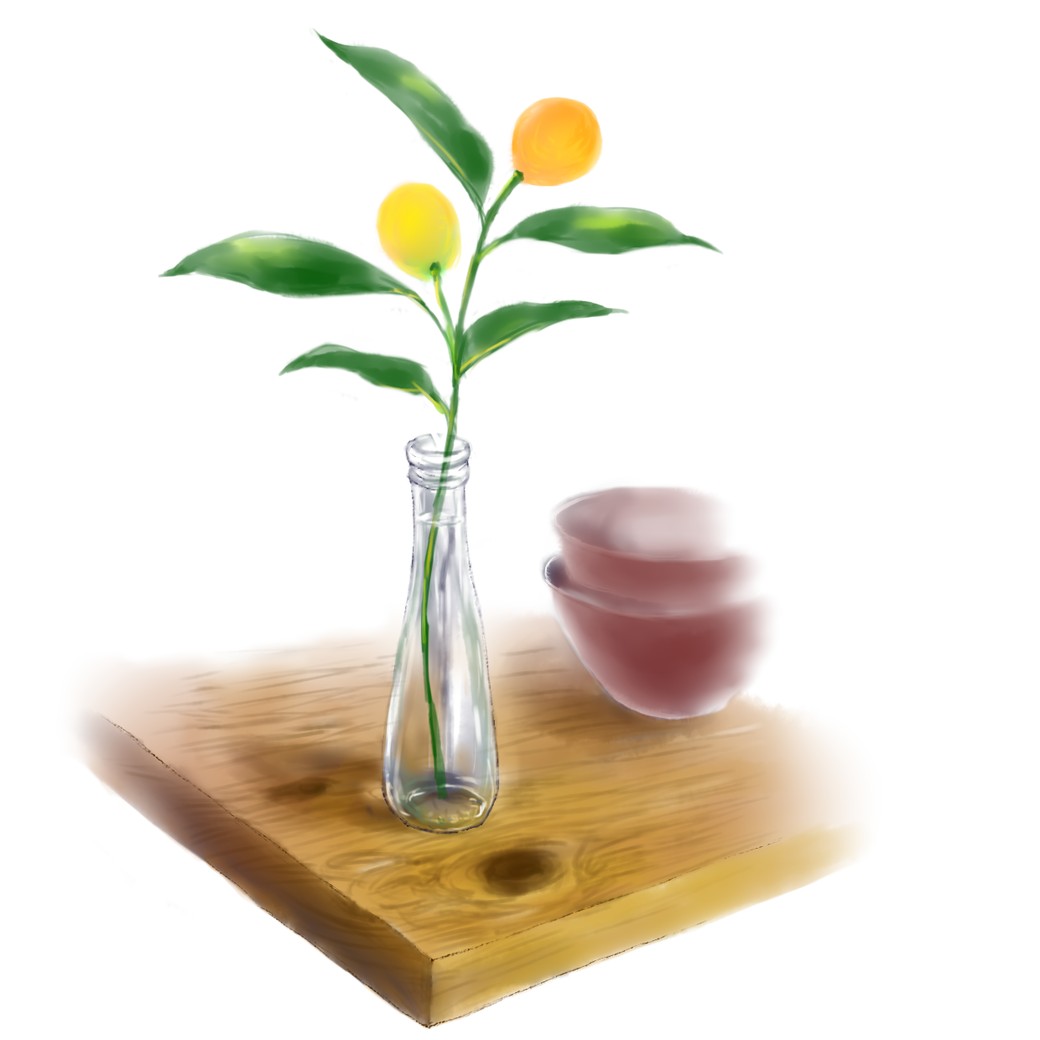
「金柑です」
「ああ、金柑。鼻が空いて、今気づきました」
たい焼きのにおいに占められていた鼻に他のにおいを感じる隙間ができたことをカズサさんは「鼻が空く」と言い表した。
「こんな香りでしたね」
カズサさんが金柑を含んだ部屋の空気を吸い込む。
「実、触ってみます?」
「いいんですか?」
千佳子は席を立つと、金柑を活けた瓶を手に取り、てっぺんの実にカズサさんの手が触れるように近づける。カズサさんは親指と人差し指でそっと実に触れ、「枝になってるんですね」と言った。
「マルフルの野間さんのお庭のお裾分けなんです」
「野間さんって、金柑育ててるんですか」
「レモンやブルーベリーの木もあるんです。いつ行っても季節のお花が咲いてて。ノマリー・アントワネットの庭って呼んでるんです」
「すごそうですね。見てみたいです」とカズサさんは指で金柑を見ながら言った。
「今度一緒に行きましょう。野間さんに言っときます」
「ここにも実がなってる」とカズサさんが枝の下のほうについている実を指で探り当て、「金柑って、金色っぽい色なんですか」と聞いた。
「黄色とオレンジの間みたいな感じです」
「こっちの実は大きくて、こっちは小さくて。太陽と月みたいですね」
「太陽と月」と聞いて千佳子が思い出すと同時に、「そう言えば」とカズサさんも思い出した顔つきになった。
「日曜日と月曜日がケンカする話って、どうなりました?」
最後にカズサさんと会ったとき、その話をしたのだった。シフトを終え、野菜売り場で買い物をしながら物語をブツブツ呟いているところをカズサさんに見つかり、声をかけられた。あのとき、読みたいと言ってくれたのに、それっきりになっていた。
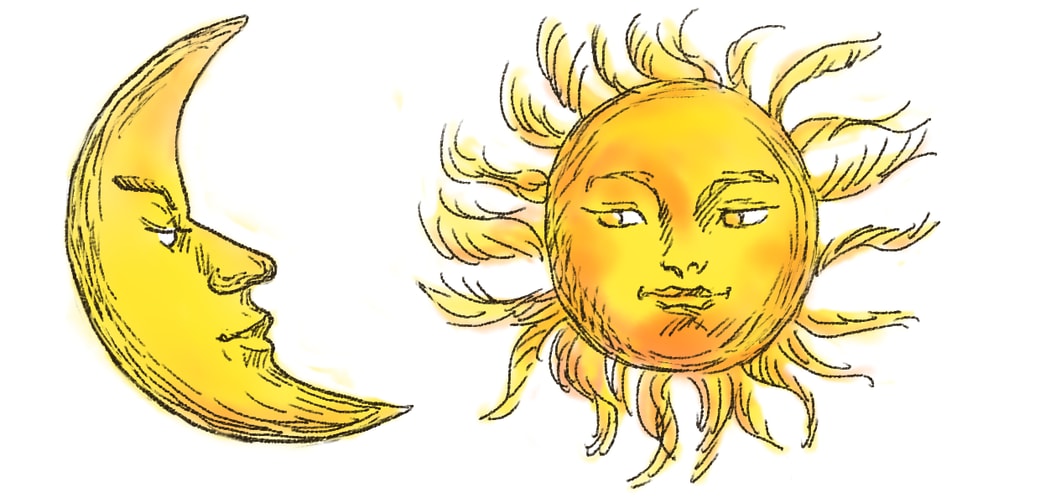
「実は、夫の両親を仲直りさせるために作ったお話で。大晦日に、ふたりをここに呼んで上演したんです」
家出した夫の母が千佳子の家を経由して野間さんの家に転がり込み、マルフルで働き始め、今も働いている話は長くなりそうなので端折った。
「それビデオ撮ってないんですか」
「ないです」
記録に残すという考えはなかったが、撮っておけば良かった。こんなことあったねと後で振り返るために。あるいは、十年後、また夫の両親が同じことでもめたときのために。
「じゃあ、今読んでください」
「今ですか?」
「せっかく作者が目の前にいるので」
作者と呼ばれて千佳子は面食らうが、カズサさんはすっかり聞く姿勢になっている。
大晦日上演のために作った台本を引っ張り出す。画用紙を二つ折りした表紙には、文香が描いた太陽と月のイラスト。開くと、大きめの文字で出力した原稿を貼りつけている。
「下手くそですけど、読みます。『一週間で一番えらいのは誰?』。日曜日と月曜日がケンカした」
大晦日のときは文香と夫と3人で役を分けたが、ナレーションもすべての曜日の役も一人でこなさなくてはならない。だが、自分のセリフが次いつ回って来るかと構えるより、全部自分でやるほうがペースを作りやすいと気づいた。
「そんなにもめるんだったら紙曜日を作る!」のところで、カズサさんが声を上げて笑い、千佳子も調子づいた。
「このカレンダーは紙でできているから、紙曜日がいちばんえらい!」と紙が威張るところも、7つの曜日たちがあわてるところも、芝居がかってやると、どんどん楽しくなった。
これが、アドレナリンが出るってやつか。
「紙曜日を作るのは、やめてくれ!」と7つの曜日たちが力を合わせて8つめの曜日が加わるのを食い止め、「めでたし。めでたし」と台本を閉じると、たった一人の観客であるカズサさんが拍手をして言った。
「いい長さですね」
内容ではなく長さをほめられた。
ほめるの、そこ?
「実は、発表会で読む作品を探していたんです」
「発表会?」
「私、朗読サークルに入ってて。そろそろ読む作品を決めなきゃいけないんですけど、なかなかこれっていう作品がなくて」
はあ、と千佳子が気の抜けた返事をすると、
「やっと見つかりました。佐藤さんの作品、朗読したいです」
「作品だなんて、そんな。申し訳ないです。だって……」
十年に一度の周期で繰り返される夫の両親のつまらない論争に巻き込まれて、すったもんだの末に生まれた副産物。隠すものではないが、晴れの舞台でお披露目してもらうのは身の程知らずではないだろうか。
「紙曜日って、すごいところに目をつけたなって思うんです。紙って、閉じることも開くこともできるじゃないですか」
はあ、とまたしても気の抜けた返事をして、千佳子は目の前に広げた紙を見る。少し前、たい焼きが置かれていた紙だ。たい焼きを包んでいた袋を開くと、皿になった。

カズサさんの言う通り、紙は閉じることも開くこともできる。閉じ込めて、他のものを締め出すこともできる。開いて、他のものを受け入れることもできる。折り紙にして風船や鶴に姿を変えることもできる。ちぎれば、紙吹雪になる。
一週間に8つ目の曜日を加えるなら、「紙」はいいところに目をつけているのかもしれない。紙曜日を思いついた夫のヒットだ。
「でも、いいんでしょうか。こんな素人の作った拙い話」
「埋もれさせておくの、もったいないですよ。せっかく生まれてきたんですから」
「カズサさん大袈裟です」
笑ったつもりだったのに、涙がせり上がった。野菜売り場でもカズサさんに泣かされたことを千佳子は思い出す。踏んだり蹴ったりで迎えたクリスマスに「佐藤さんの言葉って、優しくて、温かくて、好きなんです」と思いがけない言葉をプレゼントされた。あの日の励ましも物語が生まれるチカラになった。
「佐藤さん、またじんわりなってはります?」とカズサさんが関西弁になった。
「カズサさんダメですよ。受験生の親は情緒不安定なんですから」
そこにドアが開いて、「ママたい焼き食べたでしょー」と文香が入ってきた。テーブルにいるカズサさんに気づいて「お客さん?」とかしこまったが、カズサさんが吹き出すほうが早かった。
「ほらね。おやつセンサー発動しましたよ」とカズサさんが勝ち誇る。
「ふーちゃん、合格もらっちゃった」
「え? 何の?」
「はい。めでたい、たい焼き」
母から娘へ、バトンのように「このままの私でいいんです」が受け渡された。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第105回 伊澤直美(35)「何を証明しようとしているの?」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!
























































































































































































































































































































































































































































