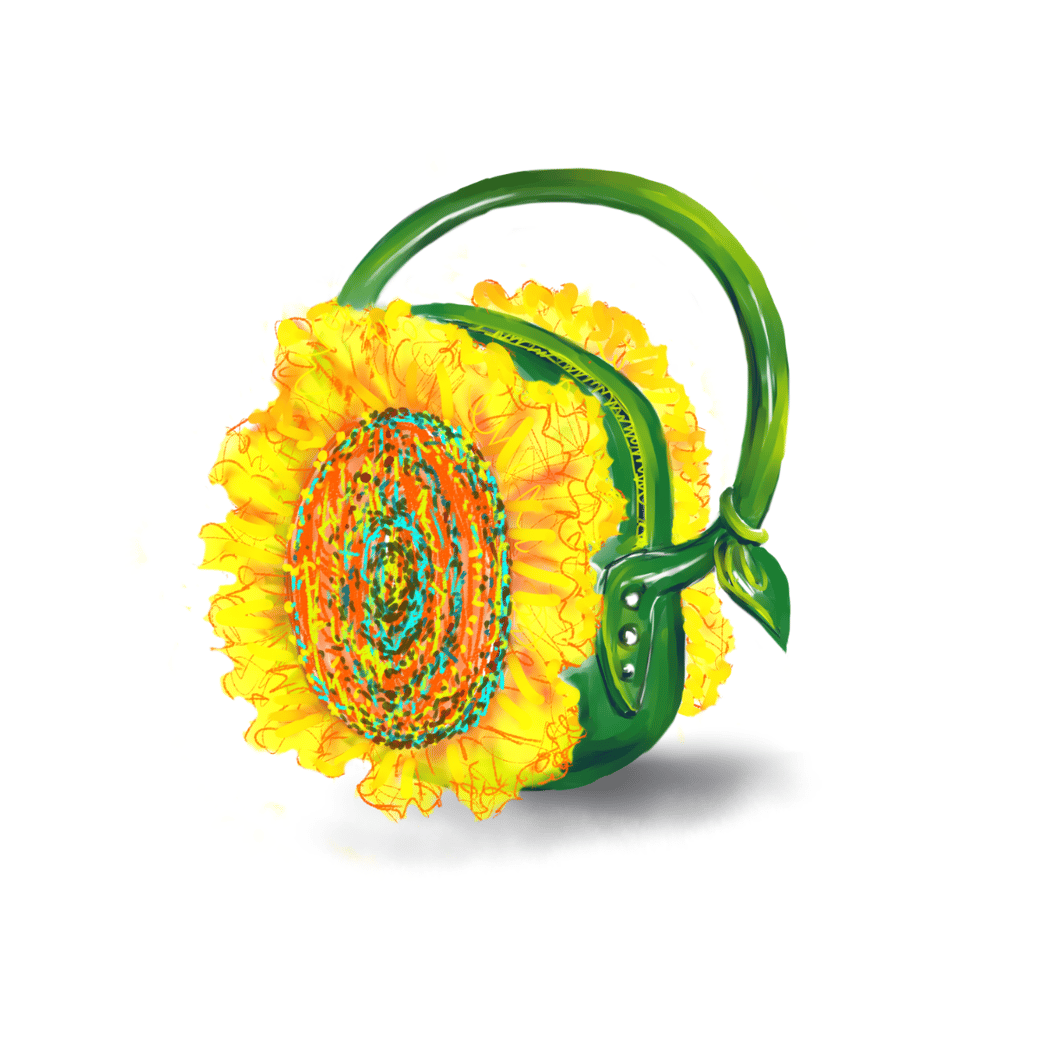第84回 多賀麻希(28)「嫉妬してくれてるの?」の魔法
6万円のひまわりバッグが売れたお祝いのシュークリームは、味がよくわからないまま、麻希の中におさまった。
前から目をつけていたパティスリーのシュークリーム。今日こそあれを食べようとモリゾウと意見が一致し、ふたりで手を取り合って店へ向かったら最後の2つで、まるで自分たちを待っていてくれたみたいだねと顔を見合わせた麻希とモリゾウを、レジの女の子が微笑ましそうに見ていた。
部屋に持ち帰り、箱を開け、シュークリームの重みを手に受け止めるまでは膨らみきっていた高揚感は、モリゾウのダメ出しにしょげたように、すっかりしぼんでしまった。
200円でお釣りが来るコンビニのシュークリームに何度も満たされてきたのに、その3倍もするパティスリーのシュークリームを食べて、こんな割り切れない気持ちを味わうとは。
「気まずくなったら、『嫉妬してくれてるの?』って言えばいいの」
服飾専門学校で同級生だったケイティの言葉が麻希の脳裏をよぎった。
ケイティの甘ったるいしゃべり方と、すれ違った人が思わず振り返る華やかな見た目とセットで。
「嫉妬してくれてるの?」は場の空気を変える魔法の言葉だとケイティは言った。身に覚えがなくても使え、嫉妬される心当たりがあるように思わせぶることもできる。自分を高見せする効果もあるのだと。
「嫉妬してるの?」ではなく、「嫉妬してくれてるの?」と言うのがポイントだと念を押された。
「嫉妬してるの?」は相手を責める言い方だが、「嫉妬してくれてるの?」は相手を立てる言い方。「くれ」のふた文字を入れるかどうかで大違いなのだと。
毛先を巻き、爪にも頬にも色を絶やさないモテ女は、さすが細かいところに気がつくと麻希は感心し、いいことを聞いたと喜んだが、使う場面がなかった。
ツカサ君と別れた後、麻希の部屋に上がり込んだ男たちは、用が済むとさっさと服を着て、妻と夕飯が待つ家へ向かった。気まずくなったりすれ違ったりするには、ある程度の時間をかけて会話を積む必要があるのだ。
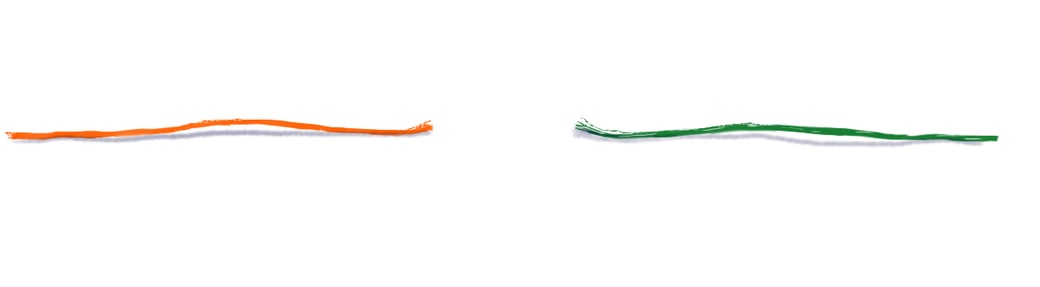
モリゾウとは一緒にいる時間は長かったが、これまで意見が食い違うことも、それをめぐって争うこともなかった。モリゾウは電気さえついていれば良しというスタンスで、生活への不満は一切口にしなかったし、麻希がやることにダメ出しどころか口出しすることもなかった。
モリゾウが動画配信の英語講師をしていると知ってから本人に問いただすまでは、稼ぎがあることを隠していたことへの不信感が募ったが、借金の返済にあてていることがわかると、モヤモヤは消えた。
溝を埋めたのは、わだかまりが解けたことよりも体の交わりを持ったことが大きいのだが、体を許すと、お互いの境い目が溶け合ってしまい、これまで立ち入らなかった領域に踏み込むことまで許してしまう。
ツカサ君が書いた脚本にモリゾウがダメ出しをするのは、ツカサ君とつき合っていた過去へのダメ出しに聞こえる。俺が書いていたら作品は日の目を見たのにと張り合い、ツカサ君を打ち負かそうとしているのだろうか。たまたまモリゾウも脚本を書く人で、今の恋人と前の恋人が同じ土俵で戦えてしまう。
「嫉妬してくれてるの?」
ケイティに伝授された魔法の言葉を口にすると、
「そうなるのかな」
モリゾウは、あっさり認めた。こんなに簡単なのかと麻希は拍子抜けする。
「俺だけ取り残されたみたいで、焦ってしまって」
はじめて結ばれたとき、「どこにも行かないで」とモリゾウは言った。具体的には聞けていないが、過去に辛い別れを経験して、一人になったらしいことはわかっている。
麻希の気持ちがツカサ君に傾いて取り残されることを恐れているのか。
「ごめん。そんなつもりで脚本読んでもらったわけじゃなくて。あれを書いた人とはとっくに……」
「星屑蛍は関係ないよ」とモリゾウが麻希の言葉を遮った。
「俺が嫉妬してるのは、今のマキマキなんだけど」

「俺なんにもしてないのに、シュークリーム食ってる場合なのかなって」
「作家」として着実にファンを増やし、売り上げを伸ばしている麻希を見て、モリゾウは焦ったという。自分は何も生み出していない、と。
演劇仲間が離れて行ったせいなのか、英語講師の仕事が忙しくなったせいなのか、モリゾウは2年近く舞台から遠のいている。
作品を作りたい気持ちはあるけれど、一緒にやる相手がいない、時間がない。あるいは、『制服のシンデレラ』を読んで、作品を作りたい気持ちを封じてしまっていたことに気づいたのかもしれない。自分は何も生み出していないというもどかしさが、すでにある脚本へのダメ出しに向かわせたということか。
場の空気を変えただけでなく、さっきまで麻希の中を巡っていた暗く澱んだ気持ちまで入れ替わったように感じる。「嫉妬してくれているの?」が引き出した答えとしては満点ではないだろうか。
そのセリフがモリゾウの創作であり演技である可能性は否定できないけれど、そうは思えない切実さがあった。
舞台作品を作るのとバッグやポーチを作るのは、過程も出来上がりもまるで違う。まさかモリゾウが布雑貨と演劇を並べ、作者である麻希と自分を比べ、気持ちを波立たせているとは思っていなかった。
思いがけなかったが、うれしかった。
モリゾウを歪ませてしまったことに快感を覚えるのは、歪んでいるかもしれない。でも、誰かに羨まれることは、麻希にとっては事件だ。
ずっと人を羨んで生きてきた。自分にないものを持っている人たちを見て、自分との差を嘆いた。劣等感というのは引き算から生まれるが、世間の評価と自己評価に大きなズレはなかったように思う。自己肯定感の低い麻希が率先して自分を安く見積るから、まわりにも同じような扱いを許してきたのかもしれない。
「マキマキ、泣いてる?」
モリゾウに顔をのぞき込まれて、あふれた涙が加速した。
ケイティ構文なら、「泣いてくれてるの?」となるのだろうか。
「だって、モリゾウが変なこと言うから」
「変なこと?」
「モリゾウも一緒に生み出したんだよ」
6万円で売れたひまわりのバッグを作る技術もその材料も、ずっと麻希の手元にあった。けれど、使われていなかった。モリゾウに「作家」と扱われたことで、「作品」を作る意欲が湧いた。モリゾウはオンラインショップという舞台を用意し、作品にライトを当て、詩のような紹介文で彩り、世の中に送り出してくれた。バッグを作ったのは麻希だが、売ったのはモリゾウだ。作品に6万円の値段をつけてくれたのはモリゾウだ。麻希は3万円と言ったが、それでは原価にしかならないと言って2倍の値段をつけてくれたのだ。
「モリゾウがいなかったら、何も生まれてないんだよ」
モリゾウが麻希の作品を引き出し、売り出してくれたのだ。本の編集者のように、映画のプロデューサーのように。それこそ現代のシンデレラだ。
モリゾウの顔が近づいたと思ったら、涙をなめられた。
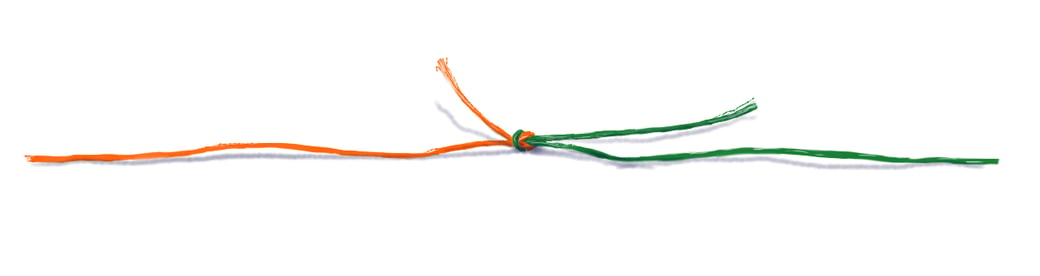
久しぶりのキスは、パティスリーのシュークリームの味がかすかに残っていた。やっぱりクリームが上品だ。涙のしょっぱさが混ざり、甘さを引き立てる。ふたりのシュークリームの余韻が溶け合う。モリゾウとの境い目が溶ける。
わたしたちはもつれたりほどけたりしながら何度も関係を結び直していくのだろう。
モリゾウと求め合いながら、ケイティは今どうしているだろうと瞼の裏に彼女を思い浮かべる。専門学校時代から20年ほど経った今もノースリーブのワンピースから長くて白い手足を自慢げに出しているのだろうか。
連絡を取り合うことはないと思うけれど、どこかでバッタリ再会したら、お礼を言おう。あの魔法の言葉、効いたよ、と。
20年前は真っ直ぐ見られなかったケイティの顔を、今ならちゃんと見て、言える気がする。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第85回 佐藤千佳子(29)「義母が転がり込んできた」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!