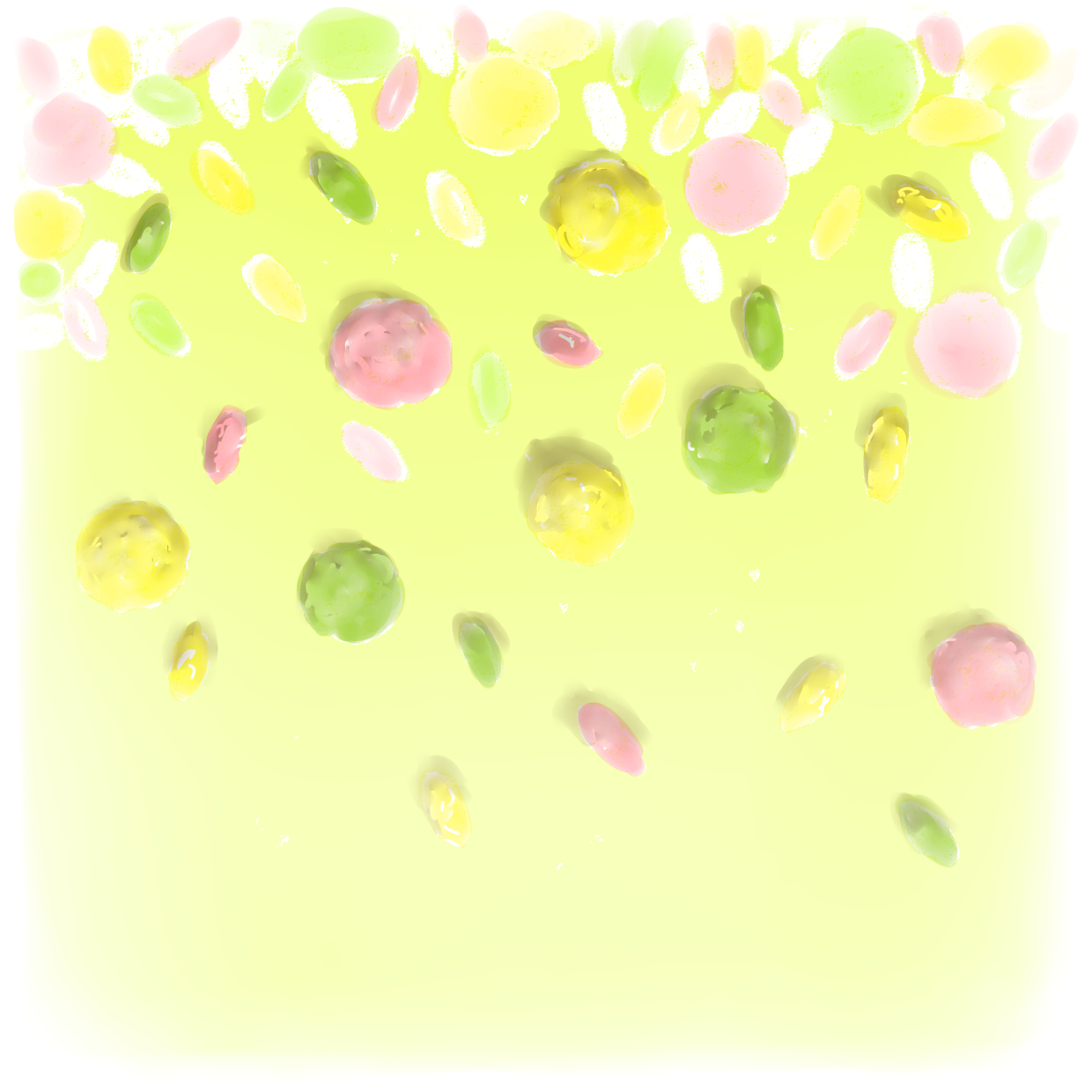第85回 佐藤千佳子(29)義母が転がり込んできた
「私のことなんて家政婦だとしか思ってないんだもの。だから、自分の考えと違うことを言われると、使用人に口答えされたみたいに、むきになるの」
月曜日の朝11時過ぎ。10時に訪ねて来た義母の話を聞きながら、千佳子は壁の時計に目をやる。12時からパートが入っている。お昼をサッと食べて出るつもりでいたが、昨夜の肉じゃがの残りは一人分しかない。
自分だけ食べるわけにもいかないが、お昼を抜いて出るとしても、あと30分ほどしかない。
「昔っからそうなの。私のこと見下してるの。女なんて馬鹿だって思ってるの」
昔と今が入り混じり、同じ話が繰り返され、終わりそうにない。「お義母さん、そろそろ」と割って入るタイミングをつかめず、千佳子は圧倒されて聞きながら、夫の両親の家を一人で訪ねた春の日のことを思い出していた。
「ロウバイの季節よね」
夫の母がそう言い、千佳子は「狼狽」の字を思い浮かべたが、彼女が言ったのは「蝋梅」という花のことだった。ふくよかな香りのする黄色い花で、持ち帰らせてもらった花をキッチンに飾り、家族で楽しんだ。あのときは娘の文香とのことで千佳子が狼狽していたのだが、今は義母が狼狽している。
普段は何か届け物があるときも事前に電話をくれ、玄関先で品物を渡し終えると、家に上がらずに去って行く。身内であっても生活に踏み込まない距離感を保ってくれているのだが、今朝は違った。前触れもなく玄関のチャイムを鳴らし、千佳子がドアを開けると、「ちょっといい?」と聞きはしたものの返事を待たずに靴を脱ぎ、
「千佳子さん、月曜日って週の始めよね?」
と聞いた。
その余裕のなさと遠慮のなさに千佳子はひるみ、月曜日の朝に、今日は週の始めかどうかをわざわざ聞いてくる義母の質問の意図がよくわからないまま、「ですよね」と答えた。すると、
「そうよね? あの人、日曜日が週の始めだって言うの」
義母は味方を得たように力強くうなずいた。「あの人」というのは義母の夫、千佳子にとっての義父のことだ。

「週の始まりといえば月曜日でしょう。ねえ、そうよね? 週の始まりが日曜日だったら、日曜日は週末って呼べないじゃない?」
ダイニングの椅子に腰を下ろすと、再生スイッチが入ったように義母は勢いづいて話し始めた。
夫の両親は「1週間は日曜日から始まるか、月曜日から始まるか」を巡って口論になり、その話を誰かに聞いてもらいたくて義母は家を飛び出したらしい。
発端は先週の月曜日だった。
結婚式の媒酌人を務めることになり、新郎新婦との打ち合わせの日取りが9月18日の日曜日に決まった。「1週間は日曜から始まる」と考える義父が「来週の日曜日になった」と義母に告げたのが9月12日の月曜日のことだった。だが、「1週間は月曜から始まる」と考える義母にとって、9月18日の日曜日は「今週の日曜日」であり、「来週の日曜日」は翌週の9月25日を指す。
9月18日の前日になって行き違いが発覚した。短歌サークルの友人と3人で観劇の予定を入れていた義母は、代わりに行ってくれる人を慌てて探した。チケットは当日手渡しの予定だったから、チケットを取ってくれた短歌仲間と手を挙げてくれた大学時代の同級生をつなぎ、劇場前で待ち合わせしてもらったという。
「開場が1時半で、媒酌人の打ち合わせが2時で、移動しながら連絡取り合って、無事チケットの受け渡しができたって報告聞くまで気が気じゃなくて。私が大騒ぎしてるのを見て、キャンセルできないのかってあの人が言うの。払い戻しなんてできないわよ。それに、お金の問題じゃないの。お友達が3列目のど真ん中の席を並びで取ってくれてたの。演者さんから見える席に穴を空けるわけにいかないじゃない? 新幹線の指定席とは訳が違うの。チケット代はいいから、とにかく私の代わりに行って来てって電話で話してるのを横で聞いて、今度は、チケット代受け取らないのかって口出してきたから、こんなことになったの誰のせいだと思ってるのって言い返したの。18日は赤口で25日は先勝なんだから25日のほうがお日柄がいいじゃないって。そしたら、急に口調が乱暴になって、怒鳴るみたいな大声で、お前はまだそんなこと言ってるのか、自分の間違いを認めろって。お前って言ったの、あの人」
「お前」呼ばわりされた話は1時間ほど前にも聞いたのだけどと11時30分を回った時計を見ながら千佳子は思う。

「1週間が日曜日から始まるか、月曜日から始まるかが問題じゃないの。そこからずれてるってことが致命的なの。わかる? 月曜日も日曜日も毎週来るじゃない? 結婚してから何回あった? ずっとずれてたの私たち。地層の断層だっけ。あれ、時間が経つほどどんどんずれるでしょ? 歯並びだってそうでしょ?」
週の始まりが日曜日の人もいれば月曜日の人もいる。どちらか一つを正解にしなくてはならないのだろうか。お義母さんにとっての正解とお義父さんにとっての正解が違っていてもいいのではないだろうか。でも、何か言うと話が長くなるだけなので、千佳子は黙って聞くことに徹する。
「私には自分の意見を言う権利もないんですかって言ったら、1週間が日曜日から始まるのは決まり事なんだから、そこにつべこべ言うお前は馬鹿だって言ったのあの人。お前もひどいけど馬鹿もひどいでしょ。とどめに文化人を気取るなら常識をわきまえろって、捨て台詞吐かれたの。文化人気取りって何?
私がいつ文化人を気取ったの? 私って気取ってるの? ねえ千佳子さん?」
義母はこの秋からカルチャースクールで短歌講座を受け持つことになった。去年自費出版した歌集が担当者の目に止まり、出版社あてに問い合わせがあり、あれよあれよと話が進み、「先生」と呼ばれる身になった。週に1度、全6回の講座をまずはお見合いのような感じでやってみましょうとなったが、秋のコースが終わったら冬もお願いしますと早くも続投を打診されているという。
「あの人、面白くないのかもね。自分は家にいるから」
義父は退職して家にいる。お昼も家で食べる。それも良くないのだと義母は言った。以前は夫が仕事に行く時間が来れば言い争いは打ち切られ、帰宅するまでにお互い頭を冷やすことができた。今は逃げ場がなくて息が詰まると義母はこぼし、
「あの人が頭を下げるまで、私、あの家には帰らない」
と言い切った。
「家に帰らなくて、どうするんですか?」
「悪いけど、ここに居させてもらえない?」
夫の両親の援助がなければ建てられなかった家だ。断ることはできない。
「私のことを馬鹿な文化人気取りのお前呼ばわりする人と顔を合わせたくないし、そんな人のために何かする気にもなれないし、こんな気持ちであの人と日曜日も月曜日も迎えたくないの。いっそ別居したほうがいいのかもね」
今日一日だけではなく長期滞在を考えている口ぶりだ。

義母を家に残し、鍵を置いて、千佳子はパートに出た。夫に連絡しておこうかとスマホを取り出しかけたが、思い直した。夫のほうが先に帰宅することはないのだし、前もって知らせる必要はない。娘の文香もバスケ部の練習があるから、家に帰ったらばあばが留守番していてびっくり、となる心配はなさそうだ。
自転車を漕ぎながら、「困ったな」と思っていることが口に出た。
お義母さんの布団、どうしよう。
この夏から夫と寝室を分け、リビングで寝ている。夫はエアコンをつけないと眠れない。千佳子はエアコンをつけると喉が痛くなる。ある夜、リビングのサッシ戸を網戸にして床で寝てみたら、夜中に目覚めることなく熟睡できた。秋になって寝苦しさは和らいだが、このままでもいいのではという気になっている。眠りにつく時間を夫に合わせなくて済むし、夜中にトイレに行く夫に眠りを破られることもない。
義母にリビングで寝てもらうことになったら、千佳子は押し出される。文香の部屋に行くわけにもいかない。布団も足りない。夫の隣に戻るのが自然だろう。
困った。夫と寝なくてはならない。
そんなことを思うのって、どうなんだろう。妻として。夫婦として。
夫婦は寝室を共にするものなのだとしたら、寝室を分けた今のわたしたちの関係は、夫婦ではなく同居人なのだろうか。
重くなったペダルを押し返しながら、千佳子は考える。
夫婦ってなんなんだろう。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第86回 佐藤千佳子(30)勝ったり負けたり人生じゃんけんへ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!