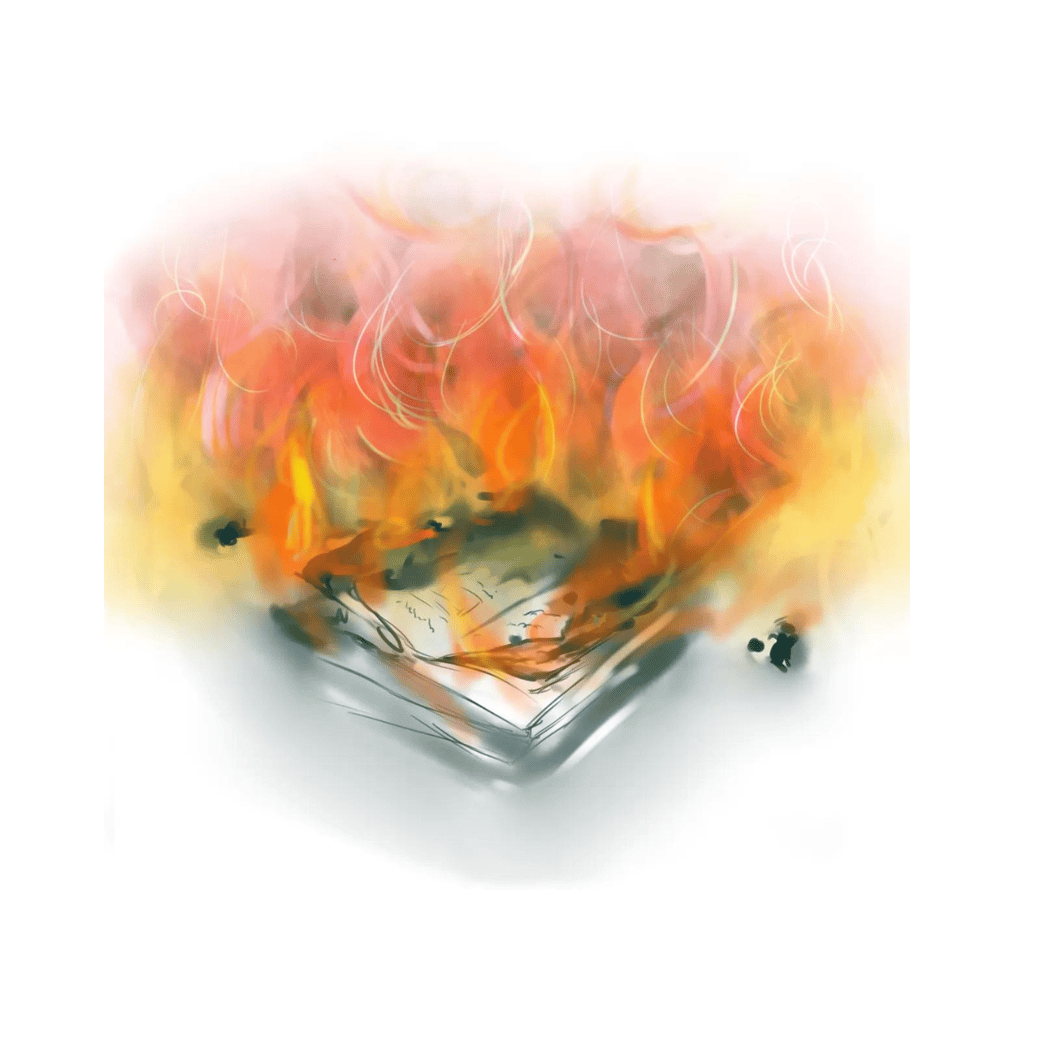第66回 多賀麻希(22) 制服のシンデレラ
モリゾウは麻希の手を取り、そこに更地ができていることを知らせたが、深追いはしなかった。
20年余りぶりに現れたエンダツの原因は、昨年の秋から募らせたモリゾウへの不信感ではないかと思われる。それ以外、麻希には悩みがなかった。30代の終わりに突如始まった青春のような日々に浮かれていたのだ。無職だと思っていたモリゾウが動画配信サービスの英語講師をしていることを知るまでは。
稼ぎがあることを隠し、家賃も光熱費も入れず、居候を続けているモリゾウに、裏切られたような気持ちになった。
過去の男たちとは違うと思っていたのに。
体の関係はなくても、吸い取られていることに変わりはなく、金銭面だけ甘えられていることに、むしろ傷ついた。
自己開示ギャンブルに打って出て、モリゾウには稼ぎを上回る借金があること、仕事はしているものの蓄えはないことを知った。その後ろめたさゆえ打ち明けられない麻希への想いを募らせていることも。舞い上がったり突き落とされたりの挙げ句、お互いの気持ちを確かめ合うことができ、体も通じ合い、何か月ものあいだ垂れ込めていた憂鬱の霧が晴れると、暦も春になった。
まだ麻希に話していないことはあるのだろうと思う。誰にいくら借りているのか。なぜ借りることになったのか。あとどれくらい返済が残っているのか。麻希が聞けば、モリゾウは答えてくれるかもしれないが、無理に聞き出すことはしたくなかった。
麻希だって、モリゾウに話していないことがあるのだ。

髪を撫でられる仲にならなければ、モリゾウにエンダツを見つけられることはなかったが、20年余りぶりに亡霊のように現れたエンダツが連れて来た過去の記憶を打ち明けるなら今だと思った。
実は前にもエンダツができたことがあってねと、ついでに思い出したような軽さで切り出せないだろうかと思う一方で、それをモリゾウに知らせたところでどうなるのだと引き止める自分がいる。
頭に更地ができるというのは、それくらい心に深い傷を負っているということなんだよと恩を着せたいのだろうか。それとも、痛い過去を開示してもモリゾウの態度が変わらないことを確かめたいのだろうか。
ついつい癖で更地に手をやり、つるつるの手触りを確かめながら、麻希は自問自答する。
そもそもモリゾウは、エンダツの原因を作ったという自覚があるのだろうか。麻希の髪に手を伸ばさなくなったのは、エンダツに触れるのを避けているからなのだろうか。
髪を触らなくなると、キスをしなくなる。キスをしなくなると、その先にも進まなくなる。モリゾウがエンダツと距離を取るということは、麻希と距離を取るということなのだ。
このまま関係が冷えて、モリゾウと体を重ね合うことがなくなってしまうのだろうか。いや、40歳にもなって、覚えたての若い子みたいに寝ても覚めても求め合っているというのが不自然だったのだ。年相応の距離と温度に落ち着いたということなのだと自分に言い聞かせるが、
エンダツめ。
一円玉大のちっぽけな円に気持ちをかき乱されているのが恨めしい。

高校時代のエンダツのきっかけになった「事件」は、東京に出てきたときに、熊本に置いてきた。断ち切るために故郷を離れたのだ。これから出会う人たちには知られたくなかった。
一人だけ、ツカサ君には話した。
ツカサ君は脚本が書けなくて苦しんでいた。コンクールに出しても出しても落ち続け、やっぱり脚本家になる夢は諦めたほうがいいのかなと弱音を吐いていた。麻希が勤めていた映画製作会社の社長が原稿を読んでアドバイスをしていたが、恋愛ものを書いても探偵ものを書いても「ツカサの書くもんは薄いんや」と感想は同じだった。
「僕の人生が薄いから、薄いものしか書けないんだよね」とツカサ君は薄い体を折り曲げて、落ち込んでいた。
「薄い」の逆は「濃い」なのか、「分厚い」なのかと麻希はツカサ君に聞いたことがある。ツカサ君は少し考えて「強い」と答えてから「かな」と続けた。ツカサ君の語尾には、「かな」がよくついて来た。
何をするのも自信がないツカサ君が、たった一つ、人よりちょっと得意だったのが、書くことだった。脚本コンクールで賞を取って、書き続ける励みにしようとしていたけれど、応募して落とされるたびに、ささやかな自信を削がれていった。今度こそとムキになり、注いだ時間の分だけ結果を出さなくてはと焦っていた。
コンクールには何百何千という応募作品が寄せられる。脚本の形に整っているだけでは勝ち上がれない。似たような話ばかりで退屈している審査員の目を覚まさせるような強烈なエピソードが必要なのだが、ツカサ君は、そんな実体験も発想も持ち合わせていなかった。
だから、麻希はネタを提供したのだ。教科書を燃やした焚き火の炎が納屋を飲み込み、裏庭を更地にしてしまった田舎町の女子高生の話を。自分のことではなく、同級生にこんな子がいてねと伝えたが、ツカサ君には麻希のことだとバレていた。「シンデレラへ」のメッセージを添えて赤い靴を贈られたとき、やっぱりわかっていたんだと思った。

麻希の話を膨らませて書いた脚本に、ツカサ君は「制服のシンデレラ」とタイトルをつけた。麻希をモデルにしたヒロインは、家の裏庭ではなく、空き家に忍び込んで放火を繰り返す。その現場に、毎回、真っ先に駆けつけ、炎にカメラを向けてシャッターを切る若い男が現れる。炎に魅せられた、居場所のない女子高生とカメラマンが少しずつ心を通わせていく。
教科書に火をつける場面は出てくるが、ほとんどはツカサ君が作り上げた話だった。茜と名づけられたヒロインが教科書に火をつけるに至った心情も丁寧に描かれていた。それはツカサ君が想像したヒロインの気持ちであって、麻希のそれとは違うのだが、「あのとき言葉にできなかったけれど、わたし、きっと、こんな風に思っていたんだ」とヒロインに自分を重ねられた。消したい過去が美しく書き換えられたような錯覚を覚えた。
最優秀賞作品がドラマ化される脚本コンクールで、「制服のシンデレラ」は最終選考の8本に残った。選考の模様がシナリオ文芸誌に掲載されているのをふたりで読んだ。「教科書に火をつける女子高生に共感できない」と選考委員の一人が言い、その意見に反対する選考委員はおらず、真っ先に議論の対象から脱落した。
「『制服のシンデレラ』というタイトルは悪くない」とそこだけはほめられたが、「タイトルから期待した内容と違い、ガッカリした」と記されていた。「僕の力不足だね」とツカサ君は淋しそうに笑った。
ツカサ君には話せたのに、モリゾウにはなぜ話せないのだろう。
教科書に火をつけた過去を思い出すと、ツカサ君との思い出がついて来る。それもブレーキになっているのかもしれない。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第67回 佐藤千佳子(23)「この国の損失」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!